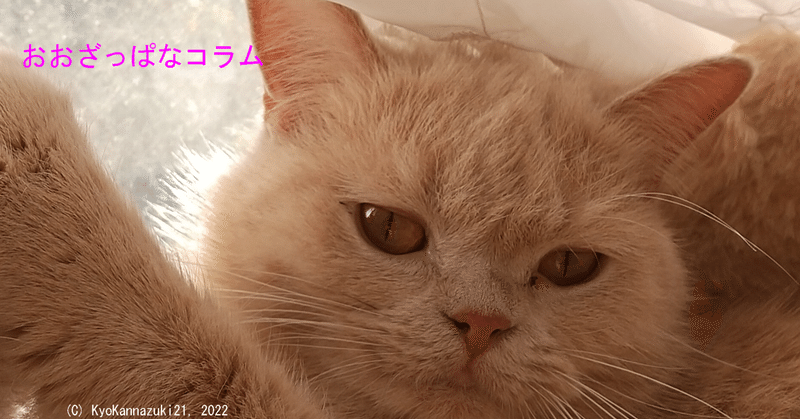
プレ皇室研究: 天照大神の墓の伝説もない! ついでに古賀市。
先日、卑弥呼の墓って、どこかの地域の周辺に、なんの伝説もないよねっていう話をしました。(そう言っている人がネットにいて、おお、なるほどなーって思った。)
でもよく考えたら、天照大神の墓、神社もないのだ!!
そりゃあ、伊勢神宮はあるけど、それって移動した結果であって、その前は、皇室の宮のあるところに祭られていたのだ。家庭内神殿ですな。
しかし、畿内に来る前のどこかは、日向だけど、それもうやむやに忘れ去られていて、いまだに宮崎県とかいっている人々もいる。
神武天皇、ニニギの天孫降臨時点あるいは、その前っていうのに、なんで神社ってのがないのだろう???
紀元前にいた場所が、本来神社になっていいのに・・・・。
まあ、なにかカモフラージュしてあるかもしれないが・・・。
まあ、「高天原」隠しで、どこにあったかわからんようにごまかしたいからだとは思うのだが、でも、祖先神だから、ニニギが天孫降臨した時点では、おばあちゃんとして80歳とか90歳とかで生きていたのかな???
だったら、奴国なんじゃない?
または、朝倉地域でもいいんだが、朝倉にちょうどいい神社がないんだよなあ・・・。
福岡県周辺で探しても、前に説明した他の神様ばっかりで、残っている明神大社がいないのだ。
残ったのは、この神社だけなんだが、聞いたことのない神様なんだなあ・・・。
「高良大社自体が名神大社、筑後国一宮であるほか、本殿に合祀されている豊比咩神社が名神大社、境外末社の伊勢天照御祖神社が式内小社、味水御井神社が筑後国総社であるとされる。
社殿は国の重要文化財に指定されており、神社建築としては九州最大級の大きさである。」
かなりでっかい神社なのだ。由緒正しい古さなのだ。(まあ、紀元前ではないが。)
「高良山にはもともと高木神(=高御産巣日神、高牟礼神)が鎮座しており、高牟礼山(たかむれやま)と呼ばれていたが、高良玉垂命が一夜の宿として山を借りたいと申し出て、高木神が譲ったところ、玉垂命は結界を張って鎮座したとの伝説がある。山の名前についてはいつしか高牟礼から音が転じ、良字の二字をあてて「高良」山と呼ばれるようになったという説もある。現在もともとの氏神だった高木神は麓の二の鳥居の手前の高樹神社に鎮座する。なお、久留米市御井町にある久留米市役所の支所の名前「高牟礼市民センター」や、久留米市内のいくつかの小中学校の校名や校歌の歌詞に「高牟礼」の名前が残っている。」
高御産巣日神を追い出すくらい、ずーずーしい神様ってなんなん???
高御産巣日神とだいたい対等なのは、天照大神であるが、天照大神のほうが子孫なんで・・・。そこまでずーずーしくできないと思うんだよね。
「高御産巣日神は、『日本書紀』では天地初発条一書第四に「又曰く〜」という形式で登場しており、また神代下では高天原から葦原中国に神などを降ろす神として主に記述されている[9]。 天津国玉神(あまつくにたま)の子である天若日子(あめのわかひこ)が、天孫降臨に先立って降ったが復命せず、問責の使者の雉(きぎし)の鳴女(なきめ)が参るとこれを矢で射殺する[10]。その矢は高天原まで届き、高御産巣日神が「もし高天原に叛く意志があるならこの矢に当たるであろう」と述べて投げ返すと、矢は天若日子を討ったという[10]。」
「天孫降臨の主宰神としての記述や神武天皇の大和入りの祭祀の主祭神として登場すること、大嘗祭の主祭神としての記録から古くは大王家の至高神であったと推定されている[12]。
大嘗祭の悠紀・主基の斎田のかたわらに素朴な黒木造りの茅葺きの仮宮八神殿があり、そこにもタカミムスビがまつられていた。この八神殿の中には素朴な竹の棚があり、その上に依り代としての神木が立てられていたといい、この神殿の古い形は田のかたわらに立てられた神籬としての神木であろうとし、タカミムスビはその神木に降臨する生産の神、田の神であったとし、遊牧系の天神説を否定する見解もある[6]。」
うーんうーん・・・本当にないんだよなあ。
どっちかというと、命令するだけだから、「XXXに降り立ちました」とかってなくて、ただあるのは、「天の安河」にいただけなのだ。
名字だとこういう人がいるが、後付け、宮崎県だし。
神社は、もっとあとで、宮崎県が日向と思い込んでいる時代のものだ。
だから、あてにならない。
こんなのがありました。
Wikiによると、九州北部にある神社はこの2つなのだが、下のはわりと新しいし、上のは村社レベルで小さすぎる。HPとかの説明もないんだよなあ・・。
「古賀神社(福岡県古賀市)
天照皇大神宮(福岡県糟屋郡久山町)」
うーん、困ったなあ。
なんでだろうか?
なんか、地元情報とかないのかなあ?
古賀市かー。海に面しているし、奴国に近いな!!

あ! 古賀市って糟屋郡じゃない! これは、有望かもしれないぞ。なにかありそうなので、後でまた調査します!!
「明治31年(1898年)、鹿部山の皇石神社境内裏から青銅製武器(細形銅剣1・細形銅戈1)が発見されました。
細形銅剣のほうは行方が知られていませんが、細形銅戈は独特の特徴を持つことにより、発見地の「鹿部」の名を冠する「鹿部型銅戈」とも呼ばれる細形銅戈の標準型式の一つで、日本列島で出土する銅戈のなかで最古型式に位置づけられるものです。」
「馬渡・束ヶ浦遺跡では5基の大型甕棺墓が確認されています。甕棺は弥生時代の北部九州を代表する埋葬方法ですが、福岡市より東側ではあまり確認されていないもので、古賀市付近はいわゆる「甕棺文化圏」の東限にあたるものと思われます。
馬渡・束ヶ浦遺跡では3基の甕棺から青銅製品が発見されました。
E地区2号甕棺からは細形銅剣2・細形銅戈1・細形銅矛1の計4点。E地区3号甕棺墓からは銅釧5点、碧玉製管玉30点・勾玉1点。
B地区1号甕棺墓には細形銅剣1本が納められていました。
弥生時代の墓に青銅製品などを納めるものがあるのは知られていますが、E地区2号甕棺は金海式と呼ばれる棺専用の大型甕で、この型式の甕棺に青銅製武器を4本も納める例は少なく、大変珍しいことです。」
金海式甕棺は、初期のタイプだ。
鏡はでていないが、なんとなくいい感じだ。
「そのうち1つの大型甕棺墓からは、2本の銅剣、銅戈・銅矛1本ずつの計4本の青銅製武器が見つかっており、弥生時代前期から中期に変わるころ(約2200年前)における地域の有力者の墓と考えられる。」
追加調査でなにかわかったら、またご報告します。
とかいたそばから、ちょっといいネタがみつかったので、追記です。
古賀神社というのは、実は皇石神社といって、でっかい石がありまして、それが、支石墓でしたー!!
「明治31年旧暦元旦、神殿後方の合せ口甕より、銅剣、銅戈が発見され、弥生時代の貴重な甕棺墓遺跡として、春日市岡本の遺跡とともに学界の注目するところとなった。
昭和47年には社地西北麓に多量の祭祀土器が発見されて遺跡の重要性を増した。」
「この神社の歴史と価値がよく分かりました。
ここは弥生時代の首長レベルの人が祀られていたのですね。
甕棺の上に支石墓の平石が載っていたというのですから、
古代の墳墓の変化を見る指標ともなる重要な墓です。しかも出て来たのは銅戈と銅剣。」
あ! ここ、立花山があるんだ!!
地元の研究者の人のコメントあった。面白い。
「「皇石」につきまして。古語「おほ」は、賞賛を表す接頭語として、オホカミ・オホキミなどと用いられること、御承知のとおりなのですが、地名に用いる「オホ」は、天上界と人間界を結ぶ聖地に用いる、とする説があります。すなわちシャーマンが祈祷する場所であったり墓地であったり。デカくもないのに大崎・大山・大島などと名付けられたところは、そのような来歴を有するようです。皇石の命名は、まさにその意識の発露ではないでしょうか。」
AI,脳科学、生物学、心理学など幅広く研究しております。 貴重なサポートは、文献の購入などにあてさせていただきます。 これからも、科学的事実を皆様に役立つようにシェアしていきたいと思います。 ありがとうございます!!
