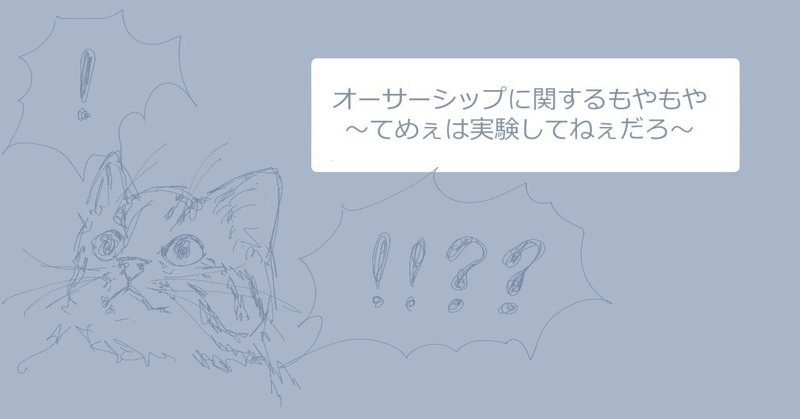
オーサーシップに関するもやもや ~てめぇは実験してねぇだろ~
こんにちは、黒都茶々と申します。
現在は定職(not研究職)についておりますが、かつて大学院の博士課程というものに在籍しておりました。
辛く過酷だった博士時代を思い出しつつ書き綴っているこれまでのnoteですが、今回は情報提供や体験のお伝えに加えて、愚痴も多分に入っています(いつもか…)。博士課程の実態や研究を知らない方にお知らせしたい内容というよりは、論文書いたことある人に向けて、「こんなことあるよね、ムカつく」と言いたいがために記事を書いています。
著者に名前が載るのは誰?
論文読んだ(タイトルのページだけでも見た)ことある人なら分かると思いますが、論文の著者ってすごい数いません? どんなグループやねん何人関わってんねん、という数の名前がずらずらと書かれていますよね。
論文書いたことない人にちょっと紹介しますと、あのずらずらっと並んでいる著者名の中で、一番その実験に貢献した人(主に、実際に手を動かして研究した人)は、一番初めに名前が載ります。大きな実験テーマで、中心担当者が2人いる場合は、1番目と2番目だったりすることもあります。その場合は、名前のところにアスタリスクとかがついてて、「この2人は同等の貢献をした」みたいに書かれます。
そして、この、名前が一番初めに掲載されていることを「ファースト」と言います。
具体例では、「君がファーストの論文いくつあるの?」という風に使われます。これは、あなたが主担当として研究した論文は何本あるのか?という意味になります。
あとは、「DC1出すときに、しょぼくてもファーストがあれば確実に採用される」とか、そんな感じ?(DC1出すときにファーストがあればいいかどうかは知りません。私はセカンド1本あったけど落ちました。セカンドだったからかな…?)
ファーストの次に大事なのが「ラスト」です。著者名がずらずら列挙されているうち、一番最後の名前です。この人は大抵その研究をやった研究室のボスで、コレスポンディングオーサー(略:コレスポ)である場合が多いです。その研究の最終責任者、みたいな感じでしょうか。
コレスポも、1人じゃなくて2人の場合もある気がします。
それ以外の、ファーストでもラストでもない、ずらずら書かれている著者名真ん中にいる人たちは、研究に参加したその他諸々の人たちです。この順番がどう決まるのかイマイチわかりません。なんとなく、貢献順(貢献度が高い人が前の方)と思っていたのですが、ちょっと分野の違う教授と共同研究した時、ファーストとラスト以外の著者の順番はアルファベット順だったので、特に決まりはないのかもしれません。
論文を読む時には、大体、ラストの名前を見て「あのラボの仕事か~」と思い、ファーストの名前を見て「あの人の仕事か~」と思いますね。有名ラボなのにファーストの名前を知らない場合は、「初めて見る名前だ、大学院生かな、ポスドクかな」と考えてみたりします。
ファースト誰にするの問題
ファーストの名前を誰にするか。
私はこのケースで揉めたことはありませんが、同期の奴はこれで痛い目をみていました。
研究室に在籍したことがない人だと、「主担当がだれかわからないなんてことがあるのか」と思うかもしれないんですが、あるんですよね、これが。
私の同期の例ですが、彼は研究室に配属された時点から、ある先輩の下で研究していました。はじめは、実験操作に慣れるため、ということで、先輩の研究を手伝っていました。同期がその先輩の研究を手伝い始めてしばらく経った頃、論文にできそうなくらいのデータが溜まってきたので、先輩は論文を書き始めます。この論文は、先輩がファースト、同期がセカンドくらいだったと思います。先輩が論文を書いている間、同期はその研究から派生した研究テーマで実験を始めました。派生したものではあるとはいえ、同期が取ったデータも多かったのではないかと思います。この派生テーマについて、ずっと、誰が主担当になるのか曖昧なまま、研究は進みました。
で、いざ論文にまとめようかとなったときに、はて、この論文のファーストはだれなんだ? となったわけです。同期やラボのメンバー(あと、先輩自身も?)は、テーマの大元は先輩が始めたとはいえ、実際実験していたのは同期だったので、ファーストは同期なんだろうなぁと思っていましたが、指導教官だった教授が、「それは先輩君の研究だろう」ということで、確か同期はセカンドになったのではなかったかな…(すみません記憶が曖昧。)
というか、今当時の顛末を思い出そうと思っていたのですが、そもそも研究のどこからどこまでを1本の論文にするか、というのも、匙加減ひとつのものなんで、もしかしたら全部合わせて1本の論文にしたんだったかなという気もしてきました。
この一連の出来事の中で、いま思い返して最も問題なのは、研究している段階で、どの作業に対して誰がどのように責任持っているか、曖昧なまま時間が過ぎてしまったことでしょうかね。(私としては、同期がそのへんを教授・先輩と上手く話し合わなければならなかったと思っている。)
コレスポ誰にするの問題
コレスポ誰にするの、というのも、揉めることがあるみたいです。すでに書いた通り、普通だとコレスポはそのラボのボスです。コレスポというのはその論文に責任を持っている人のことで、論文が雑誌に掲載された後、論文を読んだ人からの、「この実験操作は具体的にはどうやったの?」とか、「この実験で使っているこの系統を譲ってほしい」とか、そういう問い合わせ・リクエストに答える人でもあります。(だから、ポストがあまり動かない教授が務めることが一般的なのかなと思います。大学院生とかポスドクは傭兵みたいなもんだから、メールアドレスや所属がよく変わって連絡取れなくなることも多い。)
このコレスポ誰にする問題ですが、私が知っている例だと、ファーストの人がコレスポになりたいと主張しているケースがありました(コレスポというか、共同コレスポ。)。
その研究者はボスとの関係がちょっと微妙で、あんまりボスのことを信用していなかったので、もしも誰か論文を読んだ人から問い合わせがあっても、そのボスは何も答えられないだろうと考えていたのかなと思います。確かに、その論文に出てくる実験手法はその研究者の人が別のラボの人に教わって導入したもので、ボス自体はその操作はできないだろうなと私も感じていました。(その研究者の人のボスに対する不信感はすさまじく、コレスポを明け渡すと、論文の校正の時点であれこれ意に沿わない修正をされると危惧していた、というのもあったと思います。論文を投稿するときの学会や雑誌社とのやりとりは、コレスポにしか連絡がこない場合もあると思いますので。多分。)
私の聞いた限り、コレスポ誰にするので揉めたのはこのケースくらいですけれど… ないわけではない、ということで。
オーサー誰を入れるの問題
コレスポ誰にするの問題よりも、圧倒的に問題になる(問題というか、もやもやが残る)のはこれだと思います。ファーストでもラストでもない、真ん中の人たちの名前!!!
考え方は、多分正解はないように思います。
研究の関係者として名前が載る可能性があるのは、
・実験データを実際に出した人(大学院生、テクニシャン)
・パイロット実験をやった人
・実験に使ったミュータントを取ってきた人
・実験計画を立てた人
・結果の解釈についてディスカッションした人
・論文の書き方についてアドバイスをくれた人
・その研究室のボス(内容には関わっていない)
・数値を使って統計解析をした人
・研究チームにいた人
などなどがいますが、どの人をどの順番で著者に入れるかは正直なところボス(コレスポ)のポリシー次第かなと…
私のラボでは、テクニシャンはオーサーに入れていなかったですが、入れているというラボもありました。研究に関わった大学院生とかを、その論文で使われるデータは取っていなくても実験の立ち上げに関わっているからという理由で入れている場合もありますよね。なんなら、競争的資金獲得のための申請書を書くときに業績があった方がいいだろうということで、その研究に全く関与していないポスドクの名前を著者名に入れたケースも私は知っていますよ…
まず前提として、論文に名前が載るということはその論文の作成に貢献したということなので、基本的には名前を入れてもらうのは嬉しいことです。業績にもなります。これは推測ですけど、有名な先生の名前を入れたらそれだけでお墨付きというか、論文の信頼度が上がるんじゃないかという邪推もしています。(論文の掲載可否を決めるときに、どこまで名前が出るのか知りませんが。)研究の方針を相談させてもらった先生の名前を入れることで、その先生への感謝の気持ちというか、かけてもらった労力に対する見返りを示すことができるような気もします。
では、手あたり次第に関係しそうな人の名前を入れればいいのかと言うと、そんなこともないと思います。自分が筆頭著者の場合、データをほとんど自分が取っているのに関係ない人の名前がたくさん入るのははっきり言ってうざいですし、人数が少なければ少ないほど、自分の論文作成への貢献度(気分だけですが)が上がるように思います。あと、実務的な面で言えば、船頭多くして船山に上るとも言いますが、著者名に名前が入っている人が多ければ多いほど論文の方針がまとまる(全員が納得するものを仕上げる)のに時間がかかるので大変な気がするので、著者名は少ない方がいいです。
私の場合だと、その時書いていた論文の実験データの統計解析が必要になって、最初は教授の一番弟子みたいな人から、統計のやり方だけを教えてもらう(そして、その人は著者に入れない)予定だったのが、なぜか知らないけど統計解析をやってもらうことになってしまい(私に教えてやらせるよりも、その人がやっちゃった方が早いというのと、解析ソフトがその人のPCにインストールされているからという理由だった気がする)、統計解析してもらったなら著者に入れようとなり、著者に入るからには論文にも意見を出したいと言い始めたことがあって、うん、そうですね、あの時は本当にストレスマックスで殴りたいと思ってしまった。(その一番弟子みたいな人が、あんまり論文出ていない時期だったので、教授はその人の名前が入った論文を出させてあげよう(=業績を作らせてあげよう)としたのではないかと私は思っている。弟子へのプレゼントに私の苦労を差し出すんじゃないよクソが…! それに対する反発も大きくて、本当にストレスフルだったなぁ…。)いや、ホントね、「てめぇはなんの実験もしていないだろうが! おいしいとこだけかっさらっていくんじゃねぇよばーかばーか」って思ってたよ。
それとは逆のケースもあって、私が喧嘩別れした先生、私が遺伝子のクローニングしたプラスミドを使って出した(と思われる)研究結果、私の名前入れてませんでしたね。データはファーストの人が取り直したかもしれないけど、私その研究の初期段階でめっちゃ貢献させていただいていますけどね? まぁ、その先生の性格から考えて、実験道具作っただけの私の名前なんて入れる価値がないと思ったからでしょうし、名前入れて業績作ってやる意味もないと思ったんでしょう。そういうこともありますよ。
最近の論文だと、論文の最後に著者の貢献した分野について掲載されている場合もあって(実験計画を立てたのはこの人、実験したのはこの人、論文書いたのはこの人、みたいな。)、それは結構いい試みだなと思ったりしています。共著者に入るのは、論文に一瞬でも関わっていたら入っちゃいますけど、貢献度はわかりませんからね。
以上、長々と書いてしまいましたが、「オーサーシップに関するもやもや ~てめぇは実験してねぇだろ~」をお届けしました。この件でどれくらい揉めるものなのかよくわかりませんが、私の周りではまぁまぁ起こっていたので、こんなこともありますよということで。
結局、いろいろなぁなぁで研究してる場合が多いので、いざ「誰を共著者に???」ってなったときに、変な私情とかいろいろ入ってきちゃうんですよね。もっと、かちっと型決めてやれるといいんでしょうけど…ねぇ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
