
新カード解説②(デュエプレ10弾EX)
こんばんははじめまして。海月です。
書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。
自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。
とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。
10弾EXの新カードの考察第2弾です。
第1弾についてはこちらをどうぞ。
指標はこんな感じ。
9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。
7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。
5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。
3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。
0~2点 → 見なかったことにしていい。
基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。
それでは以下、本題です。
賢察するエンシェント・ホーン

事前評価:4
紙からの変更点は、回復するマナ(アンタップ)がすべてから5になった点です。
さすがに「クリスタル・フュージョン」などで莫大なマナを抱えてからこのカードでアンタップするのを危惧されたのかもしれません。
すぐに実践級になりそうになくとも、将来にわたって芽を摘んでいく感じがデュエプレ運営の性格に感じられますね。
一応、コスト軽減と組み合わせて「エンシェント・ホーン」の召喚コストを下げれば、差額分だけ使用可能マナを回復できます。

このカード自体の登場は紙の10弾(現デュエプレは30弾前後)とかなり古めなので、昔やっていた世代には知っている人も多いのではないでしょうか。
紙での使い方としては「ボルバル」との組み合わせがありました。

「ボルバル」を出す前に手札の「エンシェント・ホーン」を出し、次ターンの打点とする使い方がされていました。
一応この使い方は、「ボルバル」が殿堂入りで使用可能なデュエプレでも再現できるでしょう。
他にもSA化させての打点運用はできますが、さすがにロマンが過ぎる気もしますね。
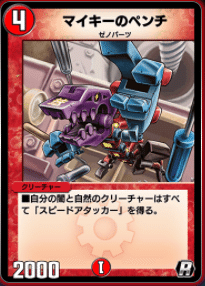
ホーン・ビーストという種族に目を向ければ、「フィオナ」のノーコスト進化元とするのはやはり考えたいところです。

目立った活躍ができていないカードですが、「フィオナ」自体はそこそこな性能を持っているので、ファンデッキの域でしょうが構築する意義はあるでしょう。
「ペガサス」の進化元としても、コストが被っている点で相性はいいです。

「ペガサス」の進化元がホーン・ビーストから自然クリーチャーに緩和されているのはちょっと損した気分がしちゃいますね…
環境レベルのデッキで考えると『サバイバー』の「シータ・トゥレイト」と組み合わせてみると進化速攻の奇襲ができて面白そうです。

難点はシールド5枚の保持でしょう。
デュエプレはやはり、始終ビートやクリーチャーコントロールが優勢なゲームメイクがされています。
このカードの着地までにシールドを割られてしまう、ということは頻発するでしょう。
現状の環境で使用されることはあまりないと考えられますが、独自の効果を持っている点は覚えておきたいです。
無限の精霊リーサ

事前評価:4
紙からの変更点は、アンタップ効果が強制になった点です。
あとは普段触れませんが、レアリティがコモンからレアに上がっていますね。
似た効果のカードとしては「アイザク」が5弾で収録されていました。

まさか「アイザク」が次でND落ちするための収録…?
一応、こちらはバトルに勝つことが条件であるため、自ら攻撃を仕掛けてもアンタップできるという差があります。
自軍に”すべてのバトルに勝つ”効果を付与できるとなかなかの脅威となりそうです。

効果としては淡泊なもののため、ステータス以外にあまり見るところはありません。
前回の「ブラッディ・シャドウ」の項で触れましたが、環境のパワーラインが4000になって来ているので、それらを軒並み押さえつけられる点は意識されているのでしょう。
それのみで採用するには力不足ですが、クリーチャーによる殴り合いが主流となるクイックピックが正式リリースされれば、そちらでは堅実な活躍をするかもしれません。
wikiによると、「シャウナ」の子分をイメージしてデザインされたようですね。

「シャウナ」が紙でSRだったのにデュエプレではBASICとなってしまったのに対して、「リーサ」がCからRになったのは何とも言えないものを感じます。
天雷の聖霊ユリウス

事前評価:7
紙からの変更点は以下。
・効果が出た時にも働くようになった
・呪文回収がランダムになった
先になぜ前の「リーサ」が”精霊”で、「ユリウス」の名前が”聖霊”かというと、エンコマのみだと"精霊”、エンコマ+別種族となると”聖霊”というルールがあるからです。
一度述べたので今後の誤字は許してくださいね。
さて、本題ですが、ナイトの呪文を主体にしつつ、クロスギアを操るサムライに対抗する特性を如実に表した効果をしています。
紙の場合はクロスギアがほとんど環境に進出しなかったので、前者の効果のみメインとなる使い勝手の悪い「デ・バウラ伯」のようでしたが、cip効果とクロスギアの活躍があってかなり待遇改善されたと言えそうです。

ブロッカーを得ていれば言うことはなかったでしょうが、それだと少々便利すぎたのかもしれません。
呪文回収効果は「デ・バウラ」、クロスギア除去に関しては「アクア・マルガレーテ」という先輩がいるため、ナイトで見ると中間に位置するこのカードは器用さを売りとする必要がありそうです。

エンジェル・コマンドとしては、同種の「アルシア」が一定の活躍を見せていたことからも、上位種のこのカードの有用性はわかりますね。

光主体のエンジェル・コマンドデッキであれば呪文を強力なものに絞る場合も多く、それらを使い回せると良さそうです。
もちろん、攻撃トリガーの隙を抑えるためのタップ系呪文との組み合わせも良しです。
その他の採用先としては、『除去コントロール』や『5色コントロール』あたりが候補になるでしょうか。
グッドスタッフの性質が強めなカードのため、優秀な種族を気にせずとも採用可能です。
器用貧乏となって使われないということもありそうな絶妙なラインでもありますが、2枚くらいは必ず保持しておきたいカードと言えるでしょう。
奇跡の精霊ミルザム

事前評価:9.5
紙からの変更点は以下。
・ウルトラ・シールドプラス(山上0~5枚の任意の枚数をシールド1枚の上に重ねる効果)の廃止に伴い、5枚を固定でシールド化する効果になった
・場を離れた時の盾回収効果が付いた
紙ではプレミアム殿堂(1枚もデッキに入れられない)に指定されている、強力無比なカードです。
とはいえこの措置はカードプールが増えて悪用法が開拓されてからのことなので、登場当初から長い間は目立った活躍のないカードでした。
ただ、デュエプレの実装にあたっては十分すぎるほど強力なカードになってきたと言えそうです。
初めに一つ断言しておきたいのは、このカードの癖が強いことは認めるものの、間違いなく強いカードです。
なぜなら、これまでの「ヘブンズゲート」に対応したブロッカーの中で、確実に5アドバンテージを得るカードは存在しなかったからです。
あの「アガピトス」ですら2,3アドバンテージがいいところなことを踏まえれば、如何に異常なことをしていることがわかります。

同じ水準のアドバンテージを得られるのは、せいぜい「ザーディア」で小型を大量に除去した場合程度でしょう。
「ミルザム」の除去に苦戦するようなビートダウンデッキの場合、「ミルザム」が着地しただけでゲームが決するほどの効果だと言えます。
仮に「ミルザム」が除去された場合も、元のシールド枚数から減っているわけではないのでそもそもデメリットではありませんね。
「ミルザム」2体出しをすることがなければ気になることは少ないと思われます。
ビートダウンデッキに対してはそもそも「ヘブンズ・ゲート」を使った時点で有利ということもあるので、「ヘブンズ・ゲート」の守りの性質だけを見るなら「ミルザム」は不要とも考えられます。
ただし、攻める側は「ヘブンズ・ゲート」から「ミルザム」が出て来ることを想定すると、攻撃トリガーで「ミルザム」を除去できない限りはリーサル+5打点を組むという無理難題を強いられる点は独特な強みです。
本領は「ヘブンズ・ゲート」を攻めで使う場合でしょう。
「ミルザム」+「アガピトス」を展開して、「アガピトス」から「アマリン」を出した場合、場に5打点が揃うことになります。
もちろん「アガピトス」の部分を「パーフェクト・ギャラクシー」に置き換えたりしてもいいのですが、それだけ揃った大型を除去せずに放置できるかと言われれば、たいていのデッキはNOです。
かと言って「ミルザム」を除去すれば5枚の手札を与えることとなり、アドバンテージ差はもちろん、返しに再度「ヘブンズ・ゲート」から展開される恐れがあります。
「ミルザム」の盾回収効果で「パーフェクト・ギャラクシー」のシールド・フォースが解除されるからアンチシナジーとか、ぶっちゃけそんなのどうでもいいってくらいの暴力性がここにはありそうです。
「ミルザム」の素のコストが重いためにほぼ「ヘブンズ・ゲート」専用機となってしまいますが、最近の『天門』は『ドロマー天門』を筆頭にだいぶ攻めの色が強くなってきました。
『ラッカマルコ』なども含めて、『天門』の有用な選択肢となっていくと考えられます。
盾回収の効果についてはメリットともデメリットとも言えませんが、一応「ミルザム」を進化元とすることで回避することが可能です。

「アルファディオス」は相当重いですが、「ミルザム」からマナカーブが繋がる点を見ても「ヴォイジャー」など絡めれば現実的です。
「シータ」に関しても『サバイバー天門』というデッキがあった以上、十分選択肢とできるでしょう。
総合、単体で見るならば、今のデュエプレではやりすぎ・壊れレベルと個人的には評価してしまうカードです。
ということでなぜこんなカードを実装するのか?という方に少し考えを傾けてみます。
①抑止力としての『天門』
10弾環境は周知の通り、『武者』を始点として環境が回っています。

その他『黒緑速攻』や『青抜き4cガントラ』などのデッキも脂がのっているのですが、これらのデッキに有利を取りやすいのが『天門』なんですよね。
細かい説明は省いてかなりざっくりとなりますが、これらは今までずっと環境にいた『天門』がいなくなったことで活躍できているという性質が間違いなくあります。
そして、これらは構造から『天門』以外に大きく不利を取りづらいという特徴も一致してきます。
どうにかして『天門』を環境に戻すことを考えた際、「武者」のパワーを超えつつ、コントロール対面にも有効な札として「ミルザム」が調整されたのでは、と考えることができます。
②それでも『天門』はきつい
特にND環境の話になりますが、今の『天門』は序盤の妨害札をほとんど採用できないため、コンボ系のデッキに好き放題されてしまうという弱点があります。
『白青メカオー』を筆頭に、『自壊ゼロ・フェニックス』などにとってはカモもいいところです。

具体的には、『天門』側の盤面干渉が早くて4ターン目の「魂と記憶の盾」、次は5ターン目の「アガピトス」によるタップキルなので、まあサンドバックにしてくださいと言ってるようなものです。
さらに、この10弾EXでテコ入れが決まっている『ナイト』がいます。

いくら「ミルザム」がドローソースのような役割を果たすとは言え、序盤から重いハンデスを打ち込まれては苦しいものがあります。
『ナイト』がどういったデッキになっていくかはまだわかりませんが、ハンデスでテンポを取りながら「クイーン」「キング」でも出すデッキになるとすれば、『天門』側は不利となりやすいでしょう。
環境に明確な不利対面があるデッキはほぼほぼトップとなり得ないので、極端な相性の立ち位置を10弾EXの『天門』は求められているのかもしれません。
さらに邪推してみると、これらの『天門』に優位を取るデッキが抑止力(場合によっては必要悪)として認められている可能性も見えてきます。
③大味強制効果のリスク
DCGの都合と言えばそれこそ都合のいい解釈ですが、この「ミルザム」も効果が強制で、出せば確実に5枚の山札を消費します。
これがいかにリスクの高いことであるかは、これまでデュエプレをやってきた人たちならばよくわかるでしょう。
山札切れのリスクが極めて高く、「バイオレンス・サンダー」が攻撃できなくなる状況が時たま起こることからも、「ミルザム」を出せる機会がある程度抑制されると考えられます。

9弾環境で一時期見られたように、流行れば「リアデス」の的とされることもあり得るでしょう。

かなり尖った対策とはなってしまいますが、「ガミラタール」で強制的に引っ張り出されると、「ミルザム」の除去時に盾がすべて吹き飛ぶということもあります。

他にも考えられる要因はありますが、ざっとこんなところでしょうか。
「ミルザム」自体は兎にも角にも”出た瞬間に5アド取る”という点で、当分『天門』の採用候補となるカードです。
5アドバンテージを取るというのはグッドスタッフ性の高さとも言い換えられるため、場合によってはマナの伸びるコントロール系にも採用され得るでしょう。
このカードのために環境が規定されるということが後々起こったとしても不思議ではないスペックを持っています。
ベンケイ・バーニング

事前評価:8
デュエプレオリジナルカードとして登場しました。
元々同コストに対になるような効果を持った「ルーレット・ビーム」が存在しましたね。

互換性があるわけではないので単純な比較はできませんが、デュエプレが多色優位なことを鑑みれば「ベンケイ・バーニング」の方が使い勝手はずいぶんと良さそうです。
多色9000というラインは言うまでもなく「キング」が意識されているのでしょう。

このカードが単色なこともあって、「キング」がどうやっても重くのしかかる赤入りのビートダウン系のデッキでは活躍することが大いにありそうです。
序盤も「ガントラ」や「アラゴナイト」「エルカイオウ」などを除去できると考えると、コントロールも含めて広いデッキで採用が検討できそうなカードですね。
多色が入らないデッキならば「ルピア」「アクア・スクリュー」「ジャンボ・アタッカー」などのパワー1000のクリーチャーが入っている場合が多く、腐りづらく汎用性が高いと評価できます。

ちなみにこのカードで除去できない多色クリーチャーは「ボルフェウス・ヘブン」「ゼロ・フェニックス」「ムゲン・イングマール」「バイオレンス・サンダー」「キリン・レガシー」「ペガサス」「ソウル・フェニックス」の計7枚です。
これ以外はすべての多色を除去可能なので、3コストでトリガーを持っている点からもパフォーマンスの高いカードです。
難点があるとすれば、赤単色であることが4色以上のデッキにする際に少々弱みとなる点でしょうか。
それでも基本スペックは高く、長きにわたって採用を考えられるカードだと言えます。
若干の余談ですが、このカードと同じ色・コストを持った汎用クロスギア除去カード「獅子幻獣砲」が紙には存在します。

性能が似通ったオリジナルカードが登場するということは、「ザンゲキ」対策として渇望されたこのカードは実装されないことを暗示しているのかもしれません。
ファントム・ベール

事前評価:5
紙からの変更点はコストが2上がった点です。
同じ元が1コストだったカードには「無限掌」が存在します。

「無限掌」も古いカードでしたが、こちらも基本編の5弾に収録されたカードのため、本記事の最初に紹介した「賢察するエンシェント・ホーン」よりもさらに古いカードです。
5弾と言えばこの後紹介するサバイバーと同期なので、よくわかりますね。
「ファントム・ベール」に代表される強制攻撃効果は、何かとコンボ要因として重宝されます。
デュエプレだと素直な使い方は『カウンターマッドネス』ですね。

場にブロッカーの「リドロ」がいる状態でこのカードを使われると案外取れる対策は少なく、やられて困るということは大いにあるでしょう。
同じカウンター的な要素としては「パーフェクト・アース」も悪くないですね。

これらの用途が素直に感じられてしまうので不思議ですが、より素直な使い方として「ヘブンズ・ゲート」からブロッカーを展開して使用するのも悪くないでしょう。
「バルホルス」と組み合わせてはもちろん、デュエプレ初期の環境で見られた、盤面のにらみ合いをした後で「クエイク・ゲート」で一掃するというシーンを再現することもできそうです。

コントロール同士がにらみ合いになった際、盾からリソースを得る手段としても考えられますね。
この辺りは「ブライゼナーガ」の採用が時たま真剣に考えられたりすることからも、まったくないこととは言えないでしょう。
紙ではトリガー30枚近く入れた『トリガービート』なんかに1,2枚差して、能動的なカウンター起動に利用したりもしましたね。
カードパワー自体は高くないですが、唯一性を持ったカードとして覚えてきましょう。
羅神兵デュアル・又左

事前評価:4
紙からの変更点はありません。
現在出ている範囲ではクロスギアのクロスコストが1となったため、効果を使えれば4マナ5000のSAとしてそこそこの性能として使えます。
「メモリー・アクセラー」「フェアリー・アクセラー」あたりと組み合わせられれば悪くないパフォーマンスを発揮できます。

「ザンゲキ」が常時SAを付与するカードのために折角のアクセルによるSA効果が活きづらいのは残念ですが、パワー5000は序盤で出て来るにしてはかなり高く、バカにならないものがあるでしょう。
「ザンゲキ」を「ビワノシン」に付けて殴っていた人ならこの辺りは少しイメージがつきやすいかもしれません。

「ザンゲキ」に依存しない速攻気味のクロスギアデッキでは使用を検討できるでしょう。
淡泊な性能ゆえに活躍の場は限られるでしょうが、侮ると痛い目を見せられることもありそうです。
聖域の守護者フォボス・エレインγ

事前評価:5
紙からの変更点は、コストが1、パワーが1000下がり、呪文回収がランダムになった点です。
1弾に「レイーラ」という同種のカードが存在しましたが、サバイバーを得たことでほぼ完全上位互換となりましたね。

実はこちらも紙から-1コスト、-1000の修正を受けているので、紙でもデュエプレでも悲しい立ち位置のカードです。
とは言っても、「フォボス・エレイン」に関してもクリーチャー展開が主体の『サバイバー』では少々噛合いの悪い効果だと言えます。
「ヘブンズ・ゲート」と併せた『サバイバー天門』が存在したことから、そちらでの採用は一応検討できるでしょう。
「ダーク・ティアラ」が強力なハンデス効果を持っていることから、白のタップ系呪文をこのカードで回収するのも悪くなく、白黒緑の『ネクラサバイバー』など検討することはできそうです。

先に紹介していた「ミルザム」も『サバイバー天門』とは相性が良さそうなので、色々と妄想が膨らみますね。
黒で考えるならば「デーモン・ハンド」などを採用して、現環境相性が悪い『武者』に対して対策を打つことも考えられそうです。
その他に有用な使い方は現状思いつきませんが、単純に「フェアリー・ライフ」などの後半腐るカードを回収して、ドローの質を高める使い道もあるでしょう。
クリーチャー主体のために1コスト軽い「シェル・ファクトリー」が基本は優先されるでしょうが、こちらも決して悪くはない性能を持っていると言えます。
ゼータ・トゥレイト

事前評価:8
紙からの変更点は以下。
・2コスト下がった
・パワーが2000下がった
・踏み倒し効果が付いた
パワーが下がってしまって「武者」の圏内になってしまったのは残念ですが、2コストの軽減と踏み倒し効果はかなりの強化を得たと言えます。
サバイバーの順調な動きを考えた場合、「ライフ」→「シェル・ファクトリー」→「シェル・ファクトリー」or「フォボス・エレイン」→「ゼータ」ですかね。
先行でもこれで5コスト以下のサバイバーが出せるので、リソースを確保しながら一気に盤面展開をしていくことができます。
アドバンテージの稼ぎ方はかなりのもので、たいていの場合で優勢になることは間違いないでしょう。
後攻だと強力な「キング・ムー」も圏内になるので、回った時の押し付け力はかなり上がると考えられます。

「ゼータ」が進化クリーチャーなことを利用して攻撃トリガー付与のサバイバーを出してもいいでしょうし、「バルス」を出して『武者』対面の対策を打つこともできます。

踏み倒し時には当然コストを払っていないので、デッキのメインでないカラーのサバイバーをタッチで差すことも考えられそうです。
冷静に6コストから3打点以上を作るのは、進化とは言えかなりのパワーを感じさせますね。
この手のカードにありがちな進化元が除去され続けられることやハンデスに対しても「グレイブ・ワーム」などの対策手段があり、しぶとく押し付けていくことができると想像されます。
性能だけ見るならばSRに匹敵するほどのパワーを持ったカードです。
個人的には詰め込みまくっていた「シータ・トゥレイト」に並ぶレベルだと感じられますね。
難点は、果たして今の『サバイバー』にこのカードを割く枠があるのだろうか?という点に尽きます。

初動枠と5コストのあたりは多少自由枠とは言えますが、フィニッシャーになってくる部分を中心になかなか抜きがたい優秀なカードが現状でも多いです。
「ゼータ」は環境を見ながら枚数調整されていくカードになるかと思われますが、選択肢としてあるには贅沢すぎるほどですね。
元々かなりの素質を持ったデッキなだけに、クロスギアがある程度対策されていく10弾EXの環境では再度環境浮上も十分に考えられそうです。
まとめ
①の記事に比べれば少し大人しいカードが多いと感じられましたが、「ミルザム」は一つ抜けた強さに感じられますね。
ちょっと強い強いと言いすぎている気もしますが、”大味”というのがより厳密でしょうか。
これは「ゼータ」にも少し感じているところで、環境を大きく壊す因子となり得そうな雑な調整に感じられるのは懸念点ですね。
とはいえ、この10弾環境で不遇だった『天門』や『サバイバー』が復権することには少なからず期待を寄せたいです。
杞憂に終わってくれるよいのですが…
よろしければ次回の③もどうぞ。
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
