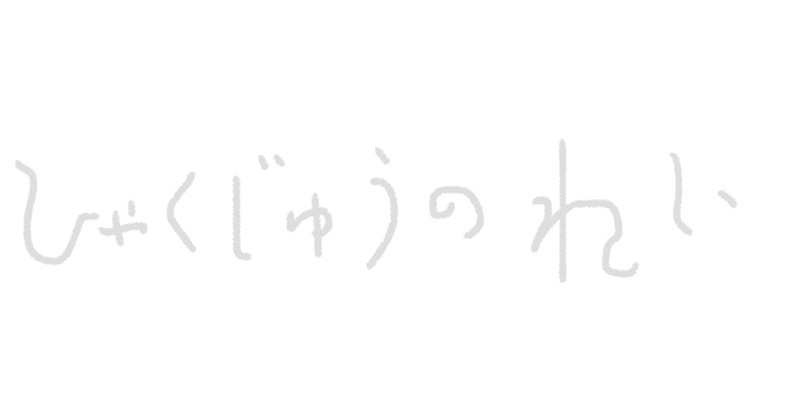
110の0
私が死んだという知らせを受けた。
ある昼下がり、急に鳴り出したスマホの着信音を止めようと電話に出ると、聞き覚えのない声が聞こえてきた。
「〇〇さんですか」
「あ…はい」
「〇〇さんはお亡くなりになりました」
男女どちらともつかない、あどけない声の相手はそう告げた。〇〇という氏名は私のことで、電話に出た本人は今、紛れもなく息をしている。しかし相手は、私が電話に出たことを確認した上で私は死んだと応えた。
「そうですか」
明らかに矛盾した状況だが、気がつくと口先で相槌を打っていた。ひとまず何でも受け入れてしまういつもの悪い癖だ。間髪いれずに相手は続けた。
「週末に××ホールにて葬儀が行われますので連絡いたしました。それでは失礼します」
電話はすぐに切れた。拍子抜けしてしまった。嘘ならば悪い冗談で済む話だが、相手は淡々とした口調で至って真面目な様子だった。いたずら電話とはあまり思えない。耳にはまだ相手の声の響きが生々しく残っていた。
本当に私は死んでいるのだろうか?
手に持ったスマホの黒い画面には私の影が映っている。もしかすると私は死んでいて、本当は生きている夢を見ているだけなのだろうか……。にわかには信じがたいが、常日頃からぼんやりと抱えている「死にたい」という欲望を達成したのかと思うと、ふっと気分が高揚した。スマホを持つ手を胸に近づける。胸が高鳴っている時点で私が死んでいる可能性などないはずなのに、電話口の言葉を信じたいがために、一旦状況を確認することにした。病気や老衰の可能性もない自身の死因なら、スマホで検索すれば何らかのニュースが出てくるかもしれない。意外と珍しい漢字の名前は、こういう時に便利だ。
検索結果の2件目に、「O県の川で死亡事故」という記事がヒットした。O県の新聞のネット記事なので信憑性は高いだろう。
「10日午前9時頃、O県A川で遺体が発見された。調査によると身元はO市在住の〇〇さん(23)と判明し…」
確かに私はO市在住の23歳だ。死因は溺死で、橋の老朽化と雨による増水が災いしたらしい。入念に準備された工作でない限り、この記事はきっと本物だろう。〇〇という人間は死んだのだ。文章を読んで思考して、指を動かしてスクロールすることができる自身の状況よりも、例え小さな記事であれ、インターネット上に公表された社会的な「私の死」は、とても強い力を持っていた。私は死んだのだ。
晴れやかな気分だった。窓から射す光は、ホコリをちらちら瞬かせながら、私の汚い部屋を露わにした。死者は「何かすること」ができないため、「何かすること」を強いられない。死者にとって当たり前の常況をとても素晴らしく思った。軽やかな足取りで部屋を出て、外出の準備をした。週末にあるという自分の葬儀に向けてやりたいことがある。くたびれた靴に踵をしっかりと踏み入れて、外へ出た。
日差しは眩しく肌に照りつけた。〇〇が死んだなら、今外を歩いている私は何なのだろう。これが幽霊というものだろうか。けれど私は肉体を持っていて、半袖からはみ出た腕には日の照りつける感覚がある。無色透明の幽霊というのは都市伝説で、実は生きた人間とさして変わらないのかもしれない。逆に他人に自分はどう見えているのだろう。通行人は特にこちらを見向きもせず、ぶつかってくることもない。人通りの少ない道なので定かではないが、皆と同じように歩けているような気がした。
行き先まで吸い込まれるように走っていく車、少し首の長い少女、しゅわしゅわと鳴く蝉の声、貼り付けたようなとぼけ顔をした俳優のポスター、道中に見かけたものがすべて夢のように思えた。今までなぜこれを現実だと信じられたのだろう。夢だとすれば合点がいくくらい、この世は不思議なことで溢れていた。

ショッピングモールはいつもより人で賑わっている。一階の端の方に輸入食品売場とアイスクリーム屋があり、その向かいに花屋がある。今まで前を通るばかりで、薄暗い店内に入るのは初めてだった。ふらふらと白い花を探していると、隅の方で新聞紙に包まれたスイセンに目が止まった。白い花びらの中に、黄色いラッパのような筒をたずさえた姿は、この世を夢だと証明しているような不思議な形に見えた。小さな花を2つ咲かせた一本を手に取り、レジに並んだ。店員に金銭を渡すと、花は滞りなくフィルムに包まれてゆき、最終的に私の手に渡された。生きた人間と変わらない対応を受けた私は、満足して家へ帰った。
週末が訪れた。葬儀の時間は指定されなかったが、私は朝早くに××ホールへと向かった。喪服にマスクを付けて帽子を深く被り、なるべく個人を特定できないような格好をした。自分の葬儀に参列するというのだから、周囲の人間にとって私はどのような立場に当たるのか分からない。けれど純粋に自分の葬儀には興味があった。死にたいと思う程度には私のことは好きになれなかったが、花を手向ける程度には私の魂を受け持った身体に恩義を感じていた。何不自由なく歩くことができて、話すことができた。会場に着くとすでに告別式の受付が始まっていた。受付には知らない人が立っている。数千円を包んだ香典を鞄から取り出して、受付の人に手渡した。
「この度は……」
早口にそう囁きながら、私は深く頭を下げた。受付の人も礼をしたので、互いに顔を上げる前に、その場を重い足取りで、ゆるやかに通り過ぎた。顔を見られないようにするのは思ったより上手くできそうだった。
受付を過ぎると、廊下の遠くの方に喪服を着た親族が集まっているのが見えた。遠くからでも、小さくうごめく黒い塊一つ一つが誰だか分かる。私もあの一族の一人なのだなと思った。急な事故死なのによく集まったものだと思う。
23歳の葬儀は小規模で、部屋は20人弱が入る程度の大きさだった。遺影には紛れもなく私の顔が写っている。不思議な気分だった。棺の中にはきっと自分の死体があるのだろう。今この世の中にとっては動いている私の身体の方が可笑しな存在だが、私にとっては目の前にある棺の中身の方が、奇妙で恐ろしい存在だった。ネットの情報より何より「私の死」を決定づけるものだ。死は遠くにあるから望めるもので、目の前にするとやはり恐怖が襲ってくる。まだ式は始まる前で辺りは誰もいない。私は棺の前へ行き、先日買った花だけを棺の上に置いた。自分との別れはこれで十分だ。私は足早に会場を後にした。

熱気を帯びた空気が腹のあたりから迫り上がってくる。少しでも早く会場から離れようと、早足で外を歩いた。汗は次々と流れ出るし、いつもより軽やかに足が動く。照りつける日差しで頭がぼんやりとして、考え事をしなければいつしか倒れてしまいそうだった。
歩きながら頭の中で過去の記憶をぐるぐると巡らせていると、ふと小さな頃に留守番をしたことを思い出した。家で一人留守番をしていて退屈した私は、受話器を取り、適当な番号を打ってどこかに電話を掛けたのだ。
どこに掛かったのか、電話の相手は出て話をしたのか、私は何かを聞いて話をしたのか、何も覚えていない。ただその後は、どこか後ろめたさを感じて、家族が帰ってくるまで押し入れの中に隠れていたことだけ覚えている。その日に家族がお土産にくれたクッキーは、ぽろぽろとしてしょっぱかったが、それがショートブレッドという美味しいお菓子だと知ったのは高校生くらいの頃だ。記憶の中にあった塩気の味が、じんわりと口の中に広がる。同時に私の口の中に勢いよく水が押し寄せてきた。
次の瞬間、私は水の中にいた。腕も顔も足の先も、すべて水の中にある。咄嗟に上を見上げると、水中の小さなごみ屑越しに、水面のような光の影が遠くに見えた。後はもうかすかな青い光だけが頼りで、後はもう息が、苦しい。頭痛と吐き気が速まった鼓動のリズムで押し寄せてくる。何が起きたのか分からないが、口の中に入り込もうとする水と、腹の中のものを出そうとする身体の間でしばらくせめぎ合った。10分ほど経った後、喉元に衝撃が走り、耐え切れず口を開いた。吐いたのは、ショートブレッドの包装紙だった。いつの間に口に入れていたのだろう。赤いギンガムチェックの柄も水中では暗い藍色で、包装紙の内側の銀色だけが輝きながら遠くへ流れていった。これで楽になるかと思ったが、吐き気は治らず、ショートブレッドの粉のようなものも吐いた。
吐き切った一瞬に訪れる相対的快楽だけが救いだ。
次の波が来た。水中にいるのに、水の流れでなく吐き気の波に襲われているのが自分でも不可解に思う。咽せながらも何とか吐くと、唇のふちにぬるりとした感触が走った。目を開けると吐き出したのは、カメレオンだった。爬虫類にはあまり詳しくないが、この突出した丸い目はおそらくカメレオンだろう。ぬっとりとした皮膚は、肉を支えて少し重たそうに垂れ下がって水中に浮いている。どこかで見たことがあると思ったら、こいつはガチャポンのカメレオンだ。かつて家から少し離れたスーパーの前にあったガチャポンで、買い物に行くごとにガチャを回して、カメレオンのゴム人形を色違いで揃えるのにハマっていた。あのおもちゃは親指に満たない小さなサイズだけど、目の前にいるのはおよそ兎と同じくらいの大きさまで膨れ上がっている。カメレオンは長い尻尾を内側に巻き込んで、苦しそうに身体を丸めて下へ下へと沈んでいった。助けようと手を差し伸べる間もなく、次の吐き気が襲ってきた。

次に吐き出したのは、昔の学校の先生だった。好きでも嫌いでもない、顔を見なければ二度と思い出すこともなかっただろう40代の先生。よりによってなぜこの人物なのか、ゆらゆらとゆらめいて今にも消えそうになっている。そのまま続けて吐き出したのは、嫌いだった同級生だ。他人の悪口をよく言う子だった。なぜ苦しみながらこの子を思い出さねばならないのだろう。私の身体の中のどこかに彼らがいたことがおぞましくて嫌になる。彼らは水の流れに乗って、幻影のようにどこかへ消えていった。
その後も近所に住む猫の尻尾や、いつか割ったカップの陶片、昔捨てたスケッチブックなどを吐いた。もう何度も吐くことで、胸のあたりがだいぶ疲れていた。水中はさらに暗くなり、肌に接触する水が冷たいことにやっと気がついた。早く楽になりたい。次の吐き気が襲ってきた。喉が圧迫される感覚は何度経験しても苦しくて、慣れることはない。吐き出したのは、自宅の枕元で普段使っているスタンドライトだった。細長いネックの先に暖色系の電球を灯らせて、静かにこちらを照らしてくる。眩しくてすぐにでも目を瞑りそうだったが、海の奥へと深く沈んでいくスタンドライトは、案外きれいだった。

ばつばつと打ち当たる雨は冷たくて、ぞくぞくと自分の皮膚を濡らしていした。空に暗色に立ち込める雲は恐ろしいから、せめて白い雪を降らせればいいのにと思う。背中に感じる砂の温度はかろうじて温かくて、私よりも人間らしいなと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
