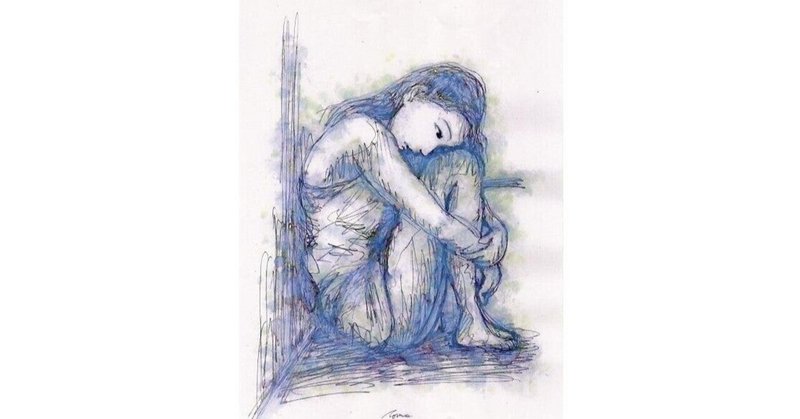
【ネタバレあり】書籍紹介『見えない違い 私はアスペルガー』
私たちは皆、規範という首枷に拘束されながら生きていて、尊敬の念と寛大さを持つことができずにいます。あなたたちはその首枷を粉々にすることができるのです。
あなたたちの”違い”は問題ではありません。それはむしろ答えなのです。
その”違い”は、正常性という病にかかった私たちの社会の特効薬なのです。
本書は、あなたたち(=発達障害当事者)に向けた献辞から始まる。かわいらしいカートゥーン調の絵柄に、明快な画面構成で大変読みやすい一冊だ。特に女性の発達障害を理解するうえで、その入門書としては最適かもしれない。
舞台は現代のフランス。主人公は27歳のOL、マルグリットだ。動物たちや恋人に囲まれ、一見幸福な生活を送っている彼女だが、時折感じる「違和感」にずっと苛まれている。
例えば、同僚たちとの食事や会話。
マルグリットは同僚たちとの雑談が苦手だ。そもそも雑談をする意義がわからないし、話自体にも興味がないうえに会話のスピードについていけない。食べ物の好き嫌いが激しい彼女には、ランチを他人と一緒にとることが難しいし、感覚過敏もあることから華やかな服装が嫌い。
仕事ぶりに問題なしと評価される一方、同僚たちからは白い目で見られ、とうとう社長からは「人間関係の面では問題があり、人事評価に影響しかねない」と注意を受けてしまう。
困り感は私生活にも及ぶ。
容姿端麗なマルグリットは、隣人の男性から好意を寄せられているが、そのことに気づけない。「今度語学を教えにウチに来てほしい」と誘われ、言葉通りに受け取ってしまい、性被害を受ける。
これは女性の発達障害でも特に取りざたされることの多い問題だ。
本書は気軽に読めるように配慮がされているようで、幸いマルグリットの精神に大きな傷を残すことはないのだが、実際には大きなトラブルになってしまうことも多いはずだ。
こういった経緯から、マルグリットは自分自身の”異質性”に徐々に気づいていく。ネットで調べた結果、出てきたキーワードが「自閉症」だった。
ここで速やかに診断に結び付くかと思いきや、そこからが長い時間の戦い。信頼できる精神科医を探すのに手間取ってしまう。今まで何人もの医師に生きづらさを訴えてきた彼女だが、発達障害に言及されることはなかった。あらためて「自分はアスペルガーではないか」と新しい医師に相談するも、「発達障害者は目をあわせることができない。あなたは違う」と診断を受けることができなかった。
私自身、当事者としてこのあたりはとてもリアルに感じた。
実は私自身、初診の医師には発達障害ではないと診断を断られた経緯がある。このあたりは海外も事情が同じようで、発達障害に対する知見は医師の間で大きな差があるようだ。
ようやく診断を受け「発達障害者」として新たな人生が始まったと歓喜するマルグリット。次に彼女は訪れたのは、いわゆる「当事者会」であった。
様々な年齢、様々な経緯から当事者会に集まった面々だが、ここで印象的なのが、診断の受け止め方が人ぞれぞれだということだ。
診断を喜ぶマルグリットのような人がいる一方、50歳の男性ジェロームは隈の浮いた目でこう独白する。
それまで他の人と違う理由をしろうとしてきて、その答えが出たわけです。死刑囚になった気がしました…
この複雑な気持ちはよくわかる。
以前、障害受容について書いたこの記事でも取り上げたが、誰もかれもが「さあ診断がおりた! 次の新たな人生へ!」と舵を切れるわけではない。それまでに起こった辛い出来事、積み上げて無駄になった努力。そういうものを自分の中で整理しなければならない。
ジェロームは50歳の男性だ。長い間一人でもがき苦しんだことだろう。この点、本作はリアルに現実を切り取っていると思う。
さて、話はマルグリットへと戻る。
診断を受けた後、周囲の反応は冷たい。
でもさ、結局誰もが少しは自閉症なんじゃない?
ワクチンが原因だ そうじゃないか!
自閉症ってよだれをたらしたり、壁に頭をぶつけたりする人のことでしょ?
全然普通そうじゃん!
調べてごらん。たぶん治る病気だよ
そんなの言い訳にするなよ!
あなた、ちょっと内気なだけよ
専門外の総合医には「発達障害じゃない」と否定され、友人からは発達障害を持つ著名な作家と比べられる。恋人から誘われた飲み会を断ると「はいはい、”アスペルガー”だもんな」と一蹴。診断を受けてからも、「生身の彼女そのもの」をきちんと見てくれる人がいないのだ。
深く傷つき、一人涙するマルグリット。恋人とは結局別れることになってしまう。
これは私自身の経験談でもあるが、確定診断そのものは、決して生きやすさに即直結するものではない。むしろ、場合によっては周囲との摩擦が表面化することもある。
特に大人になるまでわからなかった軽度の発達障害に関しては、周囲が適切な理解をするようになるまで、長い長い時間を要する。残念ながら理解されず、関係が引き裂かれてしまうことだってあるだろう。それだけではなく、新しく出会う人たちに関しても、皮肉にも診断が新たな「障害」になってしまうことがある。
障害名に怯えたか、恐々と接してくる人。子供のように扱ってくる人。障害名は決してその人の人となりを表すアイコンなどではないのにも関わらず……。
しかし、一方で新たな進展もある。マルグリットは「社会心理学で博士論文をとる」という目標を見つけ、それまでとは違う交友関係を得る。
同じ発達障害の人々はもちろん、強迫性障害を持つパン屋さんまで。彼女には今まで見えなかった生きづらさを抱えている人々のことが、理解できるようになっていた。
そして彼女は今まで経験してきたことを、漫画という新しいメディアで訴えていくことを思い立つ。それが本書。主人公・マルグリットは作者、ジュリー・ダシェその人である。
……というのがこの本のオチだ。
実体験に基づいた発達障害者の生きづらさ。そして、巻末に収録された医学的な根拠に基づいた発達障害の説明は、非常に明快なものである。
すべて読み切るのに1時間ほどかからない、手軽な読み物として、ぜひ発達障害を知らない層にも届いてほしい一冊だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
