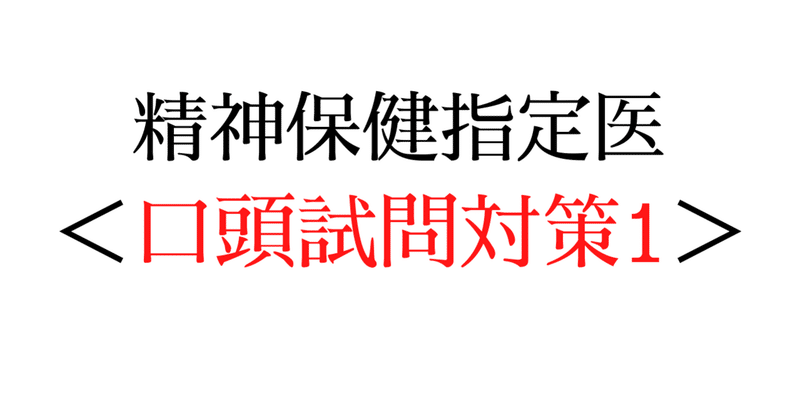
精神保健指定医新規申請における口頭試問対策1<必勝の準備> ***前日と当日には必ず読んでください***
精神保健指定医新規申請における口頭試問対策1<必勝の準備>
***前日と当日には必ず読んでください***
【はじめに】
お読み下さり、誠にありがとうございます。こちらをお読み下さる先生は、きっと症例レポートに合格され、口頭試問に進まれた方、あるいはその予定の方と思います。症例レポートの合格、誠におめでとうございます。心から、貴方の合格を喜びます。指定医の症例レポートは、専門医の症例レポートと比較し、提出数は少ないものの記載が本当に大変だったことと思います。普段の忙しい診療時間の合間、短いお昼の休憩の合間、業務終了後、病院に残り黙々とレポート作成に打ち込んだものと思います。深夜、日付が変わるまで、連日連夜の作業もあったものと思います。それを乗り越えられて、口頭試問に進まれたのです。あなたの努力に心からの敬意と尊敬を表します。合格まであと少しです。口頭試問という壁を乗り越えることができたなら、あなたは立派な指定医になれるのです。そして、患者様の人権に十分配慮した、立派な精神科医に一歩近づくことができるのです。もう少しです。大丈夫です。症例レポートを乗り越えたあなたなのです。できないわけがありません。私自身、事情があって、地方都市の地方病院に勤務しながら、口頭試問に臨みました。大都市の大学病院に所属し、何十人という先輩や同僚にサポートを受け、情報共有しながら試験に臨む同じ学年の精神科レジデントと比較し、様々な点で苦労しました。そういったレジデントの先生方が羨ましく、心が折れそうになったこともありました。私と同じような苦労をしないでほしい。苦労をするならば、その苦労は勉強と診療技術の研鑽にあてるべきと考えます。皆様が正しい勉強法で、きちんと合格されますよう、心から応援しております。あともうちょっと!大丈夫!がんばれ!がんばれ!がんばれ!
ーーー
【口頭試問を甘く考えないでください】
→これを一読すれば、大丈夫。
甘く考えていると、本番で焦ります。合格不合格に関わらず、冷や汗かくこと間違いないです。「えっ!こんなこと聞かれるの?」「えっ!なにこのガチな雰囲気!!!聞いてないんだけど!」「え!!!」
複数名の面接官を前に、焦ってしまうと、話せることも話せなくなってしまいます。そうなって欲しくない…(私のように…)。そんな想いでお伝えいたします。
【会場と雰囲気】
・会場は市街地のオフィスビルの一角となることが多い
実際に行くと、場所が非常に分かりにくいところである可能性があります。
早めに行って、必ず場所を確認ください。また、近くのカフェに入ると、明らかに受験生と思しき方や、試験官の方が休憩で入っていることがあります(実際に会場にいました!)。大声で試験内容について話していると、心証を悪くするので、試験官がいるかもしれないことに注意ください。
・試験会場の雰囲気はガチ!
受付や受験会場待合内は、それでもまだ「ふんわりとした雰囲気」です。ほぼ全員スーツです。私服姿のやや高齢の方もいますが、それでもジャケットは着用されています。携帯でゲームをしている方や、iPadで自分の書いたレポートを読んでいる方、付箋を大量に貼ったファイルを黙々と読んでいる方、中央法規出版の「精神保健福祉法詳解」(分厚い本)を読んでいる方、様々です。数十人は同じ部屋にいます。
・実際の試験を受けるために会場を移動する
そこから個別の部屋に、グループ毎に案内されます。「こちらの部屋の前でお待ちください」「案内がありましたら、中にお一人でお入りください」「お入りになったら、中の者の案内に従ってください」そう言われ、緊張度が高まります。
・中に入ると、試験官は約3名、超ガチ。
「それでは第@回@年、法第@条に基づく、精神保健指定医新規申請のための口頭試問を開始いたします」とアナウンスされ、ガチな試問が始まります。尚、ビデオにて撮影もされます。試験官で主な質問者は一人、その他追加する質問者一人。一人は観察者でした。3者の一致で試問開始され、3者の一致(3人で頷く様子)で試問が終わります。
【実際の試問】
・事前提出レポートの完成度の高さによって、試問時間/質問の数が異なります
<Aさん>
Aさんは事前のレポートは完璧の方。児童症例、措置症例等全ての条件もレポートに入っておりました。Aさんの場合は、「第@症例についての経過を聞かせてください」+ 基本共通問題(後述)1題 合計5分で試問終了となりました。
<Bさん>
Bさんは事前のレポートに不足がある方。児童症例、措置症例、欠けているものがあります。Bさんの場合は、質問のフルコース。合計15分以上の試問でした。6〜8個ほどの質問数でした。終了して部屋を出ると、隣の部屋から出てきた受験者は、次の列の方でした。
<大事な点>
事前に提出したレポートに不備がある/欠けている症例や条件がある。そんな場合でも、「=不合格」には全くなりません。大丈夫です。すでに、口頭試問に進まれたあなたは、レポートは合格しています。そう考えて大丈夫です。
「もう、ここに致命的なミスがあるからダメだ」「ここに変なことを書いてしまった」「自分には@@の症例がないから不合格だ」そう思い込まれ、悲観する方がおりますが、その必要は全くありません。あなたがミスと思っていても、それが「指定医認定」の上で、重要でない場合が多々あります。また、変なことを書いても、不合格基準にはなりません。症例の欠落/条件の欠落で落ちる場合は、すでに口頭試問前で落ちており、口頭試問を受験できていません。あなたが、口頭試問に進めたということは、「=レポートはO K」と考えて、自信を持って受験ください。そして、万一指摘を受けた場合に備えて、事前に対策の準備を行いましょう。
・試験日程について
試験日程で「中日の午後の受験者は、あまり出来が良くない人」等の情報は間違いです。試験日程で、合格不合格の確率の差、試問内容の厳しさの差はありません。そちらも気にしなくて大丈夫です。どの日程でも、きちんと合格はできます。
【想定問答対応集】
・「第@症例の経過を教えてください」
解説)まず大前提として、自分の経験したレポートについては、しっかり理解/記憶
ここから先は
¥ 1,000
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
