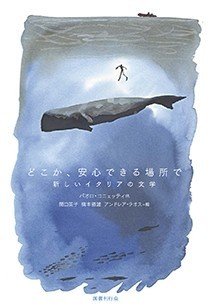道で人を助ける方法
目の前で大きな音がして人が前のめりに倒れた。地面に四つ這いになって倒れたままなかなか立てないでいるのは小柄な70代くらいの女性だった。周りを歩いていた何人かは振り返って何が起こったか確認しようとし、私を含めた何人かは駆け寄る。40代くらいの背の高い男性が後ろから助けおこす。私も仕事(病院勤務)から帰る途中で、そこは車やバイクも通る信号がない裏路地の道ばただった。倒れた女性は助けおこされているがすぐには自分でしっかりと立てず支えられながら膝が折れてゆらゆらしている。遠くから原付がこちらに走って来るのが見えたので、ちょっと寄りましょう、と誘導して駆け寄った何人かで協力して路肩に座らせると、ぜいぜいと肩で息をした。息をするたびに喘息のときのような末梢気道の狭窄音がかすかに聞こえ、ただ転んだだけでなく体調が悪いのではないかということがわかる。大丈夫ですか、ケガしてないですか、手を出してみてください。眼鏡は無事ですか。いくつか質問するが、「だい、大丈夫、すみません、大丈夫、だから、」と息も絶え絶えに話している。息切れがあるとき、文節ごとにしかしゃべれないのは息切れが強いことを示している。あまりよくないしるしだ。「落ち着くまでそばにいますよ」と声に出して言うと、支えてくれた男性や周りで心配そうにようすを見ていた人たちがスッと退いて、それぞれまた自分の帰路につきだす。あんまり寄ってたかって囲むとかわいそうな感じがしたのだと思う。このあと用事もなくて家に帰るだけだったので、病院とか警察に連れていくのも別にいいかと思いながら「咳していますね。苦しくないですか」と聞くと「風邪を、ひいてて……」と彼女は答えた。「おうち、どこですか。近くですか」と聞くと、「いいえ、遠くて……」と電車で30分ほどかかる地名を上げる。家まで送ろうかな、どうしようかな、と思い、「どうやって帰りますか」と聞いていると、駆け寄った人の中で私と一緒にのこった、服装から(ワンマイルウェアっぽい感じの服装だった)たぶんこのあたりの地元に住んでいると思しき70代の女性が話しかけてきて「シルバーパス持ってるんでしょう。バスで帰るの?」と親しげに話しかけてきた。それで、ちょっと緊張がやわらいで、倒れていた彼女は「うん、うん」と頷いた。「バスで帰れば、足は大丈夫だから」「膝が悪くて」とすこしスムーズに話せるようになっている。話しかけてきた女性が「家へ帰れる?」とまた聞いて「停留所まで一緒に行きますよ」と私も声をかけたのだが、倒れていた彼女は「大丈夫です。ほんとうにありがとう。ごめんなさいね」「一人で行けそうだから、ごめんなさい」と、なかば「ごめんなさい」を繰り返し、かかわらないでほしいのかなと思うくらい、こちらの申し出を固辞していた。それで、私も、自分が彼女にとって迷惑なことをしているような気持ちになってきて、大丈夫かなあと思いながら、じゃあ……お気をつけて、などと言って立ち上がった。話しかけてきた彼女と同世代の女性は「困ったら周りに助けを求めるんだよ。頼ってね。気をつけてね」と声をかけている。後ろ髪をひかれながら、何度か振り返ってその場を去ったが、あたりもすっかり暗くなってしまって彼女の様子は振り返っても立ち上がれたのかどうか見えなかった。
仕事でいつも「大丈夫だから」と我慢する患者さんをみている。がんの痛みを自分だけのものにして他に話さない人がいる。「あなたの痛みがわかる」とは言えないまでも、表情を見て、身体を観察し、触れて、画像検査をして病態を分析すれば「あなたの痛みが理解できる」とは言えるので、「またまた、本当は困ってるんでしょう」と混ぜ返しながら、本当の困りごとを聞いていく。この人には話せるとか、迷惑をかけてもいい(別に迷惑ではないけれども)と思ってもらえるのが治療の始まりの瞬間なのだ。そこが一番の難所であることを知っている。
道で人を助ける方法がなかった。助けられなかったと思った。倒れていた彼女は明らかに強い息切れを起こしていた。ヒューヒューと喘いでいて、気管支喘息なのか、年齢からすると心不全なのか、それとも別のなにかなのか、とにかく風邪だけであんなふうにはならないし、風邪の経過で咳喘息になったとしても治療は必要で、それをまだ受けていない感じだった。警戒心を抱かせたか、道で知らない人に迷惑をかけている感じを過剰に感じさせてしまって、結局彼女を安心できない場所で一人にしてしまった。私と一緒に最後まで残り声をかけてくれた同世代の女性の声のかけ方は見事で、私の声かけと違って知らない同士でタメ口なのだけど、ちかしくてもともと友達だったような話しかけかたがとても上手だった。「周りに頼るんだよ」という明快な一言が強いメッセージとして私に残っていた。倒れていた彼女にも残っているといいのだけど、どうかな。
奇妙なことだけど、最近読んだ本にこれと同じシチュエーションがあったことを帰る途中で紐をたぐるように思い出した。ダリオ・ヴォルトリーニというイタリアの小説家の『エリザベス』という、小説家の実際の経験をもとにした短編だ。深夜のトリノの街角で、主人公は明らかに不法滞在者である若いナイジェリア人の女性と遭遇する。彼女は道ばたで腹部の痛みをこらえていて、イタリア人白人男性の「僕」は見過ごすことができず、押し問答のすえ救急外来に連れていく。彼はなんの関わりもない彼女を助けた。同じところまではいけなかったなと思った。
『どこか、安心できる場所で 新しいイタリアの文学』国書刊行会
助けを断る人をどうやって助けたらいいのだろうか。倒れていた彼女と同じ年代のこれまで関わった患者さんのことを思い出す。がんを持っている。余命数ヶ月である。もしくはそのような家族がいて自宅で自分自身が介護をしている。高齢にともなう身体の変化がある。膝が悪い。腰が悪い。不安をかかえている。経済的に困窮している。寒い部屋で寝ている。コンビニおでんの大根とはんぺんを買って一食にしている。福祉のサポートが必要なのに受けられていない。病院受診が必要なのに受けられていない。家族と疎遠である。不仲である。暴力を受けている。長年連れ添った連れ合いが最近亡くなった。ひとりぼっちである。いろんな困っている人がいた。私が踏み込んで聞くまでそのことを誰にも話せていない人が多かった。もちろん彼女がそうだとは限らない。家に帰ったら家族がいて関係のよい子供や孫に囲まれて食事もあって薬もあって不自由ない生活をしているのかもしれない。すべて杞憂だといい。
道で人を助ける方法がわからなかった。