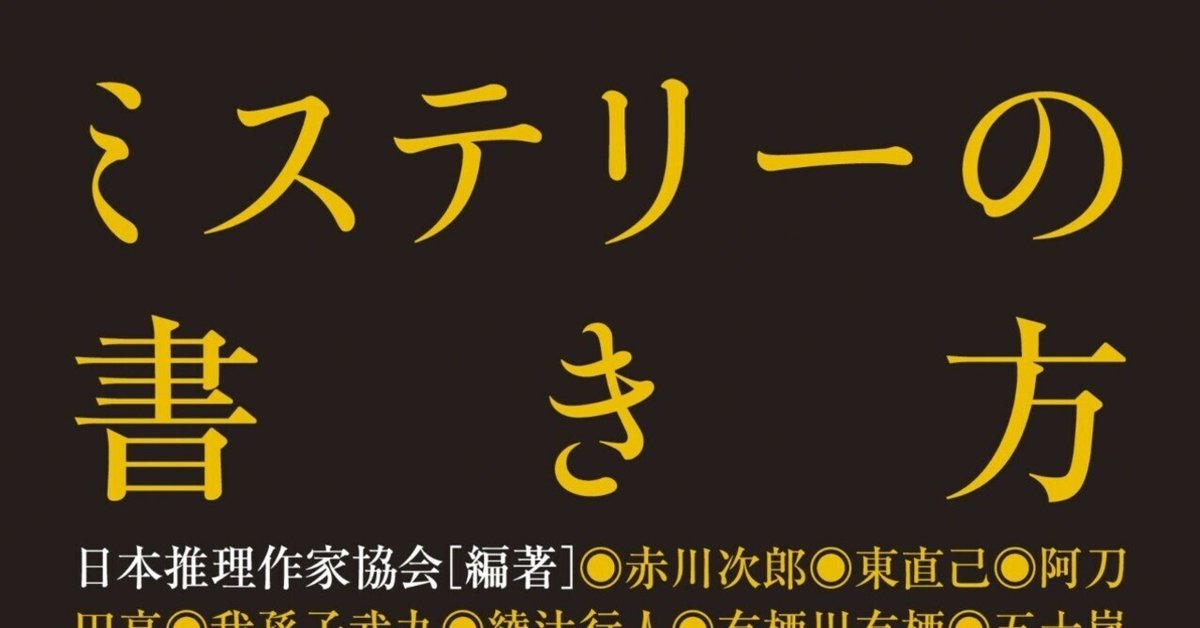
ミステリーの書き方 日本推理作家協会[編著]
ミステリーと純文学のちがい 森村誠一
文章は書けば書くほど上達する。私はまず、好きな作家の文章の模倣から始めて文体を積み上げていった。文体とは、その作者独特の個性的な文章である。作者独自の誤用や誤字も、文体に含まれる。
作家は個人の名前によって、多数の読者にアピールしなければならない。署名を入れなくとも、だれの文章ということがわかるような文体を練り上げなければならない。
オリジナリティがあるアイデアの探し方 東野圭吾
本もそうです。僕は決してたくさんの本は読んでいない。ただ読んだ本は、ミステリーだろうが何だろうが、何度も何度も読み返すようにしているんです。たとえ一回しか読まない本にしても、それこそ一日一ページとか、時間をかけて読む。ストーリーだけではなくて、読みながら自分が何を思ったかを大切にしているわけです。
クラシックに学ぶ 五十嵐貴久
作家に限った話ではなく、どのような分野のクリエーターでも、彼らが目指している地平線には、今までなかった新しい何かを作りたいというような、一種の野望があると思います。
もっと言いますと、そういう強い意志がない者は、あんまりクリエーターを目指すべきではないのではないか、とも思います。
ですが、せっかく山のようにあるテキストを使わないというのも、これは資源の無駄といいますか、非常にモッタイナイ気がします。
優れた映画、コミックなどを何度でも見返し読み返し、そこから何かを学び取る、というのはどれほど独創力に富んだクリエーターでも(無意識であっても)やっていることであり、それは決して「パクリ」というような次元の低いものではないと思います。
語り手の設定 北村薫
地上から、こう、空間十センチとか浮けるってことですね。
実際の自分ではないから自由に歩ける感じがします。”語りは騙り”だと言いますけど、フィクションの羽を広げるために、やっぱり現実と違ったところにワンクッション置くと、語りやすくなる。
太宰治「駈込み訴え」・・・もともと女性の一人称が上手な作家
自分が小説を書きはじめたときは、女性という、ふだんの自分とは違う足場を設けることが、創作の翼を広げるという意味では書きやすかったですね。
登場人物に生きた個性を与えるには 柴田よしき
非常によく見られる錯覚のひとつが、人物の服装や髪型を描くことで人物を「描き分けた」と思い込むことだ。
新人賞の応募作では普通に見られる失敗例が、とにかく出て来る人、まずは髪型とか服装、靴やバッグ、女性であれば口紅の色だとかマニキュアの色など、律儀に外見の描写が細かくなされている状態。
書いている本人は、一所懸命調べた最近流行の髪型や服装、靴などを持ち出すことで、その人物を今風のおしゃれに関心の高い若者、と描き分けたつもりでいるのだろうが、実のところ、それらの髪型や服、小物などに対して予備知識のない読者が読んだら、そんなものの名前がずらずら並んでいても、何ひとつ印象には残らず、イメージも湧かない。
あるいはその逆に、いかにもださくおしゃれでないふうな服装などを細かく描くことで、身なりに構わない人間であることを描写しようとする手段も、書き手が期待するほどの効果はあげてくれないだろう。
なぜなら、「身なりに構わない人の身なりを事細かに描写される」こと自体に、自己矛盾があるからだ。
身なりに構わない人であることを読者に印象づけたいのであれば、身なりについてあまりしつこく描くのは逆効果になりかねない。
さらにもう少し小説の技術的な部分で、書き手が過ちをおかしていることもある。
つまり、描写の「視点」が今、Aという人間にあり、そのAがBの身なりについて語っているという場合、身なりの描写の素材となる知識(服のブランドだとか靴のメーカーなどなど)は、Aの作中における知識を超えることはできないはずなのだ。
特におしゃれでもない男性の視点で描かれているはずなのに、その視点の主が、やたらと服やバッグのブランド名を列挙するのはおかしいのである。
まず確認しておこう。人物を描き分ける、というのは、外見を事細かく報告することとは、まったく別のことなのである。
p.p.305-307
外見の描写をあまり用いないで、語る言葉や仕草でいかにその人物を印象づけるか。その人物についての情報を読者に与えられるか。
それを意識して自分に課して書くようにしてみると、人物のキャラが自然と立って来るのを感じるはずだ。
なぜなら、外見の情報がなくなると読者は無意識に、それ以外の細かな部分から情報をくみ取ろうとするからだ。
p.310
断言してもいいが、最終選考の段階まで残った作品の勝利を決める上で、「作品の勢い」ほど強い武器はない。
「勢い」のある作品は、他の多々ある欠点を選考委員に一時忘れさせてしまうことすらある。
明らかに技術的、あるいは完成度で上回っている他の候補作を、一撃で敗退させることもまま、ある。
セリフの書き方 黒川博行
説明的ではない、できるだけ自然な会話を短いセンテンスでしゃべらせるのはむずかしい。むずかしいけど、苦労してそれを書くのが小説家の仕事やから、一生懸命考えます。
どうしても長いセリフになるときは、あいだに改行をいれて――「彼はソファにもたれて」「彼は煙草をくわえる」とか、なんでもいいんですけど――動作の描写を入れるようにしています。
作者が話の中で説明したいことは、会話の端々に隠すんですよ。
僕の場合はセリフが六割、地の文が四割。主人公がひとりになってるときは八割、九割が地の文ですけどね。会話だけで話を進めるというのは、単行本にしたら三ページが限度でしょう。
p.p.347-348
地の文より会話のほうが、書くのはずっとたいへんですね。手間は倍以上かかる。エンターテインメントの場合、情景描写なんかそれほどむずかしいことはない。
p.355
主人公が何者でどういう人物かというのを、横着して簡単に説明するんやなくて、会話や地の文でじっくりキャラクターを書いていけと。最初の五ページ、単純な説明はとにかく避けるようにするだけで、だいぶん印象が変わってきますよ。
エンターテインメントはとくにそうですが、地の文だけでは息が詰まります。セリフがあることでふっと息が抜ける。セリフを通じて登場人物の性格も書けるし、話のテンポも変えられる。会話の役割は非常に大きいんで、なんべんも見直して、しっかりセリフを磨いて、いい会話を書いてください。
手がかりの埋め方 赤川次郎
ミステリーを書いていて一番苦労するのは、トリックを考えることでも、ドンデン返しをひねり出すことでもなくて、手がかりをいかにして、読者の目につかないように、かつ記憶の隅にとどまっているように書き入れるか、ということです。
手がかりが、読者の記憶にぜんぜん残らない書き方をするのは不親切です。
ひとつの言葉に別の意味を持たせて、手がかりを隠している。あの真相が明かされたときは感動しました。
また、同じ手がかりを主人公に違ったように解釈させてしまう方法があります。
悪役の特権 貴志祐介
ストーリーの進行は、偶然と必然を適度にブレンドして行わなければならない。すべてをピタゴラ装置のような必然に設定すると、プロットの構築が死ぬほど大変になる上、かえってリアリティがなくなり、踏んだり蹴ったりである。よって、何らかの偶然の要素は必須である。
タイトルの付け方 恩田陸
私が考えるに、タイトルを見て、まず観客がある程度自分で何かをイメージできるもの。なおかつ、分からないところがあって、本当はどんな内容なのだろうかと興味をそそられるものです。
作品に緊張感を持たせる方法 横山英夫
物語の冒頭から間もない時点で、主人公の心を鷲掴みにする出来事を起こすことです。具体的には、その主人公にとって、最も起きてほしくない出来事を起こす――という手法を多く用いています。
誰にでも、「間違っても、こんなことは自分の身に起こってくれるな」と内心思っていることがあるはずです。考えるのもおぞましいので、日頃はあまり考えずにいる。そうした潜在的な恐怖心を炙り出す出来事を起こし、主人公に強烈な負荷をかけて一気に物語の緊張感を高めるわけです。
書き続けていくための幾つかの心得 香納諒一
挫折をせずに書き続けていくコツは、”一区切り”を大事にするということです。
p.641
読書というのは物書きにとって最上にして不可欠の趣味です。
本は読んで読んで読みまくりましょう。
流行作家といわれる人たちの最新作を読むのではなく、彼らや彼女たちのデビュー作と、その後一、二年ぐらいの間のものを集中的に読んでみたらどうでしょう。
デビュー当時の作品には、なぜその作家が現在のような作家になったのかを知る手がかりが、それこそてんてこ盛りで入っています。
そして、本当に好きな作家の場合は、その作品を書き写しましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
