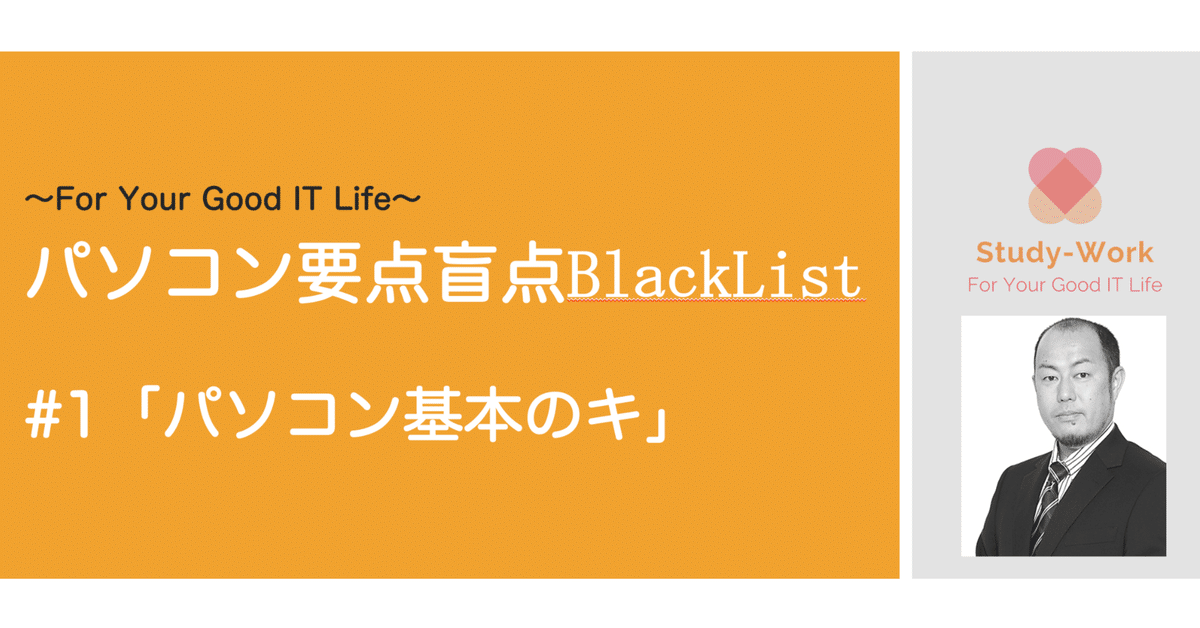
連載講座 パソコン要点盲点BlackList #1「パソコン基本のキ」
本記事は、以下をコンセプトとした連載記事です。連載やその他授業などにより、以下を実現し、対象となる方々のご活躍の場が広がることや夢の実現をご支援できれば幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<コンセプト>
誰に:パソコンのパの字も知らない方に(学生さんなど)
何を:パソコンの基本のキをお伝えし、簡単な資料を自分で作れるようにしたい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
はじめに
こんにちは。春の季節、新しい門出を迎え希望に満ち溢れている方が多いことと思います。
会社で仕事をする中でパソコンを使うケースは格段に増えました。
筆者が就職した時は「パソコン」はまだなく、汎用機の端末(ダム端と呼んでいた)でした。そのコンピュータではデータの参照や入力などはできますが、資料を作りたくても利用者自身では作れませんでした。情報システム部門や業者に相談して作成してもらうのが通例でした。時間と金がかかりました。今では、パソコンでExcel(表計算ソフト)やWord(文書作成ソフト)などで自分自身で作るのが当たり前の時代になりました。隔世の感があります。
学生さんの2割はパソコンを持ってないらしい
今の学生さんの2割はパソコンを持っておらず、論文や就活もスマフォでできてしまうようです。驚!
それを聞いて筆者は思いました。
「パソコンのパの字も知らない学生さんが就職したら苦労するだろうなあ」
と。
ただでさえ覚えることだらけなのに、その道具の一つであるパソコンも覚えないといけないという大変さは想像に易しです。タクシー運転手やるのに、車の運転をしたことがないというのと同じようなものです。
なので、
パソコンのパの字も知らない方向けの講座をやったら喜んでくださる方が居るだろうなあ
と思い、連載形式でやってみようと思います。
はじまりはじまり…
パソコンを仕事でどう使っているか?

生徒の皆さん、仕事の場でパソコンをどう使ってると思いますか?
もちろん多岐に渡りますが、多く目にするのが「顧客管理」「会員管理」といった「お客様管理」です。
昔のお客様管理は紙だった
その昔、お客様管理は紙で行われてました。病院などではそれをカルテと呼んでました。一般企業でも顧客カードと呼ぶ文庫本サイズの厚手のカードを使っているところが少なくありませんでした。
紙で管理する利点は「読み書きに精神的ストレスが低い」点です。また、用紙の色を変えたり付箋や印をつけるなどしてわかりやすく整理することもできました。
しかし、欠点もありました。お客様数や書き込む情報が大量になってくると検索しにくくなり、仕事の効率が下がるのです。また、保管している場所とは異なる場所では利用できませんでした。当たり前ですが。
パソコンでお客様管理すると超便利になった
そこで、パソコンでお客様管理をすると、お客様数が増えても容易に検索できますし、離れた場所にいてもネットワークに繋がってさえいれば利用可能にしやすくなり、大いに広まりました。
近年では、クラウドサービスの浸透により、お客様管理をExcelからクラウドサービス(サイボウズkintoneや海外製の顧客管理サービスなど)に変更する会社・組織も少なくありません。

冒頭でも申し上げましたが、パソコンは「自分で資料を作成できる」点がウけ、企業での利用が一気に広まりました。1990年代後半です。
それまでは、資料作成は手書きが主流でした。せいぜい、重要な書類を作成する際に清書的な意味合いでワープロ専用機を使う程度でした。また、社内のシステムに保存されているデータから資料を出力するには情報システム部門や業者にお願いするしかありませんでした。なので、多くのビジネスマンは資料作成に大変な手間を感じていました。
そんな時、Windows95の登場で世界が変わりました
「EUC(エンドユーザーコンピューティング)」というキャッチフレーズのもと、自分たちでコンピュータ上で資料作成をし、印刷したり、他の人にメールで送ったりできるようになりました。
「画期的に仕事のスピードが早くなったなあ」
と感じたのを記憶してます。
(これが今に通じる過重労働や低生産性の一因であると考えてますが、それは別の機会に…)

言わずもがな。コロナで大きく変わった働き方。出社したくても、お客様とお打合せしたくても、緊急事態宣言などで移動が難しい状況でしたので、必然的にZoomやTeamsなどのリモート会議ツールの活用が広まりました。スマフォでも使えますが、多くの人はパソコンでリモート会議をしているという感覚です。
以上、つらつらと述べましたが、言いたいことは「パソコンが使えないと仕事にならない時代」であるのは間違いないということです。
パソコンのつくりを知ることで用語を理解しよう

パソコンのつくりは家と似てます。
家は、土地があって、その土地は整治したとしてもぼこぼこなので基礎を作ってしっかり水平を取り、その上に家屋を立て、本棚やベッドなどを置いていきます。
パソコンも同様。
ハードウェア(部品)の細かい仕様はメーカーによって異なるのである意味ぼこぼこ。そのままではアプリがハードウェアと連携できないので、OSが間に入ってぼこぼこを埋めていきます。家における基礎のように。

「Windows」はパソコンのOSで、Windows95というバージョンが出た時は社会現象ともいうべき状態になりました。
それまでのコンピュータは、コマンドと言う英数字を入力することで動作していました。これが難解なので一般の方が使うにはハードルが高いものでした。さらにその前は英数字ではなく紙に穴を開けたものをコンピュータに読み込ませてました。
そんな中、Windows95などのWindowsOSは、呪文のような英数字を入力するのではなく、マウス操作で直感的に作業を行えるようにしました。インターネットの広まりもあり、一気に市場に浸透しました。

直感的に操作できるとはいえ、用語は覚えないと仕事で使うことは困難です。上図に記載した用語は最低限中の最低限であり、知らないと話にならないレベルです。ぜひ覚えていきましょう。
ここから先は実際の操作になるので本記事上ではお伝えしにくいです
ですので、既に特定のご連絡手段をお持ちの方々はその手段でご相談ください。
ご面識のない方でご興味ある方は、筆者が代表を務める組織にて、有償ですが個別相談が可能です。こちらのページ内にある「お問い合わせ」ボタンをクリックして表示されるフォームからご相談ください。
本記事はここで終わりです。
長文を読んでくださりありがとうございました。嬉しいです!
末尾になりますが、本記事を気に入ってくださっていただけましたらサポート(投げ銭)をしていただけるととても励みになります。いただいたサポート(投げ銭)は、記事作成に必要なツールや機器等の購入に使わせていただきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
