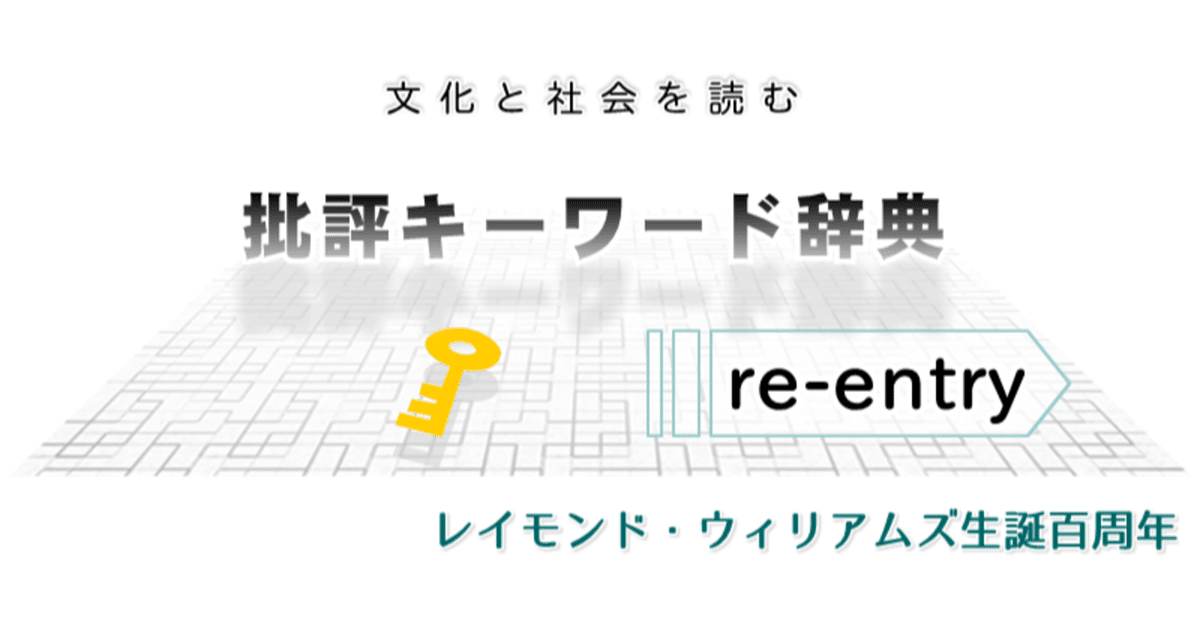
サヴァイヴァル (越智博美)
――生き残ったことの意味とは?
経済学はサヴァイヴァルの物語を愛好するから
サヴァイヴァルものをすぐれて同時代的な物語学として読む宇野常寛は、『ゼロ年代の想像力』のなかで、『新世紀エヴァンゲリオン』(TV 版)が社会的自己実現を疑い、それに頼らぬ承認を渇望する「引きこもり」に向かったことにその源流を見る。この「引きこもり」が、90 年代末からゼロ年代初期にかけて、自己愛に退却する「セカイ系」を産み出すとともに、サヴァイヴァル系物語を産み出した。とりわけ 2001 年前後から、引きこもり状態では生き残れないという「サヴァイヴ感」が社会に共有されはじめ、決断主義的に生き残りを前面に打ち出す作品が現れたというのである。その嚆矢が映画化もされた『バトル・ロワイアル』(1999年)であり、『ドラゴン桜』(2003 年)、さらには『DEATHNOTE』(2003~06 年)へと至る(11-32)。[注1] その特徴はなにより、「同格のプレイヤー同士」がそれぞれに信じたい正義を信じて、乱立し、「生き延びる」(survive)ことにある(宇野 111)。
この時のサヴァイヴのイメージは、「生存を続ける、存続する」という自動詞的な意味で使われていながらも、その存続は他者をなぎ倒した末にしか実現されない。これは、そもそも外来語としての日本語のサヴァイヴァルが、「生き残ること」(『広辞苑』)、「困難な状況を超えて生き残ること。またそのための方法や技術」(『大辞泉』)という自動詞の意味合いで使われていることと無関係ではないだろう。英語においては、自動詞のみならず他動詞の意味も日常的に使われるものだが、それは「人が自分よりも先に死に、自分のほうが長生きする」という意味だ。だから現在の日本語は、見かけ上は自動詞ではあるが、そこにそなわる「他者をなぎ倒して生き残る」というニュアンスを考えるならば、英語の他動詞の目的語部分を、敢えて自分が打ち倒す敵として想起し、その相手を倒して生き延びるという意味で含意しているとも言えなくもないかもしれない。
『バトル・ロワイアル』は、孤島がその舞台かつ闘技場〔アリーナ〕だが、孤島サヴァイヴァルものといえば、遠い先祖として『ロビンソン・クルーソー』(1719 年)、あるいはもっと新しいところでは『十五少年漂流記』(1888 年)などをすぐに思い浮かべることができる。日本のポピュラー・カルチャーでは、孤島というよりはポスト・アポカリプス(世界の終末後)的な世界へと流されたという設定の楳図かずお『漂流教室』(1972~74 年)などもこの系譜に入るだろう。元祖『ロビンソン』が「経済学はロビンソン物語を愛好するから」(『資本論』第一巻 138)と述べたマルクスをはじめ、マックス・ヴェーバー、またヴェーバーの指摘をふくらませたのであろう、大塚久雄によっても大きく取りあげられてきたことをここで思い出しておきたい。大塚は、孤島におけるロビンソンの生活に「社会的モデル」を読み取るが、それはデフォーが暮らした 17 世紀イングランドの「産業的中産階級」の様式であった(『社会科学における人間』 24)。この合理的な経済人としてのロビンソン理解は、すでにマルクスの『資本論』において提示されている。ロビンソンは「有用労働」のエージェントなのであり、またその限りにおいては、孤島は封建制の隷属状態に苦しむ「陰鬱なヨーロッパ」に比べれば、独立独歩で経済活動ができるという意味で「明るい島」ですらあった(139)。ヴェーバーにとっても同様で、ロビンソンは、プロテスタンティズムが資本主義倫理を用意するあわいに登場した「孤立的経済人」(355)である。ロビンソンが経済学に好かれるのは、おそらく彼が重商主義時代にあって、植民地経営や奴隷獲得のために航海をおこない、孤島においてはそのような時代に可能な限りの知識を駆使しつつ労働と生産、およびそのマネジメントをすることが生存の手立てだったということだろう。経済人として予測し、計画し、生産をすることが彼の「存続」、すなわちサヴァイヴァルの鍵なのである。
生き延びるために何をするのか。その手段をめぐる想像力は、私たちが自分の生きる社会をどのように想像し、想像させられているかということと無縁ではない。実際、1970 年代の作品である『漂流教室』で描かれる世界の破滅と生き残りは、冷戦期および福祉国家の想像力の産物である。砂漠化した未来の世界に校舎ごと移動した子どもたちは、教師ら大人が(ひとりを除いて)精神を病んで死んで子どもばかりになったとき、「大統領」を選び、年長者が家族のように年少者の面倒を見て、計画的に食料を食べ、最終的には食料生産も始めて、漂流した先で自足的な生活を目指す。弱きものを集団でケアして、集団のサヴァイヴァルを目指すのだ。このとき何が善で何が悪かに関する彼らの物差しが揺らぐことはない。むろん仲間割れもあるが、勧善懲悪的に解決する。命を落としそうな仲間をできれば助けたいと願い、助からないとその死を悼む。彼らの生存の鍵はむしろ、ぶれることなく規律をまっとうし、合理性を働かせることにかかっている(この部分が壊れた物語がゴールディングの『蠅の王』)。また、滅びの理由はさだかではないにせよ、未来にいる自分たちと元の時代の世界が何らかのループホールによってつながっていることを彼らは理解しており、主人公とその母は、そのメカニズムを理解しないながらも、危機的な状況にあっては、時空を超えたコンタクトを取る。その末に辿り着くのは、荒野においてよりよく生きることによって、また最年少の子だけをともかくも元の世界に返すことによって、この荒廃が母たちの未来になかったことになるようにという願いと、その試みである。[注2]
バトル・ロワイアル
転じて現代のサヴァイヴァルには、集団での生存など念頭にないようだ。リアリティ TV のヒット作『サヴァイヴァー』は、北欧で放映された『ロビンソンの冒険』の米国版として、2000 年に『サヴァイヴァー』のタイトルで登場したものだ。孤島ものゆえに当初はロビンソンの名を冠していたのかもしれないが、この番組のゲームのルールは、ロビンソンのような生産と労働を問題にしない。むしろ、宇野の言うサヴァイヴァル物語である。孤島に置かれたチームが、はじめはチーム同士で競っているが、最後はひとりになるところまで競争相手を蹴落として勝ち抜くゲームは、一見チームプレイに見えても、そのチームのメンバーの互選で排除対象を決めるので、『漂流教室』のような帰属意識に支えられたものではない。
そして、この部分を身も蓋もなくドラマ化したものが、その前年に出た高見広春の小説『バトル・ロワイアル』である。徹頭徹尾監視された孤島で、ともかくも殺し合うしかない中学生たちの戦いは、まさしくネオリベラルな社会の寓話とも言うべきものである。そもそもそのゲームの細部は国民には周知されておらず、ある日突然、選ばれたクラスがゲームに参加することを余儀なくされ、殺し合いのプロセスに入る。勝ち残るのはただひとりだけ。それぞれに配布される鉈から機関銃に至る多様な武器。あとはみずからの才覚を頼りに、殺し合うしかない。生政治(人が生きることを管理する体制)を端的に象徴する首輪「ガダルカナル二二号」によって生体反応を監視され続ける彼らには、ゲームから降りるという選択肢はなく、プレイヤーとしてのアイデンティティに封じ込められている。もはや人を殺してはならぬという道徳も無力である。あくまでフレクシブルにみずからを修正しながら、定時放送による「残り人数」の情報や地図を頼りにみずからの動きを自己責任で調整する。ここで大切なのは、みずからの身体能力のほかに、クラスメートの人間関係、動き回る能力、地図等を見て計画を立てる能力だ。上から決められる反復的なフォーディズム的労働とは対極の企業家的な能力こそがサヴァイヴァルの要件になるのである。サヴァイヴァルとは、ロビンソン・クルーソーのような、生産をすることによる生存ではなく、みずからの個人的な才覚を駆使して元クラスメートを殺して勝ち残ることの謂いとなる。
『バトル・ロワイアル』や『サヴァイヴァー』におけるサヴァイヴァルとは、競争原理に基づいて、強いもののみが「残る」こと、あるいはそのように目指すことを指している。他者を蹴散らして、ひとり生存能力の差を見せつけることであり、その極端な物語化が『バトル・ロワイアル』である。あまりにも残酷であると批判を浴びたのだが、そのむごさをたんに映像と片付けられるだろうか。あるいはまた物語として捨て置いてしまえるだろうか。サヴァイヴァルの言説が私たちの生を浸潤しているからこそ、そして生そのものが労働となる私たちの生きる現実を生々しく物語化したからこそ、見たくないという反応を引き起こしたという可能性がないと言えるのだろうか。[注3]
この競争の闘技場〔アリーナ〕に望むと望まざるとにかかわらず上ってしまったが最後、勝つこと、すなわちサヴァイヴァルを果たすことは、残りひとりの存在になることである。しかもその戦いの舞台が、自分が統御するのではない巨大なシステムのひとつの場にすぎないなら、逆にその勝者の生はむしろ脆弱だ。『バトル・ロワイアル』は、その点を見抜いているからこそ、ゲームのルールを利用しつつすり抜ける落着点を用意している。しかしながら、主人公たちが――「君と僕」として生きて行く――辛くもその闘技場たる孤島を脱出して、そのようなゲームを強いる国家への復讐を誓う結末に読者が希望を感じるとしても、その希望も頼りない。追っ手のかかる彼らの生き延びる道が、巨大な国家システムをフレクシブルに欺くことでしかないなら、ネオリベラルの寓話たるゲームの競技場としての孤島を脱出したとしても、彼らの戦いはそのまま続いていく。彼らは生き延びるというゲームへの参加へと、言い換えれば同じゲームの焼き直しでしかない別のゲームの闘技場へと、依然として封じ込められているのだ。その限りにおいて、この物語もまた新自由主義下の、そして「君と僕」のみが逃れるという点ではセカイ系に通じる、社会なき「セカイ」の物語だと言うことができる。
ネオリベラルなサヴァイヴァルの要諦は、「競争し、他者を出し抜いて勝ち抜く」という心的態度〔エトス〕を身にまとうことにある。それゆえに、おそらくこの語が元来他動詞として持っていた「人よりも生き延びてしまう」という喪失を抱え込んだニュアンスを忘却している。今日的な意味におけるサヴァイヴァルは、ネオリベラルな統治下における自己責任、自己マネジメント、競争といったキーワードで表されるような生き方を端的にイメージ化する強力な用語である。グローバル化を「勝ち抜く」という言い方はまた目的となって、ネオリベラル化がいっそう進められる。けれども、それはネイション(国家・国民)の生き残りにつながるだろうか? ネオリベラルなグローバル化が、しばしば企業の多国籍化、労働力の流動化、同時に福祉国家のセーフティ・ネットの切り崩しとワンセットになるならば、ネオリベラリズムと親和的な新保守主義が掲げるネーションも、理屈のうえではきわめて足下が危うくなる。国内においてもサヴァイヴァルの戦場としての市場経済が主導するなら、行き着く先は「ウォール街を占拠せよ」のキャッチフレーズのごとく、99 パーセントが負け組となったセカイではないのだろうか。そうやって生き抜く国家とは、何から成り立ち、またどこへ行くのだろうか。
あなたを忘れない
1990 年代以降のディザスター映画が、すべてを一瞬にして亡きものにするツナミや竜巻、隕石の襲来と、その危機に自己責任で応じるリスク社会化とグローバル化の比喩であるなら、ディザスターの後を描くポスト・アポカリプスの物語は、なおいっそうその比喩を徹底したものとも言える。コーマック・マッカーシーの小説『ザ・ロード』(2006 年)における、砂漠のごとく枯れ果て、凍てつく不毛な元アメリカを旅する父子の物語は、日々が「生き残り」を目指しているという意味でも、邪魔する者は倒すという意味でも、サヴァイヴァルの物語である。この物語では、最後の場面を除いては、危機的な状態で人々が助け合う「災害ユートピア」はない。[注4] すでに地図はぼろぼろに破れ、世界像を掴むことは不可能な世界。何がどこから襲ってくるかわからないために、つねにリスク管理を怠りなく、臨機応変に対応し、ときに「リスクを取る」父(McCarthy 79)。息子とともにみずからを善人と称するが、しかし、「あらたな世界標準」(161)のなかでフレクシブルにモラルを変更した結果、住人亡き家から物資を略奪することも、容認可能なことになる。法やモラルの停止と人間性の消滅が茫漠と拡がるディザスター後の「あらたな世界基準」の下にある世界は、ジョルジョ・アガンベンが述べるような、生き抜くためにいっさいが可能となるような場と化している。すなわち「死なすでも生かすでもなくて、生き残らせる」、「生き残りの生産」だけしかしない収容所の生権力(アガンベン 210)――人を例外状態に置く現代の生権力を連想させる生の場と化している。しかし、相手を倒す競争、そして消尽する競争が、最終的にみずからの生存、人類の生存につながらないことは明らかである。
父子の生き残り戦略は、住人を亡くした家の食料を我がものとすること、死体から靴を取り、略奪後の店の残り物をあさることという消費行動でしかない。まれに見る幸運で痛みかけのリンゴを見つけても、食べればおしまいである。納屋と家畜小屋の跡で干し草の種をむさぼり喰らう場面は、理科室で発見した種をまこうと考える『漂流教室』の子どもたちとみごとな対照をなす。生産することは頭にないのだ。このような消尽の行き着く先が、人の肉、とりわけ子どもの肉を喰らう人々の存在である。子どもすらいなくなれば人類は存続し得ない。善人を自認する父子が唯一最後の砦とする人間の条件は「人を食べないこと」である。この一点でのみ「善」を維持していると言えるのは、おそらく他者を殺して生きることが人類の生存につながらないからである。とはいえ、自分亡きあと、息子が陵辱され喰らわれるくらいなら、息子を殺すしかないと考える発想が父にある限り、人肉を食べない彼らとて、行き着く結果は二人して死ぬことでしかない。
しかし、病に冒された父は、いまわの際に「死んだ子どもを抱くことはできない」(279)から息子を殺さずに死ぬという事態を受け容れる。ここで、この父はサヴァイヴァルのあり方をラディカルに変えているように見える。というのも、父の決断とは、見知らぬ他人の「善意」に息子の生を託すということなのだから。「お父さんがここにいなくても、話しかけることはできる。話しかけてくれれば、お父さんもおまえに話しかけるよ」(279)と、みずからの有限の生を受け容れてひとりこの世を去りゆく父を見送った息子は、はからずも父の死を超えて生き延びる(サヴァイヴする)。サヴァイヴァルが捨て置いてきた本来的な意味が、つまり他動詞的な「誰々の死を超えて生き延びる」という意味がここにおいて息を吹き返すとともに、息子と見知らぬ他人のサヴァイヴァルにも希望が芽吹く。息子はこの物語のなかで、唯一、死に行く者を悼む存在だったが、今また父を悼むことにより、父をも胸に抱えていくことになる。みずから他者を切り捨てて生き延びるのではなく、はからずも生き延びてしまう際に抱え混む喪の作業とその後の他者との出会いは、まさしく、哀悼が私的な個人的なものであると同時に、自己がもともと「社会性からできあがって」おり、そのことが「複雑な秩序からなる政治的コミュニティを考える基盤になる」(Butler, Undoing Gender 19)ことを物語る。私たちは生まれ落ちた瞬間から死に向かって歩む有限の存在だ。けれども、その有限性が逆に喪を、またそれによって他者に開かれることを可能にする。
サヴァイヴァルの意味を、他者と競争して自分だけが生き延びることから、失われた他者を悼み、はからずも生き延び、その痛みをよすがに他者とつながる可能性へと変容させるとき、私たちの前に「プロジェクトの時間」(ジジェク 247)が開けてくる。『ザ・ロード』の最後に提示される、謎めいた、あり得た複数の過去の世界地図のイメージのように。
[注1] 宇野はこのようにカテゴライズするが、それについて、セカイ系であれ、サヴァイヴ系であれ、どちらもともに、新自由主義化による、市場原理主義における競争原理を根底にもったセカイを反映したものと捉えられる。
[注2」 この部分はジャン・ピエール・デュピュイが『ツナミの小形而上学』で示した、未来の大災害と現在をループ化して繋げることで出てくる発想(3-18)のみごとな形象とも言える。ここでデュピュイは、災害を直線的な時間の「未来」に起こりえる可能性として考えるのではなく、むしろ「過去と未来がお互いを決定し合う」「ループの形状」をなすものと捉えて「破局の後に続く時間に「みずからを投影」」することによって、破局を受け容れつつ運命を変える可能性を探る必要を説いている。このような時間を、ジジェクは「プロジェクトの時間」(246-49)として高く評価し、私たちの政治行動に取り入れるべきであるとする。
[注3] サヴァイヴァルのナラティヴが社会の隅々に浸潤しているからこそ、「恋」をサヴァイヴァルとして捉えることもできる。
[注4]『災害ユートピア』が、実際に存在していても、語られないことそのものが注目すべきことではなかろうか。ハリケーン・カトリーナのあと、即サヴァイヴァル闘争となっているかのように報道がなされていたことと、マッカーシーにおける大災害後のサヴァイヴァル競争は、どこかで共通しているだろう。
参 考 文 献 (リンク先をご覧ください)
〈著者紹介〉
越智博美(おち ひろみ)
専修大学国際コミュニケーション学部教授。
専門はアメリカ文学・文化。
著書に『モダニズムの南部的瞬間――アメリカ南部詩人と冷戦』(研究社)、『カポーティ――人と文学』(勉誠出版)、共著に『ジェンダーと身体——解放への道のり』(小鳥遊書房)、『文学研究のマニフェスト――ポスト理論・歴史主義の英米文学批評入門』(研究社)など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
