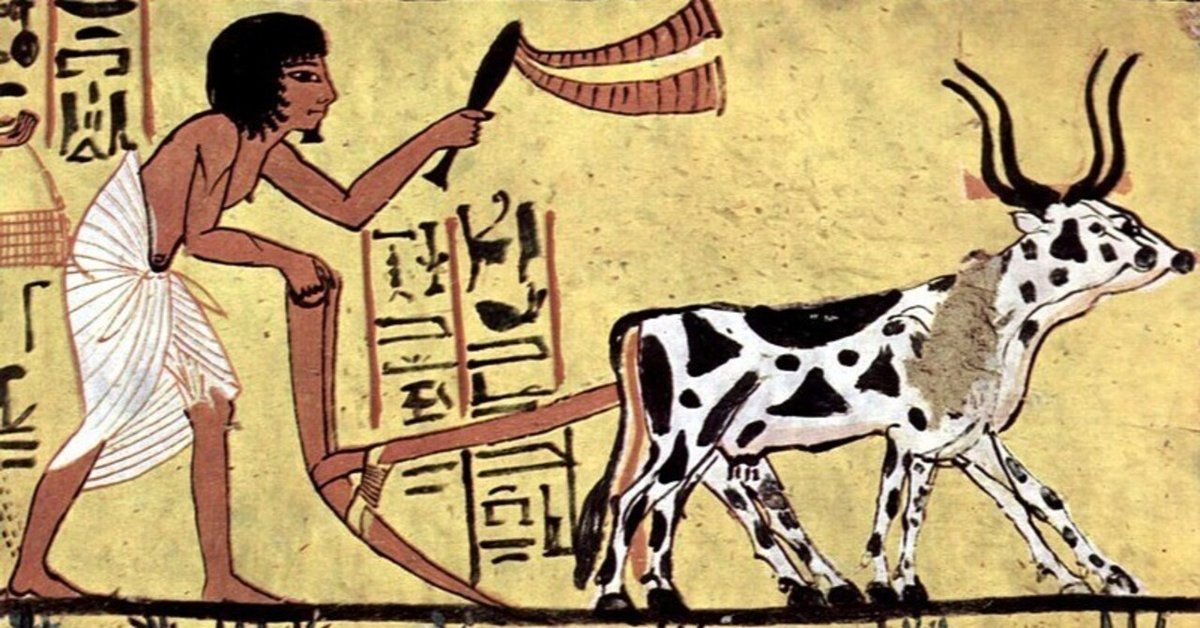
健康と文明病⑥(謎に満ちたハンドアックス)
ハンドアックスの出現と技術革新
猿人からホモ属への進化を媒介したオルドワン石器は、獣皮や肉を切る剥片を得る事が主目的で、石器の形状を前もって意識して作られたものでは有りませんでした。その為、出来上がった石器は、専門家でないと自然石と判別が困難な代物だったのです。ところが、約200万年前にホモ・エレクトスが登場してしばらくすると、最初から完成時のデザインを意識して作られた、いかにも石器らしい石器が突然出現するのです。皆さんも写真で見た事が有ると思いますが、アーモンド型や楕円形のハンドアックス(握斧)です。この石器文化は、最初に発見されたフランス北部のサンタシュール(Saint Acheul)遺跡から、アシュール文化と呼ばれています。
図50)アシューリアン両面加工石器(ハンドアックス)

実は、約175万年前頃にホモ・エレクトスが造り出したアシューリアン石器は、オルドワン石器とは全く異質で技術的にも画期的な石器だったのです。まず、最初から完成時の形状を意識して作られた初めての石器だった点と、その異常とも言える大きさです。オルドワン石器が5~10cmの手のひらに収まる程度の小さな石器だったのに対し、アシューリアン・ハンドアックスの典型的なものは15~20cm、大きなものでは30cmを超えるものも有り、格段に大きくなっているのです。そして大変粗削りながらも、初期のものから楕円形やアーモンド型と言った明確なデザイン性を持っていた訳です。
さらに注目すべき特徴は、素材として初めて大型の剥片を使ったその製作方法です。まず、巨大な原石に打撃を加えて20cmを超える大型薄片を剥がします。その後、この大型薄片の周囲に両面から剥離・整形加工を加える事で、アーモンド型のハンドアックスや、三角形の平面と断面を持つピック、逆台形のクリーバーなどを製作しているのです。オルドワン石器が場当たり的に小さな剥片石器を作っていたのに対し、大きな原石から20cmもある大型剝片を剥離するには、打撃の位置や角度、力の入れ具合等の精密なコントロールが不可欠で、かなり高度が製作技術が必要です。オルドワンからアシューリアンへの石器文化の発展は、人類の技術史においても大きな画期となっているのです。
さらに140万~125万年前頃には、予め原石の石核に求心状剥離などの調整加工を施して、そこから定形化した巨大薄片を剥がす技術が発展して来ます。これによって、鋭い刃部を持つ大型薄片の剥離が可能になったのです。その後も、剥離技術や整形加工技術の進歩によって、90万~80万年前頃にはアシューリアン石器の出来映えが格段に良くなって来ます。それ迄の、ぶ厚くキザギザ刃で無骨な印象のハンドアックスから、三次元の対称性と直線的な側縁刃部を持ち、薄く大型で芸術作品の様な洗練された美しい形状の石器が製作される様になるのです。
図51)アシューリアン石器の分布(円の直径は発見されたハンドアックス数に比例)

最古のアシューリアン石器は、エチオピアのコンソ遺跡で発見された175万年前のものです。これは、ホモ・エレクトスが約200万年前に出現して少し後、以前に紹介したトゥルカナ・ボーイが生きていた160~150万年前の少し前の時代です。人類誕生間もない初期の時代に、我々の遠い祖先のホモ・エレクトスは、この様な高度で素晴らしい石器を作り始めていたのです。そして、アシューリアン石器は時代を経るごとに完成度を増しながら、約13万年前頃まで、約160万年もの長期間にわたって作り続けられる事になるのです。また、この石器を制作したホモ・エレクトスが、アフリカを出て世界に拡散するに従って各地に広がり、その分布範囲はアフリカからヨーロッパ・中東・インドにまで及び、近年はモンゴル・中国・韓国でも発見されています。約160万年もの長大な継続期間と広大な分布範囲は、アシューリアンが如何に繁栄した石器文化だったかを如実に示しています。
使途不明のハンドアックス
この様に長く広範囲で使われ続けたアシューリアン石器ですが、驚いた事にその代表とも言うべきハンドアックスは、何に使われたのかその使用目的が不明で、前期旧石器考古学の最大の謎とも言われているのです。一般には、動物の解体や皮剥ぎに使われたとか、肉・骨・木・皮など多用途に使うスイス・アーミーナイフの様な多目的ツールと考えられています。しかし、獣皮や肉を切るという用途ではカミソリの様な鋭い刃をもつ小型剥片の方が使い易いし、骨を割って骨髄を取り出すには手のひら大のオルドワン型チョッパーで充分です。実際、ハンドアックスが出現した後も、原始的なオルドワン石器も同時に使い続けられているのです。
図52)オールドヴァイ峡谷出土の100万年以上前のハンドアックス

使用目的が良く分からないから、多用途に使った事にしようと言うのでは、悪い冗談と言う他有りません。挙句の果てには、あの有名なハンディキャップ理論を応用して、出来の良いハンドアックスは男性が結婚相手として相応しい優れた遺伝形質を持つ事を女性に示すための孔雀の羽の様なものだったという説や、貨幣代わりの交換用の商品だったと言う説まで飛び出す始末なのです。どうも現代の学者というのは、頓知が利かないと仕事にならない様です。
実は意外な事ですが、ハンドアックス(握斧)はその名前とは裏腹に、手に握って使う石器で無い事ははっきりしているのです。というのも、ハンドアックスには全周にわたって鋭い刃が付けられているからです。もし図52)の様に、握って手斧の様に使おうものなら、手が血だらけになってしまいます。つまり、ハンドアックスは手に握って何か作業する様には初めから作られていないのです。
この様な使途不明のハンドアックスに対して、アシュール文化ではクリーバー(肉切包丁)と呼ばれる特徴的な両面加工の石器も多く出土しています。この石器では斧の様に主軸とほぼ直角に直線的な広い刃が付き、分厚い基部は手で握るのに都合の良い形に作られています。この石器なら、動物の解体や骨の破砕、木の切削にも便利に使えたでしょう。このように、アシュール文化を特徴付ける2種類の石器の内、クリーバーはその用途や使い方が容易に推測可能なのに、ハンドアックスの方は様々な用途に使ったのだろうと言うだけで、納得のできる説明がなされていないのです。
そもそも手に持って皮剥ぎなどに使う道具なら、片面に刃を付けるだけで充分で、わざわざ手間を掛けて左右対称の形状にして両側に刃を付ける必要など有りません。しかも、図52)を見ても分かる様に、スイス・アーミーナイフの様に使うには、余りに大き過ぎ、重すぎるのです。その上、ハンドアックスの出現後も、原始的なオルドワン石器も駆逐される事も無く、約25万年前頃まで併用して使い続けられているのです。つまりハンドアックスは、オルドワン石器の代替として取って代わるものでは無く、両者が長期間に渡って併用されて来た事実は、それとは異なる明確な使用目的を持っていた可能性を強く示しています。
これ以外にも、ハンドアックスには説明の困難な不思議な事実が知られています。一つは、最もありふれたハンドアックスは長さ10cm以下のかなり小型のもので、道具として役に立つとは思えない様なみすぼらしい石器だという点です。その一方で、大型で美しすぎるほど素晴らしい作りのハンドアックスが存在する訳です。さらに、典型的なアシュール文化では2~3の剥片石器を除くとハンドアックスが最も多く出土し、片刃や両刃のチョッパー・礫石器はほとんど無視できる程度しかないと言います。これも、ハンドアックスを万能型石器とするなら、一人が1個ずつ持っていれば済むはずで、不思議な事です。また、ハンドアックスは先端の尖ったアーモンド型と、ハート形や卵形の2タイプに大きく分ける事ができますが、遺跡によってはどちらか一方のみが出土したり、両タイプが共存している場合もあり、形の違いに関らず両タイプとも同じ目的に使用された可能性が高いと言います。
図53)ケニア、カリアンドゥシ遺跡の大量のハンドアックス(約100万年前)

また、アシューリアン石器はアフリカ各地から出土していますが、図53)のカリアンドゥシ遺跡の様に、幾つかの遺跡では1ヶ所から数百、時には数千にもなる膨大な数のハンドアックスが出土してます。当時の狩猟バンドが、10~20人程度の少人数で構成されていたと想像される事からすると、この膨大な石器の数はあまりに不釣合いです。この専門の製作工房の存在さえ疑わさせる様な遺跡の存在や、約160万年もの長きに亘って改良しながら広範囲な地域で作り続けられて来た事実を考えると、ハンドアックスが初期人類にとって生活する上で無くてはならない、非常に重要で特別な石器だった事は明らかです。
(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
