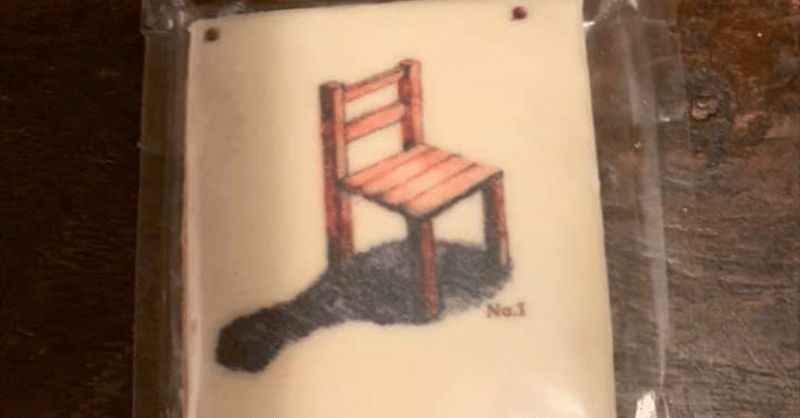
かんたんに連帯しちゃえるわたしたちの正しい後悔のために
※この文章は、2019年9月に私が発行したzine『シスターフッドって呼べない』の「はじめに」にあたるものだ。これから私が書き、発信していくことの前提は、少なくとも当分の間はこの文章にあると思われるため、ここに転載する。(『シスターフッドって呼べない』は完全手売り販売・限定100部であるため、ここに掲載することには多くの人の目に触れさせるためにも意義があると判断した。)
わたしが、彼女たちとの連帯を語るとき
女として生きることの生きがたさを、言葉にしはじめたのは、いつからだったろうか。
もちろん、これまで何度も重ねてきた女友だちとのおしゃべりで、それは、無意識ではあれ、含まれてはいた。しかし、私の個人的な苦しみを、「女」という主語で語ることを試みたのは――真昼の喫茶店で友達と最近見た映画の話をするかのような熱度で話すようになったのは――少なくとも私においては、ここ2・3年のことだ。それまでは、それは、してはいけないことだと思っていた。
主にソーシャルメディアを中心に起こった、セクハラやレイプに対する抗議運動#Metooを発端に、女たちが自身の生きづらさと、自身がこの社会で女であることを結びつけて、語り始めた。それらは無数のツイートとなり、noteの投稿となり、そのいくつかは紙の束となって、世に出た。伊藤詩織の『ブラックボックス』(2017)、韓国の作家による『83年生まれ、キムジヨン』(2018)のヒット、『早稲田文学 女性号』(2017)の増刷、フェミニズム雑誌『エトセトラ』(2019)の創刊。フェミニズム的主題を盛り込んだ作品群が、様々な形で注目を浴びている。SNSにおける、カルチャーにおける、フェミニズム。
93年生まれ、現在26歳、文系女子のわたしもまた、その影響を強く受けた。女友だちと、女として生きることについて、フェミニズムについて、私が手さぐりに語り始めたのは、まさにそのフェミニズムブームの流れに身を任せたことが大きい。
フェミニズム関連本なるものを、ライトなものを中心に読み漁り、同じくフェミニズムに目覚め始めた友人と、女として生きる上で感じる違和や生きづらさを語らっては、読書会や茶話会を開いた。フェミニズムに関するエッセイをネットに綴り、それらを発表する同人誌まで創刊した。そして今年、女性差別反対、不平等是正を提言する団体に就職した。
「これだ」と思ったらとことん、なわたしの性格のせいもあるのだろう。しかし、わたしがこうして突き進むことになったのは、周囲の、いや、遠くSNS越しの、彼女たちとの共感と、連帯感に後押しされたからに他ならない。
漂白された語りの耐えられなさ
しかし、ときおり、強烈な“ズレ”が頭をよぎる。
私が今、喫茶店で口にしている「女」と、幼い頃から持ち続けてきた「女」。その2つのイメージが、ズレ始めているのだ。
思い返せば私は、とても長い間、「女」を恨んできた。同時に、「女」である自分も憎んできた。幼い頃から、女に生まれたことを悔やんでは、女である母を恨み、クラスの女子を憎み、それでも女である私はどう生きればいいのか頭を悩ませ、女と競い、女と戦い、女を傷つけ、幾人もの女から抜きん出ること、ほかの女と私は違う、と自らを差別化・区別化することを目指してきた。
私にとって長い間、女たちは、連帯する存在ではなく、闘い、打ち勝ち、離れる存在だった。しかし今、「女」という主語で姉妹(シスターフッド)たちを語る私は、かつての、憎んでいた「女」たちを忘れている。隠している。そんな女たちを思い出したとき、今、私が温かいまなざしを与えている「女」たちとの、ズレを見た。根っこの憎悪をもみ消して蓋をして、私はまた、喫茶店で「女」たちに笑顔と愛想と共感を振りまいている。
それが、このごろ、耐えられない。女同士の僻みやそねみを漂白した語りが、とにかく恐ろしくてたまらないのだ。女性差別撤廃、男女同権、それらとてつもなく「正しいこと」を訴えるとき、私の中の、幼い私が戸惑っている。彼女は、女友達から突然無視され、男としゃべるだけでぶりっことからかわれ、母から着たくないスカートをあてがわれ、その理不尽と違和感に、もがき苦しんでいる。
大人になれば、フェミニズムをきちんと学べば、小さな私は泣き止んで、これまでの葛藤は、きれいさっぱりなくなると思っていた、のに。なのに、全然、全然、なくならない。むしろ、フェミニズムに近づけば近づくほど、女を恨み、憎んだ私の泣き声は、より強く聞こえるようになってきているのだ。
ミソジニー(女性蔑視)とは、男性の社会的優位性を担保するためになされる意識でもあるのだという。であるのなら女性がそれらから無縁でいられるかというとそうではなく、企業内で評価され男性社員と対等に関わるために、他の女を蔑む行為を行う、ということなんてざらにある。むしろ女だからこそ、ミソジニーを受け入れるか否か、より切実な選択を迫られる側面もある。だから、この社会全体にはびこるミソジニーと女性差別を批判するのであれば、自分の中のミソジニーを見つめ直すという手もあるはずなのだ。
だが、それが難しいのは、主戦場となっているSNSにおいて、わずかな断絶は仲間割れと、アンチフェミによる攻撃の対象――単なる「隙」になってしまうからかもしれない。短くわかりやすい表現が求められるメディアにおいて、小さなしがらみを取り上げることは、そのメディアの伝わる速度を下げ、誤解を生む。
もう一度ちゃんとつながるために、女ぎらいの歴史をみたい
それでも私は、女が、社会への違和感やおかしさを語り合う時の、女に対して向けている無批判な笑顔や、差別や不平等に怒っている女たちへの迷いない賛意の表明の間には、もっともっと、ためらいが差しはさまれてもよいと思う。もちろん、そんな息の長い言葉を書く人も、ためらいと自己矛盾を見つめ続けているひとも、今この世界には、これまでの歴史にも、無数にいることだろう。しかし、それらは継承されなければしょうがない。今、私も、やらなければならない。
そう考えたとき、私が冷静に直視すべきは、フェミニズムによる脊髄反射的連帯意識によって覆い隠された、自身の女ぎらいの歴史であると思った。こうして目の前に笑いかけている彼女を憎んで、軽蔑して、離れたくて逃げたくてしょうがなかったあの時期。私たちの本当の連帯は、これまであんなにも傷つけ合い、見下しあい、競い合ったあの過去を、語り合い、認め合い、あの時のふるまいを全うに後悔した先にあるのではないだろうか。
サポートいただいた分で無印良品のカレーを購入します
