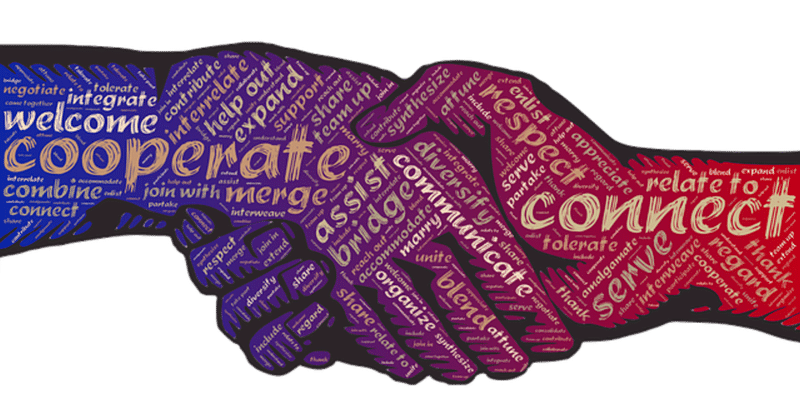
ファイブアイズによる中国への対応(RUSIの記事)
写真出展:John HainによるPixabayからの画像https://pixabay.com/ja/users/johnhain-352999/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2009195
英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)が2021年6月18日に、ファイブアイズによる中国への対応についての記事を発表した。各国連携の在り方を示したものであり、今後の中国封じ込め作戦を占うという意味で参考になると思われる。今回は本記事の概要についてご紹介させていただく。
↓リンク先(China Policy and the Five Eyes)
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/china-policy-and-five-eyes
1.RUSIの記事について
・ファイブアイズの枠組みはインテリジェンスの協調において最も成功したものであり、中国のネガティブキャンペーンの主要な標的となっているほどである。ファイブアイズが共同声明で香港やウイグルの件で批判した時には、外務省報道官が痛烈に批判を展開し、1国でもメンバー国が欠けた声明が出た場合には、ファイブアイズが分断されていると宣伝している。
・しかし中国のこの解釈は2つの点で誤っている。第一に、ファイブアイズはあくまでもインテリジェンス上の協調であり、外交政策を指示するものではなく、各国の主権を尊重している。第二に、ファイブアイズの声明ではなく、各国が共有した考えを表明しているにすぎず、中国のレッテル貼りはファイブアイズの仕組みを理解していない証拠である。法に基づいた国際秩序という価値観を共有し、支援することで、政策協調をしているように見えるが、各国の状況や関係性に応じた対応を許容しているのであり、これがファイブアイズの強みである。
・ニュージーランドがファイブアイズの権限の拡大や人権に関する発言をする主体としての疑義を呈した際、中国に融和的であると批判された。しかし実際には別の場にて非難決議を発しており、ただ単にニュージーランドがファイブアイズの役割に含まないと解釈したに過ぎない。
・アメリカは中国を主要な競争相手として位置づけながらも、貿易は継続している。イギリスは主に香港問題を巡って対立している。カナダは自国民の不当な拘束やキャシー・モンの送還などを巡って対立が深まっている。オーストラリアは一帯一路などの経済政策に制裁を課している。ニュージーランドは対立しつつも改善傾向にある。各国の違いはありつつも、協調できる部分では協調しているのであり、各国が同様の声明を発表したからといって、全く同様の政策を取るというわけではない。特に人権に関してファイブアイズだけが関心をもっている、情報工作であるという認識は誤っている。中国はメッセージの受け取り方を誤るべきではない。
2.本記事についての感想
ファイブアイズは各国の立場を尊重しつつ国際社会で行動していくと言う点においては、クアッドにとっても非常に参考になる。むしろオーストラリアから多くの知見を得られるのではないだろうか。
ただ、ニュージーランドがかなり中国に取り込まれているということもあり、この枠組みが信頼できるというわけではない点に注意が必要である。当面は情報共有の枠組みと見ておいた方が無難であり、国際社会を先導する役割を担うとまでは思わない方がいい。
一時日本が第6の目として加入するといった話も出ていたが、残念ながら日本は最も信頼できないセキュリティホールであり、この枠組みに入ることができる体制にはなっていない。むしろ加入するのではなく、組織外協力者として巧妙に対応していく方が望ましいだろう。
個別具体の技術や能力に関しては決して劣っているわけではない。特に警察の無線関係者の情報能力は高く評価されていると言われており、できることは多々あるはずである。現在の日本の実力に合った協力の仕方を模索することが必要だろう。何十年と実績を積み重ねることで、自然と信頼関係や能力向上が図られることを望むものである。
英文を読んでわからないという方は、メールにて解説情報をご提供させていただきます。なにぶん素人の理解ですので、一部ご期待に沿えないかもしれませんので、その場合はご容赦願います。当方から提供した情報については、以下の条件を守ったうえで、ご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
(1) 営利目的で利用しないこと。
(2) 個人の学習などの目的の範囲で利用し、集団での学習などで配布しないこと。
(3) 一部であっても不特定多数の者が閲覧可能な場所で掲載・公開する場合には、出典を明示すること。(リンク先及び提供者のサイト名)
(4) 著作元から著作権侵害という指摘があった場合、削除すること。
(5) 当方から提供した情報を用いて行う一切の行為(情報を編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負わない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
