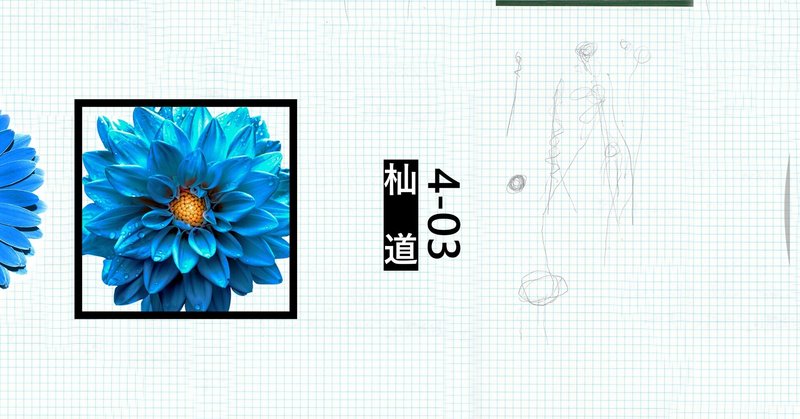
火を吐くドラゴン
7人の読書好きによる、連想ゲームふう作文企画「杣道(そまみち)」。 週替わりのリレー形式で文章を執筆します。前回はS.Sugiuraの「雨の夜、濡れた鱗のドラゴンが」でした。
【杣道に関して】
https://note.com/somamichi_center/n/nade6c4e8b18e
【前回までの杣道】
4-02「雨の夜、濡れた鱗のドラゴンが」S.Sugiura
https://note.com/ss2406/n/n86881db277ba?nt=magazine_mailer-2021-04-12
4-01「唸れ!ドラゴンブレスショットガン!」/藤本一郎https://note.com/b_a_c_o_n/n/nca6c465d4034?magazine_key=me545d5dc684e
___________________________
”想像力”というのは、とても扱いにくく、とらえがたい概念だ。実際、われわれの日常においても、「そんなものは想像にすぎないよ」と否定的に使われることもあれば、「もっと想像力を働かせなさい」と肯定的に使われることもある。”現実”との関係をどうとらえるかで、”想像”の位置も価値も変わるということか。前者であれば”現実”側に真理があり、後者では真理に至るには”現実”だけでは不足している、あるいは隠されているということか。いずれにしても、”現実”と想像の関係あるいは接合の仕方が問題になっているといえる。芸術作品においても、その虚構性の価値をめぐって、”想像力”の問題が大きな位置を占めているのは周知のことだ。
アリストテレスは『魂について』のなかで、想像(phantasia)を知覚とも思考とも異なる中間的存在ととらえている。知覚(諸感覚の統合)なしに想像力はないし、想像力なしに思考はない。感性でも知性でもないというわけだ。知覚と思考を媒介するものとしての”想像力”。ヒュームもまた、想像力を知覚と知性を媒介する中間的な存在としてとらえているが、やや否定的な面を強調しているように思える。例えば、想像とはさまざまな知覚の堆積ないし集合にすぎず、「そこでは自然が全く混乱し、出て来るものといえば翼を持つ馬や火焔を吐く龍や雲を突く巨人」を生み出すというわけである。
ヒュームにとっての想像は感覚的な諸印象とその再生産としての観念との無秩序な運動である。想像とはただただ個別のコレクションであり、枠となるもの、準拠となるものがない。ドゥルーズはこれを「アルバムなきコレクション、劇場なき劇」と呼んでいる。つまり、表象=上演される舞台〔主体〕がいまだないということである。もちろん、ヒュームも想像力の危険性だけを説いているだけではない。想像は連合という原理(接近・類似・因果性)によって想像を超出し、知性(秩序)を獲得する。コレクションからシステムへ、人間的自然への生成へ。ヒュームにとって想像力と思考を分けるのが連合原理というわけである。ただ、この連合原理はどう形成されるのか。習慣(経験)によるものなのか。それともアプリオリな(経験に先立つ)ものなのか。この問題に挑んだのがカントというわけである。
カントは”想像力”(カント著作の日本語訳では”構想力”)をヒューム以上に、積極的な面を強調している。「再生的構想力」と「産出的構想力」という、あの有名な区分である。想像力に後者の能力を見出しのは、カントの偉大な発見といえるだろう。前者が受動的な能力であるのに対して、後者は自発的な能力である。カントにとっての”想像力”の定義は、「対象を、その現前がなくても、直観のうちに表象する能力」のことであると同時に、「多様を一つの形象へともたらす能力」のことでもある。前者が「再生的構想力」に、後者が「産出的構想力」に大きく関わる。では、「多様(雑多な感覚)を一つの形象にもたらす」ことで何が産出されるのか。カントはそれを「可能的直観の任意な形式の創造」と呼んでいる。「任意な形式」とは何か。
ヒュームにあっては、想像の場は個別のコレクション(多様なものの集まり)に過ぎなかったのだが、カントはコレクション(集まり)のなかにすでに「任意の形式」(この形式を形成するのが時間・空間ということだろう)を見ている。なぜ、任意かといえば、悟性によって規定されていないからだ。実在物との関係における表象であれば、想像力の戯れとしての美を生み出し、認識との関係においては悟性への図式をもたらすというわけだ。
これこそが『判断力批判』の美の分析論で論じられていたことである。つまり、感性と悟性を橋渡すものとしての”想像力”というわけである。この両側に向けた想像力の相貌こそが冒頭の否定・肯定につながることになる。
カントにあって興味深いのは、”想像力”の暴走(戯れ)だけを問題にしているわけではないことだ。”想像力”の暴走(空想、妄想等々)は悟性によって限界を与えられている(これが「構想力と悟性の一致・調和」としての美的判断の場である)からだ。問題は”想像”を超えること、”想像力”が及ばない領域(表象不可能性)の発見である。それが美学的判断力において付録として付け加えられた崇高の分析論というわけである。したがって、ポール・ドゥ・マンの言葉を借りれば、カントにとっての”想像力”とは感性と知性を橋渡し(接合)すると同時に、橋が取り除かれてしまう場でもあるのだ。火を吐くドラゴンはいつだってリセット願望の象徴にもなる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
