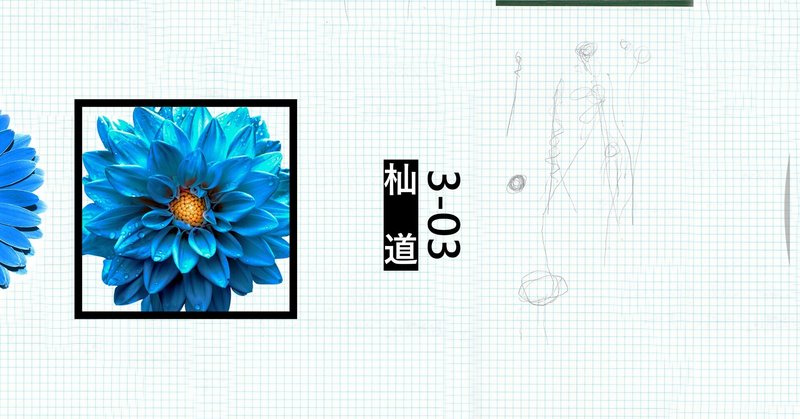
3-03 鏡像と写真、そして〈わたし〉
7人の読書好きによる、連想ゲームふう作文企画「杣道(そまみち)」。 週替わりのリレー形式で文章を執筆します。
前回はS.Sugiuraの「なにげない午後の風景」です。今回は、親指Pの「鏡像と写真、そして〈わたし〉」です。それではお楽しみください!
【杣道に関して】
https://note.com/somamichi_center/n/nade6c4e8b18e
【前回までの杣道】
3-02 「なにげない午後の風景」/S.Sugiura
https://note.com/ss2406/n/n72fe634f61de_
____________________________
「わたし」はどのようにして〈わたし(主体)〉になるのか。その一端を明らかにしてくれたのが、ジャック・ラカンの「鏡像段階」*1という概念である。生後6ヶ月後あたりの幼児は鏡に写った自分の姿を見て歓喜するという。道具的知能ではこの時期の幼児よりもはるかに優るチンパンジーは、鏡に写った自分の姿を見ても、その像が生きていないと確認してしまえば、それ以上興味をしめすことがないそうだ。人間の幼児だけが鏡像を自分の姿と思って喜ぶ能力を持っているという。こうした状態は生後18ヶ月後頃まで続くらしい。こうした幼児の行動からヒントを得て、概念化されたのがラカンの「鏡像段階」である。
鏡像に歓喜するとは、なんたる生き物か!実際、生き物としてはチンパンジーの方がはるかに健全のように思える。ラカンはこの過程に「わたし」が「主体」として形成されるメカニズムを見出したわけである。
さて、この時期の幼児は、自分という存在に対して、口や目、耳、手といった諸感覚のバラバラなイメージしかもっていない。分断された身体イメージ。ということは、自分が生きる世界も、一つのまとまりをもったゲシュタルト的な全体として構成できない。幼児は鏡に写った自分の姿を見ることで、自らの分断された身体イメージを統一的な身体として見出すことになる。ただし、いまだ未成熟な神経系器官しかもたない幼児にとっての鏡像は、いわば先取りされた「自我」の統一像ー想像的自我でしかない。ラカンはこれを「原初的な形態-理想我」と呼んでいる。幼児はこの「理想我」を獲得(実現)するために、言葉を通して二次的な同一化を試みていく。こうして(視覚優位の)イメージとしての「自我」が形成されていくことになる。
ラカンにおける「鏡像段階」という概念のポイントは、人間にはあらかじめ内的な自我というものがあるわけではなく、自我は外部のイメージを基盤にしているということである。「我とは他者なり」(ランボー)。確かに、幼児はイメージとしての統一像を先取りすることで、ある種の満足を得る。しかし他方で、その統一像は虚像であり、外部からもたらされたものでしかない。このイメージは「わたしのものか、他者のものか」。「鏡像段階」とは、自我と他者をめぐる、ある種の闘争状態、戦いの場でもあるのだ。ラカンはこうした世界を「想像界」と呼んだ。
やがて絶対的な他者-父なるものの出現によって、象徴(言葉の法)の世界-「象徴界」に入っていくことで、恒常的で統一的な、秩序ある〈わたし=主体〉を獲得していくことなる。「象徴界」は「想像界」を基盤にしていると同時に、その移行後の結果も「想像界」でのドラマ如何にかかっているともいえる。「象徴界」への移行に失敗すれば、安定した自我の獲得に至らない(例えば、統合失調症に至る)。しかし、裏を返せば、「想像界」は「象徴界」に穴を穿つ脱出口にもなるのではないか。鏡の破壊、鏡像の崩壊による「象徴界」の亀裂。
もちろんここで、ラカンの「鏡像段階」についての解釈を施したいわけではない。むしろ、素朴な思いつきを述べてみたい。「鏡像段階」の「鏡像」を「写真の像」に置き換えてみたら、どうなるかということである。もし、幼児が鏡の像ではなく、写真の像を見たならば、ということである。もちろん、事実問題ではなく、あくまでも思弁的問題として。
鏡像と写真は、同じ虚像には違いないが、似ているようで根本的に異なる。鏡の中の〈わたし〉と写真の中の〈わたし〉は違う。鏡像はいうまでもなく、左右が逆転した像(ネガ)である。したがって、鏡像はすでにして現実の〈わたし〉とズレた虚像であり、ラカンも語るように、鏡の統一像に〈わたし〉の身体が完全に重なることはない(到達できない)。対して、写真は鏡像をさらに反転した像(ポジ)である。つまり、写真は他者の眼差しによる像である。その意味では、写真はまさに完璧な他者から見た〈わたし〉の身体像にほかならない。
われわれはしばしば、録音された自分の声を聞くと、違和感を感じる。自分の声を自分で聞くことと録音された自分の声を聞くことは違う。録音された声こそが他者が聞く〈わたし〉の声である。写真にもまた同じことがいえるだろう。鏡の中に見る〈わたし〉は他者が見ている〈わたし〉ではない。いまだ確立されていない〈わたし〉が見る〈わたし〉の姿。
とするならば、「鏡像段階」の鏡像を写真に置き換えると、「想像界」における「わたしと他者」をめぐる戦いは、鏡像ほど荒々しく、苦しいものではないことにならないか。というのも、写真がすでにして他者からの〈わたし〉のイメージだとすれば、わたしと他者の葛藤は生じない。〈わたし〉の統一像は完璧に他者のものなのだから。もはや、写真の中の〈わたし〉に違和感(ズレ)を感じることもないだろう。いわんやコスプレに違和感を感じるわけがない。虚像こそがすでにして完璧な〈わたし〉であり、もはや「想像界」でのドラマを再現する必要もなければ、自我の分裂に悩むこともない。そこからどのような事態が帰結するか。他者に、虚像に、絶対的な〈父(法の世界)〉に隷属する状態か。それとも、絶対的な父が失墜し、「想像界」こそが絶対化された世界か。
注
*1:ジャック・ラカン『エクリ Ⅰ』(宮本忠雄他訳)所収の「〈わたし〉の 機能を形成するものとしての鏡像段階」を参照。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
