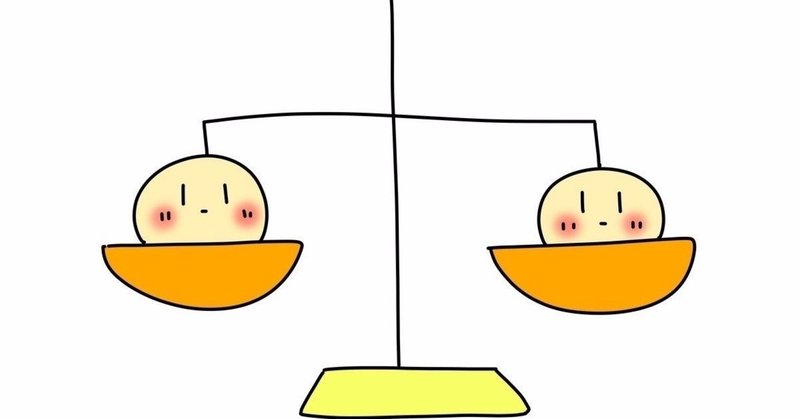
個人の安定と社会の変化をどのように結びつけるか?という問い
最近とある人と話す機会があったのですが、その中で「私は社会や経済といったマクロの観点から考えますが、菅野さんは人の考え方や心理といったミクロの観点から考えますね」というフィードバックをいただきました。
これが思ったより新鮮で、たしかに自分は当たり前のように「個人」というものに様々な現象の要因を見出しているし、だからこそ大学でも心理学を学んでいたんだろうなと思っています。
一方でその限界も見えてきていて、例えばアドラーが「すべての悩みは対人関係」と言ったりするわけですが、それは「安定した社会」の話であって、当然戦争や内紛、または今回のコロナのような危機的な社会情勢においては「対人」などと言っていられない、自分にはどうしようもできない悩みが生じてくるわけです。
もっと言うと「社会というシステム」と「個人という独立した存在=システムでありながら社会の構成要素でもあるもの」の関係性において、当然社会の変化は個人にも変化を与えうるわけです。
つまり、個人としてどれだけ安定した、幸福な状況を作り上げたとしても、社会の変化がそれを崩壊させる可能性は常に残り続けるわけです。(僕の中では「家庭の安全は赤紙に勝てない」という表現になっています。)
そこで「どうやったら社会を良い方向に変化させられるか?」という問いが常に問題になるわけですが、これも実は片手落ちの議論で、そもそも社会システムは、特定の思惑で動くにはすでに複雑になりすぎています。
もし特定の誰かや何か(例えば大統領であれ首相であれ)がその移行や崩壊を目論んだとしても、それだけでは致命的な変化にはならず、必ずそれを実行する大衆の「意思」なり「方向性」なりが必要になる(逆にいうと、それをまとめ上げれば変化が起こせる)わけです。
つまり、社会を変化させようとする場合、社会そのものではなくその構成要素であり動因でもある個人に働きかけなければならないわけですが、僕のように「個人の安定を阻害しないレベルの変化であれば興味がない」という層に対しては、そのロジックでは伝わらないわけです。
そして、さらに重要な現実として、社会は常に変化し続けています。
これは資本主義の根本が「創造と乗り越え」であり、民主主義の原理に「複数政党による選挙を通じた政権運営」がある以上、動かしがたい事実です。
すなわちここに「安定した日々を望む個人」と「変化し続ける社会」と「その変化を自分のために使いたい個人や団体」という3つの力関係が働いているのです。
しかもこれらは、決して対等なパワーバランスを持っているわけではありません。
基本的には「変化し続ける社会」が強く、その方向性を少しでも変えようと様々な人たちの思惑や行動が入り乱れている、というイメージが正しいでしょう。
注意したいのが、これは別に陰謀論などではなく、ただ人が様々な立場でこの地球上に生活している限り、当たり前に起こることだということです。
もちろん「力」がある人や団体の方が有利なのは変わりませんが、それが社会システムに直接的かつ深刻な影響を与えられるほどの「力」になることはまず無いでしょう。
なぜなら、そのような「力」が存在するのであれば必ずそれに対抗する別の「勢力」もあるはずで、それゆえにシステムはただ1つの方向に向かって変化することを免れるからです。
さて、長々と書いてしまいましたが、結局僕が言いたいことは「『安定した日々を望む個人』の力をどうしたら今よりも強められるか?」ということに他なりません。
これは「みんなで選挙に行こう!」とか「一人一人の声を届けよう!」とか、ましてや「twitterで気に入らないやつを貶めよう」とか、そういったことではありません。(むしろ最後のことはできる限り阻止しないといけないと思っています。)
そうではなく、まずは個人として自分の生活の基盤を作り、安定した状態において、そこから社会に関わる意志を持つという「その個人の変化」をいかにして生み出すか?ということです。
まさに今の自分がそうなのですが、正直社会とか政治に昔ほどの興味がありません。
それは今の生活環境である程度満たされており、幸せで、自分でコントロールできる範囲で成り立っているからです。
しかしその安定は、これまで見てきた通りに「社会システムが安定する限りにおいて」の、非常に他人頼みの安定です。
逆に、もしも自分の生活の安定を保った上で、それを補強するような方向に社会システムを進めることができるなら、そしてその実感を持つことができるなら、「社会システムの変化」が「自分の安定を補強する」という、頑健な仕組みが構築できることになります。
そしてもし、それが自分だけでなく世の中一般の、いわゆる大衆と呼ばれる人々に対しても行われるのであれば「社会が変化しながらも個々人が安定的に生活できる」という、当たり前だけれどもある種理想的な社会維持の形が見えてくるはずです。
ここで私が提示しているのは「努力して安定を達成した個人が、次に社会システムの変化にまで目を向けるために必要なメカニズムは何か?」という問いです。
個人の安定を達成する方法論はなんとなく見えていて、それはそれで向こう数年で突き詰めたい課題なのですが、多分何とかなると思っています。
一方で、望ましい社会システムについてもアレコレ議論がされており、おそらくこの辺りが落とし所ではないか?というものは、程度の差こそあれある程度見立てができるように思います。
すると最も重要なのは「どうやってその社会システムの構築・維持のための変化を(安定した)個人に担わせるか?」つまり「個人の環境を維持させることに費やす労力を社会の変化のために割く理由をどのように見出すか?」ではないでしょうか。
もっと平たく言うと「生活が崩壊しない程度に社会が安定している時代において、ある程度平穏に生きている個人が社会システムに関わるリアリズムのある理由は何か?」ということです。
この辺りが僕個人としての次の課題になりそうなのですが、そもそもこの問題設定からして一般的なものなのか、共感を得られるものなのかが分からないので、そこはこういったnoteや読書会での議論などを通じて深めていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
