過ぎ越しの食事(1)
【聖書箇所】マルコによる福音者14章12〜21節
並行箇所
マタイによる福音書26章17〜52節
ヨハネによる福音書13章21〜30節
ルカによる福音書22章1節~23節
↓
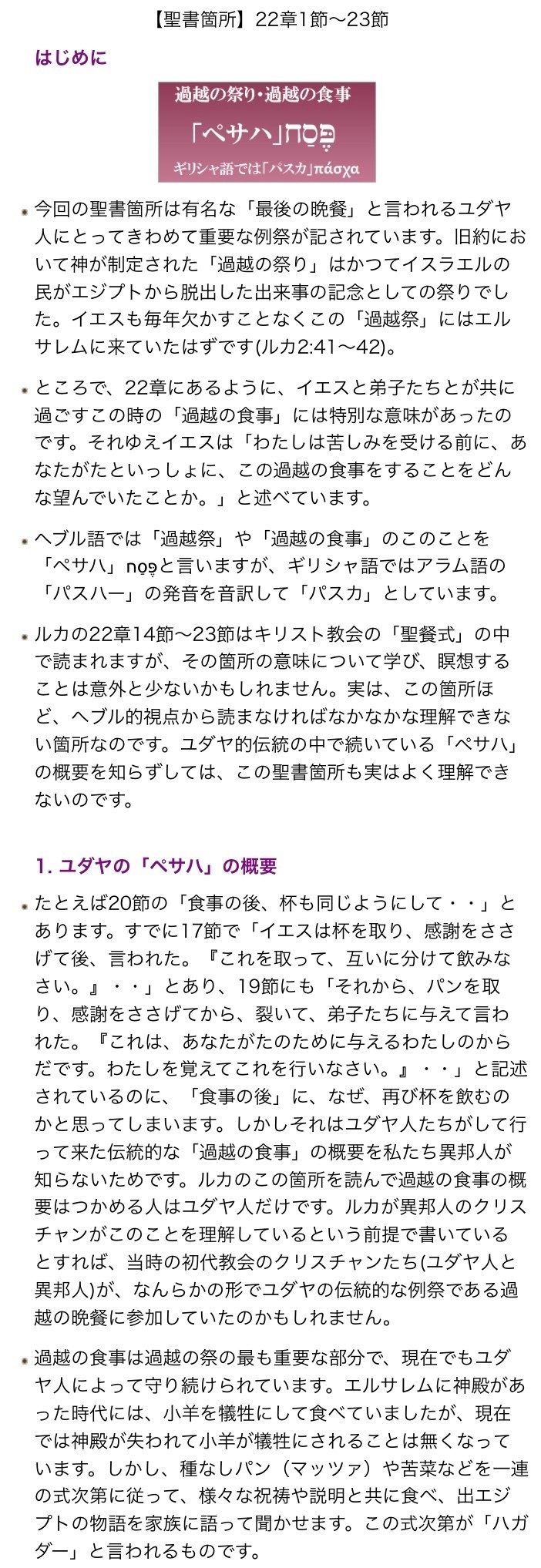
今回の聖書箇所は有名な「最後の晩餐」と言われるユダヤ人にとってきわめて重要な例祭が記されています。
旧約において神が制定された「過越の祭り」はかってイスラエルの民がエジプトから脱出した出来事の記念としての祭りでした。イエスも毎年欠かすことなくこの「過越祭」にはエルサレムに来ていたはずです。
2.41 さて、イエスの両親は、過越の祭には毎年エルサレムへ上っていた。
2:42 イエスが十二歳になった時も、慣例に従って祭のために上京した。
(ルカ2:41~42)。
ところで、22章にあるように、イエスと弟子たちとが共に過ごすこの時の「過越の食事」には特別な意味があったのです。
それゆえイエスは「わたしは苦しみを受ける前に、あなたがたといっしょに、この過越の食事をすることをどんな望んでいたことか。」と述べています。
ヘブル語では「過越祭」や「過越の食事」のこのことを「ペサハ」nogと言いますが、ギリシャ語ではアラム語の「パスハー」の発音を普訳して「パスカ」としています。
ルカの22章14~23節はキリスト教会の「聖餐式」の中で読まれますが、その(最後の晩餐の)箇所の意味について学び、瞑想することは意外と少ないかもしれません。
実は、この箇所ほど、ヘブル的視点から読まなければなかなかな理解できない箇所なのです。ユダヤ的伝統の中で続いている「ペサハ」の概要を知らずしては、この聖書箇所も実はよく理解できないのです。
1. ユダヤの「ペサハ」の概要
たとえば20節の「食事の後、杯も同じようにして・・」とあります。すでに17節で「イエスは杯を取り、感謝をささげて後、言われた。『これを取って、互いに分けて飲みなさい。』・・」とあり、
19節にも「それから、パンを取り、感謝をささげてから、裂いて、弟子たちに与えて言われた。『これは、あなたがたのために与えるわたしのからだです。わたしを覚えてこれを行いなさい。』・・」と記述されているのに、
「食事の後」に、なぜ、再び杯を飲むのかと思ってしまいます。
しかしそれはユダヤ人たちがして行って来た伝統的な「過越の食事」の概要を私たち異邦人が知らないためです。
ルカのこの箇所を読んで過越の食事の概要はつかめる人はユダヤ人だけです。ルカが異邦人のクリスチャンがこのことを理解しているという前提で書いているとすれば、当時の初代教会のクリスチャンたち(ユダヤ人と異邦人)が、なんらかの形でユダヤの伝統的な例祭である過越の晩餐に参加していたのかもしれません。
過越の食事は過越の祭の最も重要な部分で、現在でもユダヤ人によって守り続けられています。
エルサレムに神殿があった時代には、(傷の無い)小羊を犠牲にして食べていましたが、現在では神殿が失われて小羊が犠牲にされることは無くなっています。
しかし、種なしパン(マッシア)や苦菜などを一連の式次第に従って、様々な祝祷や説明と共に食べ、出エジプトの物語を家族に語って聞かせます。この式次第が「ハガダー」と言われるものです。

ペサハ」の概要(式次第=「ハガダー」)は以下のとおりです。
1.前半(儀式的な食卓)
(1) 蝋燭の点火と祈り
(2) 子どもの祝福(父親が子どもたちを祝福します)
(3)最初の杯が満たされ、回し飲みされる。
(4)水差しで両手を洗い、野菜を塩水に浸す(塩水はユダヤ人の苦難の歴史を意味する)。
三枚に重ねられた種なしのパン(マッツァ)の中から真ん中のマッツアを取り、それを二つに割って(裂いて)、一方を布に包んで置きます。
(5)二杯目の杯が満たされ、回し飲みされる(ルカ22:17)、エジプトでの苦難の歴史が語られる。
(6)詩篇113篇と114篇が食前の祈りとして唱えられる。
(7) 再度手を洗い、マッツァが割られて配られ、各自それを取り(ルカ22:19)、苦菜をドレッシングに浸し、マッツァと重ねられる。
またパンを取り、感謝してこれをさき、弟子たちに与えて言われた、「これは、あなたがたのために与えるわたしのからだである。わたしを記念するため、このように行いなさい」。
・これらを口にするのは、食事の儀式に従ってその都度一斉に行われる。
儀式的な食事はここで中断し、夕食をくつろいだ雰囲気のうちに楽しむ。
2.後半(儀式的な食卓)
(1)食事の後、第三の杯が満たされ(ルカ22:20)、感謝の祈りがささげられる(かなり長い)。
(2) 第四の杯が満たされ、詩篇115、116、117、118篇、および詩136篇を食後の祈りとして唱える。
(3)「来年こそはエルサレムで」(離散ユダヤ人のためのもの)
イスラエル在住者は再建されたエルサレムで」と唱和して式は終わる。
このように、伝統的な「ペサハ」の式次第の中でイエスが語られたことばを理解すると、不思議と流れが見えてきます。前半の冒頭部分は完全に省略されています。
ルカの福音書では、儀式的な食卓の前半の最後の部分と同じく儀式的な食卓の後半部分の冒頭で語られたイエスのことばが記載されているのです。

ちなみに、福音書にはイエスが弟子たちと共に食事をする場面が何度も出てきますが、食卓用語と言われる語彙が他にもあります。
2.「食卓に着く」という表現
過越の食事をするために、イエスもその弟子たちもみないっしょに「食卓に着いた」と聖書は記していますが、その光景は私たちが想像するような食卓ではありません。
「食卓に着く」と訳されたと動詞は「アナピプトオー」は「横たわって食事を摂る」ことを意味します。
レオナルド・タ・ヴィンチの「最後の晩餐」の絵があまりにも有名なために、皆が椅子に腰かけて食卓を囲んでいる晩餐をイメージしてしまいますが、それはヨーロッパのイメージです。
昔の日本でも食卓に着くといえば、丸い茶たくの周りに家族が座って食事をするイメージですが、ユダヤにおいては全員が横たわって食事を摂ったのです。
それがユダヤの正式の食卓であり、客を招待してもそれは変わることのない習わしであったようです。
「横たわって食事を取る」姿勢では、それぞれ自分用のクッションに左肘をついて上半身を支え、足は後方に投げ出します。そして自由な右手で中央の座に置かれた食物を取って食べます。終始この姿勢では辛いので、過越の食事では、杯を飲むときや、苦菜を食べるとき祭には、身体を起こすように決められていたようです。
全体の位置関係は、首が中央に集まり、足は放射状に外側に向けられた方です。
ルカ22:12の「席が整っている二階」という言葉がありますが、それはクッションが人数に合わせて円形状に並べられている状態を意味します。
(前島誠「ナザレ派のイエス」240~245頁参照)。
ちなみに、福音書にはイエスが弟子たちと共に食事をする場面が何度も出てきますが、食卓用語と言われる語彙が他にもあります。

3.キリスト教会における「ペサハ」の日についての大論争
イエスは最後の晩餐のときに「わたしを覚えてこれを行いなさい」(22:19)と言われました。これがやがてキリスト教の歴史の中で「聖餐式」として制定されるようになります。
しかし、はじめからそうであったわけではありません。この当たりの歴史的変遷について、メシアニック・ジューであるデビッド・J・ルドルフ氏が次のように述べています。
1.第一世紀における教会と過越祭
そもそも過越の食卓に預かるということは、神との契約関係に入っている、神の民の一部であるということを確認するためのものでした。
ですから、キリスト以前の時代においては、異邦人はアブラハムの契約から除外されたものとして、そもそも神殿犠牲を含む契約的な象徴に一切預かることができなかったのです。
逆に、もし異邦人が、それに参加できるようになるとすれば、それはとりもなおさず、異邦人であっても、神の契約の民、神の家族の一員としての特権的な地位を与えられたということを意味するものになったはずです。
こう考えると、初代教会の使徒たちは、新約聖書に記されたその神学的な確言を根拠とする限り、異邦人信者らを自分たちの祝う過越祭とその食卓に参加させていたということを、私たちはほぼ間違いなく推論できると思うのです。
パウロは、今や、キリストにあって、異邦人信者も、オリーブの木であるイスラエルに接ぎ木され、神の民の一部となったと語っています。
そうだとするなら、異邦人信者も、キリストにあって、神との契約関係を象徴的に確認する過越祭に参加することに問題はないと考えたはずです。
それどころか、パウロにとっては、異邦人信者がメシアニック・ジューの兄弟たちとともに過越しの食卓に着くことこそ、今やキリストにあって、ユダヤ人と異邦人が一つの民となったという福音の真髄を象徴する出来事として、非常に重要視したであるうことが十分推測されます。

当時、エルサレム神殿には、「異邦人立入禁止」という札が掲げられた壁が立てられていました。もし、禁を破って異邦人が入ったなら死刑となりました。
しかし、パウロは、今や、キリストにおいて、この「隔ての壁」は打ちこわされたと書いています(エペソ二・14)。
主の目には、異邦人信者は主の御体を通して神殿へ入ることができる、と見なされたのです。
!コリント五・7-8で、パウロは、異邦人者に向かって「(過越)祭りをしようではないか。」と呼びかけています。
5.7
新しい粉のかたまりになるために、古いパン種を取り除きなさい。あなたがたは、事実パン種のない者なのだから。わたしたちの過越の小羊であるキリストは、すでにほふられたのだ。
5:8
ゆえに、わたしたちは、古いパン種や、また悪意と邪悪とのパン種を用いずに、パン種のはいっていない純粋で真実なパンをもって、祭をしようではないか。
もちろん、これは広い倫理的な文脈で語られた言説であり、直接、過越祭への参加問題を論じるものではありませんが、その前提として、そもそも異邦人信者が過越祭を祝う権利がまったくないと考えられていたとすれば、およそこのような表現は適切な比喩ではないはずです。
逆に、このような比喩が十分意味を持ち得る前提として、パウロは、異邦人信者に過越祭の食卓に預かる権利のあることを、積極的に認めていたことが推論できるのです。
こうして、第一世紀の頃、異邦人信者が過越の祭りを祝うことは、すばらしい特権であったということができると思います。

2.第二世紀における教会と過越祭:時期に関する東方教会と西方教会の大論争
●第一世紀の頃、異邦人信者が過越の祭りに参加したのかどうかの証拠はありませんが、二世紀の諸教会が過越しの祭りを祝っていたことを示す証拠は残っています。もし、一世紀の頃、異邦人信者が過越祭を祝いたくないと思っていたとしたら、二世紀に過越祭が教会で祝われるということはおよそなかったでしょう。
しかし、実際には二世紀の時点で、過越の祭りは異邦人信者の中で行われていたのです。
二世紀の頃、大きな議論が異邦人教会の中で持ち上がりました。それは、過越祭を祝うべきかどうか、という問題ではなく、いつ祝うのか、という問題でした。
四世紀の教会史家であるエウセビオスの「教会史」には、二世紀の教会に起こった「過越祭をいつ祝うのか」ということに関する大論争の記録が記されています。その論争というのは、過越祭は、聖書通り、ユダヤ暦第一月(ニサン) 14日に祝うべきなのか、それともニサン14日後のはじめの日曜日に祝うべきなのか、というものでした。注意してほしいのは、これは、メシアニック・ジューと異邦人者との争いではなく、異邦人者同士、つまり、東方教会と西方教会との間の論争だったということです。
東方教会というのは、今のイスラエルやシリア、メソポタミヤ地方、トルコなどに広がる地域の教会で、実際にパウロやヨハネ、ペテロなどの使徒達が行き巡った場所でしたので、使徒的な伝統が良く保持されていました。東方教会では、ほぼ全域に渡って、神学的にも、また使徒的伝統としても、過越祭がニサン14日に祝われていました。しかも、彼らはそれぞれの地方のユダヤ人共同体と一緒に過越祭を祝っていたのです。
これに対して、西方教会というのは、今のイタリア、スペイン、ギリシャ、ゴート(フランスやベルギ一、西ドイツ地方など) そしてイギリスの地域にわたる教会で、彼らは過越祭をニサン14日の後にくる日曜日に行なっていました。そして、過越祭という言葉を使ってはいましたが、その内容は、むしろ主の復活という要素を強調していました。西方教会の意図は、ユダヤ人と一緒に過越しの祭りを祝いたくないし、ユダヤ人と同じ日に、同じスタイルでこれを祝いたくないというものでした。つまり過越祭の「脱ユダヤ化」を目指していたのです。名前だけは、過越祭としながら、その内容は本来のものとはどんどんかけ離れていってしまいました。それでも、「過越祭」という名称は、実に、8世紀まで、西方教会の中で使われていたことが記録されています。

西方教会(ローマ司教ビクトル)は、東方教会が過越祭をニサン14日に祝っているというだけで、東方教会全体を破門しようとしました。
これに対して、ポリュクラテスをはじめとする東方教会の司教たちは、使徒たちから受け継いだ伝統を止めてしまうよりは、破門されたほうがましだと主張したのです。
このとき、東方教会がどれほど強い気持ちでこれを主張したか、を考えて頂きたいのです。二世紀の時点では、異邦人教会の半分(東方教会)が、いかにニサン14日に過越祭を祝うことを大切に思ってきたかがここからも分かります。
次第に西方教会のキリスト教会全体に対する影響力と優位性が確立されるようになると、それにつれて、東方教会の使徒的慣習は不利な立場に追い込まれていきます。
そして、四世紀になって、最終的には、西方教会は武力を背景とした圧力の下で、東方教会の使徒的伝統・慣習を消滅させることになります。
それはコンスタンティヌス帝の政治的野心による教会統合政策の一環として開催されたニカイヤ公会議(紀元325年)において、決定付けられました。
2004年4月9日 於) 日之出キリスト教会
「シオンの喜び」春の記念聖会・デビッド・J・ルドルフ師講演より
もし、このデビッド・J・ルドルフ師の言うことが正しければ、「置換神学」がどのようにしてキリスト教会の中に定着し、脱ユダヤ化を生んでしまったかを知ることができます。
なぜ、ヨーロッパのキリスト教の歴史の流れにおいて、ヘブル的視点が欠落してしまったか、その経緯も理解できます。
使徒パウロは異邦人クリスチャンを「野生種のオリーブ」にたとえており、あくまでも「栽培されたオリーブ」(ユダヤ人)に接木されたものにすぎないこと、あなた(異邦人クリスチャン)が根(ユダヤ人)をささえているのではなく、根(ユダヤ人)があなた(異邦人)を支えているというこの奥義を知ってほしいと記しています。
なぜなら、(異邦人クリスャンが)自分を賢い者と思うことのないようにするためです。
ローマ11章18〜25節)。
最後に聖書の理解をヘブル的視点から読み直すことは、今や急務であると思わせられます。
キリスト教会は、神のトーラーを授けられたユダヤ人から、特にメシアニック・ジューと言われる人々の聖書解釈から新しいいのちの水を引く必要性があるように思います。これは終わりの時代に向けられた神の摂理であると言じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
