枯れたいちじくの木【聖書箇所】マタイの福音書21章18~22節

ベレーシート
今回の箇所(特に 21~22節)は聖書の中でも難解な箇所と言われています。なぜ難解なのでしょうか。おそらくそれは、神のご計画の全体像を知る知識が希薄であることに起因していると思われます。
イエシユアの語られたすべてのことばは御国の福音についてであることを忘れてはいけないのです。その視点から語られているということを知ることが、この箇所を理解する上で重要なことです。
今日のテキストです。
【新改訳 2017】マタイの福音書21章 18~22節
さて、朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。
道端に一本のいちじくの木が見えたので、そこに行って見ると、葉があるだけで、ほかには何もなかった。それでイエスはその木に「今後いつまでも、おまえの実はならないように」と言われた。すると、たちまちいちじくの木は枯れた。
弟子たちはこれを見て驚き、「どうして、すぐにいちじくの木が枯れたのでしょうか」と言った。
イエスは答えられた。「まことに、あなたがたに言います。もし、あなたがたが信じて疑わないなら、いちじくの木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かい、『立ち上がって、海に入れ』と言えば、そのとおりになります。
あなたがたは、信じて祈り求めるものは何でも受けることになります。」
1. 空腹を覚えられたイエシュア
【新改訳 2017】マタイの福音書21章18節
さて、朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。
18節には、「さて、朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。」とあります。
「朝早く都へ向かう途中」ではなく、「朝早く都に帰る途中」となっています。
面白い表現です。
なぜこんな書き方をしているのでしょうか。イェシュアにとって、エルサレムの神殿は「わたしの家」であるからです。
さて、ここで、イェシュアが「空腹を覚えられた」とあります。
滞在先のベタニアで朝食を食べることができなかったということではありません。もしそのように読むならば、的はずれの解釈となります。
イエシュアが「空腹を覚えられた」という記述が公生涯の最初と終わりにあります。
その最初は悪魔の試みを受けるために荒野で40日間を過ごした時(4:2)であり、最後はエルサレムでの最後の一週間の滞在中です(21:18)です。
「空腹を覚える」と訳されたギリシア語「ペイナオー」()は、マタイの福音書25章では、「羊

と山羊のたとえ話」で「あなたがたはわたしが空腹であったときに食べ物を与え、渇いていたときに飲ませ、・・」(25:35)とあります。
ここでの「あなたがた」とは、終わりの日に、(ヤコブの苦難の時に)未曾有の苦難を経験するイスラエルの民(正確には「残りの者たち」)を助けることになる異邦人のことを指しています。
いずれにしても、「空腹になる」こと、「飢饉」は、信仰の危機を意味します。すなわち、「空腹を覚えられる」とは、イスラエルの民の信仰が危機にさらされていることを意味しているのです。
40日間の断食をしたイエシュアは肉体的には限界に達していたでしょうが、「神の口から出る一つ一つのことば」によって霊的な糧で満たされていたのです。
そのイエシュアが「空腹を覚えられた」というのは、神のことばによって生きることができていないイスラエルの民の信仰に対して、霊的な危機感を感じられたと解釈できます。このことは今回の「実を結ばないいちじくの木」によって強調されています。
2.いちじくの木
【新改訳 2017】マタイの福音書21章19節
道端に一本のいちじくの木が見えたので、そこに行って見ると、葉があるだけで、ほかには何もなかった。それでイエスはその木に「今後いつまでも、おまえの実はならないように」と言われた。
すると、たちまちいちじくの木は枯れた。
【新改訳 2017】エレミヤ書2章 24,26節
24 また、欲情に息あえぐ荒野に慣れた野ろばだ。さかりのとき、だれがこれを制し得るだろう。
これを探す者は苦労しない。発情の月に見つけることができる。
26盗人が、見つかったときに恥を見るように、イスラエルの家も恥を見る。彼らの王たち、首長たち、祭司たち、預言者たちも。
エレミヤ書2章では、偶像礼拝をするユダの民が糾弾されています。そこでは神とイスラエルの民とのかかわりが「夫婦」に響えられています。
2章1節に一回だけ使われているヘブル語があります。それは「ケルーロート」(כלולות)です。この語彙をいろいろな聖書が以下のように訳しています。
【新改訳 2017】「婚約時代の愛」、
【口語訳、新共同訳、岩波訳】「新婚時代の愛」
【関根訳】「新嫁の時の愛」
【パルバロ訳】「許嫁のころの愛」
【文語訳】「(ちぎり)をなせしときの愛」)。
神とイスラエルのかかわりは麗しいものであったのです。
日本では婚約と結婚は区別されますが、ヘブルの社会では「婚約」と「結婚」は同義でした。「婚約」「新婚」も含めた「蜜月」(ハネムーン)の時の愛は、まさにイスラエルの主に対する「真実の愛」を意味するへブル語「ヘセド」(חסד)でした。
このへセドは本来、「神」の「人」に対する恩寵用語であり、確固としたゆるぎない愛を意味するのですが、ここでは珍しく「人」から「神」への態度として用いられています。
そしてそこから生み出される主への「従順」(歩み)を、主は忘れることなく覚えておられたのです。
ところが、神の民はその「はじめの愛」から離れてしまったのです。離れてしまっただけでなく、彼らは二つの悪
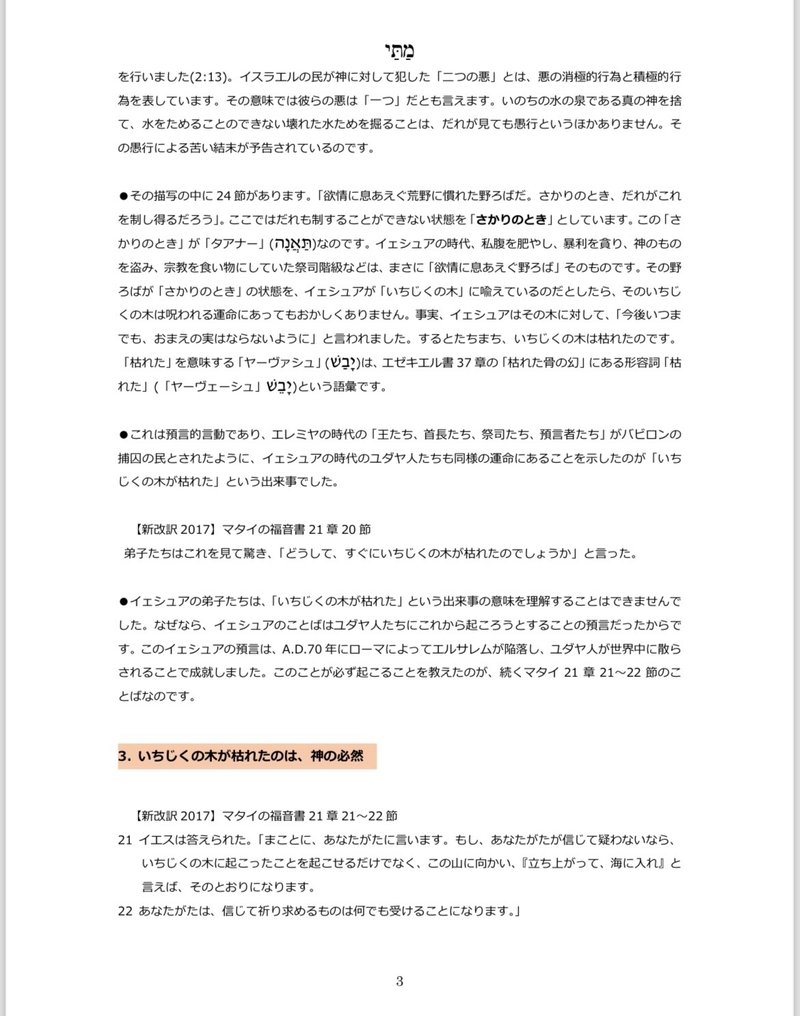
を行いました(2:13)。
イスラエルの民が神に対して犯した「二つの悪」とは、悪の消極的行為と積極的行為を表しています。
その意味では彼らの悪は「一つ」だとも言えます。
いのちの水の泉である真の神を捨て、水をためることのできない壊れた水ためを掘ることは、だれが見ても愚行というほかありません。
その愚行による苦い結末が予告されているのです。
その描写の中に 24節があります。
「欲情に息あえぐ荒野に慣れた野ろばだ。さかりのとき、だれがこれを制し得るだろう」。
ここではだれも制することができない状態を「さかりのとき」としています。
この「さかりのとき」が「タアナー」(תאנה)なのです。イエシュアの時代、私腹を肥やし、利を負り、神のものを盗み、宗教を食い物にしていた祭司階級などは、まさに「欲情に息あえぐ野ろば」そのものです。
その野ろばが「さかりのとき」の状態を、イェシュアが「いちじくの木」に喩えているのだとしたら、そのいちじくの木は呪われる運命にあってもおかしくありません。
事実、イェシュアはその木に対して、「今後いつまでも、おまえの実はならないように」と言われました。するとたちまち、いちじくの木は枯れたのです。
「枯れた」を意味する「ヤーヴァシュ」(יבש)は、エゼキエル書37章の「枯れた骨の幻」にある形容詞「枯れた」(「ヤーヴェーシュ」יבש)という語彙です。
●これは預言的言動であり、エレミヤの時代の「王たち、首長たち、祭司たち、預言者たち」がバビロンの捕囚の民とされたように、イェシュアの時代のユダヤ人たちも同様の運命にあることを示したのが「いちじくの木が枯れた」という出来事でした。
【新改訳 2017】マタイの福音書21章20節
弟子たちはこれを見て驚き、「どうして、すぐにいちじくの木が枯れたのでしょうか」と言った。
イェシュアの弟子たちは、「いちじくの木が枯れた」という出来事の意味を理解することはできませんでした。
なぜなら、イエシュアのことばはユダヤ人たちにこれから起ころうとすることの預言だったからです。
このイエシュアの預言は、A.D.70年にローマによってエルサレムが陥落し、ユダヤ人が世界中に散らされることで成就しました。
このことが必ず起こることを教えたのが、続くマタイ 21章21~22節のことはなのです。
3.いちじくの木が枯れたのは、神の必然
【新改訳 2017】マタイの福音書21章21~22節
イエスは答えられた。「まことに、あなたがたに言います。もし、あなたがたが·信じて疑わないなら、いちじくの木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かい、『立ち上がって、海に入れ』と言えば、そのとおりになります。
あなたがたは、信じて祈り求めるものは何でも受けることになります。」

21節にあるイェシュアの「まことに」(「アーメーン」אמן)ということばと、「もし、あなたがたが、じて疑わないなら」には共通の語源があります。
それを説明する前に、後者のギリシア語原文は「もし、あなたがたが、信仰を持っているなら、そして、あなたがたが疑わないなら」となっています。
これは同義的パラレリズムで、強調されているのは「信仰」です。
ヘブル語に訳すなら「エムーナー」(אמןנה)で、それは神への不動の信頼を表わします。
「アーメーン」(副詞)も「エムーナー」(名詞)も、いずれもへブル語の「アーマン」(אמן)から派生しています。
それは「神の約束は真実であり、確かであり、信頼されるべきもの」という意味です。
つまり、神のご計画や神の約束に対する信頼を意味することはなのですが、それらが意味する内容を知るために、語源の「アーマン」(אמן)の初出箇所である創世記 15章を見てみましょう。
創世記 15章はアブラムに対する神の約束とそのご計画が語られている箇所です。
神の約束の要点は二つあります。一つはアブラムの子孫が星のように多くなること。
もう一つは彼の子孫に土地が賦与されるということです。
その範囲はエジプトの川から大河ユーフラテス川までであり、アブラムがその生涯に歩いた範囲です。
その約束が実際どのようにして実現されるのか、アブラムは質問しました。
その答えはひとつの契約の中に啓示されました。
その契約は契約の当事者同士が切り裂かれた動物の間を通り過ぎることで結ばれるものですが、いざそれをしようとしたときにアブラムに深い眠りが襲い、その間に神である主だけがそこを通り過ぎました。
一方的ですが、通り過ぎた主にはその約束を履行する責任が生じるのです。
【新改訳 2017】創世記15章12~17節
日が沈みかけたころ、深い眠りがアブラムを襲った。そして、見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。
主はアブラムに言われた。「あなたは、このことをよく知っておきなさい。
あなたの子孫は、自分たちのものでない地で寄留者となり、四百年の間、奴隷となって苦しめられる。しかし、彼らが奴隷として仕えるその国を、わたしはさばく。
その後、彼らは多くの財産とともに、そこから出て来る。あなた自身は、平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。
そして、四代目の者たちがここに帰って来る。・・・・」
日が沈んで暗くなったとき、
見よ、煙の立つかまどと、燃えているたいまつが、切り裂かれた物の間を通り過ぎた。
この契約における重要な点は、「見よ、煙の立つかまどと、燃えているたいまつが、切り裂かれた物の間を通り過ぎた。」という部分です。
切り裂かれた物の間を通り過ぎたのは、「煙の立つかまどと、燃えているたいまつ」と表現していることです。
しかしこの表現は「神である主」を表わしていると同時に、神が約束をどのようにして実現するかという方法をも啓示しているのです。
その方法とは「煙の立つかまどと、燃えているたいまつ」に象徴されます。省略するなら、「かまど」と「たいまつ」です。
それは「苦しみと解放」「さばきと回復」「審判と救い」とも言い換えることができます。この二つの出来事を通して、神のご計画と約束が実現されるということです。
これをじることが、聖書のいう「信仰」なのです。
キリストの十字架の出来事の予表

話をマタイに戻しましょう。「いちじくの木」はイスラエルを意味しています。その木が枯れるとは「かまど」に徴される出来事です。
しかも、「いちじくの木」が今度は「この山」と言い換えられます。
聖書で「この山」といえばエルサレムのことです。
そのエルサレムに向かって、「立ち上がって、海に入れ」(=原文「持ち上げられよ。そして、海に投げ込まれよ」)は、異邦人の手に落ちて、ユダヤ人たちが世界中に散らされることを意味します。
「海」は、聖書においては「異邦人の諸国」の象徴なのです。これはイスラエルの民とエルサレム(神殿)が再び建て直されるために、通らなければならない神の必然的出来事なのです。
エルサレムの回復
エルサレムの神殿(宮)の回復
12の意味
ですから、イエシュアが弟子たちに「もし、あなたがたが信じて疑わないなら、いちじくの木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かい、『立ち上がって、海に入れ』と言えば、そのとおりになります」と言ったのは、神のご計画において必ずそのようになるという信仰を持つことを求めているのです。
さらに、22節の「あなたがたは、信じて祈り求めるものは何でも受けることになります。」とは、未来のことです。
21節と22節はあくまでも国の到来について語っています。つまり、イエシュアの初臨と再臨の間に起こることが語られているのです。
ですから、弟子たちが御国の約束を知り、またそれをもたらす神のご計画をじ信て祈り求めることは「何でも(=すべて)受け取ることになる」(未来形)ともイエシュアは言っています。
「何でも受けることになる」の「何でも」とは神のみこころにそった「何でも」であり、しかもそれを「受けることになる(受け取る)」のは将来のこと、つまり、国が完全に到来するキリストの再臨の時です。
これが天の国の福音における「いちじくの木」に込められたメッセージです。それゆえ、神のご計画の全体を知ること、そしてその中にある神の約束を知ることは、とても大切なことではないでしょうか。
4. エルサレムに対する主のみこころ
神は「煙の立つかまどと、燃えているたいまつ」によってご自身の計画と約束を実現されます。
「煙の立つかまどと、燃えているたいまつ」はワンセットです。したがって、イスラエルを徴するいちじくの木が「枯れた」ことで終わるのでは決してないことをじなければなりません。
なぜなら、神は「燃えるたいまつ」(原文は「火の松明」「ラッピード・エーシュ」לטיד אש)であることを暗に示しているからです。
シオンの義が朝日の如く輝き、、
【新改訳 2017】イザヤ書62章1節
シオンのために、わたしは黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。
その義が明るく光を放ち、その救いが、たいまつのように燃えるまでは。
(※シオンはエルサレムの詩的表現、エルサレムの救いを「たいまつのように燃える」ことに答えています。)
●枯れたいちじくの木の再生、海に入れられるエルサレムの救い、回復と再建を信じる仰こそが、聖書のいう信仰であり、その信仰が神の前に義(=神に対する人間の正しいかかわり)と認められるのです。
『義』
イェシュアの中に潜り込む信仰
(イェシュアの中に入る信仰)

ベアハリート
イスラエルの歴史を特徴づける三つの木
●「いちじくの木」についてイエシュアが言及されるのは、今回の箇所と24章32~33節です。そこで、聖書には「イスラエルを象徴する三つの木」があることを述べ、その中の「いちじくの木」の意義について述べておきたいと思います。
イスラエルを象徴する三つの「木」
(1) 「ぶどうの木」・・・出エジブトの出来事からバビロン捕囚までのイスラエル。
(2)「いちじくの木」・・イエシュアの初臨から再臨までのイスラエル。
(3)「オリープの木」・・イスラエルの将来。イエシュアの再臨後のイスラエル。
(1)ぶどうの木・・・旧約における「ぶどうの木」のたとえの系譜
●神の民イスラエルは「ぶどうの木」にたとえられます。以下、聖書の箇所だけを列記しておきます。
①詩篇 80篇8~14節②イザヤ書5章2,4節③エレミヤ書2章21節 ④エゼキエル書15章1~8
節
(2)いちじくの木・・「いちじくの木」についてのイエシュアの預言
今回のテキストなので省略します。
【新改訳 2017】マタイの福音書 24章 32~33節
いちじくの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出て来ると、夏が近いことが分かります。
同じように、これらのことをすべて見たら、あなたがたは人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。
ここでの「枝が柔らかになって葉が出て来ると」という表現は、イスラエルが国として復興すること(1948年)を預言していると考えられます。
それはイエシュアの再臨がいよいよ近づいていることを示しています。イスラエルにおいて「夏」は、秋である終わりの時代(仮庵の祭り)にますます近づいている季節なのです。
(3) オリーブの木・・使徒パウロの「オリーブの木」のたとえ
●「ぶどうの木」が過去のイスラエル、「いちじくの木」がイェシュアの初臨から再臨までのイスラエルを象徴とするならば、「オリーブの木」は将来のイスラエル、つまり、再臨後の回復を徴しています

ローマ人への手紙9~11章は、これら全体が包括されています。9章にはエジブトから携え出されて、カナンの地に植えられた選びの民、つまり、ぶどうの木として記されています。
10章にはイスラエルと預言されていた福音が述べられており、神は御子によって、農夫のように、いちじくの木の周りに肥料をやりましたが、その結果は良くありませんでした(ルカ13:6~9)。
しかし、11章では下図にあるように、オリーブの根が本全体に豊かな養分を与えながら、やがて豊かな実りをもたらします。
「折られた枝」は、不信仰なユダヤ人
「接ぎ木された枝」は、異邦人信者
「自然な枝」は、ユダヤ人信者(メシアニック・ジュー)
「折られたが再び接ぎ木される枝」は、メシア再臨前にイェシュアをメシアと信じるユダヤ人=「イスラエルの残りの者たち」
オリーブの木
ローマ11:17~24
●教会は、②と③の共同体です。
折られた枝
不信仰な
ユダヤ人
再び接ぎ木される枝
自然な枝
ユダヤ人信者
異邦人
異邦人
接ぎ木された枝
神の
霊的祝福
●イスラエルが頑なになってしまったことは、神がご自分の民を退けてしまったのではないことを、使徒パウロはローマ 11章で「神の賜物と召命は取り消されることがない」(11:29)と語っています。
なぜなら、教会が天に引き上げられた(携挙された)のちに、イェシュアをメシアとして拒否していたユダヤ人が回心して、びオリーブの木に継ぎ合わされるからです。
ここにイスラエルの将来があります。
そして、イスラエルは再び地上で神を証しする時が来ます。オリーブの木の根は決して枯れることがないのです。
「野生のオリーブ」であったが、接ぎ木されてオリーブの木の根から養分を受けて完成した教会と、再度オリーブの木につながれるイスラエルは、メシア王国(千年王国)において再び一つに結び合わされるのです。
なぜなら、彼らはみな「神のことば」である木を食べることでイエシュアと「一つ」とされるからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
