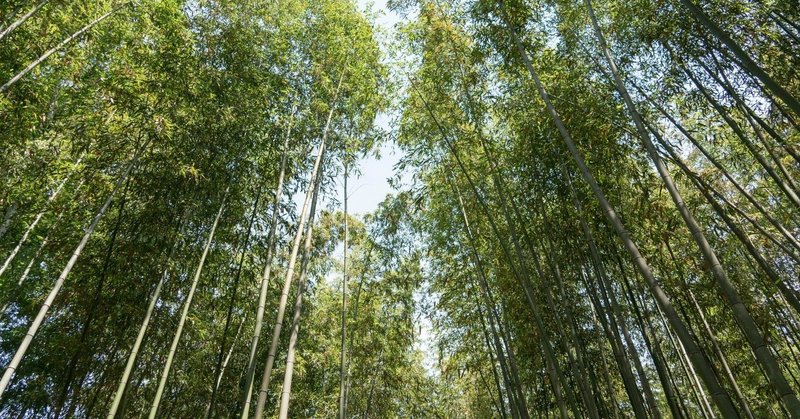
「おのまとぺ」と「ジブリッシュ」
「ジブリッシュ」とは、ざっくり言うと、「でたらめことば」のことです。
私は、これを、インプロ(即興演劇)のワークショップで知りましたが、
「ペルシャのスフィ神秘家によって開発された」という説があるそうです。
私たちは、ことばとは論理的なものだと思っています。
意味のないことばは、会話の役には立たない、
コミュニケーションがとれないと思っているかもしれません。
けれども、ことばの意味をもたない発語にも、意味はあります。
それは、感情や感覚を伝えられる、ということです。
たとえば、赤ちゃんの語ることば(喃語)は、ほぼほぼジブリッシュです。
けれども、赤ちゃんのことばを聴いて、
「意味がわからん、ちゃんとしゃべりなさい!」と怒るひとはいません。
それどころか、「あ~、そうなの、おなかすいたよねえ」
など、勝手に意味を解釈します。
そして、それはけっして的はずれではないのです。
ことばそのものより、声のニュアンス、強弱、雰囲気によって、
赤ちゃんの伝えたい気持ちを察するからです。
「おのまとぺ」が、感覚・感情から生まれる表現だとしたら、
「ジブリッシュ」とも通じるものがあるのではないか、
というのが、今日の私の思いつきです。
「ジブリッシュ」を使うとき(少なくとも私は)、
こころが自由になります。
論理を組み立てる必要がないので、
頭のなかを、風が通り抜けていくような、フリーな感覚になります。
たとえば、ある~日、森のなか~、熊さんと出会った~♪ とします。
そのときに、びっくりしたとすると、おのまとぺなら、
「ぎょぎょっ」とか、「どきーん」なんて表現になるかもしれません。
ジブリッシュであれば、その「ぎょぎょっ」とか「どきーん」が、
さらに、意味をなさない音で表現されます。
「ボビベロブァ!」とか、「ガドチョ!」なんてね。
でも、それって、やっぱり、おのまとぺそのまんまですよね。
つまり、昨日も書いたように、
「使った瞬間に、そのおのまとぺが、この世界に出現する」ように、
ジブリッシュも、使った瞬間に、
そのジブリッシュがこの世界に出現するのです。
しいてちがいを言えば、おのまとぺは、再現できる可能性がある
のにたいして、ジブリッシュは、その場かぎりのもの。
再現性はないし、再現した瞬間に、
ジブリッシュ(でたらめことば)ではなくなってしまいます。
ただ、ジブリッシュのなかで、もう一度使いたい表現が生まれたとき、
それが、おのまとぺになっていく可能性はあるかもしれません。
「ぎょぎょっ!」と表現するよりも、
「ボビベロブァ!」と表現したほうが、その気持ちをよりあらわせる
と思ったひとがいれば、その後も、そのことばを使えばいいのです。
おのまとぺもジブリッシュも、
ある意味、秩序をこわすはたらきをもっています。
もしくは、解放されるはたらきといったほうが、正確でしょうか。
おのまとぺには、たしかに共有される感覚はありますが、
風がいつも「びゅーびゅー」吹く必要はなく、
「ぶぁっふぁぶぁっふぁ」と表現したければ、してもいいのです。
すると、その瞬間、風の動きや状態に、あたらしい光が投げかけられます。
それはその瞬間は、ジブリッシュともなりえますが、継続して
使っていくなら、おのまとぺとして認知されていくということです。
宮澤賢治の「風の又三郎」より。
どっどど どどうど どどうど どどう
「雨はざっこざっこ雨三郎、
風はどっこどっこ又三郎」
どっどど どどうど どどうど どどう
彼のことばもまた、最初に口にした瞬間、それはジブリッシュであり、
紙に書きつけたとき、おのまとぺとして定着した、
と言えるかもしれません。
おのまとぺとジブリッシュ。
今日は、このふたつの表現方法の、共通点とちがいについて、
考察(というほどのことはないかな)してみました~♪
01★「おのまとぺ」という才能
https://note.com/kamewaza/n/n41222be7ee03
02★宮澤賢治の「おのまとぺ」
https://note.com/kamewaza/n/n0bb96f506746
03★「おのまとぺ」が生まれる瞬間
https://note.com/kamewaza/n/n559073b605d4
完全日刊メルマガ「今日のフォーカスチェンジ」
本日で、5948号(6000号まであと52日)
http://kamewaza.blog25.fc2.com/blog-entry-31.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
