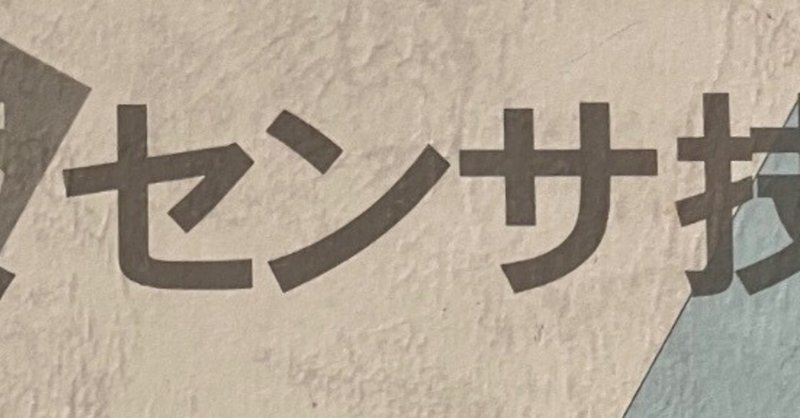
「普及版センサ技術」から考える介護イノベーション(5 温度センサ、6 湿度センサ)
はじめに
25年前の専門書「普及版センサ技術」
この本を一通り読んで、様々なセンサーについて、介護に使えそうかどうか、考えたいと思います。
回路設計エンジニアとして駆け出しの頃、回路を作るのが怖くて手が出せない、という時期が長くありました。回路設計を仕事にしたいのに、何だか変な話しですが。どこかに落とし穴がありそうな不安がありました。ベテラン回路設計者の方が、丁寧に教えて下さって、この困難な状況から抜け出す事が出来ました。この方は本当に私にとっての恩人です。この方のご指導が無ければ、私は思う様な仕事が出来ない後悔を、一生引きずっていたかも知れない、とさえ思っています。
気をつけるべき点は色々とあるのですが、特に注意すべき点は部品のバラツキと温度特性です。
抵抗でもトランジスタでもオペアンプでも。温度でスペックに変化が生じるので、それを踏まえて設計しないと不具合が起こるという事を教えていただきました。
トランジスタの温度特性は小さくないので、差動回路にして温度特性を対策する事があります。温度特性は相殺されて、2つのトランジスタのバラツキのみになります。オペアンプの等価回路は、トランジスタ差動回路になっていて、温度特性が対策されています。
オペアンプの応用が高精度なプリアンプだと、それでも入力バイアス電流の温度特性が問題になります。温度に安定なオペアンプは高価ですが、精度が必要ならそういった高価な部品を使う必要があります。
抵抗は値そのものが温度で変化するので、精度が必要なら温度変化やバラツキの小さい部品を選ぶ必要があります。抵抗の温度特性はオームの法則で電圧となり影響が現れてきます。
この様に、回路を安定に動作させる上では悪者になりがちな温度特性ですが。敢えて温度特性の大きな部品を使って温度を測定するのが、サーミスタなどの抵抗体温度センサです。
Special thanks to Mr. K!
5 温度センサ
1⃣抵抗体温度センサ
電気抵抗の温度特性を利用した温度センサは、白金(プラチナ)の金属抵抗を利用するものと、半導体を利用するサーミスタがあります。金属は温度が上がると熱雑音により抵抗値が上がる、正の温度係数を持ちます。
一方、半導体については、バンド理論によってイメージできます。半導体原子の最外殻電子が価電子帯から禁制帯を飛び越えて伝導帯に移るには熱エネルギーなどの外部刺激が必要です。半導体であるサーミスタは、温度が上がると抵抗値が下がる、負の温度係数を持ちます。
介護施設で毎日のバイタル測定に利用される電子体温計には、このサーミスタが利用されています。
プラチナは高精度ですが、価格が高いので電子体温計にはあまり利用されていません。
2⃣熱電対
熱電対は2種類の金属を接合したものです。熱電対で測定できるのは温度の絶対値ではなく2点間の温度差です。熱電対には様々な種類がありますが、クロメル線とアルメル線(両名称とも商品名)とで構成されたK型熱電対は、-200℃~+1200℃という広い温度範囲で、価格も安価なので工業用に広く利用されています。
3⃣熱放射を利用した温度センサ
絶対0度(0K、ゼロケルビン)は-273℃で、これよりも低い温度は存在しないとされます。全ての物は絶対零度よりも高い温度だと、黒体放射により熱エネルギーを放出しますが、波長は温度により変化します。
非接触で熱エネルギーを測定する方法として、サーモパイルやサーミスタボロメータがあります。サーモパイルは、熱電対を多数直列に接続した物で、非接触温度計に利用されています。サーミスタボロメータは、サーミスタを2次元に多数配置した撮像素子で、赤外線サーモグラフィに利用されています。
⚫︎電子体温計
⚫︎温度計
⚫︎非接触体温計
⚫︎赤外線サーモグラフィー
6 湿度センサ
導電性高分子材料の電気的特性が、水の吸脱着によって変化することを利用したもので、電気抵抗の変化を検出する抵抗型と静電容量型がある。抵抗型は、スチレンやアクリル系化合物に導電性を与えるために、アンモニウム塩やスルホン酸基を結合した化合物の特殊な重合体を感湿材料に用いる。吸湿することにより高分子中の電解質が移動しやすくなり、抵抗が減少することを利用するもので、イオン電導機構である。容量型は酢酸セルロースや酪酸酢酸セルロースなどの親水性高分子を感湿材料に用いる。水の誘電率が高分子に比べて大きいために、水分が吸着すると高分子の誘電率が大きくなるので、電極を設けて容量変化として検出する。
純水は電気を通さないので、誘電率が高くて、水分が吸着すると静電容量が増加するのですね。
湿度センサは一般的に、感湿材料を電極で挟んだ、コンデンサのような構造になっています。ここに電気を流し、電気的な性質の変化を検知します。感湿材料には高分子フィルムやセラミック焼結体が用いられます。
湿度センサは、湿度の測定方法によって、抵抗式と容量式の2つの種類に分けられます。
抵抗式は、空気中の水分を吸収したり、空気中に水分を放出したりするのに伴って、電気的な抵抗値が変化する感湿材料を利用します。高分子素材やセラミックなどがよく使われます。構造が簡単で、比較的安価であること、そして大量生産しやすいことがメリットです。一方で測定精度のばらつきが大きく、応答速度が遅いのがデメリットです。
容量式は、吸湿や脱湿によって感湿材の静電容量が変化することを利用したセンサです。感湿材には高分子膜が使われます。応答速度が速く、測定可能範囲が広いというメリットがあります。相対湿度0%から100%まで測れます。直線的な出力が得られるため、演算処理を軽くできます。
電子レンジにも湿度センサが使われています。食品を加熱すると水蒸気が出て、庫内の湿度が変化します。この仕組みを利用し、オート調理などの制御に使われます。電子レンジの湿度センサの多くはセラミックを利用した抵抗式です。これは、加熱により吸湿をリセットできるためです。
⚫︎湿度計
⚫︎電子レンジのオート調理機能
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
