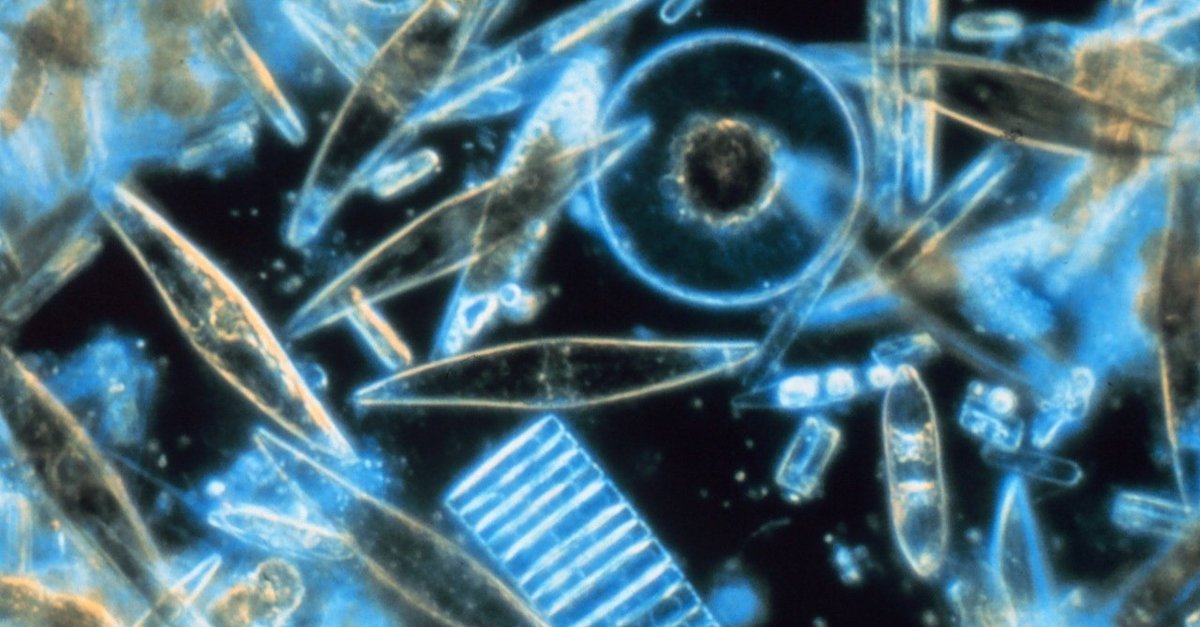
Epicross5. 集団の浄化作用
集団には集団の浄化作用がある。
人間という生き物は「社会性」というものを発展させて、自然界の中の生存競争に打ち勝ってきた。
集団の中にいるということは、自分の安心安全が担保されているということであり、集団に属することで自分自身の安心安全を守ってきた。
それが人間の欲求になっているのは、マズロー欲求階層説(第2段階、第3段階)の中で言っている通りである。
それに伴って自集団がどうであるかということ、自分たちの集団の安心安全を維持することはほぼ無意識に注意が払われている。
集団は集団であることを維持するために、自然と働く浄化作用があるのだ。
それは集団が持つエネルギーであり、集団が持つポテンシャルという意味での可能性である。
集団の浄化作用
集団の浄化作用を定義するならば、集団を維持しようとする力になるだろう。ここで言う「維持」とは現状を繰り返すという意味ではなく、瓦解することに反するエネルギーを出すという意味である。
人間がつくる集団は、その内部に自己(自集団)の問題を解決し、集団を維持し続ける方向へと導く能力を有している。
外部からの力に頼らなくても、自己治癒的に集団の問題を集団でできる可能性を秘めている。
生存競争の中で生き残る能力として身につけた、人間の「社会性」という能力いは、そんなに柔なものではない。
文明を発展させ、ここまで種の存続たらしめてきた結果が、あらゆる状況に対応してきた歴史を物語っている。
そしてそれは年齢問わずだ。
年齢が小さくても、集団ができればこの集団の浄化作用が働く。
ケンカをすれば仲直りしようとするし、何か問題が起これば相談しようとする。
集団の浄化作用は、人間という生命体に組み込まれた遺伝子なのだ。
浄化作用の危機
その浄化作用が今危機に瀕していると思う。
人間は浄化作用という自然の治癒能力よりも、機械的な「修理」を重んじるようになった。
何か問題が起これば外部機関にその判断を求めるし、問題が起こらないためにすることは制度・ルール・マニュアルをつくることだ。
定めた規定に則って、計画通りに履行されることを善しとし、それを維持するために契約というものを結ぶ。
機械的に構築されたシステムをもとに集団は維持されている。
機械的なシステムで集団が維持されているということは、機械的なシステムで安心安全はつくられている。
機械的なシステムにおいては、問題が起こることは「悪」であり、問題が起こらないことを「善」とする。
そのため、問題を未然に防ぐということに心血を注ぐ。
問題が未然に防がれるのであるから、問題が起こったときに初めて発揮される浄化作用は働くはずもない。
こうして人間が持つ集団の浄化作用という能力は、どんどん衰退していっている。
教育の現場で
顕著にそれを感じるのが教育現場においてである。
いつからか教育する側は問題が起こらないことを旨とするようになった。
何が正解で何が間違いかを教えることに躍起になっている。
理念や方針は別にして、現場においてはいかに問題や問題行動を起こさないかに関心がある。
教える側がそんな調子なので、正解を判別したり、正解とされる行動を理解したりする能力には長けているが、課題解決型の能力は身に付くはずもない。
その肝心の課題解決型の行動もマニュアル化されたものが教科書的に教えられるので、イレギュラーな事態には対応できない。
それが常態化していくと、自分の意志を人に尋ねるような有様である。
機械的なシステムによって、機械の部品のような人材が育てられている。
そして、機械の部品のように育てられた人材が、機械的なシステムを維持している。
そんな風に見える。
機械か生命体か
浄化作用というのは治癒能力である。
治癒能力というのは、生命体にこそ備わった機能である。
薬や治療を使うと状態は早く治る。
自己治癒能力は変化が緩やかなので時間がかかる。
その緩やかな変化の中で、生命体的最適が築かれていく。
薬や対処療法に頼ると状態は治るが、自己治癒能力はどんどん低下してく。
自己治癒能力を鍛えようと思ったら、過度な薬や治療に頼らないことだ。
自己治癒能力が鍛えられるということは、自身の可能性が顕在化していくということだ。
いつまでも動き続けられる生命体よりも、自ら変化・修正できる生命体の方が生き残る。
生命の足腰を鍛えるために、時間を使ってもいいのではないだろうか。
和△1金◻︎3◻︎3D30/4w5/INTP/秘密兵器。ワークデザイナー。高校時代に出会った料理人の影響で料理の道へ。「素材を活かす」料理の考え方は人材にも通ずると信じ、その人が持ち味を“思い出す”自己変容を描くセッションや研修を実施中。
