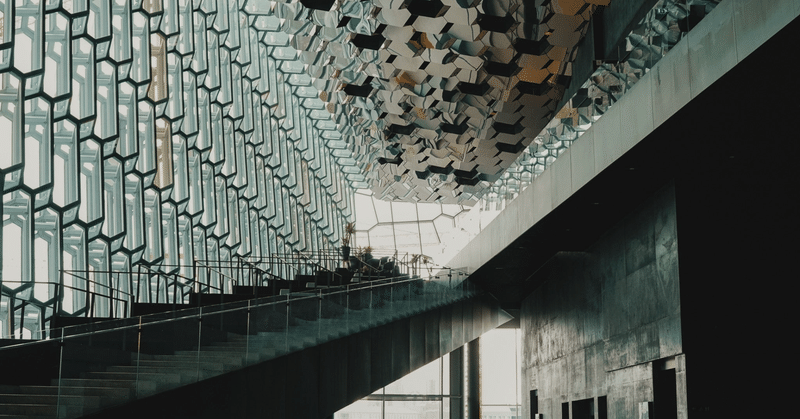
マーダーミステリーで"勝つ"方法、"負ける"条件
前提
マーダーミステリというゲームには明確に"勝ち"が存在する。
何故なら勝利点が存在するからだ。
それがTRPGのようなゲームとの一番の違いと言ってもいいかもしれない。
とは言えマーダーミステリは所詮ゲームであり、競技ではない。
"勝ち"が存在しても、それを目指すゲームという訳ではないように思う。
それでも人間誰しも勝てるなら勝ちたいものだ。
負けたくはない。
だからこんなタイトルで一回真剣に"勝ち"を目指す方法を考えてみようと思う。
もしあなたがPLならこれを参考にすることはあっても信じるようなことはしないで欲しい。
マーダーミステリーの本来の楽しさを一部損なう恐れがあるからだ。
では対象読者は誰かというと(当然PLも含むのだが)GMやシナリオ製作者だ。
GMはこのような思考で参加しているPLがいることを忘れてはいけないし、シナリオ製作者は寧ろこのようなPLを想定する必要がある。
尚、筆者は2020/10/05時点でプレイ順に
・クローズドマンションGM
・何度だって青い月に火を灯したPL
・オリジナルシナリオGM
・籠の燕は夜、夢を見るPL
とプレイ回数計四回の初心者である。
以下は初心者が初心者なりに考察した自分へのメモの色が強い。
目次
・キャラクターについて
・マーダーミステリ頻出パターン
・犯人
・探偵
・一般人
・パターンを見破る
・シナリオについて
・シナリオ構造
・事件の並列度
・キャラクター間のパス
・証拠品のパス
・メタ階層
キャラクターについて
マーダーミステリー頻出パターン
初心者の私が頻出パターンを書くのも恐れ多いが、正直これは限られると思う。
存在するパターンは
・犯人
・探偵
・一般人
の三つだ。
多少複雑な配役になる場合はこれの複合でほとんど説明がつく。
そして、この中で最も難しいと思われるのは一般人パターンである。
何故ならシナリオに絡むために何らかの難しい秘密が課されている場合がほとんどだからだ。(そうでもしないと面白くないキャラになってしまう)
それぞれ個別に見ていこう。
犯人パターン
最も情報量が多く、故に最もゲームをコントロールしやすいパターンである。
よくあるのはこれだと思わせておいて、探偵や一般人であるというような複合パターン(勘違いパターンとでも呼ぶ)だ。
マーダーミステリーというゲームの都合上、最低でも一人は確定で存在する役柄だが、自分が殺したという確定情報が存在する情報強者だ。
勘違いパターンでも情報量が多いことは変わらない。
大体の勝利条件としては「犯行がバレないこと」になる。
では、このパターンでどうすれば”勝てる”のか?
単純である。
味方を作れば勝てる。
人数の多くなりがちなマーダーミステリというゲームにおいて犯人はパッと見とても不利な状況にある。
だからシナリオ製作者は必ず味方を用意する。
でなければ一方的に犯人が蹂躙されてしまうと考えるからだ。
それに多少でもシナリオ構造を複雑にしようとすると(シナリオ構造については後述)真犯人や共犯、自分を犯人だと思っている一般人のようなキャラクターを作ることで簡単に複雑にできる。
シナリオ製作者にとって、これはある種の魔法だ。
難しく新規性のあるトリックなんてなくてもベテランすら惑わすことができるのだから。
そのような味方は最初から共犯なのかもしれないし、どちらの陣営にでもなれるのかもしれない。
しかし、必ず味方が一定数いる。
では、どのようにして発見するのか?そして、味方につけるのか?
これも単純だ。
圧倒的な情報アドバンテージを利用する。
自分から情報を公開しはじめれば一定数の信頼を得られるだろうし、あるいは隠して密談で立ち回ってもほとんどの場合有利に運ぶ。
多少であれば不用意な発言をしても大丈夫だ。
それが不用意な発言だと判断できるほど周囲は情報を持っていないのだから。
寧ろ動揺してしまえば容易にバレる。
求められるのは胆力と押し切る力だけである。
嘘をついたり、騙したりしようとすると寧ろ怪しまれるだろうから正直者でいるべきだ。
合言葉は「嘘はついてないよ。嘘はね」だろう。
逆に”負ける”条件だが、みなさんご存知の通り犯人だとバレることだ。
そしてゲームの都合上、あるいはシナリオ製作者があくまで公平なゲームメイクをする必要がある以上、全ての情報が公開されると一瞬で特定される。
もしかしたらそうなっても特定に至らないような複雑なトリックが存在するかもしれないが、正直全公開状態では消去法で犯人らしき人物なんてすぐ分かってしまう。
だからこそ早期に味方を作り、情報を握り潰す必要がある。
と、ここまで情報アドバンテージを強く押してきたが注意しなくてはならないことがある。
そもそも自分は情報アドバンテージを握っているのか?という点である。
これは後述の「パターンを見破る」で詳しく話そう。
探偵
さて、探偵と記したがこの場では主人公という意味とは少し異なる。
何故ならマーダーミステリーでは全てのPLが主人公だからだ。
ここでの探偵は犯人の敵として言葉を使うことにした。
探偵は初期の情報が比較的少ない役どころになるだろう。
マーダーミステリーにおいて純探偵という役は作り辛いものだ。
情報が少なくては動きにくく面白みが出せるかどうかをPL自身のリアル性能に依存してしまうからだ。
だが、純探偵は明確に情報を公開していくことでストレスなくプレイできるだろう。
一般人や探偵役が多ければ信頼も厚く、情報が集まることになるかもしれない。
表向きは全員が事件を解決するように動くはずだから案外考えることは単純だ。
つまり、探偵の”勝ち方”は情報の透明度を上げることである。
そう、犯人の負ける条件とほぼ等価だ。
これは今回意図的に犯人の敵という意識で書いているのもあるが、王道のものであればやはり対立構造があるのがマーダーミステリーだ。
ところで何故透明度を上げる必要があるのだろう?
自分の下に集まればそれで良いのではないか?
ここが重要なポイントだが、探偵役と周囲は知らない訳だしメタ的な話は基本NGだ。
つまり、自分が信用に足る人物であるとするには情報を公開する他にない。
もしもこんなことをしなくても情報を集められるなら、そうすれば良いが大体の場合でそうはならない。
そうして推理に注力するのである。
これが勝ちへの最善手だ。
ここまでくれば負けの条件も分かりやすいだろう。
情報が自分の下へ集まらないことである。
とはいえ、これはそもそもマーダーミステリーにおいてどの役割においても致命的である。
ところで純探偵は作り辛いと書いた。
そう、実際の所、探偵役には何らかの秘密が付与され、不用意に情報を開示出来ないことが多い。
それはRP的にであったり、あるいは勝ち点的にである。
これについてはまた「パターンを見破る」「シナリオ構造」の後に触れよう。
一般人
最難関パターンである。
何故なら真の意味での一般人などというつまらない役職はマーダーミステリーに存在しない。
いや、何の秘密もない一般人であればそれは純探偵と同義である。
ここでいう一般人とは「本筋の事件にとって」の一般人である。
「シナリオ構造」でも触れるが大体の場合においてマーダーミステリーは2-3個の事件が並列に動いている。
つまり、本筋の事件では一般人のキャラクターもそのキャラクターにとっては犯人であったり、探偵であったりする。
そして、それらの勝利条件は上で書いた通りだ。
つまり、まとめればキャラクターの勝利条件とは自分の味方を作り、情報を共有することである。
長々と書いてそんなことか、と思われるかもしれないがこれが複雑に絡み合うだけで何も分からなくなる。
そして敗北条件は言うまでもなく、情報が手に入らず、敵に情報が知られることである。
ここで探偵や犯人との明確な差異を述べておこう。
一般人の情報は(秘密を除いて)ゲーム開始時点で語られることが少ない。
探偵や犯人は主となる事件の関係者だけあって、そのような事件が起きた程度のことは全員が知っている。
一方で一般人の情報は一部のPLしか知らない。
この点では情報アドバンテージに優れると言えるだろう。
しかし、マーダーミステリーは無駄な情報を配置する暇などないし、そんなことをしてはPLの反感を買う。
つまり、一般人の事件もゲーム終盤では全員に知られることになると頭に置いておくべきだろう。
事件そのものを露見しないように立ち回るのは無理があるということだ。
であれば、事件そのものが露見する前提で動けばいい。
例えば自分から告白してしまう。
その時に大きく嘘をついてもいいだろう。
情報を開示することにはディスアドバンテージが存在するが、一方で先手を取ることは大きなアドバンテージにも成り得る。
そもそもが難しい役回りだ。
このパターンだと判断できたならぐっと大きく勝負に出るのもどうだろうか?
そして、もしも嘘を吐くなら嘘を重ねないことを意識したい。
これは一般論だが、嘘はそのタイミングで一つだけに留めるべきだ。
バレそうになったとしても貫き通すことにしよう。
絶対に2つ目の嘘で塗り固めてはいけない。
もしも2つ目の嘘を作るなら1つ目の嘘を諦めて作り変える方が賢明だ。
嘘はそれ自体が矛盾の種になる。
人数がそれなりにいることの多いゲームだ。
複数の嘘を管理するよりも一つの嘘を盤石にしたい。
と、ここまで難しさを書いてきたが朗報がある。
実は純探偵として動くと勝ちに近付くことがある。
これも「パターンを見破る」で後述しよう。
パターンを見破る
さて、ここまでパターンそれぞれの特徴とざっくり”勝ち方”をまとめた。
それが完璧な”必勝法”ではないのは語るまでもない。
まず第一にパターンにハマってしまうかというとそんなことはない。
前述のように複合型が存在するし、シナリオ製作者はあらゆる手を使ってPLの勘違いと疑心暗鬼を生じさせるものだからだ。
そして第二にパターンにハマってもその場の空気感やら周囲の動きで変化するものも多い。
極端な話だが自爆テロのような行為も可能なゲームだ。
人狼がさっさと人狼COなんてしてしまったら狂信者のやることはないのである。(いや、まあ、COするくらいならどうにかなるかもしれないが)
しかし、多くの場合はパターンにハメることで時間の足りなくなりがちなマーダーミステリで有利を取れることもある。
では、そのパターンをどうやって見破るのか、という話をしよう。
犯人は「情報アドバンテージがある」と書いた。
探偵は「推理に注力する」のが最善手と言った。
大ウソである。
正確にはそれだけを考えればいい単純なキャラなどいない。
経験が少ない筆者が言い切るのもどうかとは思うがシナリオ制作のことを考えると単純な構造で面白いシナリオにするのはとてつもなく難しいことなのだ。
やはり複雑な構造のシナリオの方が多いのではないだろうか。
例えば「自分が殺したと思い込んでいるが実の所真犯人が別におり、ゲーム中盤辺りでそれが発覚するように情報が配置されている」という犯人偽装探偵パターン。
あるいは「主事件に関与こそしていないが正体はバレてはならない」という一般人複合犯人パターン。
他にも複数の事件に関わらせたりすることで組み合わせの数はどれだけでも増やせる。
そう、実は誰かを殺したと秘密に書いてあっても犯人とは限らない。
それどころか先の例では探偵になったりするのである。
情報を秘匿しなければと思っていたら、急に情報を公開しなければならなくなるのだからたまったものではない。
逆も然りで情報を公開し事件を解き進めていたら公開され過ぎて個人ポイントが取れなくなってしまった、なんてこともあるだろう。
では、どのようにして見破るのか。
まず明確に事件の犯人であると書いてある場合は犯人パターンである。
これだけは分かりやすく、ほぼ間違いがない。
ただし、被害者の死の確証がない場合(記憶が無いとか、この状況なら死んだだろうとか)は高い確率で非犯人である。
そして真犯人が存在すると睨むべきだ。(正直これは実にメタ的でRPとしてはいかがなものか、となる状況がほとんどかもしれない。適度に考えよう)
あなたが殺害したと書かれていた場合、事前に(いるなら)GMに確認をとってもいいかもしれない。
答え辛そうにしたり、何らかの形ではぐらかされたら非犯人だ。
この時のパターンをどちらかに分類するのは難しいが、大抵は探偵パターンである。
当面の目標は真犯人を探すことになるだろう。
次に空白の時間がある場合は一般人か探偵パターンが多い。
記憶が混濁していたり、眠ってしまっていたり、襲われて気絶していた、などだ。
もしも犯行に及んだ記録が書いてあっても非犯人パターンに落ちることが想像できる。
そのような空白の時間で実は犯人というのはPLとしてもあまり気分が良い展開にはならず、面白みが薄れるからだ。
カタルシスには伏線と起伏がなくてはならない。
唐突な展開はあまり好かれないことが多い。
それも自分が悪人であったなど、一般人や探偵だと思っていたPLにとっては大抵の場合受け入れられないものだ。
逆に言えば、それでも受け入れられるようなシナリオは良いシナリオなのだろう。
そして主な事件とは別の事件について言及されている場合。
これも一般人パターンである。
そして以外にも純探偵になり得るチャンスだ。
特に真犯人を名指しすることが得点になるような状況なら積極的に動いていい。
後ろ暗い過去の事件があったり、隠さなくてはならない秘密があるかもしれない。
しかし、そんなことは一回忘れて純探偵として動いてみよう。
情報を積極的に見せ、あらゆる相手と話すべきだ。
これは特に最序盤にイニシアティブを握り、ほとんどの情報を開示することで行う。
何故なら最初からあなたの持つ別の事件について知っている者は少なく、いたとしても確証に至る証拠はないからだ。
そして中立を示すことが出来れば貴方の下に情報が集まるかもしれない。
運良く信頼されれば自分の証拠が調べられ秘密がバレる危険性も減る。
仮にバレてしまったとしても犯人が分かれば得点は入る。
自由に動きづらい犯人や探偵に対し第三勢力であることを誇示できれば自然と味方を選ぶ権利すら手に入るだろう。
それがどれだけ強いことか、語るまでもない。
とにかくパターンを見破ること。
それも各事件に対しての自分の立ち位置を素早く理解することが勝利への最短経路になる。
これを誤ったり、その後の行動を失敗すれば勝ちの目はない。
シナリオについて
シナリオの構造
これまでシナリオの構造について何回か言及してきた。
シナリオの構造にはいくつかの意味が含められている。
・事件の並列度
・キャラクター間のパス
・証拠品のパス
・メタ階層
大体この辺りだろうか?
順に書く。
事件の並列度
マーダーミステリゲームは事件が複数起きていることが多い。
これは人数がおおいことが理由になるだろう。
つまり、人数の少ないマーダーミステリではその限りでない。
並列に起きている事件の全てに対して犯人と探偵がいると思っていい。
つまり、雑に人数を2で割ればそのゲームの事件並列度が分かる。
例えば9人のゲームなら 9 / 2 = 4 余り1 だから最大で4つの事件と1人の一般人がいる。
とはいえ、各事件に 0-2人 の一般人を考えて然るべきだし、被りも考慮するべきだ。
体感で話すと最大数から2くらい引けば大体合ってるんじゃないだろうか。
次に考えるのはその事件に対して自分がどの立場にあるか、である。
これは秘密を見れば割とすぐに分かる。
何故なら自分が関わっている事件は書いてあるからだ。
秘密に書いておらず、自分が関わっている事件は後述するメタ階層の上の階層に位置するものになるだろうから一旦は除外して良い。
そうすると自然と自分がどの事件でどのパターンなのかが分かる。
書かれていない事件は全て一般人扱いだ。
このように並列に進行する事件に対してPLは一見無力だが、対策を練ることは可能だ。
キャラクター間のパス
これはキャラクターの相関図を思い浮かべられれば一番早い。
あるキャラクターと他のキャラクターは何らかの関係性がある。
そして、それは事件の動機、Why done itに成り得る。
特に血縁と色恋沙汰は昔からの定番だろう。
面白いことに人数が一人増えるだけでこのパスは複雑さを相当数増やす。
ピンと来なければ円状に9つの点を書いてその全てに線を引っ張ってみると良い。
その後に点を増やしていって線も増えた点の分だけ引いてみるとその複雑さが良く分かるだろう。
そして、これも必ずしも全部に引かれているとは限らないことに注意しなくてはならない。
というか、そんなシナリオを書くのは大変だし、それを短時間で理解させる展開はもっと大変だ。
まずは自分からどこに線が伸びるのかをゲーム開始前に図示してみて、証拠が増える度に書いていくと良いだろう。
これは案外皆やっているかもしれない。
そして、重要なのは事件への関連(パス)だ。
あなたのキャラクターはある事件において犯人であり、別の事件で探偵である。
それは相手のキャラクターも変わらない。
だからこそ、それを意識しておけば誰が敵で誰が味方か考える材料になるだろう。
証拠品のパス
マーダーミステリーのシナリオを作る時、何を考えるのが大変だろうか?
トリック?
動機?
それとも面白いギミック?
どれも大変だが、やはり証拠品が数も多く、意味のあるものでなくてはならないが、意味があり過ぎてもよくないと制限が厳しい。
ゲーム内に無意味なものは登場しない。
無意味であるということはそれだけで人をガッカリさせるし、不信感を募らせる。
しかし、初手から犯人が分かってしまっては興ざめだ。
だからシナリオ製作者は証拠を小出しにするし、重要な情報は取り辛いように仕向ける。
そして最低限の情報は関係のある者に与えられるように考える。
そう、事件の並列という話があったように関係のあるなしがここで生じている。
証拠品のパスとは事件との関連を表す道筋(パス)であり、証拠品同士のパスを指す。
メモを取る時にはある証拠品が関係する事件が何であるかを明確にしておきたい。
更に証拠品はキャラクターと結びついているものがある。
これは大抵どの事件に関連しているのかを表す指標に成り得る。
この二つのパスがシナリオの複雑度を加速度的に増させているのである。
メタ階層
これはほとんど考えなくてもいい特殊ケースである。
しかし、基本は横に広がる並列度に対して、縦の広がりを持たせることの出来るメタ階層というゲームは容易に複雑な構造を実現できる。
例えば拙作(未公開。公開予定もない)では三階層のメタ階層を用意した。
第一階層はマーダーミステリゲーム内のゲーム。
第二階層はその外にあるゲーム内ゲーム外ゲーム。(トゲアリトゲナシトゲトゲみたいだな)
第三階層は更にその外、GMである自分まで含めたマーダーミステリゲームを俯瞰する層である。
全六人で行ったこのゲームは各階層に二人ずつを配置し、数が少ない方向にしか意識が向かないようにキャラクターシートを書いた。
バランスを取るために下の階層はほとんど上の階層の影響を勝利点に受けないようにしたし、下の階層は上の階層に行くほど影響を与えられるように配置した。
これはリアルマーダーミステリー(実際にタイムスケジュールに従って行動してもらい、目撃証言や行動をしてもらった)という性質を生かすための策だったが、二階層程度なら通常のマーダーミステリでも導入できる。
先に述べたように特殊なゲームになるが頭に入れておいて損はあるまい。
ちなみに真っ当なシナリオなら下の階層の方が有利になっているはずだ。
そうでなくては上の階層が有利になり過ぎる。
よって”勝つ”ためには下の階層をコントロールし、上の階層にコントロールされないことが重要になる。
最後に
考えていたことを全部長文駄文になってしまった。
色々書いてきたが結局はRPするのが楽しいし、結局は今後もRP優先でプレイしていくのだろう。
ゲームなのだから楽しんだもん勝ちなのである。
RPに反しない範囲で全力で勝ちにいくけどな!!!!!!!!!!
(適当に勢いだけで書いたので文章としておかしい所があると思いますが指摘はいつでも受け付けています)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
