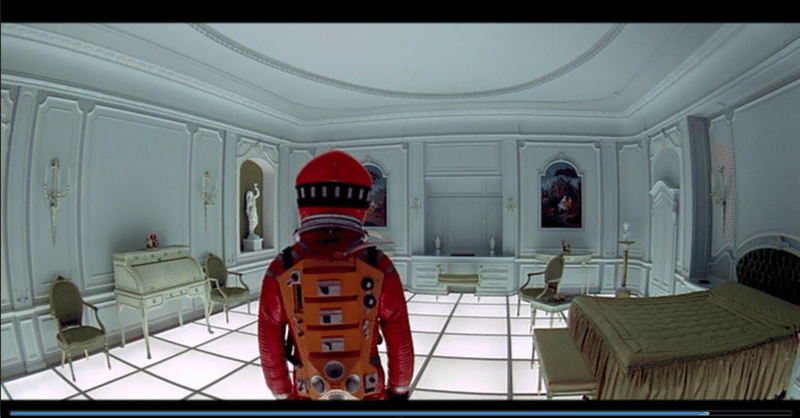
バック・トゥ・ザ・前世 パート2(完結編)
催眠術は続く。
脳裏によみがえる前世の記憶はどんどん明確な映像になり、そのときの感情まで体の中にあふれてきた。いったい、どうなっておるのだ、自分は?
自分は今どこにいるんだ?
2000年前の地中海沿岸の小さな町にぶっ飛ばされたぼくに、催眠誘導してくれているA先生は繰り返す。
「自分が作ったものに満足ができなかったんだね?」
ぼくは大工という仕事が好きだったんだろう。
だから一番おおきな仕事であったはずの広場づくりを懸命にやったはずなのに、自分の納得できる仕事にできなかったことが、かなり心残りだったに違いない。
またそれをだれに言ってもわかってはもらえなかったようだった。
自分もその理由をうまく伝えられないもどかしさを抱えていた。
「もっと先に行ってみましょう」
先生の誘導と同時に、ぼくは下に広がる町の、北東に位置する道の十字路に立っていた。
十字路はその町の終わりで、東側は人家もなにもなく荒れた大地に道が伸びていた。外から町に出入りする道だ。
反対側の町中では、たくさんの人たちが荷物を抱えて走り行き交り、騒然としていた。
広場をつくって数年後のことらしい。
逃げ惑う人たちの波の中で、ぼくは立ち尽くし、荒地に伸びる道の先をじっと見ていた。
先には乾いた風が荒れ地に砂埃を巻き上げるだけで、なにも見えない。
「なぜ? なんで道の先をみてるの?」
A先生の質問に、突然、胸のうちに大きな不安と恐怖のかたまりが湧き上がってきた。
なにかが来る。
この道から恐ろしいものがやって来る。
「ローマ軍が…大軍が侵攻して来る」
ぼくのいた町はちいさな町だったが、穏やかな町だった。
政治的な形態ははっきりしないけれど、市民に選ばれた数人の執政官のような人たちがまとめる民主的な町だったらしい。大きな国の支配下にあったのかもしれないが、ちいさな町だったので強い支配をされておらず、古い都市国家のような自治的な形態だったようだ。
そこにローマ軍が進軍してくる。
3日後に迫っていた。そのことで町は大騒ぎになっていたのだ。
ローマはあまりに大きな国家で、軍隊は地上最強最大だった。
戦うことなどできるはずもない。もしローマ軍がきたら、自分たちはひとたまりもない。その恐怖にみなが怯えていた。
「では、その3日後に行ってみましょう」
3日後、ぼくは自分がつくった丘の上の広場に立っていた。
広場から見下ろせる町の道いっぱいに、無数のローマ軍の兵士たちがひしめき合っているのが見えた。
ぼくは数人の人たちと、町の執政官を待っていた。
「待っていた?」
「はい…執政官らがローマ軍と交渉に行っているんです」
ぼくは自分が商売をやっていたせいなのか、執政官たちの下に組織された一般市民を代表するメンバーの一人だった。
存亡をむかえて現実的にどうすべきか、自分の考えを決めるため、3日前にぼくはローマ軍が来るルートに立って考えていたのである。
不安と恐怖を抱えながら。
そして3日後、ぼくたちはローマに従属することを執政官に進言していた。
現実的にあの軍隊と抗戦することなどできるわけがない。どんな条件でも受け入れ属領となるかわりに、町に火を放つな、女を略奪しないで欲しい、人を殺すなという交渉をゆだねていた。
その答えをぼくは仲間たちと、自分のつくった広場のモニュメントの前で待っていたのである。
「町がどうなったか、もっと先にいってみましょう」
突然、ぼくは居酒屋の入り口に立っていた。
5年か10年先のようだった。
なぜ居酒屋だったのかよくわからない。ローマがこの町にもたらした新しい文化だったのかもしれない。
店は広く、中央には大きな四角く囲われたカウンターのような台があり、それを中心に周囲にはたくさんのテーブルがあった。
テーブルはたくさんの男たちで賑わっていた。
町はローマの属領となったけれど、みなは新しい文化と習慣を謳歌している感じがした。
「町は平和で…きみもその店に行ってるんだ?」
「そうです」
ぼくはいつもその店で夕食をとっていた。
店の左奥にはもうひとつ狭い裏口があり、そのそばにあるテーブルがぼくの指定席だった。ぼくはいつも裏口から店に入り、そこでひとり質素な食事をしていた。
ぼくはすっかり年をとっていた。髪もヒゲも白くなっていた。
ぼくには妻もいなければ子どももおらず、家族は持たなかったようだ。
生活は貧しく、町の家々の窓やひさしの修理などをしながら、細々と生きていた。ローマが来る前と大きく変わったのは、ぼくの仕事はほとんどなくなっていたということか。
ぼくの家は、その居酒屋の裏口をでた細い路地を右に行ったところにあった。すでに工房もなく、粗末なちいさな部屋をかりて住んでいた。
見たこともなければ想像したことすらない歴史的な世界であるのに、人生の生活感や空気がリアルすぎて切なくなるほどにたまげましたよ。
「では最後です。臨終に立ち会いましょう」
臨終はそれから間もない年数が経た時だった。おそらく60歳前だと思う。
ぼくは針金のようにやせ細り、戸板のような寝台に体を横たえていた。
そばに二人の女性がいた。
ひとりは中年の女性で、さっきの居酒屋で働いている女性だった。彼女が死に際のぼくの面倒をみてくれていた。そしてもう一人は若い子で、ぼくの姪に間違いなかった。
「なにを感じていますか?」
もう自分の命が尽きるということがわかっているぼくは、数十年前につくった広場のことを思っていた。
ベッドの上で、あのわだかまりの答えを探していた。
そのときだ。
霧が一瞬にして晴れ、光が差したような感じといったらよいだろうか。
答えが唐突に見えた。
「わかりました!」
「え、なにが?」
「芸術です! 答えは芸術だったんです!」
「芸術?」
ぼくはその生涯、その町を出ることはなかった。
ただ海の向こう、大国ローマやいにしえのギリシアには、華麗で素晴らしいものがたくさんあるということを伝聞で知っていた。
華麗とはどういうことだろう、美しいとはどういうことだろう。
想像することすらできず、見てみたいと願いながら、ついに見ることは叶わなかった。
実用性も利便性もない、お腹を満たすこともまったくないけれど、人の心にうるおいを与え、暖かい気持ちにさせてくれるもの。
その視点が広場をつくるときに必要だったのだ。職人である自分にも、その町、その社会にもまだこの概念は存在していなかった——。
「芸術」という言葉がいつ生まれたのかは、ぼくは知らない。
ただ、ぼくは町の記念碑のふさわしい広場に求めていたものは、のちに「芸術」とよばれる概念であることを、死ぬ間際に悟ったのだ。
その瞬間、信じられぬほどの安堵感にぼくは包まれた。
「それを悔やんでいますか?」
先生はぼくにたずねた。
「いえ…それがわかったんです。わかったことをすごく喜んでいます。つぎに生まれ変わったら、今度はそれをやろうと自分は思っています」
「思い残すことはない?」
「ありません」
「…では、肉体から離れましょう」
体を抜ける直前、一瞬怖さにためらいを覚え、ドキドキした。スッと息を吸い込むと、ぼくは体を離れた。
下の方で、戸板の上に丸くなって動かない自分が見えた。二人の女性がそばでたたずんでいる。
ぼくはどんどん上に登って行く。屋根をこえ、町が見え、空をこえて昇っていく。眼下に地球が見えた。その先で大きな光がぼくを包み込んだ。
「…ご苦労さまでした」
先生の声で目を開けた。2時間が過ぎていた。
「どう? おもしろかった?」
呆然として、しばらく頭が働きませんでしたねえ。
いったい、なにを見たんだろうかと。
とにかく感情のすべてがフルスロットルした後の虚脱感というのでしょうか。
ただ、終わったのち、頭と心がものすごくスッキリしていたことに驚きました。
そんな感覚は初めてでした。

ぼくが見たものは、ほんとうに自分の前世なのか、それともただの夢なのか。
転生輪廻はアジアではひろく理解されている考え方ではありますが、それが事実であるのか、ぼくにはよくわかりません。そんなものはなく、ぼくが見たものも心理学的な潜在意識の働きかもしれません。
そうであっても、この「前世退行」療法というのは実に面白い意識へのアプローチだと思えました。
実際、人から悩みの相談を受けると、意外に冷静にものごとを見ることが出来ますよね。それでアドバイスをしたりするでしょ?
それと同じで、この方法は自分を客観視することができるのではないかと。
原因と結果を物語のように組み立て客観視することで、自分の抱えている悩みを他人事のようにとらえて意識する。すると悩みの原因が見え、解決するための考え方や心持ちを、自ら得ることができる。
また催眠誘導は、日頃なかなか出来にくい、精神の集中と深化をさせていく作業といえるかもしれません。
これって、いまよく目にするマインドフルネスや瞑想と同じことなのかもしれませんね。
「自分がなにを喋ったか、あとから聞くと面白いから録音しときなよ」
先生の勧めにしたがって、スマホのボイスレコーダーで術中の会話を録音しました。聞きなおすとぼくは先生の誘導にはっきりと答え、感情の動きまでわかります。
同時に先生がいかに上手に誘導してくれているかわかります。
次から次にきちんと原因を探ってくれているんですよ。だから、どんどん深く入っていけたんでしょうね。
あまりに楽しかったので、家に戻ってから、自分でも試したくなりましてね。
だって、目の前に扉は無数にあったということは、それだけの前世があるってことだし。
なんとなくやり方がわかったので、前世退行の本とかCD、youtubeの動画を手に入れて、自分でやってみました。
今度は違うのを見るぞ、と意気込んだ。
ところが30分ぐらいのものでは、なかなか先まで行けなかったですねえ。
なにより誘導してくれる人がいないので、さっぱり深くにはたどり着けません。
それでも、前世のトバ口あたりは垣間見ることができた。

1回目。
ぼくはちょんまげに浴衣姿に、雪駄で、大きな庭に立っていた。どうやら日本人。庭も自分の家らしい。
庭には池があり、取り囲むように石や樹木が植えられていて、それを眺めている。ぼくは「寒椿を池の向こう側に植えたら、冬景色には綺麗だろう」と考えてた。
時代は江戸時代の中期ごろなのか、とても安定している空気だった。
ところがぼくは憂鬱だった。原因はぼくの背後に建っている大きな屋敷で、「家」がぼくにはすごく重しになっていた。ぼくは武家の当主らしく、母親がおそろしく厳しい人で二言目には「お家が大切」という。
ぼくは造園師になりたかった、と思っている。だから、庭造りだけが息抜きできる時間だったのだ。
つぎは中国人でした。
明朝か清朝か、なんだかそのあたりである気がする。
ぼくは楼閣の二階に立って、窓から城内の町を眺めていた。時間はまもなく日の落ちる夕刻で、城内の通りにはたくさんの円筒形の赤い提灯が並んで吊るされていた。これから皇帝の威徳を知らしめるための祭りが始まるらしい。
ぼくは朝廷に勤める下級役人で、身分は高くない。ぼくの上司が宮廷内の催しを担当し、ぼく自身は城内の町人むけの催しを担当しているらしかった。ぼくはこれから始まる催しを皆が楽しんでくれるか、それを賜った皇帝と朝廷を尊敬してくれるかを気にしている。
3回目は厚いブーツを履いて、濡れた石畳の上を歩いていた。
裾が足元まである長い外套を来て、耳まで覆うような毛皮の帽子をかぶっていた。おそらくロシア人だったように思う。
すでに陽は落ち、小雪のふる夜で、ぼくは劇場に急いでいた。どうやら自分が書いたのか、演出したのか、演劇の上演に向かっているらしい。劇場に向かいながら、ぼくの心は演劇に少し飽きていた。そのかわり新しく生まれた表現のジャンルを、とても気にしていた。
生まれたばかりだけど、若い人や気鋭の芸術家たちがこぞって群がっている「映画」という表現を。
それ以上のことはわかりませんでしたけど、なんだかどれも地味でフツー。
劇的でもなんでもないところが、変にリアルで、自分で笑えてしまいました。
ま、映画のネタにはなりゃしませんわい。
ただこれまで想像さえしたことがない時代や人、環境、生活が、いきなり脳裏に浮かび上がってくることが不思議です。
ロシアも地中海も行ったことないし、考えたこともない。
なんで、そんなものが湧いてくるのか。詳しく遡るためには、やっぱ先生に誘導してもらわないと無理ですね。
でもね、次に先生にお願いする時は、どの扉をあけるかもう決めているんです。
いちばん奥にある扉、いちばん最古の前世に行ってみたいのよ。

前世って、いったいどこまで遡れるんだろ?
なにが出てくるか想像もつかないので、どきどきしちゃうわよ。
(2016年11月26日記)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
