
映画は✖️✖️を孕んでいる
映像と映像をつなぐことを『編集』といいます。
撮影現場は映画製作でも一番わかりやすいところですが、「編集」はあまり知られていない作業かもしれません。しかし映画が映画になる瞬間、とでもいいましょうか。編集作業はほかのゲージュツにはないプロセス、一番特徴のある部分です。
ぼくはこの編集作業が一番好きです。ちなみに一番キライな作業はシナリオ執筆です。まぢキライ。
編集には編集者という専門職の方がいますが、自分でやりたいという監督もたくさんいます。黒澤明監督は、
「撮影ってのは、編集するための素材を集めることなんだよ」
とまで仰せになっており、黒澤監督はもちろんですが、北野武監督も編集大好き、ご自身でやるそうです。
そこまでの誘惑をもつ編集は、いまから百年ぐらい前に『発見』されました。
映像を学んだ人には有名な実験で、旧ソ連の映画監督レフ・クレショフという人が4つの短いフィルムを使って行いました。
用意された1つめは、男の顔を正面から撮った映像。

そして、「スープの入った皿」「ソファに横たわる女性」「遺体の横たわる棺桶」の3つ。



それぞれは、なんの意図も関係も、つながりもなく撮影された、いわば単体の映像です。
さて、それを組み合わせてみます。
まず「スープの入った皿」→「男の顔」
実験ではそれぞれ動画でしたが、今回は最初の写真をしばらく見てから、男の顔を見るといいかも。


スープのあとに、男の顔が映し出されると、「男はスープを飲みたがっている」ように見えませんか?
つぎに「ソファに横たわる女性」。

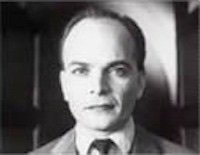
今度は男は、女性に対して「欲望」を感じている。
そして「棺桶」。


「男は死をいたんでいる」
気がつきましたよね?
男の顔はすべて一緒、同一のショットです。ところが先行する映像の後につながれると、見る側には男の異なった感情が想起させられてしまうのです。同じ表情、しかも無表情であるにも関わらずに。
これが「映像が観る側に感情を生み出すことに成功した編集の発見」です。
モンタージュと呼ばれたこの新しい技法の発見は、映画が演劇や小説、絵画、写真、音楽というそれまでの芸術とはまた違う新しい扉を開いた瞬間でした。組み合わせる映像は画面の中のサイズや音楽、照明による陰影などをつけると、より言葉を使わなくても感情を表現することができ、それが映画、映像芸術の基本的な技法となり現在まで続いています。
その編集がわかっていれば撮影するときにすべてを計算すれば、いっさいの無駄はなくなるし、撮影日数だって短くでき、すべては万々歳。となるわけですが、これがまったくそうならない。
ホントに不思議。謎です。
もちろん監督だってわかっているつもり、たぶんこうなるはずだと撮影はします。ところが編集作業に入ると、どーも違うなんてことは当たり前にあるわけですよ。
北野武監督の、その言葉がおもしろい。
「たとえば車のプラモデル、がちゃがちゃ組み立てるでしょ。で、ハンドルがないことに気がつく。やばい、ハンドルを作って(撮影)してない! 困ったな、どうしよう」
足りなかった場合、またセットを組み直し、スタッフを集め、キャストを集めなどしたら、どれだけお金がかかるかわかりません。はっきりいえば、そんなことはできません。たとえ北野武監督でも。
そこで。
「…いいや、タイヤつけちゃえ」
間々あるんですよ、こういうことが。
北野監督にかぎらず、映画監督はみなそういう経験をしていると思われます。
ところがですねえ。
そうした部分が意に反して、えらくいい効果を生み出してしまったなんてことがあるのです。あとから「あのシーンが実に映画的でよかった」などとほめられたりするから、編集はますます謎。
また逆に、必要不可欠なシーンであると現場で大騒ぎしながら撮影し、いざ編集となったところで、
「いらねーじゃん」
ということも実に多い。どんなに思い入れがあり、美しいショットであっても、それは全体から見て無駄なショット、カットだというわけです。
黒澤明監督だって、そうやって捨ててしまったショットはたくさんあったらしい。巨匠と呼ばれるようになってからもですよ。「みんな、ごめん。やっぱりいらなかったや」で。
邦画とは製作のしくみが異なるので比較はできませんが、ハリウッドの大作などは同時に何台もカメラを回し、そのシーンのありとあらゆるカットを撮影し、それを編集マンがまとめます。出来上がりがわずか数分のシーンなのに、撮影されたカットだけで、のべ数十時間分あることも珍しくない。あとから映像が足りないということを避ける意味でも、そうやっているそうです。もちろん、つかわれずすべて捨てられることもあります。
それほど「編集」は、計算できないなにかを孕んでいる瞬間でもあります。
映像は言葉に比べて論理的ではありません。しかし音楽ほどエモーショナルでもありません。その中間にありながら、組み合わせ方しだいで、それまで体験したことのない感覚や体験を生み出すことができる特性をもっているのです。
それはこの核心に、人であれば誰しも携えている芸術的感覚が息づいているからだといえるでしょう。
編集とは言葉や理屈だけでははかりしれない人間の感情を喚起し、生み出す大切なステップなのです。これが、あまたの監督をも編集に惹きつける魅力だと思われます。
最近ではスマホなどで動画の撮影は簡単になりました。また編集作業も簡単に行えるアプリもたくさんあります。もし編集に興味があれば、ぜひ体験されることをオススメします。知らなかった自分の感覚を発見できるかもしれませんよ。
ただし、つくったものは2時間は超えないようにしましょう。
むかし、香港映画は90分がマックス。それ以上の長さになるとお客さんが飽きて大暴れするとか。2時間が人の集中力の限界だそうですよ。
ところがインドの映画は4時間とかざらにあるみたい。というのも、お客さんが見たいところだけ見て劇場を出入りするって聞いたけど、ほんとですかねえ。
それはそれでスゴイ。色んな意味で。
(2016年12月24日記)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
