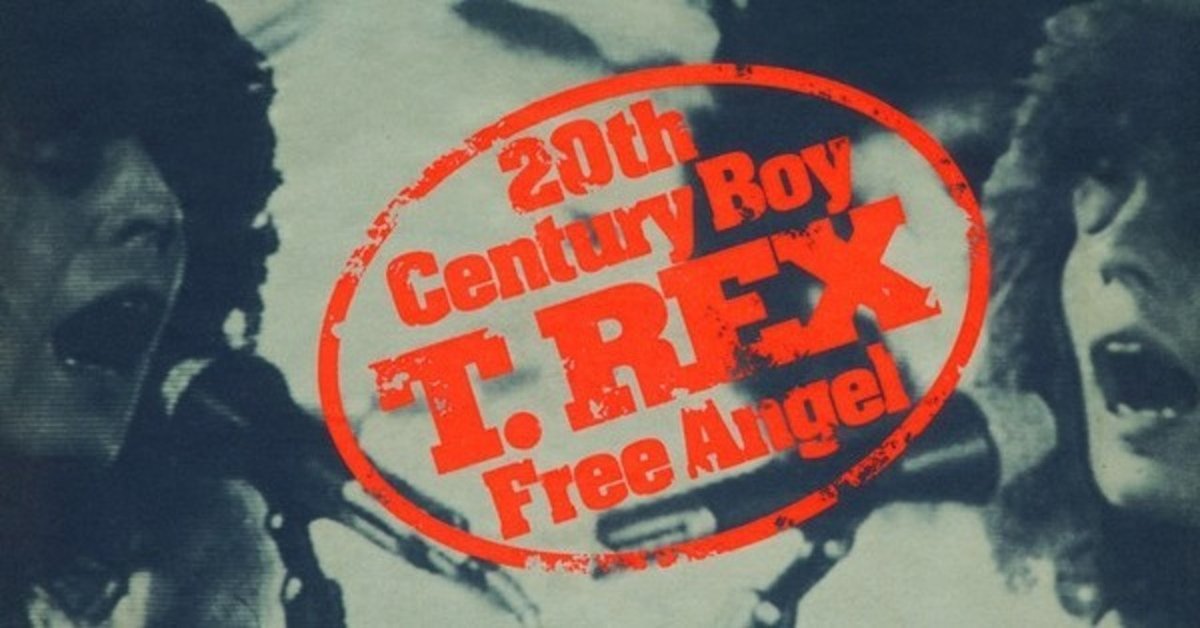
100日後に死ぬ社長 101日目
死んだらすごいって考え方は……
やめた。
―― 遠藤ケンヂ(『20世紀少年』より)
千代田区番町。江戸時代の武家屋敷がルーツの、都心の高級住宅街だ。その一角にあるコインパーキングに車を停め、人の帰りを待つ。一時間は経っただろうか。冷たいコーヒーが欲しくなる。
ぼんやりと五年前のことを思い出していた。信じていた取引先からの裏切りと種明かし。巧妙に人を破滅に追い込む仕組み。そこを借りた起業家をハメ殺すためだけに作られた悪魔のオフィス。すべてが「スポンサー」の快楽のため。悪趣味だ。いかれてる。怒りで前後不覚になる。ただ、こいつらの靴の裏を舐めてでも生き残りたいと思った。
与えられた役目は「執行役」と呼ばれるものだった。ターゲットとなる起業家を選定し、筋書きを作り、必要なリソースを集め、実行する。ひとつのプロジェクトが終わると、見たことがないほどのカネが口座に振り込まれる。自分で過去の自分を殺す最悪の仕事だ。だが次第に慣れていった。スポンサーには一度も会ったことがない。素性を知られるリスクを考えると当然のことだろう。
破滅させられることを理解した若者の反応は様々だ。その場でわめき散らして暴れる奴もいるし、大抵は必死に抵抗するが、やがて廃人同然になる。全て本物の取引で組み立てられ、巧妙に重要なエビデンスが残らないやり方を取るので、戦っても勝てないのだ。その後も「特別コース」で社会的・経済的になぶり殺される。自分のような例外を除けば、再起したものはゼロだった。―― 少なくとも昨日までは。
新宿の事務所での顛末を思い出す。
その場の全員 ――全員とは画面越しの人間含めてだ―― が、つい直前まで彼がいた空間を見つめていた。飛び降りやがった。このパターンは初めてだ。クソ、気分が悪い。この高さは絶対に助からない。もちろん俺は何も手を下していない。罪に問われることはほぼないだろう。だが、何故よりによって後輩のあいつなんだ。
手元の端末が震える。
「死んだ」「本当に飛んだ」「すごいものを観た」「こんな結末だなんて」「最高だ」「よくやった」「彼はすごい」「死んだ」「死んだ」
究極の結末にスポンサー達が喜ぶ。飯田と佐藤は唖然と立ち尽くしている。階下の状況を確かめるため、バルコニーに歩みを進める。
いない。
アスファルトに叩きつけられ、ぺしゃんこになっているはずの身体がない。
その後のことは、混乱してよく覚えていない。だから結果だけ話そう。翌日となった今、「後輩」はスポンサーの一人と会っている。俺はその帰りを待つ。

ひどい一日だった。だが、僕は生きてここにいる。そして人生最大のチャンスを掴んだ。
最初に違和感を覚えたのは、先輩が丁寧に種明かしをする最中だった。怒りと混乱でうまく働かない頭を必死で働かせる。考えろ。なぜこんな舞台を用意してまで僕に丁寧に説明する必要がある。出資が無に帰すのも、不動産が売れなくなるのも、システムの契約がなくなるのも、別でイベントを起こしてそれぞれ撮影すればいい。このタイミングじゃなくたっていい。その方が「スポンサー」とやらも長く楽しめる。種明かししなければ、仕掛けた側のリスクも減る。ではなぜ。
「会社が、そして経営者がどんなときに終わるか知ってるか。キャッシュが尽きたら? 破産宣告を受けたとき? 違う。それは単なる結果だ。そこにいる人間が絶望し切ったときだよ」
僕の会社は潰れる。それは間違いない。だがそうか、先輩の言うとおりだ。あらゆる意味で、会社が破産しても経営者は殺せない。どこかの国の大統領だって、何回も破産を繰り返しその度に再起した。いくらスポンサーの力が強大だとしても、全てをコントロールするなんてできっこない。絶望しなければ死なない。だからこんなに回りくどい舞台装置を作らなければいけなかった。恫喝し、こき下ろし、心を完全に殺すために。完全な絶望。過激な映像を画面の向こうの奴らは求めている。
「最近は変態の世界もコンプラ重視なんだよ。笑っちゃうだろ。漫画や小説だと、自作のスナッフ・フィルムを作って喜ぶ金持ちや、地下闘技場だとか、そんなんが出てくるだろ。現実ではあんなリスクが高いことはやらない」
リスクが高いからやらないだけで、スナッフ・フィルムが合法に作れるなら喜んで飛びつく連中だ。
「あらゆる場所にカメラを仕込んでさ、スポンサーたちにずっと配信してたんだ。会員専用のサイトで。よかったな、お前すげえ人気あったぜ」
奴らは僕のことを今も観ている。
「スポンサーの皆さんも社長の頑張りにちょっと感動してましたよ。本当に破滅しちゃうの?ってね」
そして少なからず、僕のことが好きだ。
画面越しに沢山の金持ちがいる。暇を持て余している。人が破滅するのを観るためだけに数千万、おそらく人によっては数億払える連中だ。そいつらが全員僕のことを観ている。
―― よくよく考えれば、こんなチャンスってあるか?
誰も想定しない筋書きを加えて、物語をもう一段スリリングにする。度肝を抜いてやる。本当に死んで、奴らが望む合法のスナッフ・フィルムを完成させるんだ。画面の中で。
ラストシーンで確実に死んだと全員に思わせる。「一度死ぬ」が「生き返らない」とは言っていない。エンドロールの後に僕は甦る。そして奴らに、このショーの演出料の請求書を突きつける。うまくいくかは分からないが、どうせ破滅ならやってみる価値はある。
どう転んでもクソなら、幕引きくらいは自分で決めよう。それも劇的に。サプライズをくれてやる。
どうすれば「一度死ねる」か。もう決めている。あそこしかない。
「観てるんだろ? これが結末だ」
できるだけ劇的に、絶望した眼を見せるように演技する。カメラへの映り方を意識する。そして、僕は飛んだ。
飛び降りた刹那、身体を建物側に引き寄せる。アドレナリンが噴き出る。八階の手摺りに狙いを定めた。よし、掴めた。できるだけ音が立たぬよう、なるべく素早く身体を八階のバルコニーに滑り込ませる。これなら九階からは僕が思い詰めた末に投身したようにしか見えなかったはずだ。あの高さから直接コンクリートに叩きつけられれば、生存する可能性は限りなくゼロだ。
「おばさん、ごめん!」
八階に祝日も人がいるのは知っていた。お互いよく働いている。オフィスの中を駆け抜け、非常階段を上る。九階ではバルコニーから三人が階下を覗き込もうとしていた。僕が近づいていることには全く気付かない。先輩の後頭部を左手で掴み、右手で股ぐらから身体を上に持ち上げた。極度の興奮のせいだろうか、重さを感じない。身体は半分手摺りの上に持ち上がっている。先輩は足をバタバタさせる。
「おい、よく聞け」
言いかけたところで残りの二人がにじり寄ってくる。
「邪魔するな。少しでも近づいてきたらこいつを落とす。なあ聞いてくれ。オレはあんたを恨んじゃいない。お互い仕事ってもんがあるよな。取引をしよう。オレを観てるスポンサーに会わせろよ。一番太い奴に」
それはできない。俺が殺される。先輩が腕の中でわめき立てる。僕は抱えた身体をさらに空中に投げ出す。あと少しバランスを変えれば、真っ逆さま落ちるだろう。
「恨んじゃいないが、うっかり手が滑ることはあるかもしれない。会社が潰れそうなんだぜ。最悪の気分だ。どうなってもいいって思ってもおかしくないだろ。俺を紹介して後で死ぬのと、今すぐ死ぬのどっちがいい?」
わかった、会わせる、だから、放せよ。とりあえず降ろしてくれ。足をばたばたさせながら懇願する。僕は逆に、先輩の身体をさらに宙に晒す。先輩がやめろと叫ぶ。
「ちゃんとエビデンスを残せって言ったのはお前だったよな。おい佐藤。お前そこのタブレットで動画撮れ。クソほど笑える画を収めるぞ。いいか、今からオレの言ったことをそのまま繰り返せ。そうすれば降ろしてやる」
スポンサー様。
「しゅポンサーさま」
おいちゃんとしろ。怖いのか? 噛んでるじゃないか。うっかり支える力が抜けちゃうぜ。
「す、スポンサー様」
言えるじゃねえか。続けるぞ。
無能な私は最後の最後にしくじりました。
「無能な私は最後の最後にしくじりました」
どうか哀れな私めをお助けください。
「どうか哀れな私めをお助けください」
まず私の会社で、彼の不動産を五億で買い取ることを約束します。
「…………。あッやめろ、て、下さい。まず私の会社で、彼の不動産を五億で買い取ることを約束します」
彼の会社に、今後最大限の支援をしてあげてください。
「彼の会社に、今後最大限の支援をしてあげてください」
つきましては彼を連れて、ご挨拶に伺います。
「つきましては彼を連れて、ご挨拶に伺います」
撮った動画を確認すると、僕は先輩の身体をバルコニーに叩きつけた。思いきり顔面を踏み、靴底を擦り付ける。僕は叫ぶ。
「ないはずの続きを観せてやる。オレに張れよ」
無駄だ。俺もスポンサーには会ったことはないんだ。注意深く隠れている。直接取引はできない。先輩が喚く。
「黙れ。お前には聞いていない」
僕はさらに靴底を顔面に押し付ける。そこにあるはずのカメラを睨み付け続ける。一分ほど経っただろうか。先輩の端末が震える。
「明日一八時、番町」
画面にはそれだけ表示されていた。
「明日またここにオレを迎えにこい。飯田、佐藤。お前らは消えろ。二度と顔も見たくない」
――そうして、僕は今日ここにいる。指定された場所で待つ。車を乗り継ぐ。豪邸の門をくぐり、黒服に付き添われながら建物を進む。ドアを開ける。中にいる男と握手を交わす。
「お会いできて嬉しいです。これで一蓮托生ですね。さあ、ビジネスの話をしましょう」
僕は生きている。これからも簡単には死なない。毒をも喰らい尽くして大きくなる。そして、偉大な会社を作ろう。
100日後に死ぬ社長 完
