新著『脱成長か脱停滞か』について語る4、近代の迷妄を破る哲学が必要
小山田:さてそろそろまとめに入るのですが、MMTの場合でも貨幣を実体的な商品の一種として捉えるのではなく、債務関係に還元することで、今までのプライマリーバランス(税収の枠内に歳出を抑える健全財政)の限界を突破し、デフレ脱却の理論的武器を与えてくれました。その意義は大変大きいけれど、結局彼の経済政策はJGP(Job Guarantee Program)で、完全雇用を目指すケインズ経済学の枠内に留まっているわけですね。もし井上さんややすいさんの言われる如く、脱労働社会化が目前に来ているのでしたら、アナクロニズムです。人口のほとんどが失業者なので、就職の当てもないのに職業訓練や軽作業をさせて、それに給与を出すことになります。それなら諸星大二郎のプラカードを持たせて歩かせるのと大同小異ですね。
やすい:貨幣を商品貨幣論のような実体的な貨幣論から関係的な貨幣論に転換したことは、廣松渉の事的世界観の影響があったかどうかは分かりませんが、哲学的な大転換をやっているわけです。ところがやはり富や価値を生み出すのは生身の人間だけだという近代の勤労社会観の迷妄からは脱却できていないわけですね。
小山田:第4次産業革命が起こって、価値や富が有り余るほど生産されても、それに伴う省力化で大部分の労働者は雇用所得を減らされたり、停滞したままになると、長期デフレになり、利潤率が低下して低成長するわけですね。それを突破するには、所得をBIやAISという形で財政から補填するしかない筈なのですが、それができないのもやはり哲学の欠如が原因ですか。

やすい:ピケティは資産が生み出す利子つまり資本利益率が経済成長率を上回るので、賃金上昇率は経済成長率より低いので、資産家と労働者の格差拡大は必然だとし、それが21世紀の低成長になるとしました。それで資本主義が発展すれば利潤率き傾向的に低下すると言った、マルクス『資本論』の古典的意義を再評価することにつながったわけです。しかしマルクスは、工業が発達すると、資本構成比で労働力の比率が小さくなることで説明しました。つまり価値を生むの生身の労働力の労働だけだから、その比率が下がると価値増殖ができなくなって、利潤率が低下するのだとしたのです。20世紀末から純粋機械化経済に向かい出して、生身の労働者の生産に果たす割合が少なくなったわけです。それで確かに利潤率も低下していますが、それは自動機械では価値を生まないからでしょうか。
小山田:自動機械やロボットに生身の労働力が代替されるのは、その方が価値生産性が高くなるからですね。利潤が減ったのは、雇用所得が減少したために需要が伸びなくて、売れないからですね。だから所得の減少分を補填し、生産性が上がって供給が増える分についても、財政から給付しないと、売れ残って、デフレになります。

やすい:ですからマルクスの説明は現象的には合っているように見えて根本的に間違っているのです。つまり財政は自動機械が生身の労働力に代替して増やした価値の部分を通貨として国民に給付すれば、経済が循環するわけですから、生身の人間労働だけが価値を生むと捉えてはいけないのです。
小山田:結局マルクスの論理は、労働主体と生産手段という形で人間と機械を峻別し、人間労働だけが価値を生むけれど、そのためには手段として機械が必要だという論理ですね。行為の主体の働きが価値の源泉で、機械自体は製品を作ったり、サービスを可能にするけれど、価値は生んでいないだということに固執するわけです。
やすい:それは資本主義体制を資本家による労働者の労働の搾取体制に還元して捉える場合に、まことに説得力のあるレトリックだったわけです。しかし機械に含まれていた価値は製品に移転することにしていますから、過去の人間労働が機械に憑依しているという憑物信仰の論理を使わざるを得なかったわけです。
小山田:やすいさんは、資本家や地主も資本や土地に憑りついて、その利潤や利子を生み出す働きを自分の働きとして捉え、利潤や利子を自らの営利、利殖活動の成果として捉えているとされています。その意味では憑物信仰では共通しているわけですね。そして機械の働きや土地の働きもマルクスはそれを生み出した過去の労働が機械や土地から製品や作物、サービスに移転することとしてやはり憑物信仰の論理で、すべて労働者の労働に還元して説明しています。
やすい:機械が働いている時は過去の労働は働いていないで、機械が働いているわけですね。それを機械は過去の労働がないと存在しないからと言って、機械に過去の労働を憑りつかせるわけです。何故そうするかというと、機械と人間を峻別し、身体的人格的個人を主体として純化して捉え、機械を人間から切り離して、手段に貶めるからです。そのことによって資本と賃労働関係を浮き彫りに出来たわけですが、それがここにきて通用しなくなったわけです。だって、ほとんど無人化した工場や店舗で価値は生まれているからです。だから生身の人間と機械などとの峻別を止揚して、包括的なヒューマニズムに立って、経済循環全体を人間として捉え返す必要があるわけです。これは根本的な人間観の転換ですね。
小山田:それは1986年刊の『人間観の転換―マルクス物神性論批判』というやすいさんの本格的な『資本論』批判がいよいよ本領発揮で、脱労働社会化に筋道をつける役割を担っているということですね。
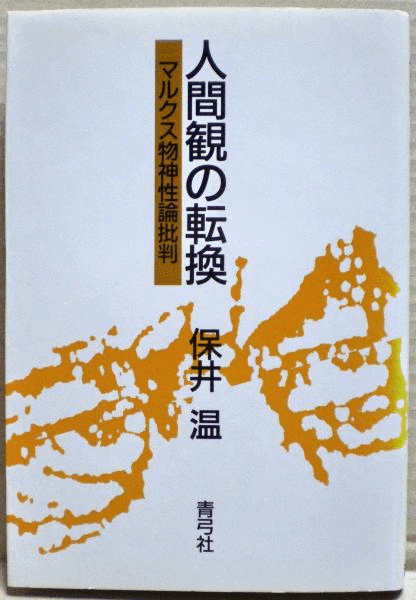
やすい:マルクスも『経済学・哲学手稿』(1844年)の段階では社会的諸事物は人間の非有機的身体として広い意味の人間に包摂されていたわけです。ただ機械もそれだけで価値や富を生めるわけではなくて、生身の身体的な個人の活動つまり生命活動、生活活動、表現活動、実践活動などによって、消費されて真価を発揮することで稼働できるわけですから、機械と生身の個人は表裏一体なのです。だから生身の人間の活動も価値を生むのに必要だったとして、活動価値を労働価値と共に商品価値に含める必要とかがこれから議論されるべきでしょう。そうでないと脱労働社会ではほとんどの生身の個人は雇用労働しないのですから、その所得を活動の報酬として得るためには、活動の必要不可欠性が認められる必要があります。
小山田:確かに、所得が減ってデフレが深刻になるから、財政から給付するでは、所得が多い人が税金を納めて、少ない人に回してやっているようにも受け止められますね。
やすい:ええ、誰かの得は誰かの損、もらえる人がいるのはそれを出している人が居るからみたいに捉えられます。だからBIにしても所得の多い人の収入を少ない人に回すことで成り立つと思って、金持ちはいやなのです。「てめえら欲しかったら死に物狂いで働いて見ろ」という発想です。
5人で1人の高齢者を支えていたのが1人で1人を支えなければならなくなると5倍の負担がかかって年金制度が崩壊するという論理もそれですね。そうじゃないそれだけ少子高齢化したのは機械に代替されたからで、機械は人の何倍も価値を生みだしているので、所得が大して増えていない生産年齢のひとが今まで以上に支払う必要はない筈なのです。
小山田:なるほど、機械も含めて人間と考えることで、財政から家計にお金を回すことも、誰かの負担が増えるように考える必要がないことが分かりますね。第4次産業革命で加速度的に富や価値が増えるのだったら、BIにしてもAISにしてもどんどん上げていかないと追いつかないわけで、財政の累積赤字でどこからそんな金が出るんだという発想自体、近代勤労社会の迷妄に囚われているということになりますね。
やすい:そのあたりの議論は『脱成長か脱停滞か―岐路に立つ資本主義』の姉妹作『岐路に立つ哲学―近代の虚妄を超える』のテーマにもなっています。

御清聴ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
