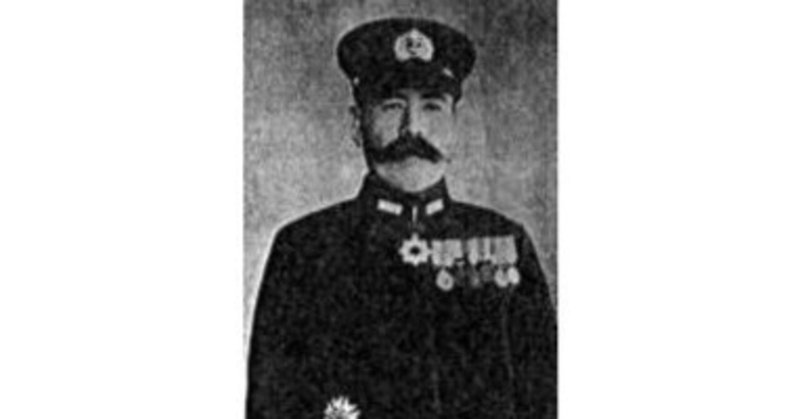
JOG(859) キスカ島守備隊を救出せよ(上)
米軍に包囲された孤島の守備隊5千2百名を救出すべく、木村昌福少将率いる艦隊は死地に赴いた。
■1.「村長さんみたいな人」
昭和18(1943)年6月14日、第一水雷戦隊司令官に命ぜられた木村昌福(まさとみ)少将を乗せた軽巡洋艦「阿武隈」が、千島列島最北端、幌筵(ほろむしろ)島に着いた。そのすぐ北はもうカムチャッカ半島の先端部である。
木村少将は「阿武隈」に乗り込んですぐに司令部幕僚を集め、簡単な打合せをしたが、司令部メンバーの感想は「ヒゲは豪傑でも春風駘蕩(たいとう)のムードがある村長さんみたいな人」だった。そんな司令官の登場に、艦橋内には緊張のなかにも和やかな雰囲気が漂った。
幌筵島には、北太平洋を守備範囲とする第5艦隊が司令部を置いていた。木村が到着すると、艦隊司令長官から、先任参謀の有近六次中佐とともに呼び出された。
司令長官から木村に与えられた命令は、キスカ島を占領している5千2百人ほどの陸海軍将兵を救出することだった。アリューシャン列島はロシアのカムチャッカ半島からアラスカ半島を首飾りのようにつないでいるが、キスカ島はその真ん中よりやや西側にある。
キスカ島は純然たる米国領土であり、建国以来初めて外国軍隊に領土を占領された米軍はメンツにかけて大反撃を行った。米軍は1万1千の兵力で、キスカ島の西にあるアッツ島を襲い、同島の陸軍守備隊2千6百余名は、壮絶な戦いの末に玉砕していた。
その際に、海軍は救援部隊も送れず、補給さえもできなかった事で、陸軍に負い目を感じ、今回はどのような犠牲を払っても、キスカ島の部隊を救出しなければならない、と考えていた。
東西を米軍に挟まれたキスカ島。その死地に飛び込んで、5千2百人もの将兵を救い出せ、とは、想像するだに容易ならざる命令であった。しかし、木村はいつもと同じように平静に「承知しました」と答えた。
■2.「帝国の隆『昌』と人民の幸『福』」
木村昌福は、明治24(1891)年に静岡県に生まれた。父親は雄弁な弁護士であり、かつ改進党員として演説会にも登壇する地元の名士だった。子が生まれた日に開かれた第2期帝国議会の開院式で明治天皇が「帝国の隆『昌』と人民の幸『福』」と述べられた一節から、父親は「昌福」と命名した。
豊かな家庭で、しかも国家のために尽くす父親の許で育てられたせいか、昌福は自分の事よりも他人の幸福を考えるという性格に育った。
コセコセと勉強したりはしないため、静岡中学校での席次は80人中39位という平凡な成績だった。しかし、ここ一番という時には、本来の能力を発揮したようで、定員わずか120人の超難関、海軍兵学校に合格している。
海軍兵学校での卒業時の成績は118人中107番という「ほぼビリ」であり、卒業後は水雷艇の艇長など、地味な道を歩んだ。しかし、木村は不満も見せずに、小さな艦艇で乗員たちを息子同様に愛情を持って育てた。
大正12(1923)年の関東大震災の際には、海軍高官が木村の操る水雷艇「鴎」に乗って、隅田川河口を視察した。流出した家屋の一部などが一面に浮遊するなか、「鴎」はそれらを巧みに避けながら、ピタッと桟橋に横付けした。高官たちから「艇長はだれだ。実に見事なものだ」との声があがった。しかし、木村は日記に「関東大震災救護任務に従事」としか記していない。
昭和14(1939)年、給油艦「知床」の艦長時代、南洋航海の帰りに伊豆諸島の近くを通った。ちょうど乗員に三宅島出身者がいたので、わざわざ同島に立ち寄る事とした。軍艦が近づける港がないので、沖合に停泊し、両親を艦に呼び寄せて息子に引き合わせた。両親と息子ばかりでなく、他の乗員まで木村の思いやりある処置に感激した。
■3.「責任は俺が取るから、決して焦(あせ)るなよ」
キスカ島守備隊救出の命令を受けた木村は、「阿武隈」に戻ると、有近に言った。
__________
とにかく至急、計画を立ててくれ。まず連れていく艦は何にするか。何を連れていくにも俺は先頭艦に乗って黙って立っているから、後は全部貴様に一任する。
先任参謀、ただひとつ注意しておくが、責任は俺が取るから、決して焦(あせ)るなよ。じっくり落ち着いて計画し、十分訓練してから出かけることにする。霧の利用期間はまだこれから2ヶ月もあるんだから。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
「霧の利用」とは、北太平洋で夏の間、発生する濃霧の事だった。艦隊が濃霧に隠れてキスカ島に近づき、将兵らを収容するのが、唯一可能な作戦だった。
そのために有近は、気象専門士官の派遣と、対水上用レーダーを装備し、最高速40ノットを誇る最新鋭の大型駆逐艦「島風」の編入を第5艦隊司令部に要望した。
すぐに気象専門官として派遣されてきたのは、九州大学地球物理学科を卒業して気象班に配属されていた橋本恭一少尉だった。橋本少尉は米国の最新の気象予報の専門書も研究し、また北太平洋の過去の気象資料を毎晩、ほとんど徹夜で分析した。
■4.「5割撤収できれば大成功」
救出艦隊の準備としては、5200人の将兵を1時間以内に収容するために、1隻あたり120名が乗れる上陸用舟艇合計22隻を、巡洋艦2隻、駆逐艦6隻に配備した。さらに警戒任務のために最新鋭の「島風」も含め駆逐艦6隻、および給油艦「日本丸」を配備する、という大規模な編成となった。
さらに、濃霧の中で艦隊行動をするための航行や給油艦からの補給の訓練、「島風」のレーダーを使って地勢や水深を把握する訓練、キスカ湾突入時の収容訓練も徹底的に繰り返された。
また二本煙突の駆逐艦は、白く塗った煙突を一本仮設して、濃霧の中で米艦のように見せかける偽装も行った。
7月4日、訓練を終了すると、木村は次のように日記に記している。
__________
何程の将士を乗艦せしめ得るや実のところ確信なかりき。少しにても乗せればそれにてよし 乗せてから敵機にやられるならば之(これ)は止(や)むを得ぬ 全部乗艦せしめ得ればあとは根拠地に到着し得ずとも「成功」というべき程の困難なる作戦なり
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
救出を待つキスカ島守備隊の方からは「(撤収が)半分できたら大成功なので、救援艦隊は余裕を持って、6割撤収に備え、準備して下さい」と申し出たほどだった。
しかし、木村はあくまで「全員撤収」にこだわり、そのための準備・訓練を進めていた。
■5.「もう来ないのじゃないか」
7月7日、19時30分、救援艦隊は出撃した。キスカ湾突入予定日は11日。島内の海軍部隊は湾周辺に駐留していたが、陸軍守備隊は山中に分散しており、突入時間に合わせて、何時間も前からキスカ湾まで歩いて行かなければならない。
難しいのは撤収に成功した場合と、失敗して今後、敵との一戦に備えなければならない場合の両方を想定しなければならない点だった。そのため、武器庫や高射砲、食料庫などを敵に使わせないように時限爆弾を仕掛けた。また敵機からまだ兵がいるように偽装するため、古い軍服を着せた案山子(かかし)をあちこちに立てた。
11日早朝、キスカ湾から約6キロの山中に陣を敷いていた高射砲部隊に、「行動開始。15時乗艦地集合」との電話が入った。ガスが出ていて、これでは敵機も飛べない。すでに身辺整理を終えていた一行は、安心して、約2時間かけて雪の積もる山道を歩いて行った。
救援艦隊はキスカ島まで数百キロの海域まで近づいたが、橋本少尉の予測は、11日のキスカ島は高気圧が発達して、「霧なし」だった。この日は米艦隊がキスカ島を砲撃した。木村は突入日を13日に延期した。
再設定した13日も、橋本は、高気圧が去らず霧は少ないと判断した。木村は翌14日に突入を再延期。今度は濃霧となったが、キスカ湾東海に米駆逐艦が哨戒していた。この間、毎回、山中の高射砲部隊は湾までを往復していた。行きはまだしも、帰りは足取りが重い。「もう来ないのじゃないか」「アッツの二の舞か」と心も重くなった。
■6.「帰ろう。帰れば、また来ることができるからな」
15日は残りの燃料からすると、最後のチャンスだった。午前2時には視界数メートルの濃霧で、キスカ島に「突入す」の暗号電信を打った。受電したキスカ島の電信室では歓声があがった。
しかし、時間を追うに連れ、天候が回復し、救援艦隊がキスカ島まで200キロほどに近づくと、視界は開けて20~30キロ。時折、青空も見えた。
「阿武隈」の艦橋では、木村を中心に、重苦しいムードに包まれていた。周辺の駆逐艦艦長から「本日をおいて決行の日なし ご決断を待つ」との信号が次々と寄せられた。
木村は目をつむり、じっと考え込んだ。どのくらい時間が経っただろう。木村はきっと顔を上げ、有近の方を向いて言った。「先任参謀、帰ろう」
そして誰に言うともなく、つぶやいた。「帰ろう。帰れば、また来ることができるからな」
午後1時15分、「突入不能」の電信がキスカ島の電信室に入った。10分後、救援艦隊が帰投するとの情報も入った。兵士たちの落胆は大きかった。「もうだめだ。アッツ島と同じように玉砕するしかない」。声を発する者はいなかったが、みんなそう思った。
「戦闘態勢に復帰せよ」との命令が下り、埋めていた砲弾や銃器を再び、使えるようにするなど、やるべき事は山のようにあったが、緊張の糸は切れてしまった。
敵機が空襲に来ても、防空壕に逃げ込まず、呆然と眺めていた。「どうせ死ぬなら、一発で死んだ方がまし。撃たれてもいい」という、あきらめの境地に達してしまっていた。
■7.針の筵(むしろ)
アッツ島の陸軍部隊玉砕に負い目を感じていた海軍軍令部は、どのような犠牲を払おうともキスカ島の部隊を救出すべし、と考えていただけに、木村の救援艦隊が無傷のまま空しく引き帰してきたことに対して、すぐに第5艦隊司令部を叱責した。
救援艦隊が幌筵に着くと、そこに待っていたのは針の筵(むしろ)だった。「臆病風に吹かれた」「断じて行えば鬼神も退くだ」「若干の危険も冒さずして、この作戦ができるか」「燃料の逼迫(ひっぱく)もわからないのか」との悪評が、いやでも耳に入ってきた。
第5艦隊には、木村に対する不信感が充満していたが、木村はいつも通り平然としていた。
第5艦隊司令部は海軍軍令部と打合せをして、「いま一回全力撤収作戦を実施す」と決定した。そして、第2次作戦では第5艦隊司令長官の川瀬四郎中将が直々に軽巡洋艦「多摩」で救援隊に同行し、突入前日の午後10時まで指揮することを決めた。
19日午後9時から開かれた救援艦隊の幹部会議では、司令長官同行に対する不満が爆発した。「突入の号令をかけるだけのために前日の夜まで同行し、あとは突入部隊に任せる、というのは、救援艦隊への不信感によるものだ」
第5艦隊司令部への批判が次から次へと出た。帰投した自分たちへの冷たい仕打ちと、木村へのあてつけのような「長官同行」に激高した幹部たちは「木村司令官のために死のう」と異口同音に言った。
最後に、じっとみんなの話を聞き、無言だった木村が一言、「わかりました」と言うと、議論は決着した。救援艦隊将兵は、腰抜けといわんばかりの批判に曝されたことで、木村の下に一つにまとまり、「次の作戦は成功させる」との決意を強く固めた。
■8.第2次作戦
7月22日午後8時10分、救援艦隊は再出撃した。突入予定は26日。翌23日は、視界1キロ以下の濃霧で、給油艦「日本丸」と海防艦「国後(くなしり)」が隊列から離れてしまった。「日本丸」とは電話連絡はとれるが位置関係が把握できず、「国後」とは連絡もつかなかった。
木村は危険を承知で、高射砲を撃たせ、その音で「日本丸」を誘導した。40分後、「日本丸」が無事、隊列に復帰した。しかし「国後」は依然、行方不明だった。
突入予定日の26日午後5時44分、濃霧の中で「阿武隈」艦橋の見張り員が「右70度、黒いもの」と叫んだ。その直後、右舷後方で衝撃がした。連絡がとれなかった「国後」が突然、姿を現し、衝突したのだった。幸い、両艦とも被害は少なかったが、事故の影響で、突入予定日が29日までずれこんだ。
木村は周囲に言い聞かせるような、大きな声で言った。
「これだけの事故が起こるほどだから霧の具合は申し分なしということだ。結構なことではないか、なあ艦長」
(文責:伊勢雅臣)
■リンク■
a. JOG(458) 駆逐艦「雷」艦長・工藤俊作 ~ 敵兵422人を救助した武士道
「貴官らは日本帝国海軍の名誉あるゲストである」
【リンク工事中】
b. JOG(046) 「責任の人」今村均将軍(下)
戦犯として捕まった部下を救うために、自ら最高責任者として収容所に乗り込み、一人でも多くの部下を救うべく奮闘した。
【リンク工事中】
■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。
1. 将口泰浩『キスカ島 奇跡の撤退 木村昌福中将の生涯』★★★、新潮文庫、H24
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4101384118/japanontheg01-22/
2. 阿川弘之『私記キスカ撤退』★★、文春文庫、H24
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B009HO4IYO/japanontheg01-22/
3. 三船敏郎(出演)『太平洋奇跡の作戦 キスカ』(DVD)★★★、東宝、H25
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B00CSLTC76/japanontheg01-22/
■おたより
■ミィさんより
40年ほど前になるでしょうか「キスカ」上映後館内で大きな拍手が起こりしばらく鳴り止みませんでした。感激して帰路に着いたことを思い出しました。
以後お勧め映画の一番に「キスカ」をあげていますが知らない人が多く(特に女性)残念に思っておりました。
日本のすばらしさに感動する必見の作品だと思います。
■編集長・伊勢雅臣より
映画『キスカ』は「参考」の「3」に挙げています。ぜひご覧下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
