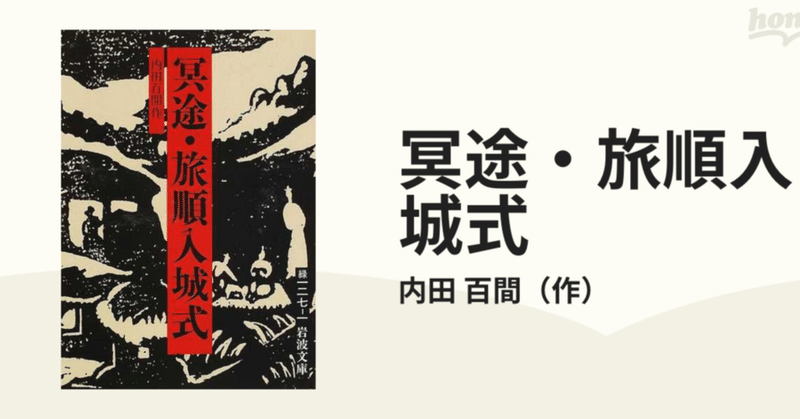
冥途・旅順入城式
内田百閒の短編集
内田百閒の文学は以前から読んでいたが、今回は岩波文庫の『冥土・旅順入城式』というふたつの単行本を収録した文庫を、主に民俗学的なエッセンスがいかに使われているかという観点から読み直してみた。
冥途
『冥途』のなかに、人偏に牛と書いて「件(くだん)」という掌編があるが、文字どおり「からだが牛で顔丈人間の浅ましい化物」に、語り手がなってしまう話である。見事であるのは、冒頭で空に月が浮かぶ風景を描き、とんぼが飛ぶ描写をしてから、広い原の真んなかで語り手は、しっぽからぽたぽたと水を垂らす化物になっている。まわりの外界から語り手とともに、気がつけばすっと「件」によって感覚される内側の世界に入っているような具合だ。見事な書き起こしだと思う。
前半の『冥土』に収録された作品は、短編というには短い掌編であり、どれも夢で見られるふしぎな世界をベースに小説にしたものだと感じられる。顔が人間で体が牛という、ミノタウロスなどのギリシャ神話の神々を思い起こされる「件」の存在は、わたしたちの興味を惹きつける。件の予言を聞くために群衆が集まる描写には、人間存在のおそろしさも描かれる。内田百閒の小説に描かれる、個人が入眠中にふれるような無意識の世界と、人類が長い歴史のなかで育んできた集団的な無意識である神話や民話の世界は、どこかで通底しているのだと思わざるをえない。
「短夜」は語り手の「私」が狐に化かされる話だが、現実から狐のつくりだした幻影の世界に入るときの描写が見事である。池のほとりで薮からでできた狐を観察していると、水中の二匹の鯉に注意がいく。鯉を見失って顔をあげると、池のむこうにいつの間にか若い女(狐)が立っている。この一瞬で、語り手は別の世界に入りこんでしまう。『冥土』では、異界が日常世界のすぐ近くにあって、薄皮一枚をめくれば、一瞬にしてその領域に移動するものとして描かれる。それは、わたしたちの心のなかで意識的な状態と無意識的な状態が、簡単に入れ替わることが可能だ、とでも言うかのようだ。
旅順入城式
後半の『旅順入城式』に収録された作品は、前半に比べると短編小説というにふさわしい長さと構成をもつ。内田百閒がどのような経験をインスピレーション源にして、夢幻の世界を描いているのかが気になるが、それはこんな風ではないかと思えるシーンが『遊就館』にはある。
夜に眠っていると、となりで寝ている妻の口から「獣のなくような声」が洩れているのに気づく。肩をゆさぶると「ぎゃっ」といって目を醒ます。妻は、となりに寝ていた死骸が自分のほうに手を差しのべてきて、逃げだそうとしたが体が動かなかったという悪夢について話す。内田百閒の小説は、自分や身近な者におけるこのような経験をもとにして、夢とうつつがくるりくるりと入れ替わる話を発想しているのではないか。
わたしが今回読んで、もっとも興味をひかれたのが「映像」という短編である。夜明けどきに雨戸が鳴る音が聞こえたと思い、ふと縁側の障子を見ると、切り込みガラスに人の顔が映っている。それは眼鏡をかけて、薄ひげを生やした自分の顔だった。自分の分身が、外から自分を見ていたことが無闇におそろしかったというのだ。それからは夜になると、分身の顔が出現するということが続く。
内田百閒がドイツ語とドイツ文学を専門にしていたことはよく知られるが、ここでE・T・A・ホフマンらドイツロマン派の文学が、ドッペルゲンガーを好んで題材にしたことを思いだす。そこで表現されるのは、人間の心や身のまわりの世界というものは本来的には無秩序なもので、ちょっとした均衡が崩れると、コントロール不可能なものが噴きでてくるという危うさをもつ。だからこそ、自分を律して勤勉にはたらき、理性の力によって社会を秩序立てようという考えが強くなる。しかし、自分の内側に抑圧した無秩序なものは、いつ自分に襲いかかってくるかわからない。その混沌とした、無意識的で、制御不可能な部分というものが、ドッペルゲンガーという瑜に託して描かれるのだ。
百閒と民俗的なもの
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
