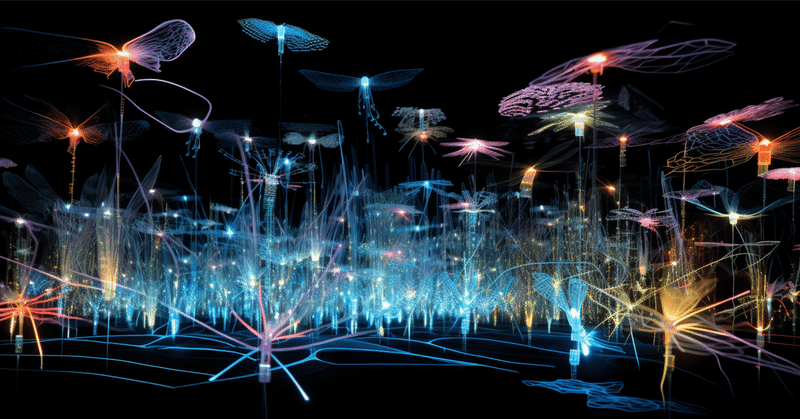
【投資】極小時価総額日本株投資 - 光通信(9435)
株式会社光通信(9435)は時価総額1兆円を超える大型銘柄です。実は先日、時価総額の極めて小さい(100億円未満とか)銘柄に投資をする「極小時価総額日本株投資枠」でこの光通信(9435)を購入しました。
今日は「なぜ極小時価総額投資枠で大型の光通信(9435)を購入したのか」について書きます。
光通信(9435)の黒歴史
株式会社光通信(9435)は1988年に重田康光氏によって設立されました。我々世代(50代半ば)にとっては、1990年代後半のITバブル期に一斉を風靡した銘柄として有名です。ちなみに当時の私、「ただの携帯販売会社なのに、なんでIT、ドットコム銘柄としてこんなに人気なの?」と不思議で仕方ありませんでしたね。案の定ITバブル崩壊後の2000年、株価の下落率はなんと99.1%とワースト記録を更新したとのことでした。
以下、当該銘柄の30年のチャートです。もはやなんだかよくわかりませんね(笑)

今の光通信は?
そんな我々世代的には黒歴史しかイメージできない光通信ですが、現在は劇的な変貌を遂げております。以下彼らの開示資料から抜粋していますが、自社の強みを「顧客基盤」「国内の販売網」とし、時代に応じて売るモノを変化(携帯→回線→保険→宅配水→電力)、安定した収益源を確保してきました。まあ昔は携帯電話をバンバン売る会社ということでしたが、いまは彼らが売れるモノはなんでもバンバン売るという会社、その辺は期待を裏切らないです(笑)

また上記の販売ビジネスだけではなく、M&A、純投資を加えた3つの柱を軸に現在はビジネスを行っています。

投資家としての顔
当方がこの銘柄に興味をもったのは、極小時価総額の日本株を投資する際、スクリーニングにかけて抽出される銘柄の多くで、大株主の欄にこの光通信が入っていたからです。現に当方がその枠で保有している銘柄の1つにも、大株主に光通信がいます。
これまではあまり気にかけてきませんでしたが、改めて今回、先日公表された当社の決算資料を見て、面白そうだなと思いました。
そもそもHPが質素。質素すぎる(笑)一方で開示資料は非常にわかりやすい。各ページで何を訴えたいか、よくわかる。
資料によれば純投資枠で投資をしている企業は627社、その時価総額の合計は約1兆円。ちなみに光通信自体の時価総額も1兆円。つまり?
その純投資枠も株式の値上がり益を狙うファンド投資と違い、あくまでも安定したビジネスを取り込んでいくという狙い。流動性も気にせず、安定したEY、Earnings Yield(持分営業利益/投資簿価)を狙うというもの(直近でEYは14%と結構いい)。
彼らが公表している投資方針としては、"「株式を買うということは、その会社のビジネスを一部保有すること」という考えに基づき、投資先企業と良好な関係の構築を目指しながら、長期間保有することを原則としている。"として、上記EYを指標としながら、安定した事業を行う、財務基盤が強固な優良企業を割安な価格で取得することを目指しています。

投資の狙い
上記の彼らの純投資家としての活動、まさに自分がこの極小時価総額の枠でやろうとしていることと非常に親和性が高いなと思いました。最近流行りのアクティビスト的に投資対象企業にバンバン株主提案するのではなく(あるかもしれませんが)、ちゃんと対話によって良好な関係を築こうとするところも当方の好みにピッタリです。持分法適用会社として、投資先企業のビジネスの業績を彼らの実績に取り組むのが主で、やみくもに株主還元を主張しているわけではありません。というわけで、自身でもこのエリアでの個別株投資は継続しますが、その補完手段の1つとしてこの光通信(9435)にも投資をしてみることとしました。
具体的な狙いとしては:
今後の日本の中小型株の成長の恩恵を期待
この純投資だけで1兆円あるのに、光通信の時価総額は1兆円。つまり光通信自体も割安に評価されているということ(では、純投資枠以外の本業とM&Aの部門の価値はゼロなのか?と)。彼らの資料を見ても、そこは認識しているようで、現在株価が1株あたり2万5千円程度であるのに対し、自社の価値は1株あたり5万円程度であるとディスクロ資料の最後のページで主張されてます。であれば、その価値を実現してもらおうと。つまり、ターゲット価格は5万円ってことですね。
ネックは最小投資金額の高さ。いま1株2万5千円。100株単位となるので、最低でも250万円程度投資に必要です(ミニ株って手段もありますが…)。ハードル高いです。
おそらく我々世代では引き続き昔のイメージが残っており、また本業の商材販売のほうは「ただのブラックな押し売り企業なんじゃないの?」という感じもあり、"ホワイト企業ではない"感満載。この辺がどう出るかリスクも感じるところではありますが、株主となって今後ウォッチしていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
