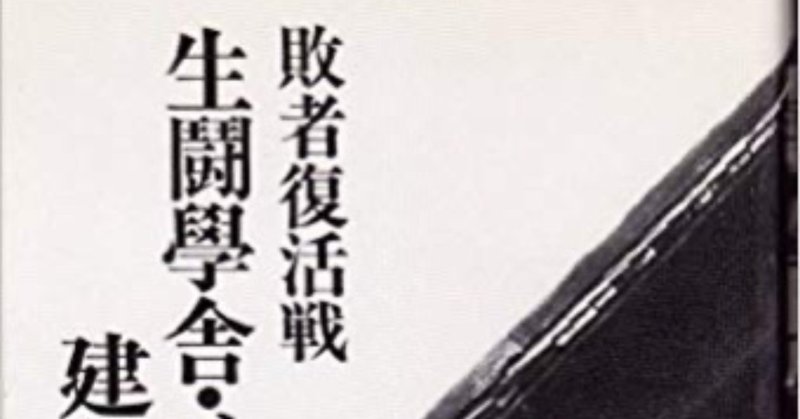
「生闘学舎」
40年前、僕は建築家志望だった。母子家庭の苦学生。でも専門書は買った。高価な図面、作品集である。バイト収入、奨学金はすべて注ぎ込んだ。「ル・コルビュジェ全集」みたいな定番でも、アマゾンなんてなかった時代にわざわざ洋書を取り寄せた。大学の図書館で借りればいいのに。だめなのだ。身銭を切って、いつでも手元に置いておきたい。一緒に抱いて寝たい。そうしないと、先達の叡智が、感性が、血となり肉とならないような気がした。ほとんどビョーキである。
闇雲に買っていたわけではない。欲しくてたまらくなるのは、“有機的”なもの。アントニオ・ガウディが一番わかりやすいだろうか、ぐにゃと生物的で、ちょっと怪奇的、そして猥雑。丹下健三や黒川記章、安藤忠雄などの整然とした作風は全然ダメ。ついには、建築家のものではない造形にも憑かれだした。「軍艦島」の廃墟や香港のスラムの砦「九龍城」の写真集だ。アジアのスラムの書籍も。そこで決定的な自己認識に至る。自分が美しく感じるのは普通のものじゃない、ということを。こうなると市販の書籍には飽き足らず、自分の足でそれらを追い求めるようになる。一眼レフを担いで日本中を歩いた。「ゴミ屋敷」、「被差別部落」、「飯場ドヤ街」を求めて。
そんなある日、大学の研究室で一人まどろんでいると、突然浮浪者のような風貌の人物がやってきた。高野雅夫である。東京都の夜間中学廃止に反対した活動家の彼が、旧国鉄の古枕木6千本を使って三宅島に自力で建てた砦「生闘学舎」。その5年間の苦闘を描いた『生闘学舎建設記録』(修羅書房)を自ら販売行脚中の彼であった。81年度建築学会賞を受賞した「生闘学舎」をそれたらしめたのは、図面を引いた建築家ではない。施主であり建設者である高野一家とその仲間、そして彼らが人生の師と崇めた島の年老いた棟梁だった。建築家なんて、ちっぽけだ。僕はそう思った。
翌年、僕はインドのムンバイに旅立つ。スラムに住み込み住民運動を組織し、4年後、反体制運動を組織したかどで国外退去にあう。
生闘学舎・〔チャリブ〕建設記録―敗者復活戦 (1982年) 生闘学舎・チャリブ https://www.amazon.co.jp/dp/B000J7P5BI/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_wasmEbSVDHSMN @amazonJPさんから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
