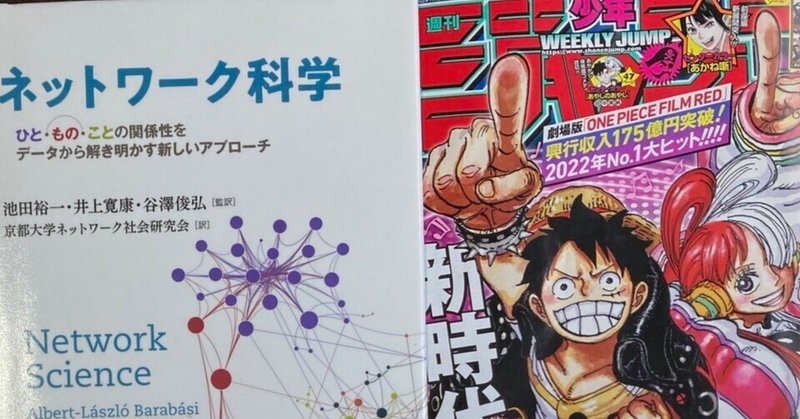
「ネットワーク科学」で理解する「友情・努力・勝利」
きっかけ
「ネットワーク科学」という本があります。
人間関係から電力網までありとあらゆるネットワークについて理論が書いてあり、400ページ以上にわたって数式やら論文やらが解説されています。
私が最近参加している読書サークルの課題図書なのですが、正直最初から最後まで読んでも全体の1割も正確に理解できたか怪しいくらいの難易度でした。私は元々理系の進路を歩んできたのですが、それでも読み切るのに1ヶ月はかかりました。
難して分厚い本を前にすると、もっとわかりやすく読みやすいのを読みたくなる。
気がつくと少年ジャンプを手にしている自分がいました。。。

ネットワーク科学の最後の100ページを読んでいるところで、難しくて心が折れ、気分を改めるために少年ジャンプを買って読み始めたら先にジャンプを読み終えてしまうという…
ジャンプを1ページを読むごとにネットワーク科学も1ページ読むという、並行読み作戦を意図していたのですが、見事に失敗しました。
「難しい本を少しでも役立てるには身近な物事に当てはめて考えればよさそうだ」
そんなことを漠然と考えながら、最後まで読もうとしていると、ふと、読み終えたジャンプから「俺は身近にいるぞ!」という声がする(幻聴)。
「そうか!ネットワーク科学を読んで学んだことを少年ジャンプが掲げる哲学への理解に役立てれば良いのだ!」
このようなひらめきによって書かれたのが本noteです。
友情
まず、友情についてです。
ネットワーク科学では人間関係を理解するときに人間を点、交友関係を線で表したグラフの形から交流パターンをとらえます。
例えば、AさんとBさんが友達同士ならAさんの点とBさんの点の間に線を引いて、友達同士であることを表します。
ここで、Cさんの点から100本の線が出ているなら「Cさんには友達が100人いる」ことを意味していて「友達100人できるかな」クエストがクリアされていることがグラフで表現されているといえます。
友達を増やすということは線を増やすということになり、その線の増えやすさは、「適応度」と呼ばれ、次のように説明されます。
適応度とは、偶然の出会いを永続的な友情に変えてしまうような、ある個人の才能のことであり、競合他社に比べてより多くの顧客を獲得するような、ある企業の才覚のことであり、また、興味を引く他のたくさんのページがあるにもかかわらず、毎日そこを訪れてしまうようなウェブページの力のことである。
一方で、その適応度は遺伝することが示唆されています(同上、p.220)。つまり遺伝的に友達ができやすい人とできにくい人がいるかもしれないということです。
「そんな…どう考えても自分にはルフィのような適応度があるとは思えない…一体どうすればいいんだっ…!」
そこで求められるのが「努力」というわけです。
努力
友達を作る努力と言っても人の心はお金では買えないので、何か仲良くなるための具体的な行動を取る必要があるということです。
確かに生まれや育ち、遺伝子を含めた生物としての特徴などから人生でどれくらい苦労するかが左右される側面がありますが、それでもマシな状況にしていくために社会的な要因としてネットワークを自分にとって適切なものにする行動は有意義と考えられます。
わかりやすい行動としては相手が求めている贈り物を渡すことです。贈与論という本では特に飲食物を与えることの呪術的な効果(何かを受け取ったら、返さないといけない気がする…という心理)などについて書かれています。実際、私も最近は贈与論という本をプレゼントする機会を作ったところ、渡した方のお仕事の業界を知るきっかけとなり、今まで詳しく知らなかった分野に触れる機会になりました。

また、その方からお返しにいただいたスターバックスのコーヒー券を使って、以前お世話になった方にコーヒーを奢る機会を作ったところ、自分が必要していた本を紹介され、贈与が循環することによるポジティブな効果を実感しました。

少年漫画のナルトでは、物語冒頭で主人公のナルトが同級生のサスケ・サクラからお弁当を贈与されることで関係が深まるシーンがあります。
同じようなことが現実にも予想を超える形で実現した例だったと言えます。
アダム・グラント氏が書いた「GIVE & TAKE」という本では、人間を大きく与える人のギバーと受け取る人のテイカー、与えることと受け取ることのバランスを取るマッチャーの三種類に分類し、それぞれのタイプの仕事面な土でのパフォーマンスなどを比較した調査結果を紹介していますが、相手に与えるギバーの中でも相手が協力的な人物かを見分ける観察眼を持ったうえで、与えたことの見返りをすぐには求めない余裕のあるギバーが人間関係を良好にしたという結果も参考になります。
勝利
人間は一人ではできないことも集団になればできるようになる社会的な動物だとも言えます。
ネットワーク科学の分野では人間の集団をコミュニティという単位でとらえます。
そこでは大きなコミュニティほど参加者を集めやすい傾向や、繋がりの少ない人がコミュニティを去る確率が高いこと、コミュニティ内の人間が外部の人と繋がりを多く持つほど崩壊しやすくなること、大きいコミュニティほどメンバーの流動性が高く、小さいコミュニティの安定性を高めるにはメンバーが固定されている必要があるなどの傾向が指摘されています(ネットワーク科学、376~377ページ)。
少年漫画のキャラクターがメンバーの入れ替わりが少ない小規模なコミュニティを安定させているのはネットワーク科学の面から見ても自然な描写なのです。
バイブル
ネットワーク科学という本は、ネットワークの重要性が増している現代において、社会科学の分野を中心にバイブル的な位置付けとなっているようですが、こうした最先端の研究と整合的な少年ジャンプという雑誌こそ心のバイブル的ではないかと思った読書体験でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
