
電子署名法とは?【電子契約の効力とおさえておくべきポイントを分かりやすく解説】
「電子署名法とは?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
電子契約を利用する際に真正性を確保するために電子署名の付与が必要です。この電子署名を付与することで、真正性を証明できる根拠となっているのが電子署名法です。電子契約を導入するうえで、もっとも重要な法律が電子署名法です。この法律にはどのようなことが定められているのでしょうか?
電子署名法を理解することで、電子契約が書面契約と同様に利用できることがわかりますので、一度は目を通しておくとよいでしょう。
この記事では、いま注目を集めている「電子契約の法的効力」に焦点を当て、電子署名法の概要やポイント、電子署名法以外で抑えるべき法律まで解説していきます。
電子署名法とは

電子署名法とは電子契約において非常に重要な役割を果たしています。正式な名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」で、2001年に制定されました。この法律は、主要な目的として「電子署名の円滑な利用を確保することにより、電子商取引を利用した社会経済活動の一層の推進を図ること」が掲げられています。
現在、電子契約の普及が進む中で、電子署名法は何度も改正を重ね、電子署名や認証業務に関連する様々な要素や実務の変化に適応してきました。これは、電子契約の実務や他の法律との整合性を確保し、不足している事項を補完するためのものです。
電子署名自体は、電子文書が本人の意思によって作成され、その後改ざんされていないことを証明するものです。通常、書面契約では記名押印が真正性の証拠とされてきましたが、電子文書においても本人の意思や真正性を証明する必要があり、それを担うのが電子署名です。そして、電子署名法は電子署名の詳細な規定を提供しています。
電子署名法を理解することで、電子契約における電子署名の役割や電子文書の法的な有効性について理解が深まります。したがって、電子契約や電子文書を利用する際には、この法律について理解を深めておくことが重要です。
電子署名法の背景と目的
インターネットや携帯電話の急速な普及と共に、ネットワークが企業間通信だけでなく、国民生活一般にも浸透している社会の変化がありました。ネットワークは、電子申請、電子商取引、教育など、紙の使用が主流だった分野からゲーム、テレワークなど広範な分野での利用に広がり、社会経済活動の根幹を支えています。
しかし、ネットワークを介したコミュニケーションでは、実際に相手と対面することがなく、相手が本当に本人であるか、通信の途中で情報が改ざんされていないかといったセキュリティ上の懸念が生じます。このような確認作業が必要な状況で、電子署名や認証業務は有効な手段とされています。しかし、当時、電子署名や認証業務が法的にどのように扱われるべきかについて明確な規定が欠如しており、その法的有効性が不透明であることが問題とされました。
具体的には、電子署名や認証が本人確認に有効であったとしても、トラブルが発生し、裁判に至る場合、電子署名や認証の法的評価が不明確であり、解決が困難である可能性が指摘されていました。このため、電子商取引などにおける信頼性に疑念が抱かれ、電子署名や電子認証の普及が妨げられる状況が生まれました。
この問題を解決し、電子契約や電子署名に関するルールを明確にし、電子商取引の信頼性を向上させ、その普及を促進するために、電子署名法が施行されました。電子署名法の制定背後には、電子契約における法的な取り扱いに関する不明確さを解消し、電子契約の法的効力を確立するという目的がありました。
電子署名法の施行に先立つ背景には、インターネットや携帯電話の普及に伴い、電子取引が増加したことが挙げられます。この増加に伴い、電子契約の法的取り扱いに関する不明確さが浮き彫りになり、電子署名法の必要性が高まりました。電子署名法は、電子契約の有効性や証拠力について明確な法整備を提供し、電子契約の法的取り扱いを明確にしました。これにより、電子商取引や電子契約における信頼性が向上し、社会経済活動の促進を支える法律として存在しています。
電子署名法で押さえておくべきポイント
電子署名法について押さえておくべきポイントは、電子契約も要件を満たせば書面の契約と同様の法的効力があるという点です。
まず、契約のほとんどは口頭のみでも成立します。このため、契約の成立それ自体は書面で残すことを必要としません。しかし、口約束で行われた契約は、後になって「言った」「言わない」というトラブルになりやすく、細かい条件などを忘れてしまうという事態を招きかねません。このため、契約の内容を書面にして、当事者同士が確かにこの内容で契約したという証を残すのです。これが、契約書を作成する意義です。
私文書は、本人(中略)の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
この規定は、契約書等の中に本人の押印があれば、その文書は「本人が作成したものであると推定される」こと(推定効)、また、「裁判所は、本人が押印した文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよい」ことを意味します。
本人の押印がある契約書に証拠力(形式的証拠力)がある、法的効力があると言われるのは、文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになるからです。
それでは、紙の契約書が存在しない電子契約では、法的効力を持つ契約書を交わせないのでしょうか?その答えは、電子署名法第2条と第3条にあります。
電子契約の法的効力を認める電子署名法第2条と第3条
電子契約の法的効力について、電子署名法にはポイントとなる2つの条項があります。それが第2条と第3条です。まず同法第2条には、以下のように電子契約における電子署名が認められるための要件が定められています。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(後略)
つまり、電子契約における電子署名は、本人が行い、契約の電子ファイルやデータが改変されていないか確認できることが求められています。
続いて、電子署名法第3条では「申請な成立の推定」が以下のように定められています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
簡単に言えば、電子契約は、本人による第2条の要件を満たす電子署名が行われている場合、真正に成立したものと推定する、すなわち、有効な契約が行われたと認められる法的根拠のある電子契約だとされているのです。
これら2つの条項によって、要件を満たしている電子契約は、法的効力をもつと言えるのです。
電子契約の法的効力について
電子署名法4条以下では、電子契約の有効性を証明するための認証業務について、認証業務を行う会社の認定要件等が定められています。電子契約の利用者としては、電子署名法3条(及び電子署名の定義を定めた電子署名法2条)の内容を押さえておけば十分です。
民法上、原則として契約は申込と承諾があれば成立し、必ずしも書面での契約締結の必要はありません。もっとも、契約当事者との間で万一争いになった場合、口頭では言った・言わないの争いとなってしまうため、裁判上でも証拠力を持つ証拠として提出できるものとしておく必要があります。
これについて、裁判上契約書を証拠とするためには、その文書が真正に成立したこと(本人の意思により作成されたこと)を証明する必要があります(民事訴訟法228条1項)。紙媒体の私文書を証拠提出する場合、その文書に本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、その文書が真正に成立したもの(本人の意思により作成されたもの)と推定されます(民事訴訟法228条4項、1項)。
また、署名がなく押印のみの場合には、私文書に押印されている印影が本人又は代理人の印章と一致していることが確認されれば、反証のない限り、本人の意思に基づいて押印されたものと推定され、当該押印が本人の意思に基づいて行われたことにより当該私文書の成立が推定されます(いわゆる「二段の推定」と呼ばれるものです)。
これに対応して、電子文書の場合についても、電子署名法第3条において、「本人による電子署名が行われている」ことを要件として、その場合には当該電子文書が真正に成立したものと推定されると定められ、電子契約の法的効力が整理されました。
認証業務について
上述のとおり、証拠力のある電子契約とするためには、「本人による電子署名が行われている」との要件を満たす必要がありますが、書面を見れば確認できる書面上の署名と異なり、電子署名は電子データ上の措置であるため、「本人による」ものかどうかを別途証明する手段が必要となります。
これについて、電子署名法上、 第三者が本人による電子署名であることを証明することを予定しており、この業務のことを「認証業務」(電子署名法2条2項)、そのうち、本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務を「特定認証業務」と定義しています(同法2条3項)。
認証業務(電子署名法2条2項)
第三者が本人による電子署名であることを証明すること特定認証業務(電子署名法2条3項)
認証業務のうち、本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務
現在、「特定認証業務」の基準に採用されている認証技術は、公開鍵暗号という暗号方式を用いたPKI (Public Key infrastructure)技術とされています(電子署名法施行規則2条)。 「特定認証業務」は、この技術を用いて、電子文書等の暗号化と本人確認を行い、電子署名が本人のものかどうかを証明するための電子証明書を発行する業務をさします。 なお、認証業務は民間会社が行うことを認められており、認証業務を行う第三者機関は「電子認証局」と呼ばれ、電子署名法4条以下においてその認定基準等が定められています。
電子署名法3条が定義する推定効の要件
電子契約を作成する際に利用される場合が多い電子契約サービスには、利用者自身が電子証明書を発行するか、否かによって以下の2タイプがあります。
当事者型
立会人型
当事者型とは、利用者自身が電子証明書を発行します。また、利用者自身で電子文書に電子署名を付与するのです。したがって、立会人型と比較して、万が一、裁判があった時に契約書の信頼性が高いとも考えられています。
一方で立会人型は、利用者自身は電子証明書を発行しません。利用者に代わり、事業者が電子文書に電子署名を付与するのです。したがって、利用者は手間とコストをかけることなく、電子契約サービスを利用開始できる点にメリットがあります。
ここで、「立会人型電子契約サービスは事業者により電子署名が付与されているので、電子署名法2条の本人性の要件を満たしていないのでは?」と疑問がわきます。
結論、立会人型電子契約サービスにより、電子署名を付与したとしても、真正な文書であると推定することができます。
なぜなら、総務省・法務省・経済産業省の3省連名で公表した「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」上で、立会人型を利用したとしても利用者の意思が明らかであれば真正に成立するとの見解が示されているからです。
つまり、立会人型であっても、電子署名を付与している事業者に対して、電子署名を指示しているのは利用者であるので、電子署名の本人性の要件は満たしていると公表しています。
皆さまのビジネスの発展を支援するために、これからも様々な情報をnoteでシェアしてまいります。ぜひ、「iidx.work」 のnoteアカウントをフォローしてください!
\ iidx.work のホームページはこちら /
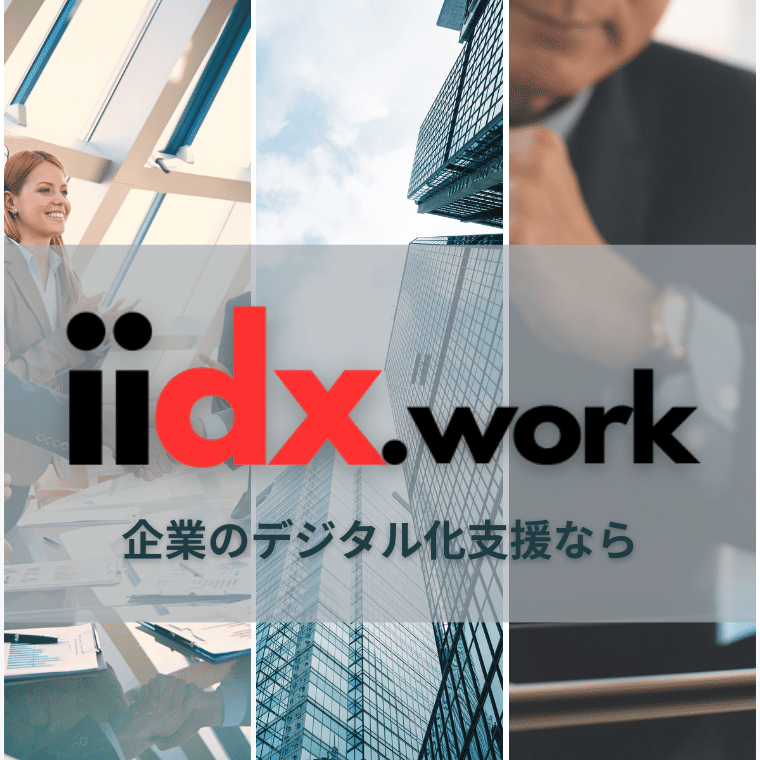
いいDXを全ての企業に「iidx.work」の専門知識と選択ガイドでビジネスの未来を描く

