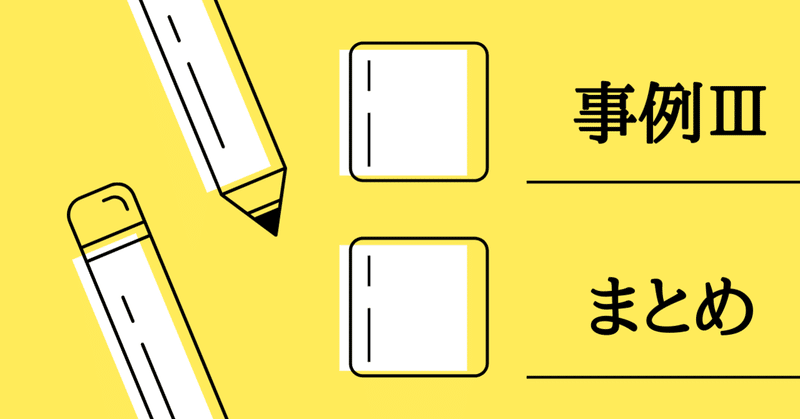
【診断士試験】事例Ⅲまとめ(2次直前テキストより)
こんにちは。なごみ地蔵です☺
本日は、「今年度、中小企業診断士試験を受験予定だ」という方に向けての記事です。
前回に引き続き、今回は事例Ⅲを取り上げます。
事例Ⅲの構造
・生産・技術がテーマで、事例企業として必ず製造業が設定される
・業務プロセスのどこかに非効率な点があり、それを改善していくというのが中心的なテーマ
・「営業」「設計」「調達」「作業(生産)」「検査」など、さまざまなプロセスの改善がテーマになる可能性がある
・4問構成であることが多い
・第1問で強みを中心としたSWOTを抽出する問題
第2問、第3問でオペレーション(業務)レベルの改善
第4問で今後の戦略面に関する問題
というのが典型的な問題構成
・C(コスト)やD(納期)の面で課題を抱えているというのが典型的なC社のイメージ
具体的な頻出論点
1.生産形態
・見込生産は「在庫問題」
受注生産は「生産リードタイム短縮」 が主な課題となる
・少種多量生産は見込生産および連続生産となることが多く、
多種少量生産は受注生産および個別生産となることが多くなる
・少種多量生産には専用機、
多種少量生産には汎用機(1つの機械で複数の加工工程に対応可能な機械。ただし、熟練工・多能工が必要) が向いている
・ロット生産…段取り替えが生じる
※段取り替え
・近年、製品多様化や在庫の最小化などから小ロット化が進展している
→段取り替えロスと在庫費用のバランスのとれた最適なロットサイズで生産することが課題
・段取り替え時間の短縮は重要課題だが、段取り替えには「時間」の問題だけでなく、「回数」という問題もある
→「回数の削減」は、生産計画の見直しや作業指示(物の流し方)の変更で可能な場合もある
2.生産計画
・生産計画とは、「量」と「時期」の計画であり、QCDのD(数量および納期)に対応する
・生産計画の面で課題がある場合には、
計画の立て方(何を重視しているか)
計画の頻度やタイミング
C社全体として全体最適な計画を立てる(部分最適になってしまっているので)
といった設定が考えられる
3.情報システム
・事例ⅢにおけるC社は、オペレーションの面で非効率な点を抱えているが、その原因が、情報の伝達や共有の面にあるという設定がある
→どのプロセスでどの情報(データ)が足りていないか、
必要な情報(データ)や共有すべき情報(データ)は何か
を考えることがポイント
事例Ⅲ対応上のポイント
1.生産管理の知識を整備すること(QCD、生産形態、生産計画など)
2.根拠の切り分け
設問の解答根拠として中心となる段落を見定め、その内容に紐づく内容を他の段落から拾う、という形で整理した方がスムーズな場合も多い
3.問題の構成
第1問はSWOT(特に「強み」)
第2,3問はオペレーションレベル(主にCとDの改善)の設問←「弱み」と絡む
第4問が戦略提示の問題←「強み」が絡む
というのが典型的
4.C社のあるべき姿
全体最適、標準化、計画的に、といった組織としてオペレーションが管理されている状況であること
5.解答の構成
・制限字数が多い設問が多く、因果関係を整理して文章を構成することになる
・「策」が問われる場合、「状況や環境変化」+「策」+「効果」といった基本的な構成イメージを持っておく
最後に
前回に引き続き、今回は事例Ⅲのポイントを簡単にまとめてみましたが、いかがでしたか?
次回は事例Ⅳの記事を更新予定ですので、引き続き読んでみたいと思っていただけたら、フォローの上、更新をお待ちいただけると嬉しいです☺
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
「この記事を読んで良かったな」
「自分も2次試験対策頑張るぞ!」
と少しでも思っていただけたら、
「スキ♡」やコメントをいただけると嬉しいです☺
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
