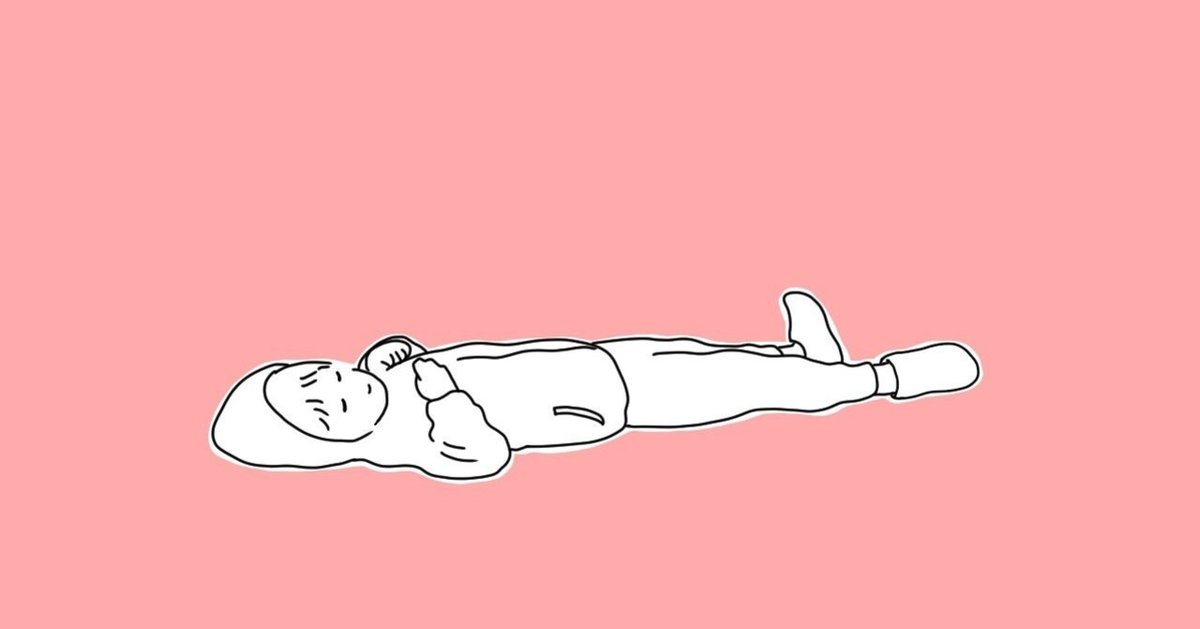
『ハラスメントが横行する職場』なんか、休んでしまえばいい!
【ハラスメント自己防衛マニュアル(12)】
これまでに書いて来たハラスメント対策は、マガジンにまとめていますので、ハラスメント被害に遭っている方は参考にしてください。
前回に引き続いて、「逃げる」ことについて、書いてみたいと思います。
1、ハラスメントが横行する職場は休んでしまえ!!
会社には、職場のハラスメントを防止する義務があるのですから、それが出来ない職場は働く場所として不適格です。
職場でのハラスメントから「逃げる」手段として一番簡単な方法は「職場を休む」ことです。
「自分責めることなく、休んで下さい。」
まず最初にこのことをお伝えしたいと思います。
ハラスメントを受けると、心身に不調をきたすようになります。軽微だからといって、それらの不調を我慢して働き続けると、症状が悪化して「うつ病」などの精神障害を発症してしまう可能性が高かまります。精神障害の症状がひどくなれば、長期の療養をしなければならなくなるかもしれません。症状が悪化して、起き上がることができなくなるまで、我慢する必要はありません。
ハラスメントによる恐怖や不安で、身体に、頭痛や腹痛、不眠などの症状が出たら、軽微であっても、迷わず専門医を受診しましょう。
2、会社の休み方は「有給休暇」「私傷病の欠勤」「労災による療養」の3つ
(1)「有給休暇」
通常、病気で会社を休むときには「有給休暇」を取得します。
年間に与えられる「有給休暇」の日数は、勤務年数に応じて段階的に増えてゆきます。そして、取得しなかった今年の「有給休暇」の残日数は、翌年に繰り越されます。翌年は、今年の「有給休暇」の残日数に、翌年分の「有給休暇」を合算した合計日数が上限となります。
また、有給休暇を取得した時の給与は、(ボーナスや残業代には影響する可能性がありますが、)通常通り支払われます。
(2)「私傷病による欠勤」
業務以外の原因による病気や怪我が理由で会社を休む場合で、有給休暇を全部使い切ってしまうと、その後は欠勤扱いとなり、会社に特別な給与補償制度がない限り、原則無給となります。
会社からの給与の支払いがなくなると、その後、健康保険から「残業代を含む毎月の給与相当額の2/3」が「傷病手当金」として支給されます。この「傷病手当金」の支給期間は、最長18カ月間となっています。
注意しなければならないのは、「私傷病」で「欠勤」になると、通常、会社は社員を「休職」扱いとする人事上の処分を行います。「休職」扱いとなると、あらかじめ会社が規定している「休職期間」の範囲内しか、その会社には在籍することができません。
病状が回復せず、復職できないままに、この「休職期間」を過ぎて欠勤を続けると「休職期間満了退職」として退職することになってしまいます。
(3)「労災による欠勤」
職場におけるハラスメントが原因で、精神障害を発症し、会社を休んで療養する場合には、労基署に申請をして労災が認められることがあります。(詳しくは厚生労働省作成の「精神障害の労災認定」を読んで下さい。)
ただし、労災認定は行政が認定するものなので、申請してみなければ、労災認定されるかどうかはわかりません。
労災認定がなされると、会社が強制加入している労災保険から「残業代を含む毎月の給与相当額の80%」が支払われます。また、労災認定を受けるまでの間に、「傷病手当金」を受け取っていた期間があれば、遡って、労災保険で支払われる額との差額も追加支給されます。
労災認定されると、会社は従業員の症状が回復して、会社に復職できるまで、「休職期間」以上に会社を休んで療養していても、簡単に従業員を解雇をすることができません。
3、会社を休むときに、考えておきたいこと
ハラスメントを受けると、精神的に追い詰められることが多いので、自分で自分の状態がどうなっているのかが分からなくなります。ですので、家族や友人に相談したり、専門医を受診して、アドバイスを受けることがとても大事です。
特に、身体にストレス症状が出始めているときには、すぐに、専門医を受診して、その時点で診断書を書いてもらいましょう。後々、どのくらい療養が必要となるかは、専門医のアドバイスを受けて決めて行けばいいのです。
会社への対応は、ハラスメントの当事者の「職場での優位性」が及ばない人を巻き込むことが大事で、一般的には、人事部門に直接相談するか、ハラスメントの相談窓口などを利用することが多いと思います。(その際に、診断書やハラスメントの事実を証明する資料があれば、これまでの経緯や現状が説明し易いと思いますが、それらがなくても、自分の心と身体の健康を守ることを優先すべきと思います。)
ハラスメントから逃げる方法として、「会社を休む」という選択肢は、自ら選択するとなると躊躇しがちですが、周囲の支援してくれる人を巻き込んで、心や身体の健康を大きく害する前に、使って欲しいと思っています。
<精神障害の労災認定;リンク先>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf
