
知っているようで知らない 「親和のひみつ」
(この記事は2020年1月14日付の禁止改訂により《オパールのモックス》が禁止されたためほぼ全文無料公開としました。末尾に有料部分がありますがこれは親和研究コミュニティへの案内であり、記事内容には関連がありません)
こんにちは。ご主人様、お嬢様。
バーチャルメイドデュエリストの曳山まつりか(@hikiyamajasmine)です。
バーチャルコロシアムからYoutubeやTwitchを通してマジックザギャザリング(MTGArena/MagicOnline)の実況プレイ配信を行なっています。
普段はバーチャルコロシアムの外には出られないのですが、兄と共にデッキを調整してリアルの大会に持ち込んでもらい一喜一憂するのが最近の楽しみです。
そんな兄に託したデッキのひとつ。それがモダンの「親和」デッキです。
兄はこのデッキをGP横浜2019で使用しトップ8こそ逃したものの運良く13勝2敗という成績を残し、先日のMCバルセロナへ参加してきました。
ホガークの海となったMCバルセロナでは残念ながら構築ラウンドは1勝4敗と箸にも棒にもひっからない成績となってしまいました。本人はスキポール空港でのトラブルが...と言い訳をしていますが、これは余談になりますので割愛いたします。
ともあれ、古くはスタンダードやエクステンデッドから「親和」デッキを使用し、バルセロナ以前にも兄はPT/MCの権利を獲得しています。一貫して何年もの間使用したことでそれなりのノウハウを蓄積してきました。プロプレイヤーや根っからの親和マニアの方には及ばずとも、この記事を通して知識や経験を共有することはきっとみなさまのお役に立てると信じています。
有料記事ではありますが、是非お付き合いくださいませ。
---------------------------------------------------------------------------
この記事はコミックマーケット(C96)1日目(2019年8月9日)において頒布された同人誌「Omni-thopter」に掲載された記事をnote用に加筆・修正してものです。「Omni-thopter」PDF版からも全文にアクセスできますので既にお持ちの方、ご興味のある方はそちらからご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------
さてみなさま、親和というデッキをどれほどご存知でしょうか?
MTGアリーナからマジックを始めた方は名前を聞いた程度、かもしれません。かつてスタンダードで猛威を振るったアーティファクトビートダウンで、数々の禁止カードを生み出し、現在ではモダン環境に存在するデッキです。
使用者はそれほど多くないものの、メタゲーム上のアーティファクト対策が緩むと上位に顔を出すような根強いファンのいる強力なデッキです。
ここ数年、親和をプレイする中でときどき感じることがありました。
それは対戦相手の方が「親和デッキを知らない」というところです。
プレイヤーの世代交代や純粋に人口が増えたこと、モダンのメインストリームから外れていることなどが原因と思われますが親和との対戦経験が少ないプレイヤーが多いのです。
これによって負けるところでは負けず、勝てないはずのところで勝つというラッキーウィンが度々起きていました。
プロレベルでは珍しい出来事かもしれませんがGPやMCQのようなさまざまなレベルのプレイヤーが入り混じる大会ではごく普通です。
もちろんモダンフォーマットには数多くのデッキが存在しています。
すべてに深い理解をすることは到底不可能であり、親和についての理解や経験が少ないのはむしろ当然のことでしょう。
親和について多くの時間を費やして研究をすることは費用対効果の面では得策とは言えません。
しかし、もし短時間で深く理解することができる記事が存在するとしたら?
親和をプレイする場合はもちろん、親和と相対するときにも大きなアドバンテージを得ることができます。
これまで、親和についていくつもの記事が存在しました。玉石混交ではありますが、世界有数の親和マニアやプロプレイヤーが執筆した大変クオリティの高い記事も存在します。
ですが、基本的にそれらは初心者に向けたものです。親和の基本は書いてあってもそれ以上に踏み込んではいません。あっても紙面の多くを占めるマッチアップガイドやサイドボードガイドなどは環境によって大きく変化する賞味期限の短い部分です。
この記事は親和のより深い部分を伝え、付け焼き刃ではなく何年経っても長く使える、アーキタイプそのもののガイドとなることを目標としています。
親和を使い始めたけど中々勝てない、逆に親和を対策したはずなのに簡単に負けてしまう。そんな方の助けになれば嬉しいです。
親和は本当に楽しいデッキです。10年以上プレイし続けていても飽きがこず、いまだ1ターン目のセットランドで迷うことや簡単なプレイミスをすることすらあります。終わってからああすればよかった、こうすればよかったと毎ゲームのように思い返してしまいます。
たとえそれが勝ったゲームだったとしても。
この最高に楽しいデッキで悩み、考え、そしてその壁を乗り越える楽しさを多くの方に知ってもらいたいのです。
記事の構成としては、前半は既存の記事と同様、初心者向け親和の大まかなプレイガイドとなっています。親和の特徴や戦略、よく使用されるカードの解説とTIPSとなっています。
後半は盤面ごとのプランの組み立て方や駆け引き、メタに合わせての構築方針などです。
ちょうどこの記事が発表される2019年8月はMCリッチモンドシーズンであり、フォーマットはモダンです。
本当にボクの力などは微かではありますが、少しでもご主人様のお役に立てれば、それ以上のことはありません。ぜひご活用くださいませ。
1.親和の特徴
親和がアーティファクトクリーチャーをたくさん並べて攻撃してくる、アグロなデッキだということは実際に対戦したことがなくともおそらくご存知でしょう。しかしながら、Zooやバーンなどの通常の直線的なデッキとは異なり以下の5つの特徴を併せもっています。
ひとつは展開力、
ひとつは柔軟性、
ひとつは攻撃力、
ひとつは突破力、
ひとつは持続力。
これら5つの要素をすべて併せ持っているのが親和です。
まずは、現在(2019年7月)の主流となっているデッキ構成をご覧ください。
Creatures
4 電結の荒廃者
4 大霊堂のスカージ
4 鋼の監視者
4 羽ばたき飛行機械
4 信号の邪魔者
1 エーテリウムの達人
2 メムナイト
Spells
4 頭蓋囲い
4 感電破
4 バネ葉の太鼓
4 オパールのモックス
2 溶接の壺
2 実験の狂乱
Lands
4 ちらつき蛾の生息地
4 ダークスティールの城塞
4 墨蛾の生息地
3 産業の塔
2 山
Sideboard
1 実験の狂乱
1 古の遺恨
3 減衰球
3 急送
2 刻まれた勇者
2 安らかなる眠り
1 呪文貫き
2 思考囲い
この《実験の狂乱》タイプは2019年2月ごろより登場し、MCロンドンでも準優勝した、いわゆる“板”なリストです。モダンホライゾン後も含め4ヶ月間ほとんどリストが変化していません。これを2019年7月現在のベンチマークとしてお話ししていきます。
ご覧の通りデッキの大半は軽いアーティファクトで構成されています。そのうち12枚は0マナのアーティファクトであり、親和の「展開力」の原動力となっています。序盤から軽いアーティファクトを一気に展開し、《頭蓋囲い》や《電結の荒廃者》《鋼の監視者》で強化し畳み掛けています。
単体でパワーが増大する《頭蓋囲い》と《電結の荒廃者》、クリーチャー全体を強化する《鋼の監視者》《信号の邪魔者》が存在するため、しばしば点と面で攻めるデッキと呼ばれます。対処する側からすると臨機応変に攻める形を変えるので非常に難儀する「柔軟性」の高いデッキです。
一瞬でクロックを爆発させる《頭蓋囲い》と《電結の荒廃者》は親和の「攻撃力」を担います。とくに《電結の荒廃者》がいることで理論上は先手2ターンキルが可能です。ビートダウンデッキでありながらコンボデッキ並みのスピードを備えています。(例:墨蛾 羽ばたき 羽ばたき モックス モックス 邪魔者 邪魔者 城塞 荒廃者の8枚)
このデッキではサイドボードに落ちていますが《刻まれた勇者》による「突破力」は見逃せません。プロテクション(すべての色)の一文は伊達ではなく、特にフェアデッキの多い環境ではあらゆる攻守共に鍵となります。また、《電結の荒廃者》もその自在な能力で相手にわずかばかりの隙も許しません。
これらを下支えしているのが《ちらつき蛾の生息地》《墨蛾の生息地》という合計8枚投入されたミシュラランドです。土地は17枚かつ、軽いカードだらけの親和という印象からすると意外かもしれませんが《オパールのモックス》《バネ葉の太鼓》を含めるとマナソースは実は25枚もあります。そのままであればすぐにマナフラッドを起こし息切れをしてしまいます。しかし、これらのミシュラランドはフラッド受けとしてもクリーチャーとしても強力なため、攻め手を継続し続けることが可能です。盤面が全体除去で空になったとしてもすぐさま攻撃に転じる「持続力」があります。また、スタンダードの赤単でお馴染みの《実験の狂乱》は親和の軽くて土地の少ない構造に驚くほどフィットしています。リソース勝負となりやすいフェアデッキ全般やミラーマッチにおいて圧倒的なアドバンテージを得ることが可能です。
と、ここまで親和の特徴として良い面を書き連ねました。これだけだと隙のない最強のデッキのように見えますね。たしかにかつてはメインボード最強のデッキとも呼ばれていたこともあります。しかし、現在のメタゲームのメインストリームにはいないことから分かるように今の親和はそういったデッキではありません。強さと共に弱点も多く存在するのです。
まず、速度面です。最速先手2ターンという速度はもちろん速いのですが確率はかなり低く、妨害も乗り越えるためにはかなりの運が必要となります。現実的なキルターンはよくて3ターンで、実際は4ターン前後がもっとも多いでしょう。これはモダンに存在するコンボデッキに対して少し遅れています。トップスピードこそはコンボデッキ並ですがアベレージでは敵いません。親和は自分より速いデッキに対しては不利なのです。
また、特定のカードに強く依存しているデッキです。2マナ御三家の《頭蓋囲い》《電結の荒廃者》《鋼の監視者》これらが機能していないゲームではかなり勝率が下がります。どれも除去に対して脆弱ですのでキーカードをピンポイントで対処されると厳しいです。
そしてサイドボード後はドレッジに続いて大きなヘイトを受けるデッキです。メタゲーム上の位置によってはさほど対策カードを取られることはないでしょうが、それでも《石のような静寂》をはじめとしたヘイトカードは強力で使われればほぼ壊滅します。対策の対策も多彩なサイドボードだからこそ正解はなく、常に同じサイドボーディングが取れるとは限りません。デッキごとに取るべきプランをしっかりと考え、ゲームごとに割り切りながらサイドボーディングを行います。
この強みも弱みもはっきりしたデッキを乗りこなすために必要なのは知識です。それぞれのカードの役割や目的をはっきりと知る必要があります。次の項からはすべての親和関連カードについて解説していきます。
2.個々のカードについて メインボード編
大半のカードが固定スロットとなっている親和ですが、それぞれのカードがどういった役割をもっているのかご存知ではない方もいらっしゃると思います。はじめての方にはご紹介として、知っている方にはおさらいの意味も込めて一枚一枚を振り返ってみましょう。
⑴デッキの核となるカード群
親和がゲームに勝つために必要になるカードたちです。これらがプレイできない手札は極力キープしないようにしましょう。

Arcbound Ravager / 電結の荒廃者 (2)
アーティファクト クリーチャー — ビースト(Beast)
アーティファクト1つを生け贄に捧げる:電結の荒廃者の上に+1/+1カウンターを1個置く。
接合1(このクリーチャーは+1/+1カウンターが1個置かれた状態で戦場に出る。これが死亡したとき、アーティファクト・クリーチャー1体を対象とする。あなたはこれの+1/+1カウンターをすべてそれの上に置いてもよい。)
0/0
MCQの参加プロモカードにもなっている名実ともに親和の顔です。
このカード1枚で無限に記事を書くことができるほど奥深いカードでもあります。シンプルな能力ですがほぼすべてのカードとシナジーを持つデッキの要です。場に出ているパーマネントを食べることで自在に盤面をコントロールします。オールインをはじめ、クロックの上昇、除去を避けてアドバンテージを獲得するなど、非常に器用なカードです。
1枚でも場に存在すると盤面が非常に複雑化しますので、手札になくとも引いた場合のことは常に考えましょう。
TIPS
・《荒廃者》Aで《荒廃者》Bを食べると接合が誘発するため、+1/+1カウンターがひとつ増えます。
・呪文や能力、戦闘の解決前に生贄に捧げることで単一の対象を持つ呪文(例:《謎めいた命令》のバウンスドローなど)を対象不適正で打ち消したり、絆魂のライフゲインを阻止することが出来ます。
・接合は相手のクリーチャーにも行えるため、接合先が相手しかない場合や、《呪文滑り》などで対象を変更させられてしまうことがあります。

《Cranial Plating / 頭蓋囲い (2)
アーティファクト — 装備品(Equipment)
装備しているクリーチャーは、あなたがコントロールするアーティファクト1つにつき+1/+0の修整を受ける。
(黒)(黒):あなたがコントロールするクリーチャー1体を対象とし、それに頭蓋囲いをつける。
装備(1)
電結の荒廃者》とともに親和の打点を支える二枚看板のもう1枚です。+4,5程度は朝飯前、ロングゲームであれば+10も珍しくありません。
《大霊堂のスカージ》や《刻まれた勇者》との組み合わせは非常に強力で、フェアデッキとのダメージレースではとても重要になります。
TIPS
・忘れられがちなのが、黒黒を支払うことでインスタントタイミングでの装備移し替えが出来ることです。複数体でアタックしたときに意表を突いたり、呪文を構えたあとのターンエンドにマナを節約することを忘れないようにしましょう。マナベース次第ですが、基本地形に沼を入れるとより起動しやすくなります。

Steel Overseer / 鋼の監視者 (2)
アーティファクト クリーチャー — 構築物(Construct)
(T):あなたがコントロールする各アーティファクト・クリーチャーの上に+1/+1カウンターを1個置く。
1/1
全体強化を行うクリーチャーです。タイムラグはあるものの効果は絶大で特に《荒廃者》との組み合わせは極悪とすらいえるでしょう。相対する場合には間違っても生かしたままターンを返してはならず、2ターン生き残ればかなりの確率で勝利をもたらします。各種ミシュラランドにも乗るので起動する際には忘れずにクリーチャー化しましょう。
強力なカードですが最近は採用枚数が減少傾向にあります。モダン環境の高速化で完全に遅いカードとなってしまったこと、《レンと六番》や《溶岩の投げ矢》などの格好の標的であることがその理由です。この逆風を超えた構築が次世代の親和を見つける鍵かもしれません。
TIPS
・カウンターは監視者自体にも乗ります。2回、3回と起動していくうち監視者自身も大きくなっていきます。起動するだけでなく自身で攻撃しにいくことも選択肢に入れましょう。

Master of Etherium / エーテリウムの達人 (2)(青)
アーティファクト クリーチャー — ヴィダルケン(Vedalken) ウィザード(Wizard)
エーテリウムの達人のパワーとタフネスはそれぞれ、あなたがコントロールするアーティファクトの総数に等しい。あなたがコントロールする他のアーティファクト・クリーチャーは+1/+1の修整を受ける。
*/*
3マナと重いものの、その分盤面に与える影響力の大きいクリーチャーです。
面と点の戦略を一人で完結させる強力なロードで、生き残れば速やかにゲームを終わらせることが可能です。
色マナが必要かつ重いので《刻まれた勇者》と枠を争いますが、裏目の少ないカードであるためメインで採用する可能性は高いでしょう。
TIPS
・《大霊堂のスカージ》と同じく有色のアーティファクトです。有色でも《神秘の炉》でプレイすることが可能です。

Etched Champion / 刻まれた勇者 (3)
アーティファクト クリーチャー — 兵士(Soldier)
金属術 ― 刻まれた勇者は、あなたがアーティファクトを3つ以上コントロールしているかぎり、プロテクション(すべての色)を持つ。
2/2
《エーテリウムの達人》と枠を争う3マナ域です。
フェアデッキにおいてこのカードを対処することは非常に難しく、《頭蓋囲い》や《電結の荒廃者》と組み合わせると安心してオールインが可能です。
ブロッカーとしてももちろん優秀で、攻守の隙を埋めて一気に逆転にもっていくことが可能です。
反面、無色のクリーチャーには無力で、エルドラージやミラーにはただの《スケイズ・ゾンビ》と化します。メタゲームによって《エーテリウムの達人》と合わせてどのようにメインに採用するか構築段階でよく検討しましょう。
TIPS
・金属術が達成できなくなるとプロテクションも失います。《荒廃者》でオールインする際には気をつけましょう。
・生贄や全体除去には耐性がありません。黒相手で単騎の場合は常にミシュラランドをクリーチャー化するマナを残しましょう。
・しばしば無色のクリーチャーに止められることがあります。5色人間やバントスピリットなど《霊気の薬瓶》デッキ相手に大活躍しますが《幻影の像》に止められる可能性を常に意識しましょう。
・プロテクションはダメージの軽減を行うため《頭蓋割り》などで対処されます。バーン相手にも活躍するカードですが、信頼しすぎないようにしましょう。
⑵脇を固めるカード群
強力な主役となり得るカードを紹介しましたが、それだけでは十全な活躍は望めません。
主役を輝かせる名脇役があってこそ力を発揮するのです。
盤面にするパーマネントの数がそのまま親和の力となる以上、素早く展開し戦線を作り出す軽量カードは力が弱くともなくてはならない存在です。

Ornithopter / 羽ばたき飛行機械 (0)
アーティファクト クリーチャー — 飛行機械(Thopter)
飛行
0/2
《電結の荒廃者》が親和の結節点とすれば《羽ばたき飛行機械》は潤滑油です。
《電結の荒廃者》のカウンターの載せ先、《頭蓋囲い》の装備先、金属術の達成など活動は多岐に渡ります。
守勢に回った際もダメージレース時のチャンプブロック役としても優秀です。
地味なカードですが、欠かすことのできない名脇役です。
TIPS
・サイドアウトする際の0マナ域は《メムナイト》になることが多いですが、コントロールやコンボなど地上のブロッカーが少ないデッキ相手ではパワーのない《羽ばたき飛行機械》が抜けていきます。
・《信号の邪魔者》も同様ですがパワーが0のため《罠の橋》を乗り越えることができます。攻撃指定後に《荒廃者》や《頭蓋囲い》を装備してダメージを通すことが可能です。

Memnite / メムナイト (0)
アーティファクト クリーチャー — 構築物(Construct)
1/1
追加の《羽ばたき飛行機械》とも呼べる潤滑油カードです。単体のカードパワーはかなり低いので、多くは採用したくはありません。
サイドアウトされることも多いカードですが、パワーがあるということは非常に大事でコントロールやコンボデッキなどには《羽ばたき飛行機械》よりも優先されます。
TIPS
・《オパールのモックス》の金属術を達成するために0マナ域は5-8枚程度確保するのがベターです。マナがかからない以上カードパワーが低いカードが多いですが、抜きすぎるとデッキが回らなくなりますので注意しましょう。

Welding Jar / 溶接の壺 (0)
アーティファクト
溶接の壺を生け贄に捧げる:アーティファクト1つを対象とし、それを再生する。
潤滑油その3です。脆弱な《鋼の監視者》や《電結の荒廃者》を守り、そうでなくても置いておくだけでもプレッシャーを与え盤面構築を有利に運ぶことができます。反面、追放除去やバウンスには無力で、相手を選ぶカードと言えます。
TIPS
・《臭い草のインプ》とタフネス1のクリーチャーで戦闘が行われた場合、ダメージとバジリスク能力の両方に対して再生能力が必要になります。
・再生をする際にはタップされてしまうので、マナアーティファクトなどは破壊効果の解決前にマナを生み出すか、考えましょう。

Vault Skirge / 大霊堂のスカージ (1)(黒/Φ)
アーティファクト クリーチャー — インプ(Imp)
((黒/Φ)は(黒)でも2点のライフでも支払うことができる。)
飛行
絆魂(このクリーチャーがダメージを与える場合、さらにあなたは同じ点数のライフを得る。)
1/1
絆魂つきの飛行クリーチャーです。
前述のように《電結の荒廃者》や《頭蓋囲い》と組み合わせるとあっというまにダメージレースをひっくりかえすことが出来、フェアデッキ、特に赤単に対してはこのカードをどう生き残らせるかが勝敗の分かれ目です。
あえて《鋼の監視者》や《電結の荒廃者》を避雷針として除去を誘い、《スカージ》で逆転するようなゲームプランを取る必要もあるでしょう。
TIPS
・1マナでプレイすることが多いカードですが、ファイレクシアマナは黒マナで払うことができます。不要なペイライフをしないよう気をつけましょう。
・同様に実際は2マナのカードのため《虚空の杯》、《仕組まれた爆薬》、《爆発域》などのカードでは巻き込まれるラインが異なります。
・色付きのアーティファクトのため、ミラーで《刻まれた勇者》を止めることができません。また《全ては塵》に巻き込まれてしまいます。

Signal Pest / 信号の邪魔者 (1)
アーティファクト クリーチャー — 邪魔者(Pest)
喊声(このクリーチャーが攻撃するたび、他の各攻撃クリーチャーはターン終了時まで+1/+0の修整を受ける。)
信号の邪魔者は飛行か到達を持つクリーチャーによってしかブロックされない。
0/1
《大霊堂のスカージ》と並ぶ、代表的な1マナ域です。
親和はよく、点と面で攻めることのできるビートダウンデッキと呼ばれます。
《鋼の監視者》と共に面で攻めるプランを支えます。同時に回避能力をもっているため、《電結の荒廃者》や《頭蓋囲い》との相性も非常に良いです。
《羽ばたき飛行機械》と並ぶ潤滑油的なカードであるため、単体でのカードパワーは低いです。シチュエーションも選ぶため、サイドボーディングの際にはそのマッチアップで本当に必要なカードなのかを注意深く検討する必要があります。
TIPS
・飛行をもっているのではなく、飛行か到達を持つクリーチャーにしかブロックされません。
・《信号の邪魔者》が2枚攻撃している場合、それぞれのパワーは1になります。

Galvanic Blast / 感電破 (赤)
インスタント
クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。感電破はそれに2点のダメージを与える。
金属術 ― あなたがアーティファクトを3つ以上コントロールしているかぎり、代わりに感電破はそのパーマネントかプレイヤーに4点のダメージを与える。
ほぼ1マナ4点の《稲妻》です。書いてあることはただただ強力であり、クリーチャーの除去や本体への詰めとして場所を選ばず活躍します。
劣勢に立ったとしても、常にトップデッキする可能性にかけてライフを詰めていくと報われることもしばしば。
ただ、他のカードとのシナジーはなく単体で完結するカードであり、複数引きすぎると本来のゲームプランが取れないことも多いため、4枚も必要かどうかは構築時のメタゲームをよく見つめて決定しましょう。
TIPS
・金属術が達成されていない場合は2点になります。レスポンスで除去を撃たれないか注意しましょう。

Experimental Frenzy / 実験の狂乱 (3)(赤)
エンチャント
あなたはいつでもあなたのライブラリーの一番上のカードを見てもよい。
あなたはあなたのライブラリーの一番上のカードをプレイしてもよい。
あなたはあなたの手札からカードをプレイすることはできない。
(3)(赤):実験の狂乱を破壊する。
2018年、親和に新たなブレイクスルーをもたらしたカードです。
これまで不足していたアドバンテージを一気に獲得するカードで、《バネ葉の太鼓》、《刻まれた勇者》に続く革命と言えるでしょう。
デッキの構造上、土地が少なく軽いカードが多いため非常に相性がよく、次々にカードをプレイすることができます。
フェアなミッドレンジやコントロールデッキには劇的に効くカードで、これ1枚が原因でゲームが決まることも。反面、隙も大きく速度には貢献しないためメインへの投入はメタゲーム次第となります。
4マナ域には近い立ち位置のカードがいくつか存在し、《神秘の炉》や《ウルザの後継、カーン》、《アンティキティー戦争》、《ボーラスの工作員、テゼレット》などがあります。
⑶マナベース
親和のマナベースは土地とマナアーティファクトで構成されています。概ね合計で24から26枚であり、実はマナソースが豊富なデッキです。5色供給できることから柔軟なサイドボードを構築することが可能です。

Mox Opal / オパールのモックス (0)
伝説のアーティファクト
金属術 ― (T):好きな色1色のマナ1点を加える。この能力は、あなたがアーティファクトを3つ以上コントロールしているときにのみ起動できる。
親和のブン回りを支えるカードです。ほぼ元祖モックスと同じように使うことができ、その加速性能はモダンレベルを超えています。
あらゆる色マナを供給できることも非常に大事で、《頭蓋囲い》の装備移し替えも可能です。
注意点としては金属術を達成していないとマナが出ないため、同じターンでプレイする場合、できるだけ3枚目のアーティファクトとしてプレイしましょう。またターンを返す場合は割られたり、金属術の達成が崩れる場合があるので優先的に使用しましょう。
また不用意に手札に抱えていると、ハンデスで落とされ機能不全となる場合があります。虚空の杯にも影響を受けやすいため、ジャンドやエルドラージなどには金属術がそのターン達成されないとしても即座にプレイしましょう。
TIPS
・伝説のため場には1枚しか存在しませんが、使用していない方を残すことで《水蓮の花びら》のように使うこともできます。《電結の荒廃者》などでうまくロスを少なくして活用しましょう。

Springleaf Drum / バネ葉の太鼓 (1)
アーティファクト
(T),あなたがコントロールするアンタップ状態のクリーチャーを1体タップする:好きな色1色のマナ1点を加える。
色マナ供給源その2です。0マナクリーチャーとの組み合わせで1ターン目からマナ加速としての運用も可能です。
マナは大きくかかりますが、クリーチャーがいなくともミシュラランドを通してマナフィルターとして使うこともできます。この場合は召喚酔いは関係ありません。
クリーチャーを出してからプレイすると対応で除去される可能性があるので、基本的に先に《バネ葉の太鼓》をプレイしてからクリーチャーを出していきましょう。
TIPS
・場にクリーチャーがいなくても、各種ミシュラランドをクリーチャー化することで色マナを供給することができます。特に《頭蓋囲い》の黒黒を捻出する際には非常に役に立ちます。

Inkmoth Nexus / 墨蛾の生息地
土地
(T):(◇)を加える。
(1):ターン終了時まで、墨蛾の生息地は飛行と感染を持つ1/1のちらつき蛾(Blinkmoth)アーティファクト・クリーチャーになる。それは土地でもある。(それは、クリーチャーに-1/-1カウンターの形でダメージを与え、プレイヤーに毒(poison)カウンターの形でダメージを与える。)
2種類投入されるミシュラランドの片割れです。
通常のダメージよりも倍の効率を持つ毒ダメージは隙を見せた相手を許しません。
1点1点の重みがかなりのプレッシャーとなるので、攻撃できるタイミングがあれば通常ダメージがメインのプランであっても積極的に狙っていきましょう。思わぬトップデッキやチャンスをものにすることが出来ます。
ブロッカーとしても非常に優秀で、相手クリーチャーのサイズをひとつ下げることでダメージレースに大きな差を生むこともあります。
TIPS
・2-3ターンキルを狙うための要のカードです。相手にする場合には盤面のアーティファクトの個数を常に気にしましょう。
・クリーチャータイプはちらつき蛾であるため、《ちらつき蛾の生息地》でパワーアップさせることが出来ます。

Blinkmoth Nexus / ちらつき蛾の生息地
土地
(T):(◇)を加える。
(1):ターン終了時まで、ちらつき蛾の生息地は飛行を持つ1/1のちらつき蛾(Blinkmoth)アーティファクト・クリーチャーになる。それは土地でもある。
(1),(T):ちらつき蛾クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+1/+1の修整を受ける。
ミシュラランドのもう一方です。
こちらは通常ダメージである代わりに、ちらつき蛾クリーチャーをパンプアップする能力をもっています。
回避能力持ちのクリーチャー兼土地であり、マナフラッドの受け皿としても優秀な存在です。デッキすべてを余すところなく使う親和デッキを体現したカードとも言えるでしょう。
なお、パンプアップ能力はクリーチャー化している場合は召喚酔いに影響されるため、ブロック時には注意しましょう。
TIPS
・ミシュラランドはトロンの使う《忘却石》では流れません。トロン相手には《電結の荒廃者》のカウンターが載せられるようマナを必ず浮かしておきましょう。
・ブロック時には都合3マナで2/2の飛行クリーチャーとなります。迂闊に攻撃してきた《帆凧の掠め取り》やスピリットトークンなどを忘れずに止めましょう。

Darksteel Citadel / ダークスティールの城塞
アーティファクト 土地
破壊不能
(T):(◇)を加える。
唯一モダンで許されているアーティファクト・土地です。
他の禁止されている土地と同様に様々なシナジーを形成するため、存在そのものが強力です。
《電結の荒廃者》の餌、《頭蓋囲い》や《エーテリウムの達人》のカウント、各種金属術の達成などなくてはならない存在です。
TIPS
・破壊不能を生かして《アーティファクトの魂込め》と運用するとお手軽なフィニッシャーが誕生します。
・《石のような静寂》や《カーン》の下ではマナが出せません。サイドボード後は土地をセットする順番に注意しましょう。

Spire of Industry / 産業の塔
土地
(T):(◇)を加える。
(T),1点のライフを支払う:好きな色1色のマナ1点を加える。この能力は、あなたがアーティファクトをコントロールしているときにのみ起動できる。
ライフの支払いは必要ですが、安定して色マナの供給ができるカードです。
《空僻地》とどちらが優先されるかは判断の分かれるところですが、環境に直接的なアグロなデッキが多くいるかどうか、サイドボードに《思考囲い》/《強迫》などの1ターン目にキャストしたい手札破壊があるかどうかなどが基準になります。
TIPS
・マナが余っている場合、《大霊堂のスカージ》をプレイするときは《産業の塔》から黒マナを支払った方が1点ライフを得します。

Glimmervoid / 空僻地
土地
終了ステップの開始時に、あなたがアーティファクトをコントロールしていない場合、空僻地を生け贄に捧げる。
(T):好きな色1色のマナ1点を加える。
《スランの採掘場》のアーティファクト版です。ライフロスなくすべての色マナが供給されるのは強力です。《ダークスティールの城塞》と組み合わさればデメリットは完全になくなります。ただし、そうでない場合《粉砕の嵐》などで一緒に巻き込まれてしまいます。また1ターン目にクリーチャーしかプレイできず除去されて一緒にセルフランデス、などもままある光景です。現状では全体的にリスクの高いカードと言えるでしょう。
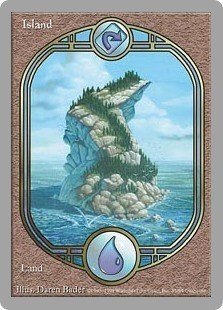


Basic Land / 基本地形
現在のモダン環境では《流刑への道》、《暗殺者の戦利品》、《廃墟の地》など対戦相手に基本地形を与えるカードが多く活躍しています。
どのカードも親和に通用するカードであり、非常にサーチをする機会が多いです。
環境そういったカードが少ない場合は基本地形を0-1枚、多い場合には2枚程度取ることで色マナの事故軽減や4マナ域へのアクセスの手助けとなります。
メインボードに青いカードが採用されることが多いため、メインボードには《島》か《山》、あるいは両方を採用することが多いです。
先日兄が使った構成のようにメイン/サイドどちらにも青いカードがない場合は、《沼》を採用することで《頭蓋囲い》のインスタント装備や《大霊堂のスカージ》の助けとすることもできます。
⑷その他メインボードに採用されうるカード
過去に採用されていたり、時折見かけるカード群です。いま主流でなくとも、未来では再び脚光を浴びる可能性があります。温故知新ということで、どういうカードが使われていたかを知っておくのもよいでしょう。

Ensoul Artifact / アーティファクトの魂込め (1)(青)
エンチャント — オーラ(Aura)
エンチャント(アーティファクト)
エンチャントされているアーティファクトは、他のタイプに加えて基本のパワーとタフネスが5/5のクリーチャーである。
より前のめりな戦略を取る際に候補に上がるカードです。《大霊堂のスカージ》につければ5/5飛行絆魂と《ライラ》相当のクリーチャーが2ターン目から攻撃しはじめます。
《ダークスティールの城塞》につければ無敵のファッティに。《墨蛾の生息地》も一時的にですが5/5となり、毒の詰めに大きくカウントをのばせます。

Glint-Nest Crane / 光り物集めの鶴 (1)(青)
クリーチャー — 鳥(Bird)
飛行
光り物集めの鶴が戦場に出たとき、あなたのライブラリーの一番上からカードを4枚見る。あなたはその中からアーティファクト・カード1枚を公開してあなたの手札に加えてもよい。残りをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。
1/3
《魂込め》とは逆にアドバンテージを得られるカードです。自分で《頭蓋囲い》を見つけて装備する様は非常に賢い鳥なのだと感心させられます。その場で飛行クリーチャーが残るのは全体的な戦略とも合致しており、コントロールやミッドレンジが幅を効かせる環境では一考の余地があるでしょう。

Shrapnel Blast / 爆片破 (1)(赤)
インスタント
この呪文を唱えるための追加コストとして、アーティファクト1つを生け贄に捧げる。
クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。爆片破はそれに5点のダメージを与える。
《アーティファクトの魂込め》と同様により前のめりな戦略をとる場合の候補です。《感電破》と1点の差ですが5点のインパクトはすばらしく、4枚撃てば相手は死にます。
過去にはバーン戦略に振り切った「ハサミタルモ親和バーン」なるデッキがGPで活躍した歴史もあります。再びこの戦略が日の目を見ることもあるでしょう。

Tarmogoyf / タルモゴイフ (1)(緑)
クリーチャー — ルアゴイフ(Lhurgoyf)
タルモゴイフのパワーは、すべての墓地にあるカードのカード・タイプの数に等しく、タフネスはその点数に1を加えた点数に等しい。
*/1+*
前述の「ハサミタルモ親和バーン」だけでなくモダン初期の親和では採用が珍しくないカードでした。相手に出されると分かりますが、非常に簡単に《タルモゴイフ》が5/6程度まで成長します。《石のような静寂》や《新カーン》に影響されないカードとして期待が高まります。

Thoughtcast / 物読み (4)(青)
ソーサリー
親和(アーティファクト)(この呪文を唱えるためのコストは、あなたがコントロールするアーティファクト1つにつき(1)少なくなる。)
カードを2枚引く。
以前はよく見かけたカードですが、環境の高速化に伴い締め出された格好となったカードです。
実質1マナの《霊感》が弱いわけがないのですが、青マナの供給が不安定かつマナを使っても盤面に影響がないことでテンポがあまりよくないことが原因です。
《光り物集めの鶴》の方がそのままクリーチャーが残ること4枚のカードを掘れることで役割を譲った形となりました。とはいえ強力なカードには変わりはありませんのでまた日の目を見る日もあるかもしれません。
3.個々のカードについて サイドボード編
親和は無色デッキでありながら5色デッキでもあります。サイドボードの選択肢は実質無限ではありますが、よく使われるカードはある程度限られています。メタゲームに合わせて取捨選択をしましょう。

Thoughtseize / 思考囲い (黒)
ソーサリー
プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは手札を公開する。あなたはその中から土地でないカードを1枚選ぶ。そのプレイヤーはそのカードを捨てる。あなたは2点のライフを失う。
対コンボ・対コントロールのオールマイティなハンデスです。テンポロスを最小限にしつつ、相手のスピードダウンに貢献します。コンボ相手には序盤1-2ターン目に、《石のような静寂》がない状態のコントロールであれば中盤3-4ターン目に打つことで全体除去を抜いてプランを崩したり、前方確認をしてのオールインを行うことができます。さらに追加のハンデスを取る場合にはライフロスが痛いため《強迫》が良いでしょう。

Dispatch / 急送 (白)
インスタント
クリーチャー1体を対象とし、それをタップする。
金属術 ― あなたが3つ以上のアーティファクトをコントロールしている場合、そのクリーチャーを追放する。
親和用の《剣を鍬に》です。デメリットなしでの追放除去は破格で、《ワームとぐろエンジン》や《ホガーク》を後腐れなく除去することができます。対クリーチャーデッキへの追加の除去として、またフィニッシャー枠のカードである《ライラ》や《ワームとぐろエンジン》、《グリセルブランド》、《原始のタイタン》などに対処するために投入します。

Rest in Peace / 安らかなる眠り (1)(白)
エンチャント
安らかなる眠りが戦場に出たとき、すべての墓地にあるすべてのカードを追放する。
カードかトークンがいずれかの領域からいずれかの墓地に置かれる場合、代わりにそれを追放する。
定番の墓地対策です。先出し・後出しどちらでも問題なく、エンチャントであるがためやや割られにくいのが親和にとってはメリットです。アーティファクトに偏ったデッキであるため、アーティファクトでないことはサイドボード後はメリットになりうるのです。
墓地活用デッキ全般に有効ですが、自身の《電結の荒廃者》の接合が誘発しなくなることに注意をしましょう。

Leyline of the Void / 虚空の力線 (2)(黒)(黒)
エンチャント
虚空の力線があなたのゲーム開始時の手札にある場合、あなたはそれが戦場に出ている状態でゲームを始めてもよい。
いずれかの領域から対戦相手の墓地にカードが置かれる場合、代わりにそれを追放する。
基本的には《安らかなる眠り》がベターですが、”ホガークの夏”など明らかに環境速度が間に合っていない場合にはこちらの採用も検討されます。後出しは不可能ですがその分マナもかからずテンポがよく、相手だけが影響をうけるので《電結の荒廃者》を問題なく運用可能です。《搭載歩行機械》を擁する鱗親和相手には相手だけ機能不全を強いることができるので非常に役に立ちます。

Grafdigger's Cage / 墓掘りの檻 (1)
アーティファクト
墓地やライブラリーにあるクリーチャー・カードは戦場に出ることができない。
プレイヤーは墓地やライブラリーから呪文を唱えられない。
軽量でお手軽な定番墓地対策です。ほとんどの場合手札にあれば1ターン目に設置が可能で、いざとなれば《電結の荒廃者》で食べることが可能なうえ自身への影響もありません。非常に扱いやすいカードです。反面、割られると相手の復帰は容易く、一気に逆転されてしまうことも。
サーチ系コンボにも有効で、特にネオフォームはこれ一枚でピタッと止まります。

Tormod's Crypt / トーモッドの墓所 (0)
アーティファクト
(T),トーモッドの墓所を生け贄に捧げる:プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーの墓地のカードをすべて追放する。
さらに軽量な墓地対策です。効果は限定的ですが序盤のアーティファクトカウントとして投入できるためデッキを阻害しません。ドレッジなどには力不足ですが、リアニメイトなどにはこれで十分でしょう。

Surgical Extraction / 外科的摘出 (黒/Φ)
インスタント
((黒/Φ)は(黒)でも2点のライフでも支払うことができる。)
いずれかの墓地にある基本土地カードでないカード1枚を対象として選ぶ。それのオーナーの墓地と手札とライブラリーから、そのカードと同じ名前を持つカードを望む枚数だけ探し、それらを追放する。その後、そのプレイヤーは自分のライブラリーを切り直す。
利用が特定のキーカードに頼られている環境であれば採用する価値があります。
ただ基本的には効果が限定的な割にデッキから浮いているカードのため、そこまで優先度は高くありません。イゼットフェニックス隆盛時にも、ダメージレースで遅れをとるわけにいかないため採用されることはあまりありませんでした。

Spell Pierce / 呪文貫き (青)
インスタント
クリーチャーでない呪文1つを対象とする。そのコントローラーが(2)を支払わないかぎり、それを打ち消す。
テンポを取りやすい軽量カウンターです。コントロールやコンボのビッグアクションや除去を弾くのに便利なカードで、うまく刺さるとゲームが決まります。反面シチュエーションを選び、青マナを立てる必要があることから振れ幅の大きいカードでもあります。
全体除去対策だとしても《至高の評決》や《終末》にはなかなか刺さらないので、どのスペルに対して撃つカードなのかを吟味して投入しましょう。
真価を発揮するのは対バーンや対感染で、一手差で決まるタイトなダメージレースを一気に突き崩します。

Stubborn Denial / 頑固な否認 (青)
インスタント
クリーチャーでない呪文1つを対象とする。それのコントローラーが(1)を支払わないかぎり、それを打ち消す。
獰猛 ― あなたがパワーが4以上のクリーチャーをコントロールしているなら、代わりにその呪文を打ち消す。
《呪文貫き》と似て非なる役割の軽量カウンターです。
《風景の変容》をカウンターで対処することのできる唯一の方法です。
確定カウンターとして運用するためにはデッキの構造をファッティよりにする必要がありますので、メインボードとちぐはぐにならないように注意しましょう。

Etched Champion / 刻まれた勇者 (3)
アーティファクト クリーチャー — 兵士(Soldier)
金属術 ― 刻まれた勇者は、あなたがアーティファクトを3つ以上コントロールしているかぎり、プロテクション(すべての色)を持つ。
2/2
メインボードの採用も多いですが、サイドボードに落ちることも多いカードです。
トロンやエルドラージ、高速コンボが多い場合はメインから外してサイドボードに多く取りましょう。効果的なデッキは多く、劇的であるためサイドカードであっても4枚枠をとる価値はあります。
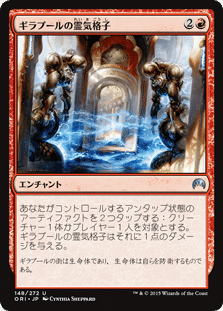
Ghirapur AEther Grid / ギラプールの霊気格子 (2)(赤)
エンチャント
あなたがコントロールするアンタップ状態のアーティファクトを2つタップする:クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。ギラプールの霊気格子はそれに1点のダメージを与える。
アーティファクトがティムと化すエンチャントです。
ミラーや感染など小粒なクリーチャーが多いマッチではゲームを決める性能があります。
また、《石のような静寂》下でアーティファクトを活用できる数少ない方法で、白系コントロール相手にも非常に有効です。

摩耗 (1)(赤)
インスタント
アーティファクト1つを対象とし、それを破壊する。
融合(あなたはこのカードの片方の半分または両方の半分をあなたの手札から唱えてもよい。)
損耗 (白)
インスタント
エンチャント1つを対象とし、それを破壊する。
融合(あなたはこのカードの片方の半分または両方の半分をあなたの手札から唱えてもよい。)
エンチャントとアーティファクトの両方に対処できるユーティリティカードです。
何にでも対処ができることでサイドのスペースが節約できますが、中途半端なカードでもあるためスタンスが決まっていれば別のカードを優先した方がよいでしょう。

Ancient Grudge / 古えの遺恨 (1)(赤)
インスタント
アーティファクト1つを対象とし、それを破壊する。
フラッシュバック(緑)(あなたはあなたの墓地にあるこのカードを、そのフラッシュバック・コストで唱えてもよい。その後それを追放する。)
対アーティファクト専門カードです。ミラーやトロン、鱗親和、ウルザ、青単プリズン、ランタンなどアーティファクトを活用するデッキ相手には必ず欲しい1枚です。
1対2を分割かつインスタントタイミングで取れるカードは他になく、アーティファクト対策としては最高峰です。

Damping Sphere / 減衰球 (2)
アーティファクト
2点以上のマナを引き出す目的で土地が1つタップされるなら、それは他のタイプや点数の代わりに(◇)を生み出す。
プレイヤーが各呪文を唱えるためのコストはそれぞれ、そのプレイヤーがこのターンに唱えた他の呪文1つにつき(1)多くなる。
トロンや各種フェニックス、ストーム・感染・ネオフォームなどに有効なマルチアンチアーティファクトです。単体でアドバンテージを稼ぐことができませんが、シチュエーション次第では劇的な効果を発揮します。反面自身が影響を受けやすいことや、後半に引いてもあまり価値がないことに注意しましょう。

Torpor Orb / 倦怠の宝珠 (2)
アーティファクト
戦場に出るクリーチャーは能力を誘発させない。
クリーチャーのCIP能力を封じる効果のあるアーティファクトです。5色人間は完全に機能不全となる他、ソプターコンボも止めることが可能です。アミュレットタイタンにも有効で、1ターン遅れさせることができる他、サイド後のガンとなる《女王スズメバチ》を大幅に弱体化することができます。またローグデッキではありますが、エルフやサヒーリなどCIP能力を活用したデッキは一定数存在するので、5色人間が流行った場合には採用の価値があるでしょう。

Spellskite / 呪文滑り (2)
アーティファクト クリーチャー — ホラー(Horror)
(青/Φ):呪文1つか能力1つを対象とし、それの対象を呪文滑りに変更する。((青/Φ)は(青)でも2点のライフでも支払うことができる。)
0/4
避雷針となるクリーチャーです。《欠片の双子》デッキが活躍していた時代ではメインボードに採用されていたほどのカードで、単なるアンチカードではなく非常に器用なカードでもあります。現代の双子、サヒーリデッキを咎める他にも、《電結の荒廃者》を滑らせることでミラーマッチや鱗親和を機能不全に陥れたり、感染デッキのパンプを奪って毒カウンターを稼がせないといったこともできます。また、《歩行バリスタ》に対しての数少ない有効な対処法の一つです。ジャンドの《コラガンの命令》をひとまとめにしてアドバンテージの喪失を防いだり、《ヴァラクート》のダメージを1点ずつ軽減したりすることもできます。何より普通に活用して安全にオールインすることができるのです。

Pithing Needle / 真髄の針 (1)
アーティファクト
真髄の針が戦場に出るに際し、カード名を1つ選ぶ。
選ばれた名前の発生源の起動型能力は、それらがマナ能力でないかぎり起動できない。
非常に効果範囲の広いユーティリティカードです。
指定のためには環境のデッキを把握する必要がありますが、特定のデッキには効果は抜群です。
概ねコンボ相手に投入することが多く《グリセルブランド》や《献身のドルイド》、《飛行機械の鋳造所》などを指定するだけで機能不全にすることができます。
また直接対処が難しいプレインズウォーカーや、デッキのガンとなる《歩行バリスタ》や《忘却石》への有効な回答となります。ハンデスからの先置き指定が出来ればベストでしょう。
《墨蛾の生息地》プランを見据えている場合には、《廃墟の地》や《幽霊街》を指定していきましょう。

Mystic Forge / 神秘の炉 (4)
アーティファクト
あなたはいつでもあなたのライブラリーの一番上のカードを見てもよい。
あなたのライブラリーの一番上のカードがアーティファクト・カードか、無色であり土地でないカードであるなら、あなたはそれを唱えてもよい。
(T),1点のライフを支払う:あなたのライブラリーの一番上のカードを追放する。
サイドボードの部分で記載していますが《実験の狂乱》と同じ枠のカードです。
ほとんど同じことができますが、大きな違いは手札からのプレイが可能であること、またアーティファクトかエンチャントかということです。
手札のカードがプレイできることで設置する際のジレンマが起きず有効活用できる点や、色マナが構えやすい点、アーティファクトとしてカウントされる点は非常にデッキにあっており大きなメリットです。
反面、スペルと土地がプレイできないことや、《コラガンの命令》や《古の遺恨》で割られてしまうのはマイナスです。特に《実験の狂乱》が活躍する対ジャンドに対しては致命的な欠点のため、赤いデッキが多いときは採用を慎重にしましょう。ジャンドではなくBGが主流の場合にはその差がほとんどなくなりますので、検討の余地が生まれます。
唱えることができるのは「アーティファクトおよび無色のカード」であるため、色付きのアーティファクトであるところの 《大霊堂のスカージ》、《エーテリウムの達人》は問題なくプレイすることが可能です。「唱える」ですので、《ダークスティールの城塞》をプレイすることはできないのでご注意を。《実験の狂乱》とどちらを採用するかは、環境に左右されますので都度よく吟味しましょう。

Blood Moon / 血染めの月 (2)(赤)
エンチャント
基本でない土地は山(Mountain)である。
アミュレットタイタンやヴァラクートなど、土地コンボに有効なカードです。
またボーグルデッキなど土地の枚数を絞った多色のオールインデッキにも活躍します。
以前はジェスカイコントロールなどの多色コントロールにも有効だったのですが、廃墟の地の流行で基本地形の採用枚数が増え、マナベースへの攻撃はあまり効果的ではなくなりました。
また一見トロンに有効にみえますが、《忘却石》に強いこちらのミシュラランドも使用できなくなるデメリットの方が大きいので、トロン対策をしたい場合は《高山の月》や《減衰球》を使いましょう。

Whipflare / 鞭打ち炎 (1)(赤)
ソーサリー
鞭打ち炎は、アーティファクトでない各クリーチャーに2点のダメージを与える。
実質相手だけに《紅蓮地獄》です。感染やドルイドコンボに有効で、赤単や人間にも活躍が見込めます。
対ドレッジ相手にも《ナルコメーバ》や《臭い草のインプ》で戦線が膠着しやすいため、突破手段として《刻まれた勇者》とともに必要なカードとなります。

Dismember / 四肢切断 (1)(黒/Φ)(黒/Φ)
インスタント
((黒/Φ)は(黒)でも2点のライフでも支払うことができる。)
クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで-5/-5の修整を受ける。
《急送》と同じく追加のクリーチャー除去です。《急送》の方が効果は強力なのですが、こちらのメリットは無色マナでプレイできること。《溜め込み屋のアウフ》を除去したり、《石のような静寂》下で《黎明をもたらすもの、ライラ》を処理することのできる数少ないカードです。
《大霊堂のスカージ》同様、黒マナを支払うことが出来るシーンは多いので注意しましょう。
4.ゲームプランの組み立て方
一気にカードの紹介を行いましたがいかがでしたでしょうか。
正直、これだけ多くのカードの役割をすぐに把握することは難しいと思います。
まずは何度もプレイをして、少しずつカード同士の相互作用を体験していくのが近道だと思います。
ただ、漫然とプレイを繰り返してもあまり効率はよくありません。
親和は基本的に序盤にオールインが可能な高速ビートダウンですが、その中でもゲーム毎に少しずつ違うルートが存在します。
まずはそれぞれのプランがどのような特徴を持っているかを把握しましょう。
⑴毒殺プラン

一番はじめに紹介するプランは毒殺です。ポピュラーなライフを攻めるビートダウン戦術を最初にもってこないのは、このプランが最も速く、プレイヤー同士の経験値の差が非常に出やすいからです。トーナメントは常に強いプレイヤーと対戦するわけではなく、すべてのマッチで100%のプレイが行われることもありえません。トーナメント全体での勝利を目指してまずはラッキーウィンを確実に拾えるようにしましょう。
《墨蛾の生息地》がからむ毒殺ルートそのものは最速2ターンキルであり、3ターンキルへのルートも非常に多いです。
特にコンボ相手にはハンデスからの毒殺ルートが理想で、可能であれば積極的に狙っていきたいですね。
また、前述の通り対戦相手には意識されづらく、対親和に習熟していないとケアしきることができないルートなのでタップアウトされた瞬間がチャンスです。
相手に悟られないように気配を殺して、さもまだ数ターン残り時間があるように振る舞うのが大切です。決してアーティファクトの枚数を相手にわかる形で数えてはいけません。また長考もしないようにしましょう。初手のキープの時点でカウントをしておけば改めて数える必要はないはずです。《電結の荒廃者》は実質速攻のついた《頭蓋囲い》です。
《墨蛾の生息地》の起動と合わせても4マナで達成できます。
何度でもいいますが決して悟られてはいけません。タップアウトを誘うために《鋼の監視者》や《エーテリウムの達人》などの大物はどんどん差し出しましょう。
また、狙うハードルを少しでも低くするためにコツコツと《墨蛾の生息地》で攻撃することが大事です。もちろん、十分な数のアーティファクトがあるのであればあえて毒では攻撃せずに意識をずらすのも大切です。
もちろん対親和に慣れたプレイヤーには通用しませんが、そうでない相手も多いのです。勝てる時に勝つことは、負けた原因を探すことよりも重要なことだとボクは考えています。
⑵一点突破プラン

毒殺以外の通常ダメージのルートでは、点もしくは面でのアプローチとなります。
まずは分かりやすい点でのアプローチです。
主に《頭蓋囲い》が活躍するルートで、飛行クリーチャーや《刻まれた勇者》に装備して大ダメージを狙います。速ければ3ターン、除去などを受けつつも4-5ターン程度で殴りきるのを狙うルートです。
《頭蓋囲い》は、黒黒を支払うとインスタントタイミングで装備先を変えられることを常に意識しましょう。
このルートでは《刻まれた勇者》の安心感が光ります。《頭蓋囲い》だけでなく《電結の荒廃者》でのオールインもあるため、攻撃1回分のダメージだけでなく2-3ターンでの合計ダメージを計算することが大事です。
《稲妻》などのダメージ除去を主に使うプレイヤー相手に《電結の荒廃者》を使う場合、《刻まれた勇者》でなくとも隙さえあれば《大霊堂のスカージ》などに接合して大型飛行クリーチャーを作ることも有効です。
攻撃が通るのであれば接合しないまま不要なアーティファクトをどんどん食べ、《荒廃者》のサイズをあげてライフを詰めていくのもよいでしょう。
《感電破》をトップデッキしていくのを期待して動いていくのです。
ただし、パワーがなくともクリーチャーの数は減らしすぎないように。丁寧に単体除去を重ねられてせっかく育てた《荒廃者》の接合先がなくなる場合があります。
⑶面プラン

親和の展開力がよく現れたプランです。0〜1マナクリーチャーを一気に展開し《信号の邪魔者》や《鋼の監視者》でバックアップしていきます。
ほとんどのクリーチャーが回避能力持ちで早々に手札を使い切るため、ミシュラランドとともに序盤から攻勢をかけていくこととなり、中盤以降も《鋼の監視者》でどんどん強化されるため長期戦にも耐えられます。
序盤の展開力は圧倒的で、あまり慣れていない人が想像しやすい親和の動きと言えるでしょう。
しかしながら、実はあまり積極的に狙うべきではないプランです。初手の依存度が高いため、このルートを取らざるを得ない場合にはもちろんそうするのですが、面で攻めるという言葉とは裏腹に非常に脆いのです。軽い=カードパワーが低いわけで、底上げを行う《信号の邪魔者》や《鋼の監視者》が除去をされたり機能しなくなると途端に烏合の衆と化します。
お互いに相手が不明なメインボードではいざしらず、除去も増えるであろうサイド後にそういった手札をキープする場合、覚悟が必要です。それはマリガンしなければならないというわけではなく、捌かれても仕方がないという割り切りです。
とはいえ親和というデッキはデッキ全体でシナジーを構築しているため、どんな手札でもドローの受け入れは非常に広いです。
《信号の邪魔者》や《鋼の監視者》が対処されたとしても上からそれらの2枚目や、《頭蓋囲い》、《エーテリウムの達人》を引き込めば良いのですから。
⑷《実験の狂乱》プラン

親和の勝ち筋の中でもっとも時間が遅いのがこのルートです。《実験の狂乱》あるいは《神秘の炉》の圧倒的な物量に頼ったルートです。コントロールやミッドレンジ相手に有効で、ビートダウン相手にも間に合えば機能します。
序盤の攻勢が失敗し、結果的にそうなる場合が多いのですがマリガン後や一部のデッキには積極的に狙っていくことになります。
赤単フェニックスやウルザソプターなど、構造的に不利なデッキに対しては相手を妨害したのちに物量で押す方法を取らざるを得ません。
特にウルザソプターに対しては、飛行機械の鋳造所を対処したあとにも《真冬》や《罠の橋》などのカードに耐えるため、《狂乱》でのリカバリーやアーティファクト破壊を探す必要があるのです。
サイドボード後は対戦相手のアンチカードが増え、序盤に押し切ることがむずかしくリソース面でもシビアになります。そういった状況をひっくり返すことのできる貴重なルートです。
以上、親和の戦術をおおまかに4つのプランに分類してご紹介いたしました。
4つのプランといっても、最初から最後までひとつのプランを辿るのではなく、初期手札からドローを重ねていくうちに刻一刻と変わっていくものです。
忘れてはいけないのは目の前には常にいくつもの選択肢(プラン)が存在することです。
毒やダメージ、短期決戦や長期戦に固執せず、その都度その都度変幻自在にプランを組み替えていくこととなります。
これは非常に難しいことで、ボクも常にミスをしてしまい反省を繰り返しています。
難しいからこそ本当に楽しい部分でもあります。ぜひ一緒に頭をひねっていきましょう。
5.プレイについて
ゲームプランの選択がうまくいっても、個々のプレイで判断ミスをしてしまっては非常にもったいないですよね。
ここでは基本的な部分からボク自身も判断に迷うところまで含めていくつか細かいプレイについてご紹介します。
⑴キープ基準について
まずキープ基準についてはこれまでも多く語られたものであり、プレイヤーごとの見解も千差万別なので、ボク以外にも先駆者の記事も参考されると尚良いでしょう。
基本的に親和のキープ基準、特にメインボードはモダンのデッキの中では比較的ゆるい方に入ります。
デッキの動きとして必要なのは最初に紹介した核となるカードたちであり、それらをプレイすることができれば相手に脅威を突きつけることができるからです。
最低限《頭蓋囲い》、《電結の荒廃者》、《鋼の監視者》のいずれかと、2ターン目までにそれらを着地させることができるマナが揃っていれば問題ありません。これらが1ターン目に出せる手札だったり、2枚以上あったりするとさらに強力です。
他にも《エーテリウムの達人》や《アーティファクトの魂込め》、相手によっては《刻まれた勇者》や《光り物集めの鶴》なども、プレイすることが可能な手札であればキープする基準を満たしているといえるでしょう。
親和のデッキコンセプトは強力です。マナ加速があるに越したことはありませんが、先手のメインボードであれば多少の出遅れはカバーできる強さがあります。マナ加速がなくとも3ターン目にストレートに《頭蓋囲い》を装備してアタックできる手札であれば喜んでキープしましょう。それが出来るのであれば多少マナフラッド気味の手札でも問題ありません。余ったマナはミシュラランドに注ぎ込めば良いだけなのです。装備コストや《実験の狂乱》など実は浮いたマナの使い道には困らないデッキです。
それよりもキープしてはいけないのは、展開はできても「展開するだけで終わってしまう」手札です。
《メムナイト》や《羽ばたき飛行機械》などは、いくらたくさんあってもそれだけでは勝利には貢献しません。1ターン目に手札を使い切ったとして、その盤面は本当に相手にとって脅威でしょうか。《頭蓋囲い》、《鋼の監視者》もなければマナコスト相応の脆弱なクリーチャーです。彼らはデッキの潤滑油です。それらをサポートするカードができれば2枚、マリガン後でも少なくとも1枚はないとゲームプランが立てられないのです。
親和は土地が少なくマリガンしやすい上にドローサポートもアドバンテージ源ほとんどないデッキです。ロンドンマリガンが導入されたといえど、相手のわからない状態で積極的にマリガンを行う価値はありません。シビアにならず、ゆったりとキープをしましょう。
⑵土地の置き方
1ターン目に金属術達成が必要でない限り(オパールのモックスがある場合)基本的にミシュラランドから設置していきます。また早いターンでは通常のダメージよりも毒の価値が高いこと、《ちらつき蛾》のパンプ能力が一種の速攻に近いということもあり《墨蛾》から優先して設置していくのがベターです。もちろんライフを削る算段がついていたり、守勢に回って《ちらつき蛾》で自身をパンプしなければいけない状態であれば例外です。
《産業の塔》など色マナ発生源は必要になってから設置しましょう。色付きカードや《頭蓋囲い》のために黒黒を出す時以外は優先して出す理由がありません。
ただし、サイドボード後やトロン相手に《ダークスティールの城塞》を出すタイミングには注意してください。
《大いなる創造主、カーン》や《石のような静寂》がある状態ではマナが出なくなるため、一手損になる可能性があります。
⑶毒orダメージ
毒で攻めるべきでしょうか、ダメージで攻めるべきでしょうか。
つまり《ちらつき蛾》で攻撃すべきか《墨蛾》で攻撃すべきか。
この問題は常に遭遇し、場面ごとに様々なものを考慮しなければならないため一定の答えを出すことが難しいものです。
個人的な経験上では、マナに余裕があり相手のライフがまだ遠く打点が低い場合は毒も並行して貯めていく方が良いと考えています。
《墨蛾》というカードを相手にとっての脅威に昇格させることでカードの価値をあげ、多角的な攻め方で選択肢を減らすことに繋がるからです。
もちろん相手にとってライフがリソースであったり、単体除去が多い場合にはプランが崩れやすいのでライフを狙う方が良いでしょう。
どちらも裏目がありますが、どちらがより相手にとって対処しづらい結果になるかを考えながらプレイすると正解に近くなると思います。
⑷本命のカード
《頭蓋囲い》、《電結の荒廃者》、《鋼の監視者》。これらのカードは親和の根幹をなしていてそれぞれ非常に強力ですが、同時に非常に脆いカードでもあります。
これらを複数手札にもっている場合どの順番でプレイするのが良いでしょうか。
セオリーであれば起動回数が多くなれば多くなるほど強い《鋼の監視者》ですが、相手に除去をまだ使われていないのであれば《電結の荒廃者》からプレイする方が良い結果をもたらす場合があります。
例えば人間デッキなどは《反射魔道士》や《拘留代理人》などが除去枠として取られています。これらは枚数が少ないため、一度対処された場合は2枚目がある可能性は低いです。
盤面にもよりますが《霊気の薬瓶》がない状態であれば、1ターン遅れたとしても人間デッキ相手では《電結の荒廃者》よりも《鋼の監視者》の方が盤面の構築に貢献するでしょう。避雷針とするわけです。
他にもサイドボード後の白いデッキ相手には、《電結の荒廃者》からプレイすることで《石のような静寂》に合わせて不要なアーティファクトを食べ、被害を最小限に食いとどめることができます。相手が《石のような静寂》目当てにマリガンをしていた場合には勝ち筋が見えるかもしれません。
⑸1ターン目のプレイ
慣れないうちは《オパールのモックス》も0マナアーティファクトもない場合の1マナのカードのプレイに悩むかもしれません。基本的には《バネ葉の太鼓》、《大霊堂のスカージ》、《信号の邪魔者》の順になります。後続の動きに不要だったとしても《バネ葉の太鼓》が最もドローの受けが広いです。0マナクリーチャーを引けばマナ加速となり、クリーチャーを出していたとしてもどちらにしろ《太鼓》でマナソースとして使用するからです。クリーチャーを出してしまうと除去されるリスクがあったり、《太鼓》以外に土地などのマナソースがない場合、ハンデスで落とされて事故に陥ってしまう可能性があります。
⑹《電結の荒廃者》
扱うのが本当に難しいカードです。特にオールインの際には気をつけましょう。
時には思い切りが必要ですが、相手に残っているマナや入っているであろうカードの枚数、見落としているカードがないかを入念に確認してください。本当にオールインする必要があるか、しなかった場合はどうなるのかをよく考えることが大事です。オールインまでいかなくとも、自発的なサイズアップは注意して行いましょう。
タフネス4までいけば《稲妻》1枚で落ちないことは常に意識するべきで、赤いデッキを相手にする場合は《羽ばたき飛行機械》を2/4のすると心強いです。
自身のサイズアップを行う場合にも、相手のライフはあと何回の攻撃で削ることができるのか、またフェッチやショックインの見込みも計算しつつ削っていきましょう。
複雑そうに見える《荒廃者》のダメージ計算ですが実際は見かけ以上にシンプルです。ただの足し算で、《信号の邪魔者》、《鋼の監視者》、2枚目の《電結の荒廃者》、《ちらつき蛾の生息地》、いずれも機能した場合それぞれ+1されるだけです。鱗親和よりはるかに簡単です。冷静にひとつずつ計算していきましょう。
6.アンチカードについて
親和をプレイする上で避けて通れないのが、サイドボードからのアンチカード群です。
単純なアーティファクト破壊の《削剥》や《自然の要求》などから、《古えの遺恨》、《コラガンの命令》などの1対2交換カード、《粉砕の嵐》、《忍び寄る腐食》などの全体除去に《石のような静寂》のような機能不全に追い込むカードなど多岐に渡ります。
特にモダンホライゾン以降は《溜め込み屋のアウフ》、《大いなる創造主、カーン》、《活性の力》などさらに親和を取り囲む環境は厳しさを増しています。
アンチカードの存在で辛うじて《オパールのモックス》の禁止が免れているといっても過言ではない以上、これらをどう乗り越えるかが親和を使う上での大きな課題です。
それぞれのカードについて考えていきましょう。

Stony Silence / 石のような静寂 (1)(白)
エンチャント
アーティファクトの起動型能力は起動できない。
親和アンチカードの代名詞的存在です。白いデッキであればサイドボードに1枚は潜んでいても驚きはしません。出された場合の勝率は恐らく3割程度で、2ターン目に出された場合はそれよりもさらに厳しいでしょう。
ほとんどのカードが機能不全に陥り、《荒廃者》も《監視者》も2マナ1/1のバニラとなります。
先手2ターン目に《頭蓋囲い》を装備している、あるいは《信号の邪魔者》などでの軽量ビートダウンが行える盤面になっていないと勝つことは難しいです。
それだけ劇的なカードであるため、《石のような静寂》1枚に負けたあとは、つい《損耗+摩耗》や《自然のままに》を入れたくなります。
しかし、ちょっとまってください。よほどアーティファクト対策が厳しい時期(アイアンワークス全盛期)などを除けば、モダンのアンチカードは概ね墓地に向かっています。
レガシー以上に多種多様なデッキがしのぎを削るモダン環境では、特定の戦略にのみ刺さるカードは1〜2枚程度しか枠を取られることはありません。
仮に青白コントロールのサイドボードに《石のような静寂》が1〜2枚取られる傾向があったとしても、青白コントロールに遭遇する確率、さらにサイドボードにある確率...さらにゲーム中にプレイされる確率...さらに2ターン目に着地する確率...さらにそれを破壊するカードを持っている確率(例:損耗+摩耗)....さらにそれをプレイできる確率(《静寂》下で色マナを出せるか)...と考えた場合、そのサイドボードカードにどこまでの価値があるかをよく考えましょう。
親和はリソースがシビアなシナジーデッキです。手札のすべて、デッキのすべてを使って勝利を目指します。もし《石のような静寂》がプレイされずに《損耗+摩耗》を抱えてしまったがために1点ダメージが足りなかったら...?
よく考えてサイドボーディングを行いましょう。

Collector Ouphe / 溜め込み屋のアウフ (1)(緑)
クリーチャー — アウフ(Ouphe)
アーティファクトの起動型能力は起動できない。
2/2
ジャンドやBG、5色人間、ドルイドコンボなどからプレイされます。
中でもドルイドコンボはサーチ手段もあるため、プレイされることを見据えて動くことが必要になります。
《石のような静寂》と異なり《感電破》1枚で処理できるため、そこまで致命的ではありません。
とはいえ大幅にテンポを崩される上に、ほぼ必ず除去しなければならないクリーチャーのため厄介です。
基本的には上記のデッキに対しては《急送》などのクリーチャー除去を自動的に増やすことなるため、特殊なサイドボーディングは必要ありません。
色マナが出せなくなると除去ができなくなるため、できる限り色マナを浮かせてプレイを進めましょう。《鞭打ち炎》なども効果的で、ジャンドに対しても《血編み髪のエルフ》や《闇の腹心》も巻き込めるため役に立ちます。

Karn, the Great Creator / 大いなる創造者、カーン (4)
伝説のプレインズウォーカー — カーン(Karn)
対戦相手がコントロールしているアーティファクトの起動型能力は起動できない。
[+1]:クリーチャーでないアーティファクト最大1つを対象とする。あなたの次のターンまで、それはパワーとタフネスがそれぞれそれの点数で見たマナ・コストに等しいアーティファクト・クリーチャーになる。
[-2]:あなたは、ゲームの外部か追放領域にありあなたがオーナーであるアーティファクト・カード1枚を選び、そのカードを公開してあなたの手札に加えてもよい。
5
トロンとエルドラージトロンにナチュラルに搭載されている厄介極まりないカードです。
3ターン目トロンランドを揃えてからの《カーン》、《歩行バリスタ》or《罠の橋》は悪夢と言えるでしょう。サイドボードカードをもってくるのはまだマシで、忠誠値をあげながら《ダークスティールの城塞》をクリーチャー化させられてしまうと《感電破》で落とすことも困難になり、よしんば倒したとしてもかなりの損害を得たあとになります。
出される前になんとか盤面を構築するか、即座に《感電破》で処理するのが良いでしょう。
登場するのは早くて3ターン目、普通であれば4ターン目というのが救いで、ハンデスで落とせればそれに越したことはありません。

Kataki, War's Wage / 戦争の報い、禍汰奇 (1)(白)
伝説のクリーチャー — スピリット(Spirit)
すべてのアーティファクトは「あなたのアップキープの開始時に、あなたが(1)を支払わないかぎりこのアーティファクトを生け贄に捧げる。」を持つ。
2/1
最近は見かけることは減りましたが、親和アンチカードの元祖です。
基本的に採用するデッキはクリーチャーデッキなので《アウフ》とあまり対応は変わりません。
かなり縛られますが盤面を維持しつつも変わらず《頭蓋囲い》などは使えるので、対処が難しければすばやくゲームを終わらせるプランに切り替えましょう。

Dead of Winter / 真冬 (2)(黒)
ソーサリー
ターン終了時まで、すべての氷雪でないクリーチャーは-X/-Xの修整を受ける。Xは、あなたがコントロールしている氷雪パーマネントの総数に等しい。
アンチカードというわけではないですがウルザソプターや氷雪系コントロールから打たれる3マナの《神の怒り》です。
これまで3マナの全体除去は《神々の憤怒》が基本だったため《刻まれた勇者》に全幅の信頼を置くことができたのですが、このカードの登場で大きく揺らぎました。
3マナと軽く《呪文貫き》も合わせづらいので、他の全体除去と同様ハンデスで落とすのが良いでしょう。
ちなみに《神々の憤怒》の話になりますが解決後は《荒廃者》の接合は誘発しません。うっかり流されてしまわないように注意をしましょう。

Shatterstorm / 粉砕の嵐 (2)(赤)(赤)
ソーサリー
すべてのアーティファクトを破壊する。それらは再生できない。
元祖アンチアーティファクトの全体除去です。
打たれてしまって通った場合、どうしようもありません。
《忍び寄る腐食》と異なり《溶接の壺》も効果がありません。
可能な限りライフを詰めた状態で、残った《ちらつき蛾》とライブラリートップの《感電破》に命運を託しましょう。

Fracturing Gust / 引き裂く突風 (2)(緑/白)(緑/白)(緑/白)
インスタント
すべてのアーティファクトとエンチャントを破壊する。あなたはこの方法で破壊されたパーマネント1つにつき2点のライフを得る。
インスタントのためなにもかもをもっていかれます。さらにライフ回復まで。
100マッチあって1回打たれるかどうかのカードなので、打たれた場合は運が悪かったと割り切りましょう。
ここまで色々なカードをご紹介しましたが、実際のところ手を焼くのは劇的なアンチカードよりも普通の《稲妻》、《致命的な一押し》、《流刑への道》などの軽量除去や、《古の遺恨》、《コラガンの命令》などの1対2交換するカードです。
1枚1枚丁寧に除去されていくだけで本来の動きをすることは不可能ですから、それらに強い《刻まれた勇者》をうまく活用していきましょう。
また組み立てたゲームプランの中でどのカードが大事なのかをよく考え、うまく除去を誘導することが重要です。例えばライフレースの効率だけを考えて《大霊堂のスカージ》に装備や接合をしていないでしょうか?効率的な行動を取ったつもりが相手にとっては脅威がひとつになり対処がしやすくなっているのかも知れません。
多少ライフゲインで損をしたとしても最後に1点残っていればよいのです。立っているだけの《羽ばたき飛行機械》に装備した方が相手の選択肢を奪うこととなるでしょう。
最後にモダンホライゾン以降、親和を意識せずに投入されている《レンと六番》や《溶岩の投げ矢》といった非常に困るカードが環境に増加しています。これらについても諦めず構築段階から工夫をしていくことが今後必要となっていくでしょう。
7.メタゲームに合わせてのチューニング
⑴親和に合ったメタゲームとは
実際のゲームが戦術的な部分であるとすれば、メタゲームは戦略です。
そもそも親和を使うべきかどうかまで遡ることになりますが、親和が有利なメタゲームは概ね「フェアデッキが多くアーティファクトへのガードが下がっている」状態です。
兄がMCバルセロナの権利を獲得したGP横浜時点のメタゲームは、まさに理想的な状態と言えるでしょう。
イゼットフェニックスを筆頭にドレッジやBG系、青白コントロール、5色人間が主流のデッキであり、イゼットフェニックスとドレッジは目の敵とされ墓地対策が多くアーティファクトへのガードがはっきりと下がっていました。
個々のマッチアップの相性は同じデッキでも時代によって変わるため割愛しますが、
傾向として親和は自身よりも相対的に遅いデッキに強く、自身よりも速いデッキが苦手です。
2019年7月現在の環境において見かけるアーキタイプに沿って例をあげてみます。
【相対的に親和より遅い】
・5色人間
・緑トロン
・青トロン
・エルドラージトロン
・ヴァラクート
・バーン
・ジャンド
・BG
・青白コントロール
・マルドゥパイロマンサー
・バントスピリット
・ジェスカイサヒーリ
・デルバー
・フェアリー
・イゼットフェニックス
・グリクシスデスシャドウ
・アブザンミッドレンジ
・マーフォーク
・ライブラリーアウト
【相対的に親和より速い】
・ネオフォーム
・感染
・アミュレットタイタン
・ドレッジ
・ホガーク
・ストーム
・ブリーチ
・赤単フェニックス
・ウルザソプター
・ホロウワン
【親和より遅いが構造的に親和に強い】
・鱗親和
・氷雪コントロール
・白黒トークン
感覚的な部分が多分に含まれるためうまく伝わっていると良いのですが……。
相対的な速度は、単純なキルターンだけではなく除去・手札破壊・打ち消しなどの妨害要素も含めてどちらが攻め手に近いかで決まります。
あくまでこれらは単なる傾向で、本来かなり有利であったトロン系やジャンドについては《大いなる創造主、カーン》や《レンと六番》が採用された影響で、正直手放しで有利とは言いづらい状態が続いています。
有利だったものが不利になったり、その逆も然りでマッチアップごとの相性は実際にテストを重ねない限り明確なものは出ません。
とはいえこの傾向を指針としてメタゲームを広く俯瞰した際に、親和を使うべきかどうかの判断は下しやすいかと思います。
親和よりも遅いデッキが多いメタゲームであれば、仮にTier1のデッキが親和に強くとも選択する理由となるのです。
⑵どんなときでも親和を使いたい
というわけでメタゲーム上で有利なときに有利なデッキを選択するのは当たり前のことなのですが、そうでないときも親和をプレイしたいという方もいると思います。
必ずしも親和に有利ではないメタゲームではどういう構成を取るべきかということも考えていきましょう。
親和の構成と一口にいっても、長い長い歴史の中で概ねメインボードの大半はほぼ固定化されています。参考のため最初のサンプルリストを再掲します。
Creatures
4 電結の荒廃者
4 大霊堂のスカージ
4 鋼の監視者
4 羽ばたき飛行機械
4 信号の邪魔者
1 エーテリウムの達人
2 メムナイト
Spells
4 頭蓋囲い
4 感電破
4 バネ葉の太鼓
4 オパールのモックス
2 溶接の壺
2 実験の狂乱
Lands
4 ちらつき蛾の生息地
4 ダークスティールの城塞
4 墨蛾の生息地
3 産業の塔
2 山
Sideboard
1 実験の狂乱
1 古の遺恨
3 減衰球
3 急送
2 刻まれた勇者
2 安らかなる眠り
1 呪文貫き
2 思考囲い
この中で変更する機会の多いスロットは以下の8枚です。
1 鋼の監視者
1 感電破
1 エーテリウムの達人
2 溶接の壺
2 実験の狂乱
1 山
もちろん《感電破》や《鋼の監視者》をもっと減らすアプローチもありますが、ゲームプランの部分から再度話をする必要があるため今回は省略します。
2019年7月のごく一般的なリストの中での調整だと考えてください。
その上で考えるポイントをいくつかご紹介します。
・《エーテリウムの達人》or《刻まれた勇者》
わかりやすい2択ですね。打点は低いものの突破力と信頼性に優れる《刻まれた勇者》は、無色のデッキとコンボデッキ以外相手には無類の強さを発揮します。
逆に対処されやすいものの全体の底上げと自身が大きい《エーテリウムの達人》は、除去の少ないコンボデッキに対してキルターンを速めてくれます。
《刻まれた勇者》は本当に劇的なカードで、このカードをメインに多くとりたいと思うかどうかが環境把握の試金石となるでしょう。少なくともサイドボードにはある程度の枠を割きましょう。
・《鋼の監視者》の枚数
遅く、脆いカードです。キープ基準であり生き残った場合は圧倒的な盤面を作り上げるため、個人的には4枚採用することが多いです。しかし、前述のジャンドなどの除去の多いデッキ相手には満足に活躍することは希なので、枚数を抑えることとなります。
・《溶接の壺》の枚数
鋼の監視者と同様、除去の多いデッキが環境の中心にいるかどうかで変わります。再生効果があまり役に立たないコンボデッキ相手には、同じ0マナアーティファクトであればパワーのある《メムナイト》の方が遥かに有効です。
・《感電破》の枚数
非常に強力なカードですが、盤面構築に寄与しないためあまり枚数を引きたくないカードでもあります。《氷の中の存在》や《闇の腹心》、最近は見なくなりましたが《詐欺師の総督》など環境の中心に必ず除去したいクリーチャーが存在するかどうかが判断の基準となります。
・《実験の狂乱》の枚数
メインボードに取られていますが、そもそもまったく必須のカードではありません。3〜4ターン目までに親和の理想的なムーブに対して寄与するカードではないからです。
着地したときの効果は絶大でついつい採用しがちですが、色つきかつ重いカードということで入っているだけで事故の可能性を高めます。
とはいえ、親和が活躍しやすいのは自身よりも遅いフェアデッキが多い環境です。
そういったフェアデッキに強い《実験の狂乱》がメインボードに採用されるのは自然な流れと言えるでしょう。
親和にとって不利な、自身よりも速いデッキが多い環境ではうまく生かし切ることができません。その際にはもっと尖ったカード、より加速する《アーティファクトの魂込め》や《爆片破》、相手を減速させる《思考囲い》などと入れ替えていきましょう。
・基本地形の枚数
メインボードとサイドボードの色付きカードを勘案して、どの土地を採用するか考えましょう。
基本地形は5色供給が可能な特殊地形らに比べると弱いカードです。
採用されている理由は《流刑への道》、《廃墟の地》、《暗殺者の戦利品》の受け皿とするためです。
これらのカードが多い場合には2枚、少ない場合には1枚あれば十分でしょう。
現在はメインボードに《感電破》や《エーテリウムの達人》がいる関係上《山》と《島》が採用されることが多いですが、《達人》などの青いカードがなければ《頭蓋囲い》のために《沼》を採用することにも価値があります。他にも緑や白のカードを採用しているのであればそれに沿った基本地形を入れましょう。完全に多色化している場合は1枚も基本地形を入れないことも選択のひとつです。
メタゲームの仮説立て
先ほど「どんなときでも親和を使いたい」と申し上げましたが、一年間を通して常にモダン環境に触れているという方はきっと少数派なのではないかなと思います。
スタンダードやリミテッド、レガシーやあるいはヴィンテージなど多種多様なフォーマットの中でGPやMCQなどきっかけがあり、モダン環境に”帰ってくる”方が多いのかなと想像します。ボクもその一人です。
そうしてモダンをプレイするときは必ず「今の親和はどういったものが多いのかな」というところからスタートします。
勝っているデッキリストを見つけ出し、それらの共通項を通して何故そのメタゲームに対してその構成になっているかを類推します。
《刻まれた勇者》はメインボードに入っているでしょうか。デッキを加速するカードが入っているでしょうか。それともロングゲームに向けたカードが入っているでしょうか。
それらとMagicOnlineやプレミアイベントのメタゲームを照らし合わせます。
概ね常にモダンをプレイしていたりプレミアイベントで結果を残しているプレイヤーは、その時点の環境に最適化されたリストを構築しています。そのリストを起点として何度もプレイすることで現時点、あるいは未来とのズレを発見することができるでしょう。
それらを微調整していくことで、より環境に沿った形を見つけることができるのです。
⑶サイドボードの作り方と無限の可能性
研究と微調整は、メインボードではささいな変更にとどまるかも知れません。しかしサイドボードには大きな影響をもたらします。
多くのデッキが存在するモダンではすべてに対応することは不可能であるだけに、どれだけサイドボードを作り込むかがチューニングの肝となります。
残念ながらサイドボードの構築にこれといったセオリーはありません。定番の採用カードは3章で紹介しましたが、あれがすべてではありません。
ざっくりとした方向性として、複数の役割を持つ多くの種類のカードを1〜2枚ずつ採用して全方位的なサイドボードにするか、割り切って強力な効果を持つカードを数種類取ったサイドボードにするかの2通りがあります。個人的には《光り物集めの鶴》などでデッキを”掘る”ことができる場合を除いて、割り切った”勝ちたいところに勝つ"サイドボードを作る方が好みです。親和が強力なオールインデッキである以上、多少のブレはプレイスキルや運で吸収できるでしょう。
また、新たなサイドカードの模索も常に行なってくことも非常に大切です。
メインボードと異なり、サイドボードに必ず入っているカードというものはありません。MTG Goldfishなどで様々なプレイヤーのデッキリストを眺めると、まさに千差万別でたくさんの発見があります。《金屑の悪鬼》を初めてみたときはとても驚きました。
新しいセットが登場したときに使用せず先入観で評価してしまうことがありますが、それはもしかすると他のプレイヤーよりも一歩先に進むチャンスをむざむざ捨てているのかもしれません。
メインボードの話ではわかりやすくするために固定スロットを多く挙げましたが、実は《感電破》、《鋼の監視者》ですら固定スロットではありません。
一歩前に進むためには固定スロットのように見える部分に手を加えることで、初めてブレイクスルーを得ることができるのです。最近では《虚空の杯》をメインボードに搭載したタイプが目を引きます。
ボク自身これまで《ボーマットの急使》、《エイトグ》、《敬慕されるロクソドン》などを試しては失敗していました。スクラップ&ビルドの成功率は低くなかなかうまくいかずに歯がゆさを感じることもありますが、それは必ず経験値として蓄積されます。どんどん失敗していきましょう。

ボク自身、現在は《ゴブリンの技師》を採用してシルバーバレット戦術を盛り込んだタイプを模索しています。残念ながらミシックチャンピオンシップには間に合わず断念しましたが、まだまだ可能性を秘めたアプローチだと考えています。せっかくですので以下にリストをご紹介します。
Creatures
4 電結の荒廃者
4 大霊堂のスカージ
4 ゴブリンの技師
4 羽ばたき飛行機械
4 信号の邪魔者
2 メムナイト
1 エーテル宣誓会の法学者
1 刻まれた勇者
1 鋼の監視者
Spells
4 頭蓋囲い
4 バネ葉の太鼓
4 オパールのモックス
1 溶接の壺
1 罠の橋
1 弱者の剣
1 飛行機械の鋳造所
1 墓掘りの檻
1 真髄の針
Lands
4 ちらつき蛾の生息地
4 ダークスティールの城塞
4 墨蛾の生息地
3 産業の塔
1 山
1 沼
Sideboard
2 安らかなる眠り
2 思考囲い
1 四肢切断
1 古の遺恨
1 急送
1 減衰球
1 トーモッドの墓所
1 報復のワンド
1 ギラプールの霊気格子
1 呪文滑り
1 屑鉄場のたかり屋
1 胆液の水源
1 神秘の炉
親和は固定パーツも多くコンセプトも強固なため、変化の余地が少ないと思われがちです。
しかし、実際はコンセプトが強固なことでさまざまな戦略を受け入れる懐の広さをもっています。
もし、親和というデッキを気に入ったのであれば自分だけの親和デッキを生み出すこともひとつの楽しみになると思います。
note版追記

現在は(2019年8月)ホガークが跳梁跋扈し、カーンが活躍する環境であり正直に言いますと親和の立ち位置はよくありません。しかしながら、これまでとは異なるアプローチで試行錯誤が進んでいます。
前述の《虚空の杯》入りタイプがMOのモダンリーグやSCGが徐々に結果を残しつつあります。もしかするとこの親和が環境の一戦に復帰するためのプロトタイプかもしれません。
Creatures
4 電結の荒廃者
4 大霊堂のスカージ
4 羽ばたき飛行機械
4 エーテリウムの達人
3 鋼の監視者
2 メムナイト
Spells
4 頭蓋囲い
4 バネ葉の太鼓
4 虚空の杯
4 オパールのモックス
4 感電破
2 溶接の壺
Lands
4 ちらつき蛾の生息地
4 ダークスティールの城塞
4 墨蛾の生息地
3 産業の塔
1 山
1 島
Sideboard
2 呪文貫き
1 苦花
2 減衰球
1 英雄的介入
1 ハーキルの召還術
1 天啓の光
2 安らかなる眠り
2 ギラプールの霊気格子
2 神秘の炉
1 倦怠の宝珠ボク自身、これからプレイテストを進める段階で語れるものはありませんが、常にアイデアを持ち偏見をなくすことで、さまざまな逆風を乗り越えていくことができるでしょう。親和はそれだけポテンシャルのあるデッキだと思います。
8.さいごに
非常に長いこの親和ガイドを最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。
まだまだ細かい部分にはいくら時間があっても足りないほどですが、一旦筆を置こうかと思います。
拙い文章であることは恥ずかしながら承知しており、これだけの文章量をもってでしか親和について語ることができないのが心苦しいです。冗長でありながらその分多くの情報を伝えられたのではないかと思います。
この親和ガイドを通して親和というデッキに興味をもってプレイしたり、逆にうまく親和を倒すことができたとしたら書き手としてこれ以上のことはありません。
ボク自身、ひとつのデッキに対してこれだけ多く語る言葉をもっているとは思いませんでした。執筆を通して親和というデッキを俯瞰することができより一層理解が深まったように思います。
まだまだ長い親和道の入り口に立っているだけという点ではボクも、今この文を読んでいるご主人様もそう変わりありません。ぜひ共に登っていきませんか。果てしなく続く、この親和坂を...。
それではまたお会いいたしましょう。
おつりか!

ここから先は
¥ 500
Twitterや配信などでいつでもご質問ください。お役に立ちたいです!
