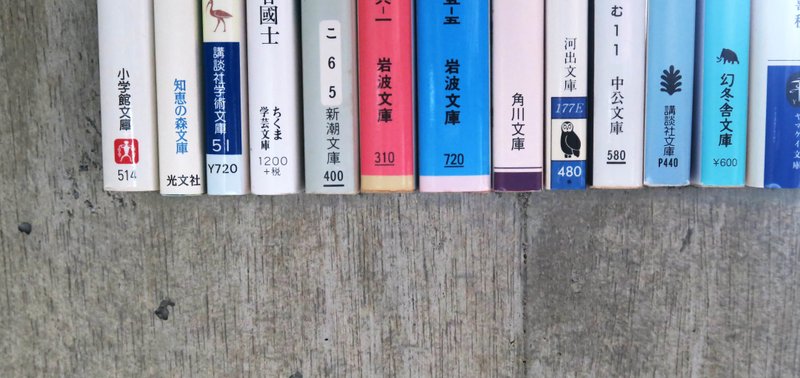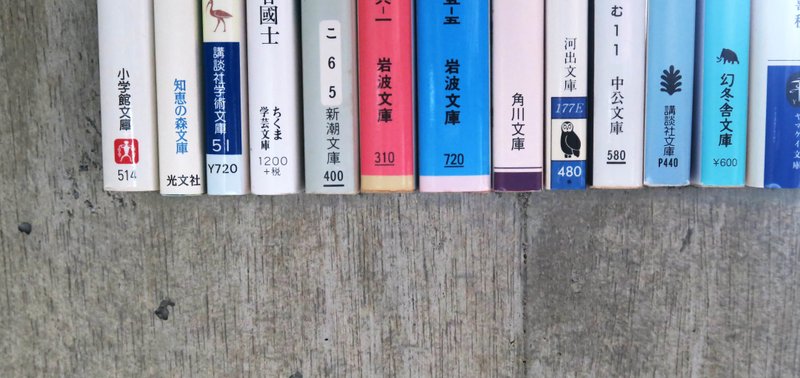『アイデアの接着剤_所詮、大衆ですから』
コロナ禍の影響で、テレワークが当たり前になってしまった今日この頃。だいぶ現在の生活にも慣れてそろそろ飽きてきたところですが、2020年当時はどのように自分を取り巻く環境を考えていたのか振り返ってみたくなりました。以下が2020年11月当時に書き記した当時の心境です。
●リアルではない仮想現実的な現実の生活
ほんの数年前までは、家にいる方が珍しくて、国内外を問わず常にどこかに出掛けていて、それはそれで落ち着かなくて、いつか腰を下ろしてしっかりと思想の深淵に静かに沈潜していき