渡辺氏への処分は妥当?ジャッジの意義?処置指針とは? 調べてみました!
はじめに
まず、この文書の筆者はMTGをアリーナのみプレイしており、ルールや罰則規定については調べた範囲の理解であることと、渡辺氏については「すごく有名な人、そして強い」くらいの認識であるため、氏の過去の実績や人間性を考慮した擁護を一切しないことを前提として記します。
昨日(5/10)、MCロンドンにおける渡辺雄也氏に対する失格処分についての調査結果が発表されました。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0032515/
何らかの私の意図が入る可能性があるため要約はしませんので、原文をお読みください。
またこの文書は、素人ではありますがルール面から本件の処分の妥当性と一部のジャッジの言動の是非を問うものであり、特定の個人および団体への利益または損害を与えることを目的としたものではないことを、強く強調しておきます。
罰則の妥当性について参考とした文献は以下の通りです。
マジック違反処置指針
https://mtg-jp.com/gameplay/rules/docs/0006838/
マジック:ザ・ギャザリングイベント規定
https://mtg-jp.com/gameplay/rules/docs/0006837/
マジックジャッジオフィシャルリソース-失格プロセス
https://blogs.magicjudges.org/o/disqualification-process-ja/
マジックジャッジオフィシャルリソース-Player Investigations
https://blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee/
2013-2014年度最優秀新人賞の剝奪について
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0011462/
David Williams-wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Williams_(card_game_player)
MTG wiki
http://mtgwiki.com/wiki/
処罰規定については、最も厳格であるとされるプロレベルで参照される違反処置指針を参考にしております。
罰則の妥当性について
まず、本件がどの規定によって処罰が決定され、果たしてその決定が妥当であったかについて、マジック処置指針を基に考えていきます。
①罰則の一般理念について


マジック違反処罰指針1「一般理念」によれば、懲罰の目的は、プレイヤーの再犯防止であり、ポリシーに抵触する行動について説明すること、教育のために必要なだけの処罰を与えることが必要であると明文化されています。
また、ヘッドジャッジには指針から逸脱した懲罰を決定する権限が与えられていますが、それは、
テーブルが倒れた
ブースターに他のセットからのカードが入っていた
といった稀なことだけを指し、イベントのラウンド数、プレイヤーの年齢や経験などは例外事象として認められないと記されています。
以上のことから、「本件については規定上の例外には含むことができず、規定に則った処罰が行われていなければならない」こととします。
②マークドによる処分について



マークドに関する罰則は、処置指針3-8「区別できるカード」に規定されています。
これによれば、デッキに入っているカードが他と区別できる状態であった場合の懲罰は「警告」で、特徴パターンを所有者が認識することで重要な利益を得る場合は、格上げとして「ゲームの敗北」の懲罰となります。
本件の場合、特定の土地に特徴的な傷がついており、特徴パターンを認識することによって重要な利益を得られると解することができる(反論はあるようですが認識していれば少なからず試合を有利に進められる)ため、ゲームの敗北の懲罰であれば妥当に見えます。
③故意の違反による失格



本件で適用されるであろう処罰指針3-8「区別できるカード」の項で与えられる懲罰である「ゲームの敗北」以上の懲罰となれば、4-8「故意の違反」による失格処分がこれに相当します。
故意の違反は「ゲーム上の誤り」「イベント上の誤り」と区別するため、意図や認識を確認するためにジャッジによる調査が必要と記されており、
・そのプレイヤーが自分の行動で有利を得ようとしている
・そのプレイヤーが自分が不正なことをしていると認識している
の両方を満たさなければ適用されないとあります。

ただし、1-1「懲罰の定義」によれば、
「失格処分はヘッドジャッジがイベントの完全性にかかわる問題があるとすれば、証明なしで与えられることもある。」
とのことで、 (上記故意の違反内の要件規定とどちらが上位に相当するかはわからず)場合によっては故意の証明が取れずとも、失格処分を言い渡せるとも解せます。いずれにせよ、失格プロセスによれば、選手に証言の機会を与えること、証言を集めることが求められるようです。
以上より、本件における失格処分は、4-8「故意の違反」に該当したからであり、なおかつヘッドジャッジの判断により故意の証明なしだが失格に足る十分な情報により判断され、与えられたものであることはほぼ間違いない(それ以外に失格に相当する条文がないため)と言えるでしょう。
④故意性の有無
これについてはジャッジがどのようなプロセスで故意であると判断したかマークドの状況以外は不明瞭であるため、私からはあまり触れないでおこうと思います。
「複数回のデッキチェックが行われ、その度に問題なしとされた」
「TOP8への進出が(ほぼ)決まっており、メリットがほぼ皆無であった」
「直前のデッキチェックでOKを貰ってから一度も試合をしていない状態でチェックされ失格となった」
ことが故意性を否定する材料として挙げられていますが、いずれも故意がないことの証明として「決定的」とは言えません。
が、そもそも故意であることを要件とした刑罰であるなら、社会通念上、法手続(刑法)上では一般的に、被疑者が故意がないことを証明する義務を負うのでなく、容疑をかける側がその故意の証明を行う義務を負います。
よって、後にも触れますが「team cygamesや渡辺氏の発信では故意がないことの証明にはならない」という指摘は社会正義から大きく逸脱していることのみ記しておきます。
⑤追加処罰の妥当性
残念ながら、出場停止などの追加処分については、プレイヤーの知れる限りで明確な基準は示されておりません。ここでは処置指針懲罰の一般理念に記されていることと同様の目的で下されるものと類推して話を進めます。(事実と異なる場合は指摘を受け入れますが、もしそうでない場合、派生事項である追加処分が本元の規定の意義から逸脱していることとなり、それはそれで問題です。)
渡辺氏に下された処分は30か月の出場資格停止およびMPLおよびプロツアー殿堂からの除名となっておりますが、この処分の妥当性を考察するに十分な数のマークドによる処分案件の比較対象を得られなかったため、同様にマークドで処分を受けたDavid Williams及び過去に出場停止処分を受けた他の日本人プレイヤーの例を挙げることとします。
・David Williams マークドされた特定のカードがカットをするたびにトップデックに来るように曲げていたことが検証により確認できた。1年間のトーナメント出場停止。
・斎藤友晴 遅延行為による失格。1年半の出場停止及び殿堂入りの取り消し。
・石川錬 トーナメント司会者への偽証、デッキ不正及び不正行為の繰り返し。2年間の出場停止
上記の例に比べ、かなり重いものであることは(という感想はジャッジ界隈からも上がっているほど)明らかと言えます。この処分が下ったことを肯定できる理由については、以下のような推測がなされているようです。
・過去に違反を繰り返していたことが確認できたから
・コミュニティへの影響度が大きい殿堂入りプレイヤーであることを重く見られたから
・team cygamesと共に意見声明を出したことにより心証が悪くなったから
過去に違反を繰り返していたことは10日発表の調査結果からの推測でしょうが、いつ頃の出来事であったのかさえ明らかにされておらず、(https://mtg-jp.com/reading/publicity/0011462/ と比較すると解りやすい)説明不足と言われても致し方ない状況で、重い処罰の理由としてはコミュニティの納得を得ることはできないのは当然です。

また、処置指針1「一般理念」には「プレイヤーの過去の実績等が違反を変更する事由とならないが、取り調べにおいては考慮されうる」とあります。この『取り調べにおいては考慮されうる』という玉虫色の文言の解釈には、影響力の強いプレイヤーへ重い処罰を下せるとの読み方と、それまでの素行の良し悪しによっては規定内で軽くも重くもなるとの読み方が存在します。が、懲罰の妥当性で触れた「懲罰の目的は再版防止であり、教育のために必要なだけの懲罰を与えること」「プレイヤーの経歴などは規定を逸脱した懲罰の理由とならないこと」を踏まえた場合、殿堂入りしたようなプレイヤーへより重い処罰を下せる文言と解するのは、規定上の妥当性が見出せませんし(異論はあると思います)、殿堂入り取り消しの斎藤氏への処分と比較しても不均衡であると言わざるを得ません。
そして、team cygames及び渡辺氏による声明の発表についてですが、「一般理念」における「再犯防止」「教育に必要なだけの処罰」「他のプレイヤーへの抑止力や教育」という懲罰の目的を、どのように解したら処罰が重くなる事由となるのでしょうか。
「違反していないという声明の発表は反省していない証拠、教育のためにはより重い罰が必要だ。これで他のプレイヤーも処分への抗議など公に行わなくなるだろう。」
以外に解釈のしようがないのですが、「一般理念」にははっきりとこう書いてあります。
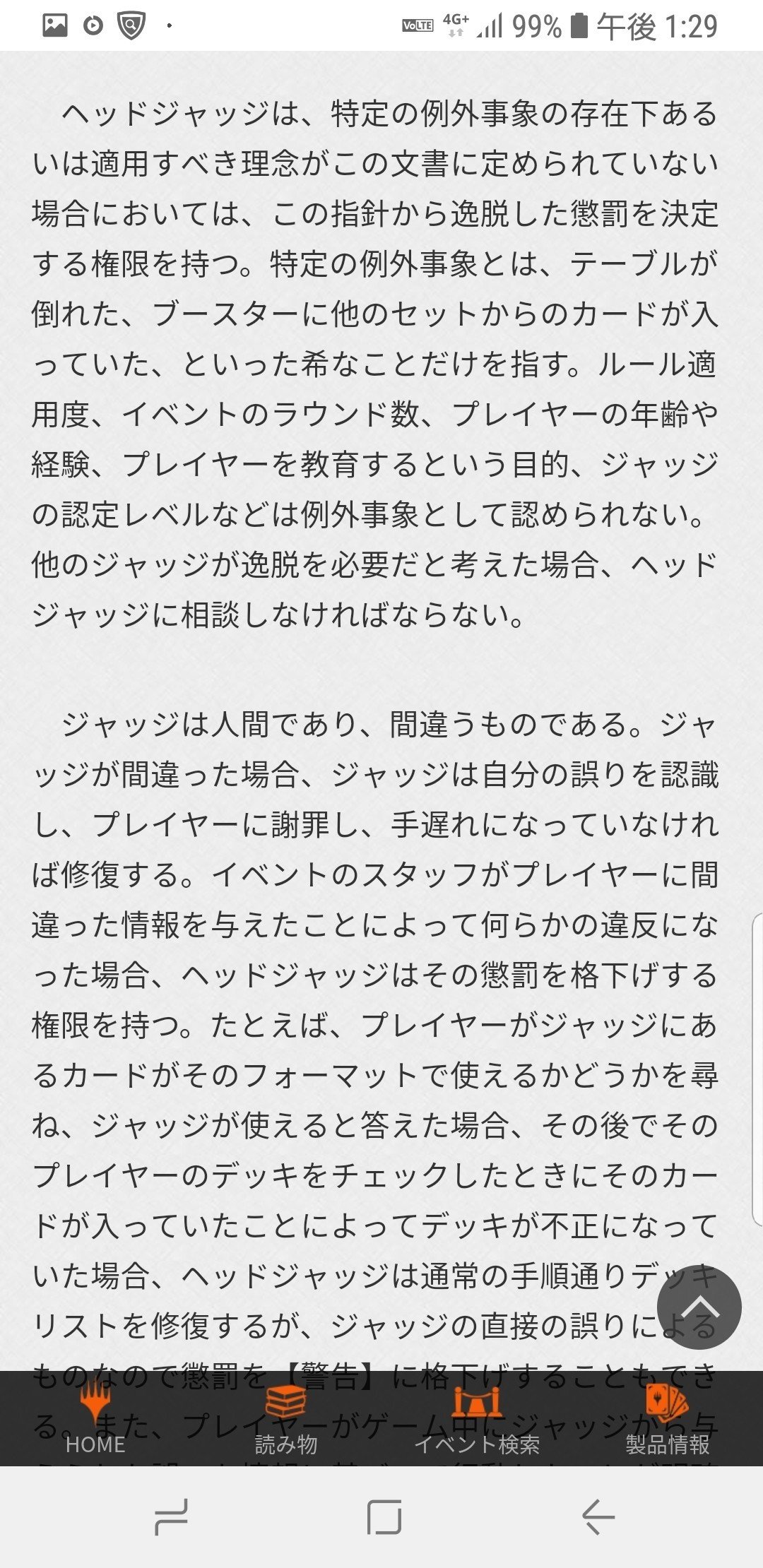
「ジャッジは人間であり、間違うものである」
と。抗議を公の場で行えないとするならば、第三者がジャッジの誤りについて考える、知る機会は永久に訪れないのではないですか。
⑥処罰の妥当性についてのまとめ(個人の感想)
上記は全て、ジャッジが処置指針の通りに完全に誤りなく裁定を下したことを前提として書かれています。ジャッジ側に好意的に考えるのであれば、
「渡辺氏への失格処分は故意の違反でそれが証明された、もしくは証明なしだが十分な情報をジャッジが得ていた」ので妥当な判断と言えるでしょう。
しかしながら、故意であると判断した理由はマークドの事実のみしか書かれておらず、複数のデッキチェックを通った後に失格となったプロセスについての説明はない。通常よりも重い追加処分が下ったことについても経緯の説明が意図的としか思えないほど省かれている。
こんな状況で何を納得しろというのですか。
今回の経緯からは、懲罰の根拠となる処置指針をきっちり守りました、そんな姿勢は微塵も感じられないではないですか。
説明も証明もなく処罰され、抗議すら公にすることができないことへの恐怖をプレイヤーが持つことの、何が不思議なのでしょうか。
別にジャッジが意図的な不正をしただろう!と言っているのではありませんし、確証もなしに安易にそのような論に乗っかるのは愚かしいとすら思います。それでも、本件の処分全てが規定から逸脱せずに下されたとは、ルールと発表を見比べる限り到底考えられないわけです。
この状況で理屈はどうであれジャッジがすべて正しいと断言できるのであれば、それは無根拠な信頼にほかならず、思考の放棄です。
こんなとき、ジャッジ資格を持つ者の責務は、コミュニティからのジャッジの信用を落とさないことであり、そのためには沈黙か、コミュニティの納得を得られるような説明を行うことかの二択で、説明の能力がないのであれば前者一択ではないのですか。
それなのに…
一部のジャッジ界隈とその周囲について
まず、私自身は他のTCGでの経験上、「TCGのジャッジなど所詮は人間。裁定には従うが全幅の信用をするに値しない」くらいの認識でした。
MTGを除いては。
いくらかジャッジの権威を絶対視している香ばしい人がいるけれど、プレイヤーもジャッジも他のゲームよりいくらか物事の分別がつく大人が多いのだろうと思っておりました。
つい先日までは。
ここ数日での一部のジャッジやその周辺の発言は、長きMTGの歴史が積み上げてきた信頼を地の底に落とすには十分すぎるほどであったと、多くの方が思っているようです。
ここから先は、誰がどんなことを言った、という個人の特定はせずに、私が観測した範囲で見られ、なおかつある程度の支持を受けていた、規定や理念、プレイヤーの認識と照らし合わせて不可解な言論について検証していくこととします。
①「ルールとジャッジを疑ったら競技は成り立たない」
先に述べた通り、処置指針1「一般理念」にはっきりと「ジャッジは間違うものである」と明記されております。MTGのあらゆる規定はプレイヤー及びジャッジが公平公正であるよう規範を示しているものであり、信用を担保するものではありません(としか読めません)。
また、TCGに限らずあらゆる歴史と権威ある競技においてミスジャッジや不正・買収の類は幾度となく問題となっており、その度に改善が試みられてきましたし、この先もそうでしょう。
何故あなたたちのみがこの世の競技のジャッジの中で突出して公正公平でそれは担保されていると、根拠もなく無垢に主張ができるのですか。
②「team cygames及び渡辺氏の発表には不正を覆すだけの力が全くない」
故意を説明、証明するのはジャッジの責務であることは規定に書かれていても、疑いをかけられた者へ「していない証明」を求める条文は(私が目を通した限りでは)見当たりませんでした。無実の立証を被疑者へ求めることは、MTGだけでなく、あらゆる近代的な法規範への挑戦ですよ。
中世に魔女裁判が行われていた時代に逆戻りしたいのであればそのままの姿勢で構わないでしょうが、それで多くの人の理解を得られると思わないでいただきたい。
③「複数のデッキチェックが行われるのは普通、その後失格になったという事実があるだけ」
複数回のデッキチェックを行うことは何も問題はないでしょうけれど、その結果直前のチェックで通ったデッキが一度も使用されないままチェックを受け失格となった。考えられる可能性は以下のようになるのではないでしょうか。
A.「それまでのデッキチェックでも僅かな異変が認められたが、ラウンドを経るごとにそれがはっきりしていったため処罰した」
B.「それまでデッキチェックを行っていたが、異変を発見することができなかった。ジャッジの力量不足」
C.「それまでのデッキチェックで故意であることがほぼ確証できるだけの異変を発見したが、あえて泳がせた」
D.「第三者の介入」
E.「渡辺氏は次のラウンドでIDができなかった場合に備えて入念にマークドを行ったが、無事IDした後もそのままにして談笑を続けた。デッキチェックを控えていることが容易に想像できたのにも関わらず。」
F「渡辺氏はID後メリットこそないがマークドをせずにはいられなかった。どこまでジャッジの目を潜り抜けられるのかというスリルに抗えなかった。」
妥当性が高いのはABCのどれかだと考えられるのですが、Aの場合それは即ち試合の進行によってついたマークドで、故意性が否定されます。Bに関してはミスジャッジがあったことを認めることになります。渡辺氏の悪意を前提とした論だとEも支持されるようですが、他の可能性と比較検討して、著しく行動の妥当性を欠いていることは明らかですし、これは氏の過去の実績等を考慮に入れずとも不自然なものであり、冷静な分析とは見なせません。
そしてCですが…
④「不正を発見してもあえて泳がせた、これは普通にあること」
マジック:ザ・ギャザリングイベント規定1-8「フロアジャッジ」の項にはこう書かれています。

「ジャッジはゲーム上の不正な行動を防ぐために介入してはならない。ルールが破られた直後に介入し、問題が複雑化するのを防ぎ、ゲームの完全性を復元し、必要に応じて懲罰を与えること」
これはどこからが不正な行動と言えるのかという定義の問題ですが、文面通り解すのであれば、R15までに不正な状態であると確認できたなら、それは即座に対応するべき案件であるはずです。その時点でも処置指針上の「区別できるカード」に則って懲罰を与えることができますから。
もし不正な状態を見過ごして対戦を進めたのであれば、「問題が複雑化し、ゲームの完全性を復元することが困難」な状態を、一人のプレイヤーへ厳罰を与えるためにあえて作り出したことになります。
この発言がジャッジ経験者から出てきたというのは、従来もより厳しい罰を与えることを(確証がなくても、可能性があれば)、トーナメントの完全性が損なわれることの防止よりも重視していたということですよね。これ、競技として一番問題なのではないですか。
⑤「ジャッジの裁定にブログなどで意見を書いたら心証を悪くする、(基準は公開されていないが)これが当たり前」
懲罰の意義に記されていない基準で懲罰の量刑を判断することの妥当性とは何でしょうか。
「はい、私たちの中での基準であなたの処罰は重くなりました。基準は貴方たちに公開はしていませんけどね!」
これが近代競技でまかり通ると本気で思っているのでしょうか。
選手調査のプロセス(https://blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee/)を読んでも明確にそういった類の記載は見当たりません。
「サイゲもBAN基準を公開しろ」という意見を嬉々として取り上げていた人たち、恥ずかしくないのでしょうか。
競技とソーシャルゲームの違いだとか、サイゲは誤BAN認めたこともあるだろうとか、そういった話で比較するとあくまで主観の話になるのであえて主張はしません。
それ、逆に自分たちの基準が不明瞭であることを認めているのに等しいのですが、大丈夫ですか。
⑥「調査結果の発表は十分なもので、詳細すぎるとイカサマの手口の公開に繋がるため控えたのではないか」
他の例(https://mtg-jp.com/reading/publicity/0011462/ など)と比較して特別簡素である理由にはなりません。また、懲罰における一般理念を参照しても、十分な説明を行うことが懲罰を下すにあたっての基本スタンスであることは疑いようもありません。
⑦一部のジャッジとその周辺に対して思うことのまとめ
総じて、「貴方たちの(少なくともプレイヤーへ認知されていない)当たり前には私たちからしたら何の価値もない」の一言に尽きます。
もし、そういった選手へ公開されていない基準による判定が常習化しているのであれば、それは真に公正な競技とは呼べません。
自分たちの判断は即ち事実、プレイヤーの認知しない基準、だまし討ちによる厳罰化…
これによってもたらされる利益なんて、ジャッジの虚栄心を満たすこと以外に皆無じゃないですか。
ジャッジはジャッジのためにジャッジをしているのではなく、競技の円滑な運営のために存在していると理解していない方々がこんなにもいることには正直驚きました。
プレイヤーが知り得る限りの情報で認識していた「ジャッジの理念」とは、裏側ではこうもたやすく踏みにじられていたものなのかと、落胆を禁じ得ません。
それでも、多くの沈黙を貫いているジャッジの方々が良識的で、驕らず、公平公正であることを私は今でも信じていますし、期待しています。ですから、お願いですから自浄作用を働かせていただきたい。これ以上ジャッジへの信用を落とす輩を野放しにしないでいただきたい。
さいごに
私は与えられた情報から判断する限り、渡辺氏が故意に不正を働いたとも、ジャッジが意図的に証拠をねつ造したとも思っておりません。
そしてそれは両者ともそうでなかったことを確信するに至っておりません。
何故ならば、情報も説明も不十分であるからに他なりません。そんな状況であたかも確証があるかのように自説を吹聴することは、どんな立場であれ等しく、最も愚かで、公正な競技を作り上げていくことを責務とする者(プレイヤー、ジャッジ双方)の行いとしては到底許されるべきではないと考えます。
所詮は少しルールを調べた程度の初心者の戯言なので解釈に誤りがあるかもしれませんが、多くのプレイヤーが疑いを持ってしまう余地があるのは突き付けられた事実です。このような状況がいち早く改善され、末永くMTGがコンテンツとして生き続け、競技シーンの公平公正さが他の競技同様に改善され続けていくことを望みます。
5/11 P.M.05:09 懲罰の妥当性⑤追加処罰の妥当性について、プレイヤーの実績と刑罰の決定についての引用意図及び判断のプロセスが、より明確に伝わるよう修正。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
