
21. キツネの秘密
キツネが現れたのはそのときだった。
「やぁ」キツネは言った。
「こんにちは」王子さまは丁寧に返事をしたが、振り向いても何も見えなかった。
「ここだよ」りんごの木の下から声がした。
「きみは誰?」王子さまは言った。「とても素敵だね…」
「おれはキツネだ」キツネは言った。
「こっちに来て一緒に遊ぼう」王子さまは彼に提案した。「どうしようもなく寂しいんだ…」
「きみとは一緒に遊べないよ」キツネは言った。「飼いならされていないからね」
「あぁ!ごめん」と王子さま
けれど少し考えてから彼は言った。
「 “飼いならす” ってどういう意味?」
「見ない顔だな」キツネは言った。「何を探しているんだい?」
「人間を探しているんだ」王子さまは言った。「 “飼いならす” ってどういう意味?」
「人間はさ」キツネは言った。「銃を持って狩りをする。困っちゃうね!やつらはニワトリも育てている。いいところと言えばそのくらいだ。ニワトリを探しているのかい?」
「いや」王子さまは言った。「友だちを探しているんだ。“飼いならす” ってどういう意味?」
「すっかり忘れ去られてしまったことだよ」キツネは言った。「 “絆をつくる” っていう意味だ」
「絆をつくる?」
「そうさ」キツネは言った。「きみはまだ、おれにとって十万といる少年と同じただの少年だ。おれはきみを必要としていない。そしてきみもおれを必要としていない。おれはきみにとって十万といるキツネと同じただのキツネだ。でももしきみがおれを飼い慣らせば、おれたち二人は互いを必要とするようになる。きみはおれにとって世界で一人の存在になる。おれはきみにとって世界で一匹の存在になるんだ」
「わかってきた気がする」王子さまは言った。「ある花がいてね…たぶん彼女はぼくを飼い慣らしたんだと思う…」
「そうかもしれないな」キツネは言った。「地球ではどんなことがあってもおかしくない…」
「あぁ!地球の話じゃないんだ」王子さまは言った。
キツネはむっと不思議がった。
「他の星ということかい?」
「うん」
「その星に狩人はいるか?」
「いないよ」
「それは素晴らしい!ニワトリは?」
「いないよ」
「上手くいかないものだな」キツネはため息をついた。
けれどキツネは話を戻した。
「おれの毎日は単調なんだ。おれはニワトリを追いかけて、人間はおれを追いかける。どのニワトリも似たり寄ったりで、どの人間も似たり寄ったりだ。だからちょっと退屈してる。でもきみがおれを飼い慣らしてくれれば、おれの毎日は輝かんばかりだ。おれには他の誰のとも違う足音がわかるようになる。他の足音はおれを地中にもぐらせる。きみのは音楽みたいに、おれを巣穴の外に呼び出してくれる。それに、見て!ほら、あそこに麦畑が見えるかい?おれはパンを食べない。おれは麦がなくても困らない。麦畑を見ても何も感じやしない。それは悲しいことだよ!でもきみは金色の髪をしてる。きみが飼い慣らしてくれたら素晴らしいだろうなぁ!金色の麦はおれにきみのことを思い出させてくれる。そしておれは麦畑を吹く風の音だって好きになる…」
キツネは口をつぐんで、王子さまをじっと見つめた。
「頼むよ…おれを飼い慣らしてくれ!」彼は言った。
「そうしたいけど」王子さまは答えた。「あまり時間がないんだ。たくさん友だちを見つけないといけないし、いろいろなことを知らなきゃいけない」
「飼い慣らしたもののことしかわからないんだ」キツネは言った。「人間はもう何も知る時間がない。出来合いのものを店で買うだけだ。でも友だちを売っている店なんてないから、人間にはもう友だちもいない。友だちが欲しいなら、おれを飼い慣らしてくれ!」
「何をすればいいの?」王子さまは言った。
「焦らないことだ」キツネは答えた。「きみはまず、おれからちょっと離れたところに座る。こうやって草むらの上にね。おれはきみを横目で見るけど、きみは何も言わない。言葉は誤解のみなもとだから。でも、日を追うごとに、きみは少しずつ近くに座っていい…」
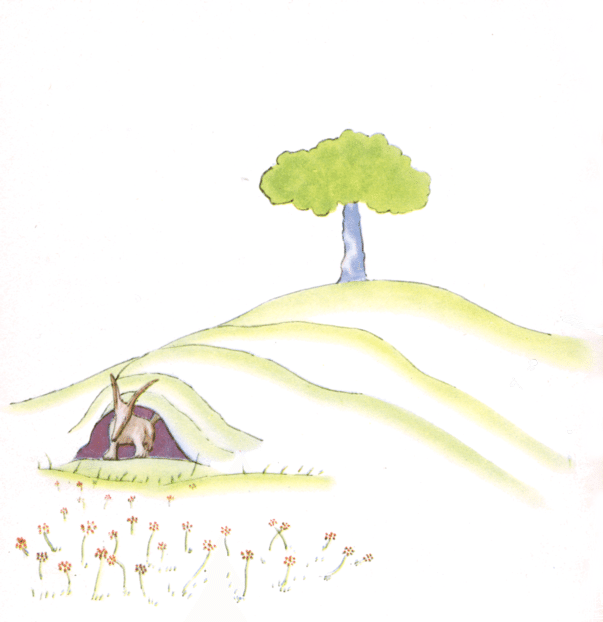
翌日、王子さまはまたやって来た。
「昨日と同じ時間に来てくれたらもっとよかったな」キツネは言った。「きみがもし、たとえば午後の四時にやって来るとしたら、おれは三時には胸が弾む。時間が過ぎるにつれてどんどん嬉しくなる。四時になったらもう、そわそわして心配になってくる。幸せがどんなものかわかるんだ!ってね。けど、きみが気まぐれな時間に来たら、おれは何時に心の支度をしたらいいかわからない…しきたりが必要なんだ」
「しきたりってなに?」
「これもすっかり忘れ去られたものだよ」キツネは言った。「それがあることで、ある日が他の日と、ある時間が他の時間と区別される。たとえば、おれを狩りに来るやつらにもしきたりがある。あいつらは木曜日には村の娘たちと踊るんだ。すると木曜日は素晴らしい日になる!おれはぶどう畑まで散歩に行ける。もし狩人たちが気まぐれに踊ったら、何曜日でも同じになって、おれの休日もまるでなくなってしまう」

こうして王子さまはキツネを飼い慣らした。そして出発の時刻が近づくと、キツネは言った。
「あぁ!泣いちゃいそうだ」
「きみのせいだよ」王子さまは言った。「ぼくはきみに辛い思いをさせるつもりなんてなかったのに、きみが飼い慣らしてほしがるから…」
「そうとも」キツネは言った。
「でも泣くんでしょ!」王子さまは言った。
「そうとも」キツネは言った。
「それじゃ何も残らないじゃないか!」
「そんなことはない」キツネは言った。「麦の色があるからね」
それから彼は言い足した。
「もう一度バラを見に行ってみな。きみのバラは世界で一つなんだって、きっとわかるから。それからおれにさよならを言いにおいで、そうしたらきみへの贈り物に、秘密を教えてあげよう」
王子さまは再びバラに会いに行った。
「あなたたちは全然ぼくのバラに似ていない、あなたたちはまだ何でもない」彼はバラの花々に向かって言った。「誰もあなたたちを飼い慣らしていないし、あなたたちは誰も飼い慣らしていない。ぼくのキツネもそうだった。十万といる他のキツネと変わらないただのキツネだった。でもぼくの友だちになった、だから今は世界で一つの存在なんだ」
バラの花々はすっかり困っていた。
「あなたたちは美しい、でも空っぽだ」彼は続けた。「あなたたちのためには死ねない。もちろんぼくのバラだって、通りがかりの人から見ればあなたたちと変わらないかもしれない。でも彼女ひとりだけで、あなたたちみんなよりも大切なんだ、だってぼくが水をあげたのは彼女だから。覆いをかぶせてあげたのも彼女だから。風よけを立ててあげたのも彼女だから。ケムシを殺してあげたのも(二、三匹、蝶になるから逃がしてあげたけど)彼女だから。愚痴や自慢話を聞いたり、ときには黙っているのを聴いてあげたのも彼女だから。だってぼくのバラだから」
そして彼はキツネのもとに戻ってきた。
「さようなら」彼は言った…
「さようなら」キツネは言った。「これがおれの秘密だ。とても簡単なことだよ。心で見ないとよく見えない。肝心なことは、目には見えないんだ」
「肝心なことは、目には見えない」忘れないように王子さまは繰り返した。
「きみがきみのバラのために費やした時間が、きみのバラをそれほど大切なものにするんだ」
「ぼくがぼくのバラのために費やした時間が…」王子さまは忘れないように言った。
「人間たちはこの真理を忘れてしまった」キツネは言った。「でもきみは忘れちゃいけないよ。きみは、きみが飼い慣らしたものにずっと責任を持つんだ。きみはきみのバラに責任があるんだよ…」
「ぼくはぼくのバラに責任がある…」忘れないよう、王子さまは繰り返した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
