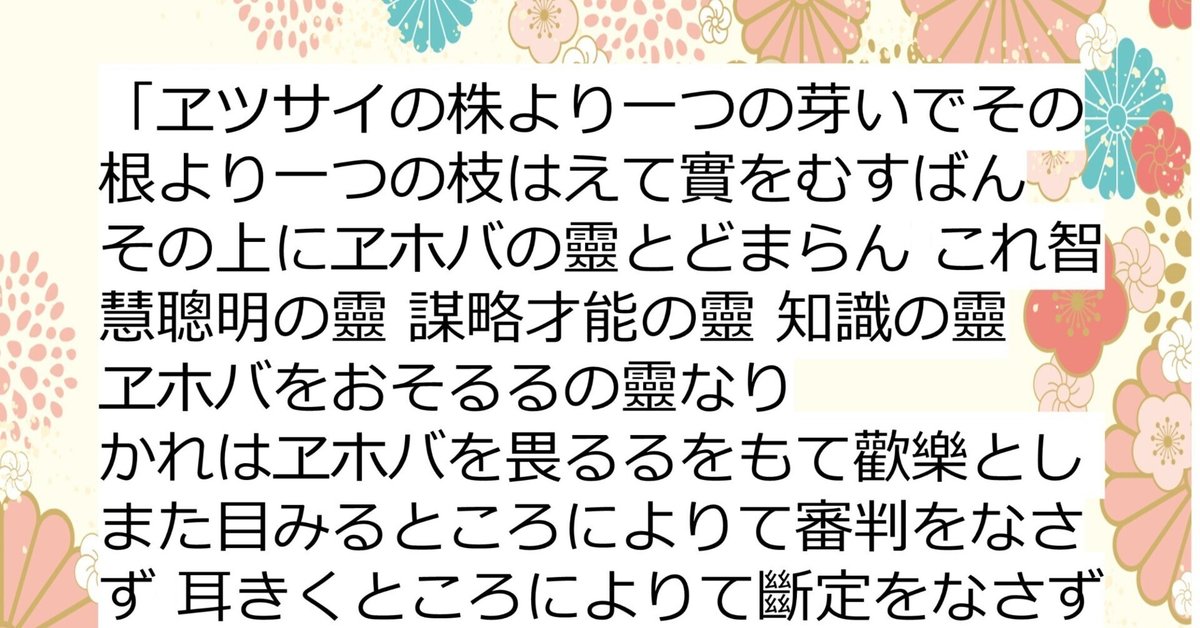
ヱホバを畏れるという聖霊のはたらき
「ヱッサイ」はユダのベツレヘム出身の羊飼いで庶民の中の庶民です。古代イスラエル王国の2代目の王となるダビデは彼の第8子であり、祖父のオベデはルツとボアズの息子なので彼自身は孫にあたり主イエスの祖先になります。冒頭の「ヱッサイの株」以下「ヱホバの靈とどまらん」までの句は、ヱッサイの木が切り倒されて切り株となるということがダビデ王によって南北が統一されたイエスラエル王国の絶望的な末路と、そのような最低最悪の状況から、主なる神(ヱホバ)の霊がとどまる理想的新王(メシア)が誕生するという希望が預言されている。その霊は、知恵聡明の霊、謀略才能の霊、 知識の霊、ヱホバを畏れる霊という四つの霊(ルーアハ)が「存在」するということではなく、同じ「主なる神(ヱホバ)の霊=聖霊」の四つの「賜物・はたらき」を示している。これを「知恵」と「聡明」と「謀略」と「才能」と「知識」と「畏れ(敬虔)」の六つと数えたり、ギリシャ語70人訳及びラテン語訳(ウルガータ)では七つを数える。王に与えられる霊の政治的な賜物・はたらきの中心は正しい裁きをなさしめることであるが、根本にあるのはヱホバを畏れさせ、しかもそのことを「歡樂」させる…喜ばせること。その点では庶民の私たち一般信者にも通じる聖霊のはたらきである。私が日頃体験しているところの内なる聖霊のはたらきかけは、聖化によって品行方正な道徳的人間にすることではない。キリストの十字架による贖罪の恵みを頂いてはいても、この世の生涯においては罪人であり、メシアの裁きにおいては唇の息をもって殺されるべき悪人にもなり得る煩悩具足の凡夫(=単なる自我)であることに変わりはない。特に私の如き者の聖霊体験においては新約聖書ガラテヤ書5:22~23に書かれている「御霊の実」のような倫理的なことではなく、…そういう面もなんぼかはあるかも知れないがその前に、この旧約聖書イザヤ書11:2~3で言われている主なる神(ヱホバ)を畏れ(「ヱホバを畏るるは知識の本なり」箴言1:7、「ヱホバを畏るることは智慧の根本なり」箴言9:10、「ヱホバを畏るることは智慧の訓なり」箴言15:33)、しかもその畏れることを喜ぶこと、この喜びという福音がないと「御霊の実」は律法的課題と化す。「此日は我らの主の聖日なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと」(尼希米亞⦅ネヘミヤ⦆記8:10)…「ヱホバを喜ぶ」とはヱホバとの関係にあることを喜ぶということ。私にとって聖霊すなわちヱホバの霊のはたらきは何よりもその喜びを自分の心に満たして、絶望的な状況に陥っても希望を捨てずに生き抜く力を与えること。自分が滅んでは愛も平和もない。まずは自分が対神関係を生きること。対人関係はそれからである。

キリスト教関係のメディアでも伝えられない、あるいは伝えきれないキリスト教界のタブーに挑戦します。面白さを心がけているのでご期待下さい。
