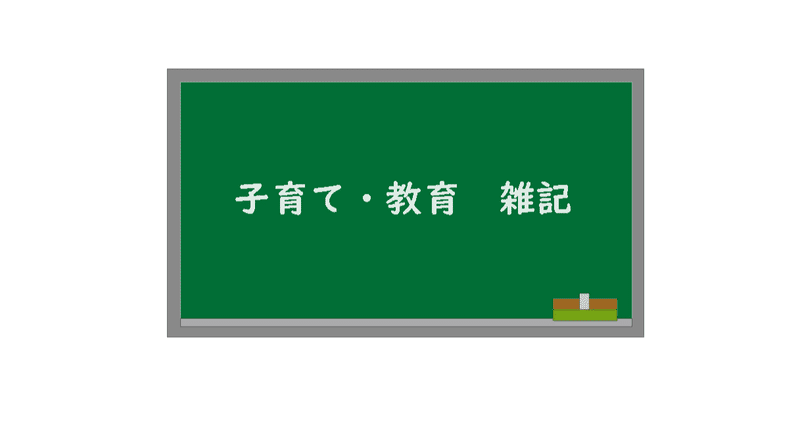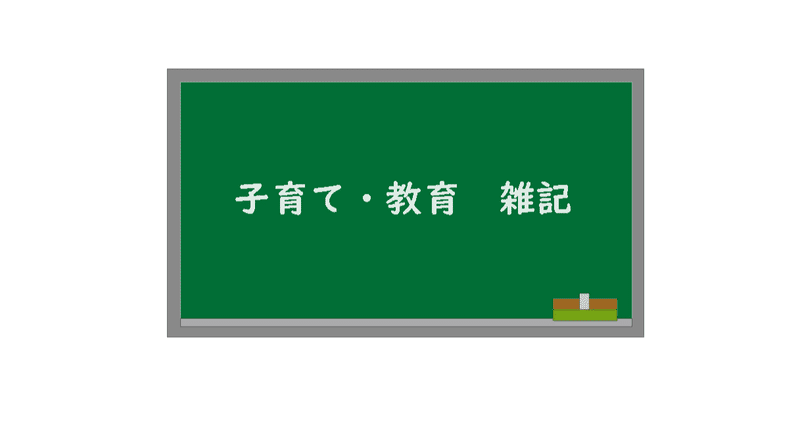幼児期に「知覚力」を鍛える事の大切さ
知覚力とは五感を通じて見たり聞いたり触れたりして感じる情報を、自覚的な体験として再構成する働きのことをいいます。
これからビジネスパーソンに求められる能力として、注目を集めている「知覚力」です。先行きが見通せない時代には、思考は本来の力を発揮できなくなる。
そこでものを言うのは、思考の前提となる認知、すなわち「知覚(perception)」です。「どこに眼を向けて、何を感じるのか?」「感じ取った事実をどう解釈するのか?」
この知覚力は、知識と知識をつなげる助けもしてくれ