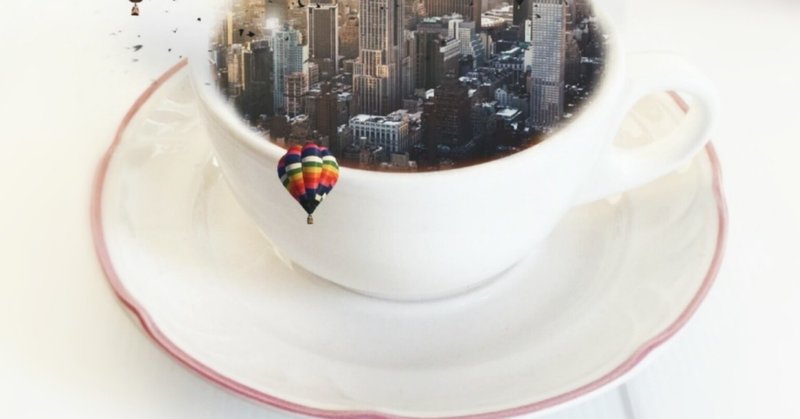
『苦味が与える常態行動心理学的影響』
子供の時は苦味や酸味や辛味が駄目で甘味を好む傾向にありました。 大人になって苦味の旨さや辛味、酸味の良さが解ってきました。 子供の頃、ビールは泡がたつ苦い飲み物と言う印象しかなくそれを美味いとする大人の気持ちがわかりませんでした。 では何故子供にはその味が解らず大人になるとその味が解るのでしょうか? 原因は脳の働きに有ります。 子供の頃は大人よりも経験値が少なく脳内データも大人ほど充分に揃っていません。 故にデータ収集にとても鋭敏になります。 大人でも真っ暗やみの中、丸腰で放り出されたら五感を鋭敏にして危機察知に全力を注ぐと思います。 それは生物学的な生存本能が成せる技です。 子供の頃はその状態が数年間続くと考えて下さい。 大人でも長く緊張状態が続くと疲労感を覚えます。 それは子供も同じです。 故に子供の頃は生物学的生存欲求が高まる故に味覚も鋭敏となり苦味や酸味や辛味が大人より強調されるのです。 されど経年により様々な経験を積んでいくとそれらから受ける刺激になれてきます。 刺激になれてくると辛味、酸味、苦味に対する刺激反応が遅くなります。 人間の脳は刺激に反応して細胞を分裂させて成長進化し生き永らえて居ます。 子供の頃は五感から受ける刺激に対して全て鋭敏に反応するので余剰情報として寧ろ苦味や酸味や辛味が余計なのですが大人になると経年による経験値獲得により脳が刺激を受けにくくなる為に苦味や酸味や辛味を欲し刺激を得ようとします。 されどそれもやはり慣れが何れ生じてきます。 すると更に刺激を求めるようになります。 現代人に味覚障害が多いのは実はそういう理由による所が大きいのです。 更に刺激はストレス回復にも繋がります。 それ故に最近は低年齢層にも刺激を求める傾向が強まっています。 これはとても危機的状況にあると言って良いでしょう。 この状況を打開するのは大人の務めです。 大人がもっと子供に対してリーダーシップを発揮出来る存在にならねばなりません。 それが未来の子供を救う唯一の手だてだと私は考えます。

サポート頂いた方の思いを私なりに形にし世界へ発信していきたいと考えています。人は思いによって生かされている事を世界へ発進する為の資金に使わせて頂きます。
