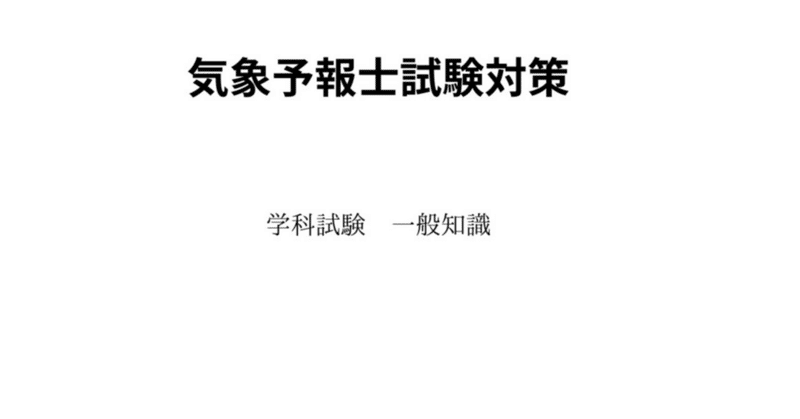
気象予報士試験 学科 一般知識 大気の熱
空気の熱力学などを学んだ後は、地球の大気を温める熱源と熱の伝搬について学びます。大気の熱源の大部分は太陽からのエネルギーです。
気象学などの教科書では、「黒体放射」とかプランクの法則、シュテファン・ボルツマンの法則などの説明があり、難しいなぁと感じる人もいるかもしれません。
山を張るわけではありませんが、どうしても理解が困難な場合は捨て問にしてその他で確実に得点するという戦略もあります。実技試験ではこの部分についての理解が不十分であっても大丈夫です。ただ、単に捨ててしまうのは勿体無いので、(理論的な部分は一旦おいておいて)過去問を解く際にもう一度戻ってくることにしましょう。
本日は理論的な部分はなるべく触れず、実体験的に親しみ?が湧きやすいところから学んでいきましょう。
🔵太陽定数
太陽からのエネルギーが地球に到達した時のエネルギー量です。太陽の表面温度や地球までの距離などを使用して複雑な計算式から導くことができます。この数値は試験対策上覚えておく必要はありません。
🔵可視光線
太陽からのエネルギーの約半分(47%)は可視光線と呼ばれる領域に属する電磁波です。そのほか、紫外線や赤外線があります。成層圏の気温上昇に寄与するのが紫外線でしたね(復習です)。
🔵反射
太陽からのエネルギーは地表や雲で一部は反射されて宇宙空間に戻っていきます。この反射率を「アルベド」と言います。
地球全体の「アルベド」はプラネタリーアルベドと言います。大きさは約30%と言われています。この地球全体のアルベドは覚えておいた方が良いです。試験に出ます。
黒色と白色の液体を日向に置いておくと、黒色の液体の方が水温が高くなりますよね。黒色の方が白色よりもエネルギーを吸収しやすいということは、皆様日常の経験から体得していると思います。
「アルベド」は反射率のことでした。ですから、エネルギーを吸収せずに反射してしまう白色の方が黒色よりも「アルベド」は大きくなります。
海のアルベドは10以下です。キラキラしていて反射しそうですが、海は上空から見ると意外と黒い色をしています。珊瑚礁の浅瀬は綺麗なブルーですが・・・。
地上に降り積もった雪のアルベドは80〜95と言われています。太陽からの入射エネルギーのほとんどを反射していると言えます。スキー場ではサングラス付きのゴーグルでないと目が疲れますよね。日焼けもするし。
また、厚い雲のアルベドも70〜80です。厚い雲を地上から見ていると真っ黒ですが、宇宙空間から見ると鮮やかで大変明るい白色です。宇宙空間からの雲の見え方は、気象衛星の撮影した画像を見てください。気象庁のほか、各お天気予報会社や検索エンジンからアクセスできると思います。
🔵吸収
太陽からのエネルギーのうち紫外線の部分は熱圏・成層圏の酸素・オゾンによってほぼ100%吸収されます。ほぼと言ったのは、ほんの一部の紫外線は吸収されず地表に到達します。日焼けの原因となる紫外線です。紫外線は英語でUltra-violet。UVという表示を色々なところで見かけると思います。
地球に生物が繁栄できたのは、有害な紫外線を上空の大気中の分子が吸収してくれたお陰でもあります。
赤外線の部分は水蒸気や二酸化炭素などによって吸収されます。
赤外線の部分で特定の波長は、大気中の分子で全く吸収されません。この特定の波長の領域を大気の窓と呼んでいます。この特性を利用して気象衛星による雲や気温等の観測が行われています。
🔵散乱
昼間の空が青く見えるのはレイリー散乱によります。散乱の強さは波長の4乗に反比例するという特性があります。青色が最もよく散乱しますので私たちの目には青色の光が多く見えるために空は青色となります。散乱に寄与する空気分子は波長の10分の1の大きさです。
他方、可視光線の波長とほぼ同じ大きさの粒子によって散乱される場合をミー散乱と言います。ミー散乱では可視光線の波長の長短に関係なく散乱するので分光が起きません。分光の現象で典型的なのは虹です(綺麗ですよね)。上空では機窓から円形の虹を見たことがあります(脱線しました)。
さて、ミー散乱の典型的な例は、雲や霧が白く見えることです。
🔵全天日射
太陽からの光は、地表に直接太陽から届く直達日射と、散乱によって迂回して地表に達する散乱日射の二つがあります。この二つの日射を合わせて全天日射と言います。
専門知識の観測の項目で学びますが、直達日射量がある一定の基準を超えた時間を日照時間として観測しています。
雲や霧といった現象により太陽光線が遮られてこの基準値を下回ると日照時間としてカウントされません。
🔵放射平衡温度 −18℃(255K)
地球に大気がないと仮定した時の放射平衡温度は −18℃ と言われています。まるで氷河期ですね。しかし、地上の平均気温は約15℃ですので、その差の33℃は温室効果によるものと言われています。温室効果が全くないととても地球は寒い環境になってしまいます。
🔵地球の放射収支(よく出る問題)覚えておくと便利。
太陽から地球にやってくるエネルギーを100とすると、大気上部でその約30%が宇宙空間に反射されてしまうことは、プラネタリーアルベドということで学びました。
エネルギーの50%は地表面が直達日射(20%)、散乱日射(30%)到達します。
残りの20%のうち、雲で3%が吸収され大気中の空気が17%を吸収します。
地球からの放射について教科書などで詳細に述べられていますので確認しておいてください。過去問を解いていた感覚では太陽放射エネルギーの収支のほうがよく出題されていたと思いますので省略します。
🔵緯度による平均的なエネルギー収支
赤道などは暖かく地球全体の熱収支としてはプラスとなっています。そして、1年のうち約半分が夜となる極地方ではマイナスとなっています。熱量の分岐点は緯度40度付近です。40度よりも緯度が低い場合は太陽から受け取るエネルギーは地球外への放出と比べて大きく、反対に40度よりも高緯度では太陽から受け取るエネルギーよりも地球外への放出の方が大きくなっています。両極付近の高緯度が氷河などに覆われているのはそのためです。
🔵北半球と南半球
北半球と南半球ではどちらが太陽のエネルギーを受け取る量が多いでしょうか。
実は南半球なのです。地球の公転軌道で近日点は1月頃となっています。1月頃は北半球では冬ですね。南半球の方が北半球よりも多くの熱量を受け取ることができます。
気象の現象予測に一見すると直接関係ない地球の熱量といった大きな問題について見てきました。
地球が受け取る熱の移動のために海洋では海流が、大気も熱の運搬のため各種の擾乱が発生します。熱帯低気圧や温帯低気圧は低緯度地方で受け取った熱を高緯度に運ぶ役割があります。覚えることが多く大変ですが、この基礎知識は実技試験を解く際のベースにもなるので頑張りましょう。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
