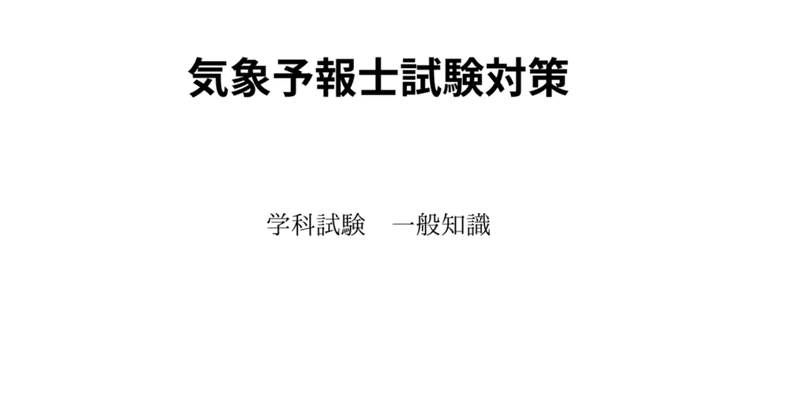
気象予報士試験対策 学科 一般知識 降水過程、十種雲形と霧
🟣まずは雲粒
水蒸気が上昇して冷却されて凝結することで雲粒ができます。エーロゾルなどの微小物質が空気中にあれば凝結核として働き、水蒸気が凝結しやすくなります。
また、海上の上空にある吸湿性のエーロゾルである海塩粒子は水蒸気の凝結を起こりやすくしています。
🟣雲粒が降水粒子に成長
(1)併合過程 暖かい雨
雲粒同士が結びつき、より大きな粒子が落下中に小さい粒子を取り込んで降水粒子に成長していきます。併合過程と言います。大きな粒子は落下速度が大きく、このような粒子の落下により併合過程による降水粒子の成長が進みます。
雲の中の気温が0℃以上の場合に限ります。主に熱帯地方の雨は暖かい雨によるものが多いです。
(2)凝結過程 冷たい雨
水蒸気が雲粒になることも凝結過程と言いますが、ここでは併合過程との対比で使用します。雲の中の気温が氷点下である雲頂高度が高い雲で降水粒子が成長する様子を見ていきましょう。氷と水では飽和蒸気圧が異なり、氷の方が小さいです。雲の中の飽和水蒸気圧が氷の飽和水蒸気圧よりも大きく、かつ、過冷却水の飽和水蒸気圧よりも小さい時は、過冷却水滴の表面から水蒸気が蒸発して氷粒に取り込まれます。氷粒のことは氷晶と言います。日本付近での雨は冷たい雨が多くなっています。
🔵雲の種類 10種雲形
全ての雲が雨をもたらすわけではありません。巻雲などの高層の雲は雨をもたらしません。
上層雲 高度:上空5km〜13km
(1)巻雲 cirrus (Ci)
最も高い雲。すじ雲。温暖前線や低気圧の接近の前触れになる。
(2)巻積雲 cirro-cumulus (Cc)
巻雲よりも少し低い高度。うろこ雲。いわし雲。小さな塊の白い雲が規則的に並ぶ。
温暖前線や低気圧の接近の前触れで、巻雲についで出現する。
(3)巻層雲cirro-stratus (Cs)
淡く白っぽいベール状の雲。太陽や月にかかるとカサ(暈)ができる。後述する高層雲と異なり、日光を通すので影ができる。天気が悪くなる前触れとして出現する。
中層雲 高度:上空2〜7km
(4)高積雲 alto-cumulus (Ac)
巻積雲のような形状で色は、白または灰色。ひつじ雲。まだら雲。小さな塊が規則的に並ぶ。巻積雲と比べ雲が厚く、下から見上げると下部が黒っぽくなっていることで巻積雲と見分ける。巻積雲よりも一つ一つの雲の塊は大きい。
(5)高層雲 alto-stratus (As)
灰色または青色っぽい一様な層状の雲で、全天を覆うことが多い。高層雲の中で薄い部分は太陽をすりガラス越しで見たように太陽の輪郭はわかる。厚い高層雲は降水をもたらすことがある。温暖前線や低気圧の接近時に、巻雲、巻層雲の次の出現する。
下層雲 高度:地上付近〜上空2km
(6)乱層雲 nimbo-stratus (Ns)
まさに雨雲!と呼ばれる雲の一つ。雲底は灰色や黒色。層の厚い雲であり全天を覆う。太陽光線も遮る。低気圧の中心付近や前線付近に出現し雨を降らせる。
(7)層積雲 strato-cumulus (Sc)
白または灰色っぽい雲。曇天の時に現れる。降水をもたらすことは少ない。雲海という現象を起こす雲。
(8)層雲 stratus (St)
雲の中では、最も低い高度にできる雲。灰色の雲。地上に達すると霧となる。雲海という現象を起こす雲。
(9)積雲 cumulus (Cu)
お天気コーナーで曇りのマークを示す綿菓子のような雲。形状はモコモコしている。晴れた日に発生することが多い。白く輝いているが、雲底付近は黒く見えることがある。雲底の形状は平らである。積雲が発達すると「雄大積雲」となり、強い降水をもたらすことがある。「雄大積雲」がさらに発達すると後述する積乱雲になる。
(10)積乱雲 cumulo-nimbus (Cb)
雄大積雲がさらに発達した雲頂高度が高い雲。入道雲。雲頂が対流圏界面に達すると円状に水平方向に広がり、かなとこ雲と呼ばれることもある。雷雲。
竜巻などの強い突風、短時間強雨、落雷、降雹などシビアーな天気をもたらす。航空機は特に危険。
霧について
霧は視程が1km未満になった時をいいます。視程が1kmを超えている場合を「もや」(靄)と言います。試験では「もや」を漢字で記述することは求められていません。
ただ、定義を正確に覚えておく必要があります。
霧は発生メカニズムによって次の5つに分類されます。この霧の種類についても学科試験、実技試験ともに出題されています。
(1)移流霧
暖かい空気が温度の低い海面上を移動した時に発生する霧です。北海道東方海上や釧路沖、北海道の十勝・釧路・根室地方の海岸付近で初夏から夏にかけて発生する霧が有名です。
(2)放射霧
晴れた日の夜明け前に放射冷却で地面が冷やされた時に空気中の水蒸気が凝結して発生する霧です。太陽が出て気温が上昇すると消滅します。
(3)蒸気霧
相対的に暖かい水面から蒸発する水蒸気が冷たい空気で冷やされて発生する霧です。混合霧とも呼ばれると教科書に書かれていますが、試験で混合霧という用語が出た例を見つけていませんので、よく探してみます。
(4)滑昇霧
山の斜面を湿潤空気が滑昇した時に断熱膨張によって湿潤空気が冷却され飽和に達した時に発生する霧です。
(5)前線霧
温暖前線からの暖かい降水が前線の下層にある寒気内で一旦蒸発して水蒸気となり、それが再び冷却されて発生する霧です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
