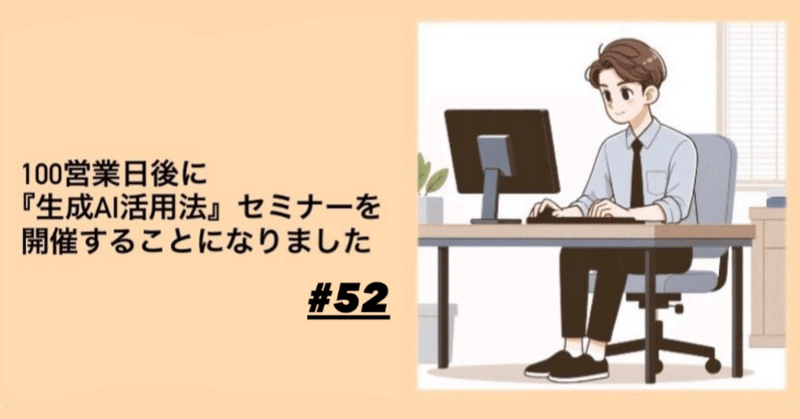
#52【わかりやすい…!】東京都のAIガイドライン読んでみた
おはようございます。
49営業日後に『生成AI活用法』セミナーを開催するアヒルです。先日久々にDOGSOを目の当たりにしました。
今年4月、東京都のデジタルサービス局は『文章生成AI利活用ガイドライン』というものを発表しました。

今後業務の中で生成AIを活用していく上で、改めてリスクやセキュリティについて確認しておきたいなと思い、今回は都のガイドラインを読んでみてふむふむと感じたことをまとめていきます。
『文章生成AI利活用ガイドライン』とは?
Googleに対抗する検索機能を備えたGPT-4oに聞いてみます。
東京都が発表した「文章生成AI利活用ガイドライン」は、都職員が安全かつ効果的に文章生成AIを活用できるように策定された指針です。
このガイドラインの主な目的は、行政サービスの質を高めることです。
都職員のために作られたものとはいえ、自分のような民間企業の社員でも参考にできるような構成になっています。
具体的には、
1. 利用上のルール:
AIの使用に関する基本的なルールを定め、職員間のテキストの一貫性を保ち、情報伝達の精度を向上させます。
2. 効果的な活用方法:
AIの活用事例を紹介し、実務に即したアプローチを推奨しています。
3. 技術導入の敷居の低減:
未経験者でも分かりやすい解説が含まれており、多くの職員がAIを活用する意欲を持つように配慮されています。
このように、ガイドラインでは文章生成AIの利用上のルールや効果的な活用方法が説明されています。
職員がAIを使用する際のベストプラクティスやコツが提示されているので、これを参考にAIを活用できれば、業務の効率化やコミュニケーションの改善が期待できます。
入力情報とセキュリティ
推奨生成AI
都が推奨している生成AIツールは、MicrosoftのCopilotです。
その理由には、以下のような点が挙げられるそうです。
・入力データが学習目的で利用されない
・入力データの保存をサーバー側で行わない
また、Copilotを使うにしても、画面に保護済みマークが表示されていることをきちんと確認することが大切とのこと。

入力データ
東京都では、入力するデータは機密性ランクごとに分類し、対応を考えていました。

いくら学習されないとはいえ、秘密文書のような大切な情報は、入力不可として規制しています。
自分の会社でも、こーゆー情報は入れてはいけないといったしっかりした決まりを改めて周知していく必要があるなと感じました。
またコンプライアンスの観点から、AIによって生成された回答を、まんま対外的に利用する場合は「生成AIが作成」した旨を明記するとも書かれています。
入力だけでなく、出力されたデータに関しても扱いは慎重になる必要があります。
まとめ
東京都の発表した『文章生成AI利活用ガイドライン』に目を通し、大事そうなところをまとめてみました。
デザインがとても見やすいので、読むのにそこまで苦労はしませんでした。経済産業省が出してるAI事業者ガイドラインみたいなのはもう…3,4ページくらい読んでそっ閉じしました……。
自分が社内でセミナーを開く頃には、その辺のセキュリティの話もしっかりできるようにならないとなと思います。
お読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
