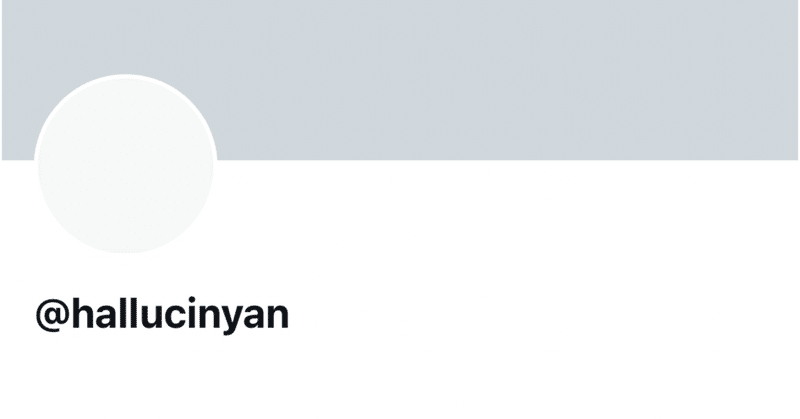
思い出インターネット
はるしにゃんのTwitterアカウントが凍結されたらしく、そのことについてつらつらと考えていた。
はるしにゃんというのは2010年代前半にTwitterで活躍していた批評家で、ブログや同人誌などを舞台に旺盛な批評活動を展開していた。彼は2015年に亡くなっており、単著を残しているわけでも、商業誌で執筆していたわけでもないので、今では知らない人の方が多いかもしれない。
はるしにゃんは当時「メンヘラ」と呼ばれていた人たち、およびその現象についてのエッセイや批評、小説などを書き、それらの成果を同人誌の形でまとめることによって、一定の反響を得ていた。
ぼくがはるしにゃんを知ったのは2014年頃で、まだTwitterをはじめて間もなかった。ぼくは高校一年生で、不登校になる寸前、というような状態だった。
その頃のぼくは、福島の片田舎に住んでいた訳だが、Twitterで活動している大学生をしきりとフォローしては、熱心に呟きを追っていた。彼らのほとんどは東京や京都の大学に通っており、文学やサブカルチャーについての造詣が深く、酒やドラッグに酔ってはツイキャスで配信をし、ブログに文章を書き、ときたま同人誌を出したり、自殺未遂をしたりしていた。
そんな中でもひときわ異彩を放っていたのがはるしにゃんだった。
はるしにゃんは、不思議とぼくのフォローしてる人たちと直接、ないしは間接的な知り合いであることが多く、よく彼のことが話題にのぼっていた。良い話題、悪い話題とそれは様々だったが、とかく話題には事欠かない人だった。
とは言え、ぼくがはるしにゃんに興味を持つようになったのは、彼の死後のことである。彼は2015年の夏のある日、マンションから飛び降りて自殺を遂げた。享年24。
今でもそのけがあるが、ぼくはそもそも、自殺者の書いた文章というものが好きである。高野悦子、南条あや、二階堂奥歯。特にそれが、作品といった完成されたものではなく、あくまで日常雑記的な、ありのままの思考が記されているものほど、ぼくは好きだった。
それで、はるしにゃんが自殺したとき、遡行的に、彼の文章はぼくにとって俄かに価値を帯びた。2015年の夏というと、ぼくは不登校を経て通信制高校に通いはじめていた頃で、日々最悪な気分で生きていたはずである。
はるしにゃんが自殺した直後から、ぼくは彼の書いた文章を手当たりしだい読み漁った。Twitterのログ、同人誌(これは後に友人から貰ったものだが)、ブログ、ツイキャスの配信アーカイブ、Instagram……。
だが当然、彼が若くして自殺を遂げたという理由だけで、ぼくは彼の文章を読み漁っていた訳ではない。彼のつむぐ言葉に、独自の輝きがあったこともまた、確かである。
いま思い返してみると、2010年代前半に「メンヘラ」と呼ばれていた、あるいは自称していた人たちは、病んでいるにも関わらず、底抜けに明るかった。明るいというより、ポップだった。それについては色々な観察が可能だろうが、要するに、それが当時の流行であり、「メンヘラ」たちが自らに課した流儀でもあったのだろう。自分の苦しさを他人に押し付けない、それを「コンテンツ」(これも当時はやっていた言葉だ)としてフォロワーに提供すること。面白がってもらうこと。それによって「メンヘラ」自身も、危ういところで壊れかけの自我を支えていた。
もちろん、そうした「メンヘラ」のありかたに危険がなかったわけではない。実際に何人かの有名ツイッタラーは自殺してしまったし、そこに自らを「コンテンツ」として提供していたことの影響が皆無だったとは言えまい。だが他方、「メンヘラ」という属性を担うことによって生きやすくなった、あるいはすんでのところで自殺をとどまった、という人もいたに違いない。
そういった状況の中で、はるしにゃんの果たした役割は複雑である。
基本的に彼は現代思想のタームなどを援用しながら俯瞰的に「メンヘラ」を論じると同時に、自らもどうしようもなく「メンヘラ」的であり、同時に「メンヘラ」についての同人誌を作ったりしていた。
もう彼のTwitterもブログも消えてしまった今ではかつての印象を語るほかないが、結局彼の魅力とは、オタク的な自意識と現代思想の知識、それに「メンヘラ」的な精神性との、歪な混淆にあった。そして彼はその歪さを行為においても実践し、生き、そして才気を撒き散らしながらも、大成することなく逝ってしまった。
ぼくは彼の関わった同人誌では『つらぽよ本』、『イルミナシオン』、『メンヘラリティ・スカイ』しか持っていない上、それすらも貰い物なわけだが、そのなかでも『イルミナシオン』所収の「イルミナシオンは愛を求めて」は出色の出来だと思う。本作ははるしにゃんの自叙伝とも言える作品で、彼がなぜ「メンヘラ」になったのか、なぜオタクになったのか、なぜ批評に惹かれたのか、などが赤裸々に、そして飄々と語られている。
これは僕という批評かぶれの落魄した、薄汚れたボロ布をまとったくすんだ魂の記録である。僕は富山に生まれた。一九九一年の二月のことだ。富山という僻地、そうそれは文化的にも僻地なのだ。僕は標準語を愛している。方言を不意に使ってしまうたびにざらざらとした嫌悪感に包まれるし、イントネーションを間違えるたびに顔を赤らめる。僕は神経質だ。
というのが冒頭の一文である。この一文を読んだだけでも、彼の並々ならぬ才気の程がうかがい知れる。彼は多く思弁的、批評的な文章を書いてきたが、ぼくの印象では、そのどれもが高調子でどこか借り物めいていた。しかし本作においては、頻出する現代思想の用語ですらが、彼の実存には必要不可欠なものであったのだと納得させるだけの力がある。彼は自らのフラジャイルな自意識を守るために現代思想を身に纏う。しかしそれは鎧でしかなく、彼の血となり肉となり、独自の思想へと昇華される以前に、彼は力尽きてしまった。それがはるしにゃんという天稟ある若者の悲劇だった。
「イルミナシオンは愛を求めて」。タイトルにもある通り、彼は本作で愛を求めても得られない悲しみを綿々と綴っている。いや、もちろん、明示的にそう書かれているわけではない。だが、鏤められたジャーゴンのあわいから響いてくる声はただひとつ。「僕は愛されたかった」
僕は頭でっかちすぎる。僕は理解しているのだ。さまざまなることを、さまざまなる仕方で。だがそれでもダメなのだ。
だがそれでも僕は楽しかった。この不毛な人生が。世界には萌えとコミュニケーションしかない。そして僕は萌えもコミュニケーションもできない人間を知っている。僕は恋愛をしたことがないが、萌えもコミュニケーションもそれなりにいまは楽しい。そして運命だって直視している。
彼の見つめていた運命とはなんだったのだろう?
それを知る手がかりはもう、インターネットのどこにも残されてはいない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
