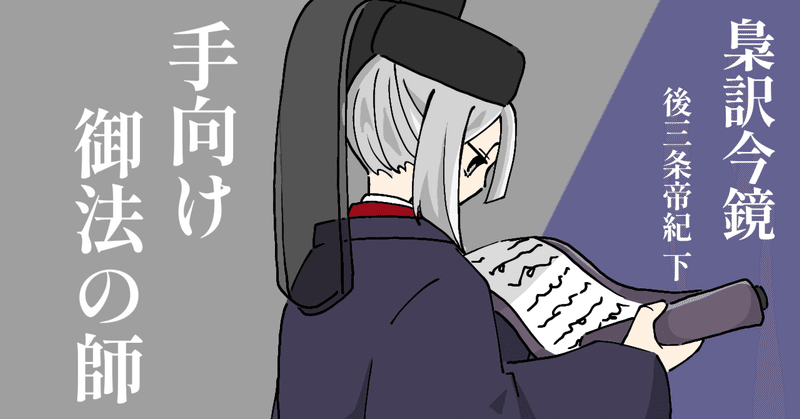
梟訳今鏡(6) すべらぎの中 第二 手向け、御法の師
手向け
この後三条天皇が世を治められてから、この国のことはみんな整備されたんです。
そのすばらしい善政の名残で、今に至るまで平和な世の中が続いているわけなんですよ。
この天皇は気丈なご性格でありながら、人情味に溢れているところもおありでいらっしゃいました。
石清水八幡宮での放生会に長官、参議、諸衛の次官たちが加えられたのもこの御世からのことですよ。
この時から仏教の方面でも本格的なことがたくさん始まったんです。
円宗寺で法華会、最勝会の時に講説する僧侶が置かれたり、延暦寺、園城寺にいる聡明な高僧たちは昇格して僧綱となったりして、この御世では仏法の深い教えが世に広まっていたんですよ。
そうそう、天皇は初めて日吉神社への行幸をなさったり、法華経を非常に大切になさったりもしていたんです。
あの天台宗の教えが広がっていく元である日吉神社を大事にされようとのお考えだったんでしょう。本当に仏教を重んじられていたんですねぇ。
日吉神社に祀られているのは法華経を守護する神様でいらっしゃるんですよ。
ですからここの神様は法華経という真の仏教の教えを護るために、世の人々すべてを広くお恵みされて、ご利益もはっきり施されていたそうです。
そういえば、天皇が石清水八幡宮へはじめて行幸なさった時、見物に来たたくさんの牛車が金物飾りを打って装飾してあったのをご覧になって、御輿をお止めになり、その金物飾りをみんな抜かせられたということがございました。
その中に天皇の乳母子様の牛車もあったのですけど、乳母子様が
「あなたさまの行幸という特別な日です。私の車だけはお目こぼしいただきたい」
と申し上げ、その理由も含めてしっかりご説明されたんでしょうかね。乳母子様のお車ばかりは金物飾りを抜かれずに済んだそうです。
それから、先程のとは別日の賀茂神社への行幸の際には金物飾りを抜いたあとが残った牛車がたくさん並んでいたみたいですよ。
さて、先帝(後冷泉)の頃に大極殿で火事があってから10年過ぎていたんですけど、この天皇(後三条)が帝位についてからすぐその修復工事が始まったんです。
それからまた4年ほど経って修復が終わり、新しくなった大極殿へのお渡りがございまして、そこで修復祝いの漢詩文などが作られました。
この天皇は昔の賢帝たちに劣らず様々なことを執り行われたので、山から吹きおりてくる風に枝が音を立てることさえないような天下泰平の世の中でありました。
この天皇の御世がもう1000年くらい過ぎてもいいくらいでしたのに、天皇は世の中がきっちり整備されたのをご覧になって安心されたのかもしれません。
もしくは帝位という高いお立場で、ただでさえ様子を把握しづらい世の中のことを、宮中の最奥から治められることの支障の多さゆえに一旦上皇となって、より自由なお立場から思い通りの政治を行おうとされたのかもしれませんね。
この天皇は在位4年ほどで東宮(白河)に譲位されてしまわれたんですよ。
それで、退位された後三条院は御母君禎子様と御娘君一品宮聡子様たちをお連れして住吉神社へ詣でられた時の
すみよしの 神はうれしと 思らむ
むなしき船を さしてきたれば
という、上皇となられたご自身について詠み込まれたお歌があるんですよ。
それにしてもこのお歌は聞けば聞くほどますます趣深い感じがして、いいなぁと思います。
さて、この天皇が上皇となられてからもっと長くご存命でいらしたなら、どんなにすばらしかったでしょうかねぇ……。
でも、後三条院は譲位されたその翌年に崩御されてしまわれたんです。
世の人々はみんな惜しがって、その死を悼みました。
後三条院はご在位の間に政務についてのあれこれを記しておかれてから東宮(白河)に位を譲られたわけですから、もう十分だとかお思いになったんでしょうよ。
ああそうだ。とある人がですね、後三条院がどこか別の国が乱れきっているのを見かねられて、それを正してやろうと決心されて、この国をお去りになられたという夢をみたとか言っていたことがありました。
他にも嵯峨の地の遁世人がみた夢で、楽器の音色が空に響き、紫色の雲がたなびいていたので、近くの人に
「これはどういうことなんだ」
とたずねましたら、その人が
「院が極楽の国に生まれ変わられたんだよ」
と答えてくれたなんてものもありまして、その遁世人は夢をみたあとに後三条院の崩御の知らせを聞いて、「あれは正夢だったのか」と確信したんだとか。
御法の師
後三条天皇は東宮でいらした時から仏道に関心を向けていらっしゃったんです。
そんな東宮時代、勝範座主とご対面された際に、
後三条(東宮)「真言と止観(天台宗)を両方学び修得していて、その他に漢籍なんかもよく理解している僧を紹介してくれ。私が信頼している僧たちの中にはそういう者がいないから」
と仰せられて、勝範は
勝範「顕教(天台宗)も密教(真言宗)も習得している僧はありふれておりますが、唐国の書物まで理解しているとなるとなかなかいませんからねぇ。ですが、なんとかたずね出してご紹介させていただきましょう」
と申し上げまして、比叡山へ帰っていきました。
それから少しして、東宮の元へ薬智という僧が参ったんです。
でもその時に東宮は正式な牛車などをお貸しになられなかったんでしょうかね、薬智は狩袴という普段着姿で、馬に乗って御所にやって来たんですよ。
薬智「勝範座主に申し付けられて参った者です」
それで東宮はその薬智という僧と御簾越しにご対面なさいまして、蒔絵で飾られた硯箱の蓋の上に天台宗のお経を1巻おいて差し出されました。
それをその場で薬智に読ませて、東宮が様々なご質問をされましたら、薬智はそれらに対し1つ1つ丁寧にお答え申し上げたんです。
また、真言宗のお経については1度も読ませずにご質問されましたら、それもまた丁寧にハッキリお答え申し上げたそうです。
そして、今度は仏教の経典以外の漢籍についてご質問されましたら、これもまたスラスラと、経典の文章さえ引用しながらお答え申し上げたんだとか。
後三条(東宮)「お前は阿弥陀仏の極楽と弥勒の兜率天、どちらへの転生を望んでいるんだ?」
薬智「私は特にどちらも望んではおりません。ただ、法華経を1部と両界の修法などを毎日おこたることなく続け、弥勒様の出現される世まで修行しようと思っていまして、あの大鬼王ほど長く長く生き続けたいなぁとだけ望んでいます」
そうそう、この話を聞いた後日に誰かに聞いたんですが、須弥山のほとりには大鬼王という鬼がいて、その鬼は仏道修行をしているんだと書いてあるお経があるんだそうです。
鬼というのは化生の生き物……つまり神仏が姿を変えたものでございますので、産まれてから程なくしてひっそりと修行を初め、決してなまけまいとするんだとか。
さて、東宮はこの時、無事に即位できますようにというご祈祷も格別にすることができないお立場でいらっしゃいましたから、
後三条(東宮)「特別に祈祷などしなくてもいいから、日々の修行の合間にでも私のことを気にかけて、ただ私の安穏を祈っていてくれるか」
とだけ薬智に仰せられました。
それから天皇として帝位につかれて後に、再び薬智をたずねさせられたそうなんですが、その頃にはもう薬智は亡くなっていました。
なので、天皇は薬智の弟子を僧綱に為して、お祈りのお礼をされたんです。
この弟子は「大上の法橋」とか申す僧侶だったかと思います。
それにしてもこの後三条天皇は東宮時代に多くの苦難を経験されまして、普段から不安な思いでお過ごしになっていたんです。
例えばある日、当時検非違使別当だった経成という者が直衣姿に冠の纓を丸めて止める柏挟みをして、白羽の胡籙を背負うといった非常時のいでたちで、東宮の御所の中門の廊に陣取っていたということがありました。
それを見て東宮御所では「なにがあったんだ」と女官を始め、みんな隠れて震え上がってしまったんだとか。
この東宮御所は二条大路と洞院通りの交差点にある二条東洞院であったのですが、この当時、その周囲を兵が取り囲んでいたので、東宮御所では「兵士がたくさんいるぞ」「包囲されているんだ」と噂しあっていたんです。
そこへ非常時の格好をした検非違使の別当経成がやってきたというわけですから、もう何があってもおかしくない状態になったんです。
そこで東宮も身軽な直衣姿になられ、いざという時のご準備なども様々なさった上でじっとしておられますと、その別当が部下を呼んで、
経成(別当)「犯人は見つかったか」
部下「はい。既に逮捕しました」
と会話しているのが聞こえました。それから別当は何も言わず、中門の廊から立ち去ったんです。
実はこの時、重大な罪を犯した者が東宮御所付近に隠れていたんです。
それで検非違使たちが「もしかすると犯人は東宮御所に逃げ込んでいるかもしれない」と考えて、御所を包囲していたんですよ。
そういったこともあったりして、本当に日々不安なお気持ちで、そのうち東宮位を辞退させられることになるかもしれないとまでお考えになって、恐れられていたんです。
ですが、殿上人で衛門府次官の行親と申した、人相判断が上手いと評判の男がおりましてね。その者が「東宮はまさに世を治められるべきお方です」と申したことがあったそうなんですよ。
そしてその者が言った通り、東宮は即位して、類まれなすばらしい為政者となられたんです。
さて、後三条天皇の御母君でいらっしゃる陽明門院禎子様についても少しお話しましょうかね。
この方は三条院の御娘君で、後朱雀院がまだ東宮でいらした時に御息所でいらっしゃいました。
そして御年22歳にしてこの天皇をお産みになったんです。
そして長元10年2月3日、御年25歳で皇后宮となられました。
この時にそれを耳にした江侍従という人が
紫の 雲のよそなる 身なれども
たつと聞くこそ うれしかりけれ
と詠んだとか。
そして禎子様は寛徳2年7月21日にご出家され、治暦2年2月に「陽明門院」という女院号を与えられたんですよ。
この方はお歌なんかも大変優美な感じにお詠みになっていらしたようです。
例えば退下中、後朱雀院におくりたてまつられたもので
今はただ 雲井の月を 眺めつつ
巡りあふべき ほども知られず
なんてお歌がございます。まことに昔の名歌にも劣らない感じですよね。
この陽明門院様の御母君である皇太后宮妍子様は道長様の次女でいらっしゃいます。
