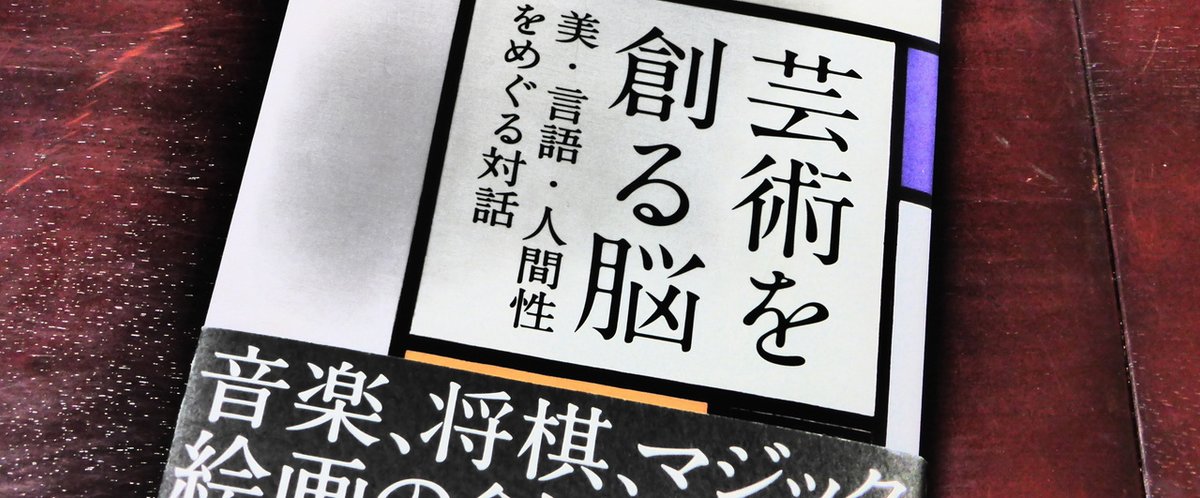
『芸術を創る脳 美・言語・人間性をめぐる対話』(酒井邦嘉[編]、曽我大介、羽生善治、前田知洋、千住博 東京大学出版会・刊)
すごいものを読んでしまった。
拙著『バベル』を書く際に、脳と言語の関係について東京大学の酒井邦嘉教授に教えを乞うた。昨年12月に本書を上梓されたと聞き、すぐ手に入れていたのだが、「どうしてもっと早く読まなかったのか!」。こんなに面白いのに。
本書は、指揮者・作曲家の曽我大介氏、将棋棋士の羽生善治氏、クロースアップ・マジシャンの前田知洋氏、日本画家の千住博氏という各界の第一人者と、酒井教授との対談形式で書かれた、「創作と脳」の秘密を明かし、なおかつさらなる「人間という生物(と脳)の不思議」に思いを馳せるものである。
非常に奥の深い専門的な書物なのに、脳についても、音楽・将棋・マジック・絵画のどの分野についてもドシロウトの私が読んでも、まったく抵抗を感じないほど読みやすい本だ。対話という形式のおかげだろう。
随所でシビレた。本を抱えたまますっくと立ち上がり、奇声を上げてそのへんを駆けまわりたくなるほど感銘を受けたこともしばしば(えっ、お前は感銘を受けると走り回るのかって。そうなんですよw)。その道の第一人者の言葉には、考えに考え抜かれた深みと含蓄がある。たとえばこんな具合だ。
"いかに適切な指示を出すかは、先輩のマエストロ(巨匠)たちを見て学ぶところが大きいのです。私の先生の一人であるジュゼッペ・シノーポリは、「音を大きくして」と言わないのです。例えば、「温めてください」と言う。そうすると、「大きくして」と言うよりも人間的な感情に近く、指示の意図が伝わりやすくなります。" (P.28 曽我大介氏)
"将棋でもたくさん手が読める、正確に指せる、よく考えて計算できるという能力はもちろん大事なのですが、もっと大切なことがあります。それは、「この手はダメだ」と瞬間的に分かることです。" (p.69 羽生善治氏)
『バベル』のために取材をしていた時、たとえば脳に与える薬物を変えただけで、性格も変わるということがわかった。温厚な紳士が、ある睡眠薬を飲まずにいると、癇癪持ちの暴れん坊に変わったりするという。「ジキルとハイド」を地で行くような話だ。人間の性格や感情すら、「脳」が支配しているのか--。それなら、たとえば美しい夕焼けを見て感動する人間の「心」は、どんなしくみで機能しているのか--。
もちろん本書は、人間の創作や心の秘密をすべて解明するものではない。ただ読み進めるうちに、「人間という生き物は、どうしてこんなに不思議で面白いのだろう」と、しみじみ考えてしまう。そして、音楽に将棋、マジックに絵画と、まったく関係のなさそうな四つのジャンルを取り扱っているのに、実はこれらの芸術に携わる人々の言葉が、ひどく共通していることにも気がつく。
しばらく時間をおいて、また何度も読み返したい。そんな本だった。
