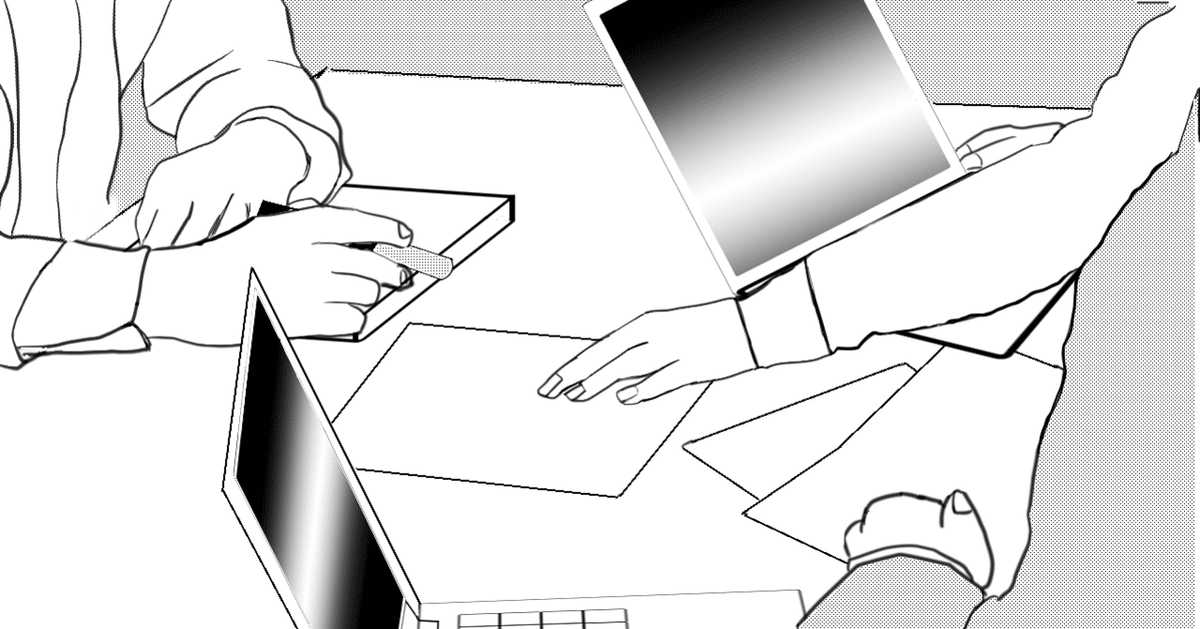
司法試験 倒産法 平成24年度 第1問
問 題
次の事例について,以下の設問に答えなさい。
【事 例】
A株式会社(以下「A社」という。)は,コンピュータ・ソフトウェアの製造及び販売を業とする会社であり,平成20年頃には,年間で50億円を超える売上げを計上するなど,順調な業績を維持していたが,平成22年末頃以降は,徐々にその経営が悪化し,平成23年9月5日には,破産手続開始の申立てをするに至り,同月15日,破産手続開始の決定を受け,弁護士Xが破産管財人に選任された。
〔設 問〕
以下の1及び2については,それぞれ独立したものとして解答しなさい。
1.A社は,平成22年12月頃,売上げの半分以上を占めていた取引先が破綻し,当該取引先からの支払が突然途絶えたため,以後は,その資金繰りが悪化した。
そこで,A社は,メインバンクを含む金融機関に新規の融資を求めたものの,十分な額の融資を得ることができそうになかったため,取引先からの紹介を受け,いわゆる事業再生ファンドであるBアセット株式会社(以下「B社」という。)と交渉した結果,将来の他社とのM&Aを念頭に置いてB社から最大で20億円をめどに融資を受けられることとなり,まず,平成23年2月1日に5億円の融資を受ける旨の契約をB社との間で締結し,その融資は,同日,実行された(以下においては,利息については考慮せず,当該契約に基づくA社の債務額は,5億円とする。)。この契約においては,A社は,同年8月1日をもって,借入金を返済する旨の条項が含まれていた。
A社によるスポンサー企業等の開拓は,その後も精力的に続けられたが,業界の景気の更なる悪化などのため,適当なスポンサー企業等を獲得するには至らなかった。その結果,A社の経営状況は,同年6月頃から深刻さを増したものの,B社からの上記の5億円の融資金の残りを利用することができたため,一部の金融機関に対する債務の返済計画を相手方の同意を得て変更した以外は,全ての債務を約定どおり弁済していた。
一方,B社は,同年6月頃には,A社への上記の融資は失敗であり,その回収に向けた準備が必要であるとの判断に至ったことから,当該融資の段階でその担保のために抵当権の設定を受けていたA社所有の不動産の評価を進めたところ,2億円しか満足を受けられる見込みがないことが明らかになった。そこで,同年7月25日,B社の代表取締役らがA社を訪れ,5億
円の融資の返済期日を同年9月1日に変更するとともに,その見返りとして,A社の有する複数の売掛金債権(全てが優良債権であり,その評価額は,2億円であった。)を追加担保(譲渡担保)としてB社に差し入れることを求めた。A社の代表取締役であるCは,同年7月25日,やむを得ず,これに応じて,当該売掛金債権について債権譲渡担保を設定し(以下「本件
債権譲渡担保設定行為」という。),A社とB社は,同月28日に債権譲渡登記を経由した。
A社は,この当時,同年8月中旬までに弁済期が到来する債務を幾つか負担し(この他には,同年8月中に弁済期が到来する債務はなかった。),その総額は,1億円に達していたが,B社に対する債務の支払の猶予を受けたことで余裕ができたため,何とか,これらの債務を全額決済することができた。ただし,CらA社の経営陣は,同年7月末時点で,A社の余裕資金はぎ
りぎり1億円であり,他方で,同年8月中に新たな弁済資金の調達の見込みがなかったため,同年8月中旬には弁済資金が枯渇するものと予想していた。そして,実際にも,その予想どおりに資金状況は推移し,返済期日が同年9月1日に変更されたB社に対する上記の債務の支払をすることができなかった。
以上の場合において,A社の破産手続開始後,A社がB社のためにした本件債権譲渡担保設定行為をXが否認することができるかどうかについて,予想されるX及びB社の主張を踏まえて,論じなさい。
2.A社は,平成23年5月27日,株主総会を開催し,①取締役としてDらを選任すること,②定款を変更して,本店を移転すること,③1株当たり5000円の配当をすることをそれぞれ決議した。ところが,A社の株主Eは,同年7月29日,当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起した。
なお,この訴訟においては,DがA社を代表して訴訟追行をしていた。
以上の場合において,当該訴訟は,A社に対する破産手続開始の決定によってどのような影響を受けるかについて,論じなさい
関連条文
破産法
2条11項(第1章 総則):定義(支払不能)
44条(第2章 破産手続の開始 第3節 破産手続開始の効果):
破産財団に関する訴えの取扱い
45条(第2章 破産手続の開始 第3節 破産手続開始の効果):
債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い
78条(第3章 破産手続の機関 第1節 破産管財人):破産管財人の権限
80条(第3章 破産手続の機関 第1節 破産管財人):当事者適格
162条(6章 破産財団の管理 第2節 否認権) :
特定の債権者に対する担保の供与等の否認
会社法
330条(第2編 株式会社 第4章 機関 第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任)
:株式会社と役員等との関係
民法
653条2号(第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任):委任の終了事由
一言で何の問題か
偏頗行為否認における支払不能の時期,訴訟の中断受継と取締役の当事者適格
つまづき・見落としポイント
支払不能の判断、会社破産後の取締役の地位、破産管財人の受継可否
答案の筋
概説(音声解説)
https://note.com/fugusaka/n/n98cc9a01c105
1 A社が一般的かつ継続的に弁済をすることができない状態、すなわち支払不能に陥ったのは,8月中旬ではなく9月1日時点であり、「支払不能になる前30日以内」とは言えず、本件債権譲渡担保設定行為を偏頗行為として、否認することはできない。
2 破産財団に属する財産等に影響を及ぼす訴訟であれば、中断され,破産管財人へと受継される。この点、委任者たる会社の破産によってその財産の管理処分権が破産管財人に専属し、委任関係を継続する意味が失われるという民法653条2号の趣旨を踏まえると、組織法上の訴えについては,破産財団の管理処分とは無関係であり,委任関係は終了せず,受任者たる取締役はなお訴訟追行を行える。
ここから先は
¥ 1,000
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
