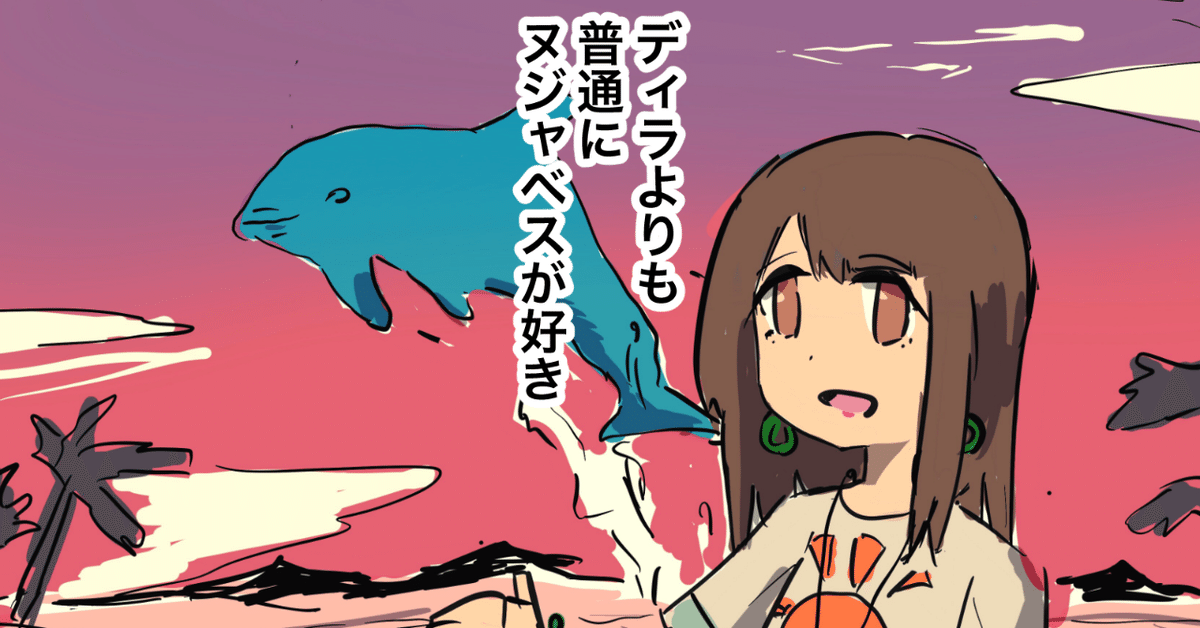
Nujabesについての個人的メモ
NujabesがLo-Fi Hip-Hopの始祖としてカリスマ的な評価を世界的に受けている。
もちろんNujabesの音楽はかつてより評価が高かったが、2020年という時代にこんなにもNujabesの存在感が増してくるとは思わなかった。10周忌に渋谷の交差点でNujabesの映像ジャックが行われ、舐達麻が歌詞に引用し、そして海外音楽メディアの大手で有るGeniusが彼の特集を行う。こうやって一つの天才は、そして歴史というものは生まれるんだなぁ、などとぼんやり思った。
ただ、実をいうと自分はNujabesにそれほどハマったことが無い。そもそもLo-Fi Hip-Hopの源流となったJazzy Hip-HopとしてNujabesを聴いていたっけ……というのが本音だ。形式的にはJ DillaやPete Rockとかと同じジャンル分けをされるが、どちらかと言うと音響系に近い位置に、また、さらに言うと自然の美しさや人との繋がりを歌う歌詞、綺麗なメロディ、DIYにこだわるその様から、雑な言い方をするとオーガニック系だな……という印象を持っていた。オーガニック系ってなんだ、と思うかもしれないが彼の代表曲であるluv sicの歌詞とかを見ると言わんとしていることがわかるだろう。
そう、なんとなくNujabesというのはヒーリングミュージックに近いところにあって、こうしてLo-Fi Hip-Hopとして名を馳せる以前、個人的な頭の引き出しの仕分け方としては、2000年代初頭の坂本龍一と同じところに入っていた。彼らの音楽を聴いていると、美しいメロディに身を任せ、頭の中がクリアになっていく瞬間がやってくる。
そういえば昔、1999年に坂本龍一のenergy flowが「この曲を、すべての疲れている人へ」というキャッチコピーと共にCMで使われると、日本に空前の癒しミュージックブームが発生した。この流れで多くのアンビエントやピアノ曲のコンピが発売され、中でも「〜the most relaxing〜 feel」や「image」といったイージーリスニングのアルバムはミリオンを記録するなど売れに売れた。
この「癒し」というのは現代のLo-Fi Hip-Hopを聴いた時によく形容される「chill」と非常に近い感覚なんじゃないかな、と思う、つまり、かつて日本で流行った「癒し」ブームが「Chill」と名前を変えて世界規模で奇妙なリバイバルを起こしているような印象を受けるのだ。そしてNujabesの音楽は「癒し系ミュージック」の文脈で語ることはそう的外れなことではないと感じる。その理由として、2005年発表のReflection Eternalを挙げたい。
luv sicと双璧をなす、Nujabesの代表曲されるこの曲は、彼がヒーリングミュージックに意識的だったことのわかりやすい例だ。なぜならこの曲のサンプリング元は巨勢典子というピアニストの「I Miss You」という曲だからだ。
このネタ元の巨勢典子はバリバリのニューエイジ系のミュージシャンで、彼女のCDは以下のサイト(https://swbluemoon.com/)から購入できる。このサイトを見ると「ヒーリングミュージック」「瞑想用音楽」のジャンルに彼女の音楽は入っているし、そもそもショップのジャンル自体が「癒しサウンド専門ショップ」だ。このピアノのメロディに、1999年のenergy flowに連なる音楽だという印象を受けるのは僕だけではないはずだ。
しかし坂本龍一は癒しブームに対して懐疑的で、その後ノイズミュージックなどのいわば「反癒し」的なジャンルに向かっていくのに対して、Nujabesは(もちろん数多くの音楽的魅力があることはある上で言うなら)あくまで音楽の持つヒーリング要素の部分に純粋にフォーカスしていったという印象がある。
また、ビートの面でもJ DillaやPete RockといったJazz Hip Hopミュージシャンの特徴であるクオンタイズを行わない、タイミングがずれたグルーヴ感をNujabesは(おそらくあえて)抑え目にしている。
J Dillaのビートを聴くとわかるのだが、異様にタイミングがずれまくっていることで生まれるグルーヴが強烈で、どうしても聴きながら体を横に揺らしてしまう。また、サンプリングするネタの部分もジャズの「スウィング」の部分を切り取っていることが多い。そう言う意味ではJ Dillaなどの音楽はあくまで本質はリズムミュージックであり、メロディの美しさに没頭するような音楽ではないと言えるだろう。
対してNujabesのビートは人を揺らすのでは無く、むしろ静かに音に没頭できる様に組まれている。その為一聴するとリズム構成はHIp Hopのビートなのだが、リズム自体が曲の主役になることはまずない。ビートは上メロをスムーズに聞かせるための推進力であり、曲の本題はそのゴリゴリに癒される上メロである。
さて長々と書き連ねてきたが、一言でいうと、「見た目はHip Hop、中身はニューエイジ」というのがかつての僕のNujabesの印象だった。そしてどちらかと言うとリズム重視の音楽が好きだった自分は、そのヒーリングをあまり求めていなかったのがハマらなかった理由だったように思う。
しかし、Nujabesの癒しは現代において重要な意味を持つようになった。Lo-Fi Hip-Hopは作業用として聴く人間だけでなく、睡眠障害などを患い、あるいはメンタルヘルスに悩むティーンのヒーリングミュージックにもなっているからだ。(下記リンク参照)
YouTubeのLo-fi hip hop、その象徴とも言える「ループする少女 (Study Girl)」が突如頭を抱え出し包丁自殺を図る——。
— INSPI(インスピ)|広告デザインとアイデアの教科書 (@inspi_com) September 9, 2019
これはVICEが英国で実施した“LoFi Beats Suicide”という自殺願望のある学生をターゲットにした施策。「まさに今の私」という共感や自殺を思い留まらせるコメントが多数寄せられた。 pic.twitter.com/Vm2PGtLUaS
彼らがLo-Fi Hip-Hopに、さらに言うとNujabesに求めているのは、ただの流し聞きをするための音楽というよりも、痛みに寄り添ってくれる優しい芸術なのかもしれない。この「Chill」とメンタルヘルスの関係性と言うのは近年非常に強くなっているように感じている。例えば XXXTENTACIONは生前キングダムハーツの下村陽子の音楽を眠る前に聴き、救われたと語っていた。
このXXXTENTACIONの語る「救い」と睡眠障害のティーンに寄り添うLo-Fi Hip-Hopの文脈は非常に近しいものを感じる。また僕が知らないだけで、似たような出来事は他にも数多く起こっているのだろう。音楽を生活のBGMにする以上の、切実さがここには見て取れる。
ニューエイジ系から日本の癒し系、そしてNujabesを経由してChillへ。奇妙な変遷を辿りながら、時代が一周したことで、Nujabesは世界的に重要な音楽となった。(もちろんかつてから世界的に愛されるミュージシャンであったことは当然の歴史として。)ただこうして見ていくと、リバイバルとしての見方以上に、聞き手側にとって「癒し」の重要度が以前よりも上昇しているからこそ起こり得る現象なのかもな、と思ったりもした。こうしてある一つの音楽は元の文脈を離れ、また違う文脈へと繋がれ、大きな歴史になっていくのだなと思った出来事でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
