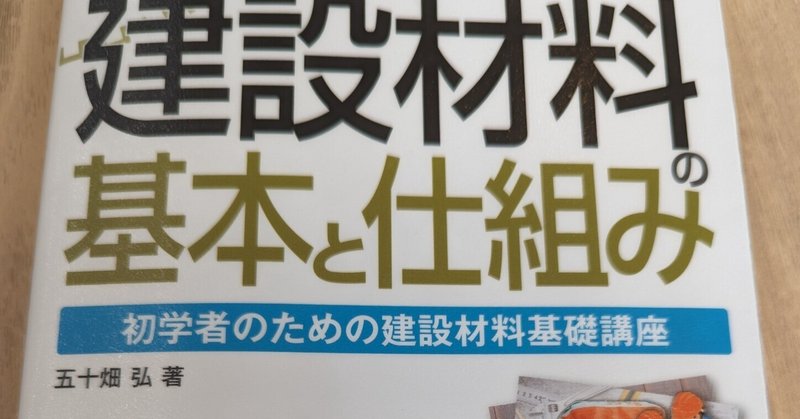
【土木工事】建設材料(コンクリート)の基礎(読書)
1.コンクリートの特徴
・容積比率
セメント(7~20%)、水(7~20%)、細骨材(20~35%)、粗骨材(5~50%)、空気(3~6%)
・強度特徴
圧縮に強く引張に弱い。
(圧縮強度18~150N/m㎡)(引張強度:圧縮の10分の1以下)
・物理的性質
自重(コンクリート自体の重さ)が強い。
橋などの構造物では死荷重大となる欠点、ダムなど重力式構造物では安定性確保の利点となる。
水密性が高く、水を通しにくい。
・耐久性
短期的には高い耐久性、耐火性もある。
・その他
材料の入手は容易、造形の自由度大、品質管理への影響大、再生利用が困難
2.コンクリート材料
①セメント
・種類(各セメント乾燥速度や材料費率などで種類がある。)
ポルトランドセメント(6種類)、混合セメント(3種類)、エコセメント(2種類)
◇物理的特徴
・密度は3g/㎤程度
・粉末度(粒子の細かさ)は2500~4000㎠/g以上
→粉末度が大きいほど水和作用が活発で凝結が進み、強度も大きくなる。
(材齢が少ないほど堅調に顕れる。)
(マスコンクリート水和熱を抑えることで温度応力による初期のひび割れを抑える必要がある。)
・凝結
セメントが硬化する前に、こわばりを生じて流動性を失う段階。
→水をセメントと練り上げてから凝結の始発の時間が各コンクリートで決まっている。
早強コンクリートでは45分、それ以外が60分と規定されている。
通常は、凝結の始発が2~3時間、終結が3~5時間となっている。
・安定性
セメント内部に含まれる石灰や酸化マグネシウムが多い場合、水和反応で異常膨張が発生することがある。
・風化
セメントは空気中の水分と二酸化炭素を吸収する。
→軽微な水和反応や炭酸カルシウムの生成(強度の低下を引き起こす。)
②骨材
モルタルやコンクリートを作る際に、セメントや水と混ぜ合わせる砂・砕石などのこと。(コンクリート体積の65~80%を占める)
→構造材としてのコンクリートの抵抗性を高める
→安定して安価に原材料として供給可能
有機物・泥などを含まず清浄で、物理的・化学的にアルカリシリカ反応などを生じない安定性が望まれます。
球状or立方体に近い形状で適当な粒度分布があることが求められる。
※細骨材と粗骨材がある。
③フライアッシュ
火力発電所などの微粉炭燃焼ボイラーの燃焼ガスから補修される微細な灰成分の粒子。
主成分は二酸化ケイ素、アルミナ、酸化鉄等
比表面積が小さく、所定の流動性を得るための単位水量の減少・ワーカビリティの向上が期待
→セメントの一部の代替として使用
→水和熱の発生が抑制され、マスコンクリートに適する
④ポゾラン
水の存在下で水酸化カルシウムと常温で反応し、接着性のある不溶性化合物を生成して硬化する性質がある。
→緻密な内部組織を持つコンクリートが期待される。
→水溶性分の水酸化カルシウムが減少することで、化学抵抗性が向上。
⑤シリカフォーム
高純度の二酸化ケイ素を主成分とする平均径0.1μmの微細な非結晶状粒子。→流動性が高く、材料分離が少なくなり、施工性が向上。
→強度発現性が増大し、水密性、化学抵抗性が向上。
⑥膨張剤
コンクリートのひび割れ防止に活用。
⑥混和剤
単位水量の低減、強度発現性の向上、流動性の向上などの特定の効果を期待するため製品。(コンクリートに数%程度混ぜる。)
⑦AE剤
微細な空気泡をコンクリート中に連行することで、凍結融解作用を受けるコンクリートの劣化防止
コンクリートの流動性を高め、作業性を向上できる。
圧縮強度は反対に下がる。
(空気量が1%増加すると、圧縮強度は5%程度低下する。)
⑧高性能減水剤
セメント粒子の表面に付着させることで、静電的な反発作用で、凝集したセメント粒子を分散させる。
→セメントペーストの流動性が向上。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
